『論語入門』井波 律子 著、岩波書店(岩波新書)、2012年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序
井波 律子の『論語入門』を読んでみることにする。井波の本としては、『故事成句でたどる楽しい中国史』を読んだばかりで、ついでにいうと、昔々のBlogに書いた『中国の五大小説』(上)を、再掲載しているところです。
孔子の『論語』っていうと、日本人ならば、まぁ断片的には多少知っているが・・・要するにあまり知らない。そして『故事成句でたどる中国史』の孔子の部分は、なかなか面白かった。っということで、井波先生のお導きで、多少は勉強してみようかなとも思ったのでした。今日のところは「序」。それでは読み始めよう。
本書は、つごう五百有余条の『論語』から、百四十六条を選びだし、各条を「孔子の人となり」「考え方の原点」「弟子たちとの交わり」「孔子の素顔」の四章に分類・収録するという構成をとっている。(抜粋)
著者や冒頭で本書についてこのように説明している。そして、孔子の生き方、考え方、弟子たちのとの関わりかた、溌剌として感情等を、具体的にたどっていくことにより、孔子という人物のイメージを浮き彫りにすることを試みるとしている。
『論語』の成立と発展
『論語』は、孔子の対話の記録である。また『論語』は孔子の著書ではなく、彼の弟子たちが孔子の没後、直弟子や孫弟子が孔子の会話の記録を収集・整理し、編纂したものである。
この成立について、江戸時代の儒学者伊藤仁斎は、『論語』二十篇のうち、前半十篇(上篇)がまず整理・編纂され、後半十篇(下篇)はが後に付加されたという説を主張した。仁斎は、前半十篇の表現が総じて、孔子の生気あふれる言葉づかいを、簡潔かつストレートに伝えているのに対して、後半十篇の表現は理に落ち、やや精彩を欠いているとした。
紀元前二世紀の前漢の武帝は、孔子が編纂したとされる五経(易、書、詩、礼、春秋)と合わせて『論語』を知識人士大夫の必読書と定めた。これ以降二千年にわたり、これらの書物は連綿と読み続けられた。特に『論語』は五経に比べて読みやすいこともあり、知識人士大夫だけでなく、庶民階級層にも浸透した。
さらに南宋の朱子が、『大学』、『中庸』、『論語』『孟子』を四書と称して、孔子の思想のポイントを示すものとして重視するようになると、『論語』はとりわけ普及した。
日本での『論語』とその魅力
『論語』の日本への伝来は、『古事記』『日本書紀』に応神天皇の時代と書かれている。これが伝説としても、少なくとも六世紀初頭には伝来していると思われる。それ以降、日本でも千年以上にわたって読み継がれ、江戸時代には寺子屋などを通じて庶民階層にも普及した。
近代以降は、中国でも日本でも、『論語』は、古色蒼然とした堅苦しい聖人孔子の教訓書というイメージが強まり、敬遠されるようになった。しかし、近年『論語』が再び注目を集めている。それは、混迷を深める今日、『論語』を通じて生きる指針を求めようとする動きであると考えられる。
しかし、著者は、このような教訓書としての『論語』の捉え方を残念なものとして以下のように言っている。
『論語』がいずこにおいても色あせない大古典として、長らく読み継がれてきたのは、単に教訓を記した無味乾燥な書物ではなく、読む者の心を揺り動かす迫力と面白に富むためだと思われる。『論語』の魅力、面白さは、その中心をなす孔子という人物の魅力に由来する。(抜粋)
孔子の生涯
孔子(本名、丘、あざな仲尼)は、春秋時代の後半に小国魯に生まれた。司馬遷の『史記』によると紀元前五五一年に生まれ、没年は紀元前四七九年、七十三歳であった。
父は、叔梁紇、母は、顔氏で母は正妻ではなかった。孔子は極めて強健で身長は九尺六寸(約二メートル二〇センチ)で「長人」と称された。
父は孔子が生まれるとまもなく亡くなり、やがて母とも死別する。孤児としてあらゆる機会をもって礼法などを学ぶ、一方、生計を立てるために魯の貴族に仕え倉庫管理や家畜の世話などもした。
そして三十歳ころに学者として認められるようになり、弟子入りする者も増える。孔子は自らの理想を実践に移すべく、政治参加を志すがその機会はなかなか訪れない。
そして孔子が五十三歳のとき念願の魯の大司寇(司法長官)の地位につく。孔子は三大貴族の勢力を削ぐために活動するが、反発され失脚してしまう。
この後、孔子は弟子たちを連れて魯を離れ諸国遊説の旅をする。そして足かけ十四年の旅を終え、六十八歳の時に魯に帰国する。以後七十三歳で死去するまで、弟子の教育と『詩経』をはじめとする古典の編纂に専念した。
ここで著者は、孔子の生涯が不遇の連続であると考えることもできるが、そうではないと注意している。孔子は訪れた国々で賓客として遇され、いわゆる放浪の旅ではない、そして諸国では、弟子たちを次々と就職させ、旅に出ている間も魯には弟子たちにより拠点が維持されていて、孔子の帰国を待っていた。
これらの点を考え合せると、孔子を単に不遇な放浪の思想家というロマンティックな観点からのみ、とらえることはできないと思われる。(抜粋)
『論語』の注釈書
論語には、多くの注釈書がある。そのもとになるのは、
- 「古注」・・・・・魏の何晏の『論語集解』
- 「新注」・・・・・南宋の朱子の注釈
である。
日本の注釈書としては、
- 伊藤仁斎の『論語古義』
- 荻生徂徠の『論語徴』
が挙げあれる。
関連図書:
井波律子(著)『故事成句でたどる楽しい中国史』、岩波書店(岩波ジュニア新書)、2004年
井波律子(著)『「中国の五大小説」(上) 三国志演義・西遊記』、岩波書店(岩波新書)、2008年
目次
序 [第1回]
第一章 孔子の人となり [第2回][第3回][第4回]
1 みずから語る生の軌跡
2 実践としての学び
3 生活のなかの美学
第二章 考えかたの原点 [第5回][第6回][第7回][第8回][第9回][第10回]
1 核となるキーワード
「君子」──徳は孤ならず
「仁」──誠実な思いやり
「孝」──父母への敬愛
「礼」──真情の表現形式
「道」──理想社会への希求
「文」──文化のとらえかた
「鬼神」──不可知なものとの距離
「狂」──過剰なる者への好意
2 政治理念と理想の人間像
第三章 弟子たちとの交わり [第11回][第12回][第13回][第14回][第15回][第16回][第17回]
1 教育者としての孔子
2 大いなる弟子たち
顔回──「賢なる哉」、最愛の弟子
子貢──「一を聞いて二を知る」秀才
子路──「由や果」、純情な熱血漢
さまざまな弟子との語らい
3 弟子、孔子を語る
4 受け継がれゆく思想
第四章 孔子の素顔 [第18回][第19回][第20回][第21回][第22回][第23回][第24回]
1 ユーモア感覚
2 不屈の精神
3 激する孔子
4 嘆く孔子
5 辛辣な孔子
6 楽しむ孔子
あとがき
主要参考文献
関連地図
孔子年表
主要語句・人名リスト
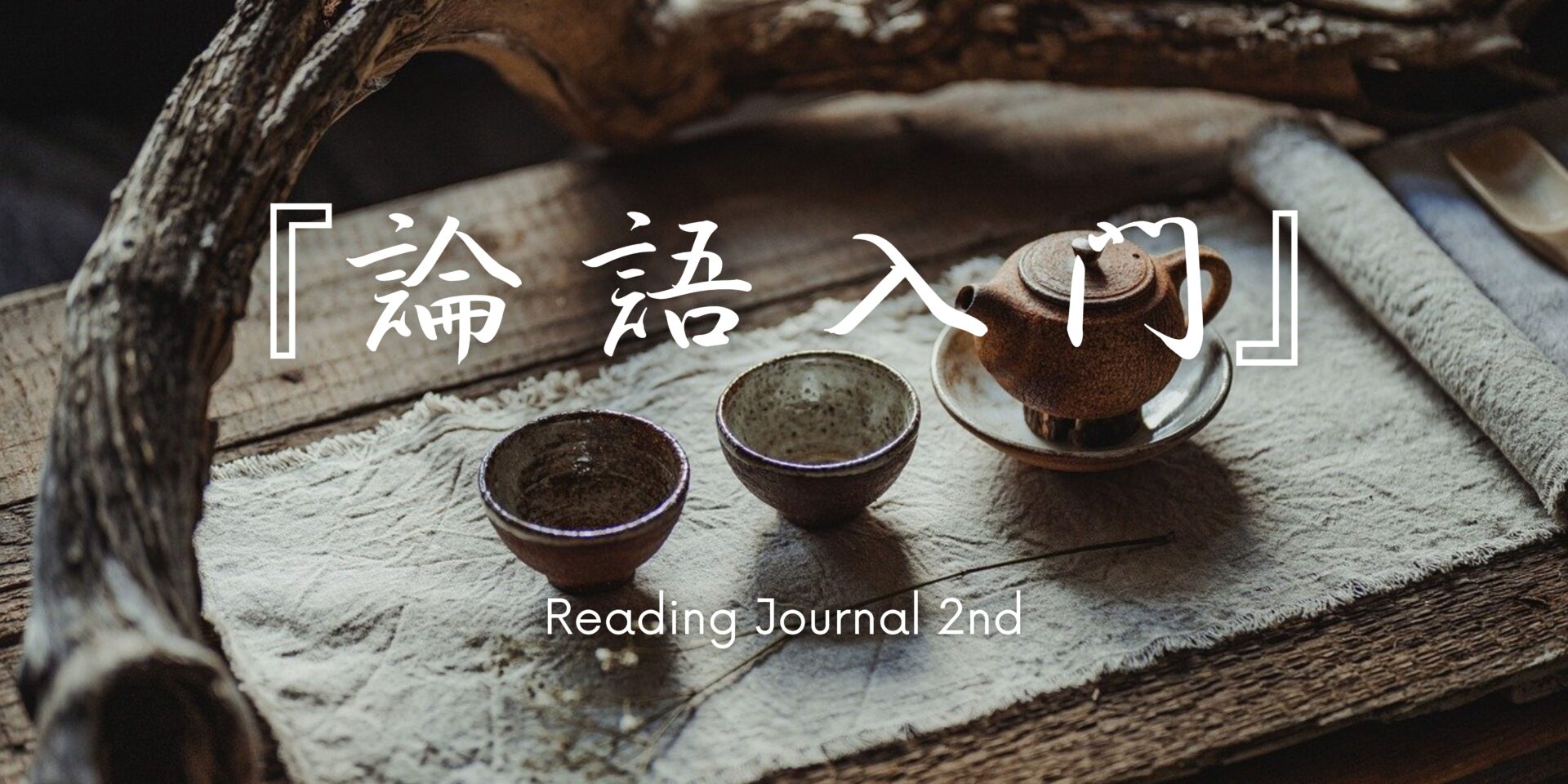


コメント