『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第六章 「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」 — 故事成句をあやつる人びと 1 耶律楚材と王陽明(後半)
今日のところは「第六章 山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」、「1 耶律楚材と王陽明」の”後半“である。”前半“では元王朝の話であったが、”後半“は明王朝の話である。それでは、読み始めよう。
明王朝の成立と退廃
明王朝を設立した洪武帝は、しだいに残酷な独裁者となり、次々と功臣を粛清した。そして光武帝が死去すると明は混乱し始める。洪武帝を継いだ健文帝は、各地の諸王(洪武帝の息子たち)のとりつぶしを図った。そのとき、燕王朱棣が挙兵し首都南京を陥落させ健文帝は生死不明となった(靖難の変)。そして朱棣が即位し永楽帝となる。
永楽帝は、モンゴル高原に遠征して明の領土を拡大し、鄭和をリーダーとする艦隊に世界各国をめぐる航海を行わせるなどした。
しかし、官僚を信用せず、宦官を重用する。永楽帝にはじまる宦官の重用が、明王朝衰退の最大の原因となった。
「江南第一風流才子」呉中の四才
このころ中央政局の混乱をよそに、商業が発展し、都市が空前の繁栄をとげ、社会は大きく変化した。こういう状況で江南の大都市蘇州に祝允明、唐寅、文徴明、徐禎卿からなる文人グループ「呉中の四才」があらわれる。
彼らは、書画詩文のいずれの分野においてもすぐれた才能を発揮し、自由な文人生活を送った。
彼らはいずれも高い教養を持っていたが科挙に合格しなかった。特に唐寅は、最終試験でカンニング事件に巻き込まれて落第し、受験資格を失ってしまう。唐寅は故郷の蘇州にもどり、「江南第一風流才子」という印を作り、注文に応じて詩文や書画をつくりその対価で、自立した文人として生き続けた。
宋代以来、長らく中国の士大夫知識人にとって、科挙に合格し高級官僚になることが唯一の理想的生き方でした。明代中期に至り、呉中の四才のように官僚志向をふりきり、自由で自立した生き方を求める人々が出現したことは、画期的な出来事だったといえます。(抜粋)
「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」王陽明と陽明学
このころ哲学・思想界に「陽明学」の創始者王陽明が出現した。彼は科挙に合格し官界に入った。軍事的才能もすぐれ、最後は南京兵部尚書(陸軍大臣)までになる。
陽明学は、朱子学とは異なり、「心即理(自分の心の中にある理を基本とする)」を唱えた。また、各人の「良知(天性の活力)」が完全に実現されることが知であるとする。
陽明学の基本理念「知行合一」は、良知が完全に実現される場合、認識と実践は当然、統合されることを指します。
やや難解ですが、要するに王陽明は理や知を外物に求めるだけでなく、あくまでも人の心の中に求めようとするのです。(抜粋)
王陽明は、「素の数頃にして源無き塘水為らんよりは、数尺にして源有る井水の生意窮まらざるもの為らんには若かず(水源のない広々としたため池の水であるよりは、水源からこんこんと水の湧きでる小さな井戸水であったほうがいい)」や「山中の賊の破るは易く、心中の賊を破るは難し」などの言葉を残した。
陽明学の文学への影響
明末となるとこの陽明学が文学にも影響を及ぼす。王陽明の流れをくむ李卓吾は、俗文学の『水滸伝』と戯曲の『西廂記』を絶賛し『論語』や『孟子』を批判し、それまでの文学感を逆転させた。そしてこのような流れから中国のシェークスピアと呼ばれる大戯曲家湯顕祖、「三言」と称される三部の白話短編小説集の編者馮夢龍などの多くの文学者が出た。
明の滅亡
明王朝は、無能な皇帝とそれを包囲する宦官や悪徳官僚のため衰退し、李自成率いる反乱軍により滅亡する。そしてこの李自成を追い払った満州族の清軍が駐豪全土を制圧した。
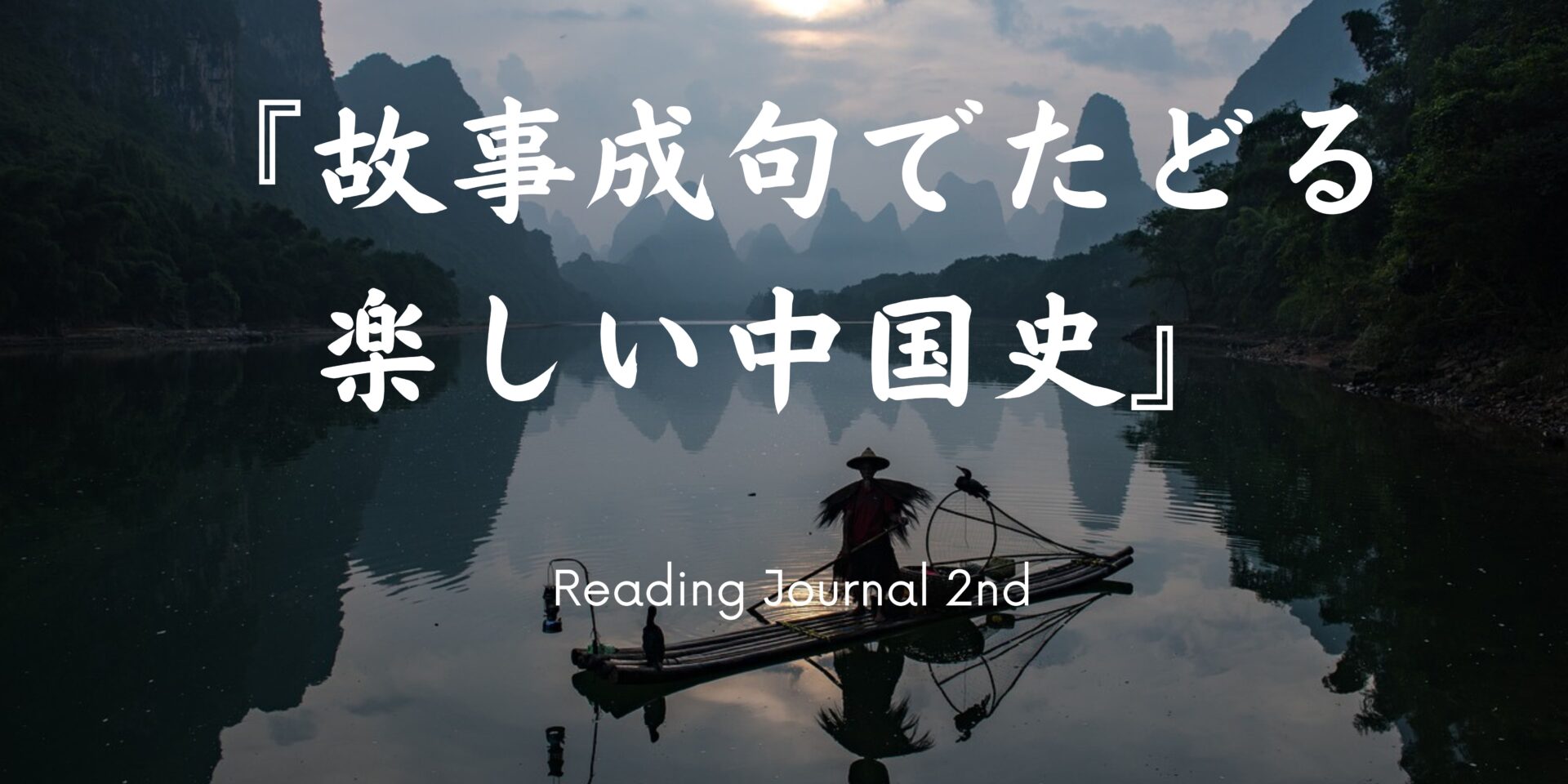


コメント