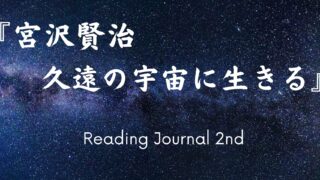 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd [読書日誌]『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』
北川前肇 [全14回]
この本は、宮沢賢治の一生やその作品を、健治の信仰であった法華経から解き明かそうとするものである。著者の北川は、小学校卒業後仏門に入り、題目を唱える生活の中、健治の作品に触れ健治の生き方を問い続けていた人である。『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』より
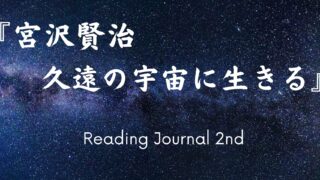 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd