 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd [読書日誌]『フランス 26の街の物語』
池上 英洋 著
西洋食文化の歴史にその名を刻んでいるフランソワ・ヴァテルはシャンティイ城の料理人だった。彼はコンデ公の「食の総監」にまで上り詰めるが、その完ぺき主義のために精神を病んでしまう。そしてここシャンティイ城が悲劇の場所となる。:『フランス 26の街の物語』より
 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 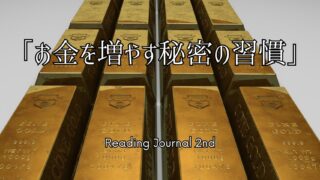 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 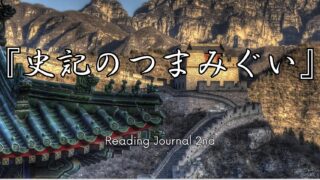 Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 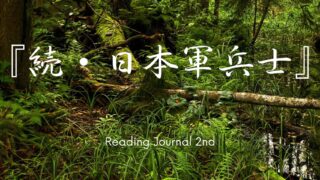 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 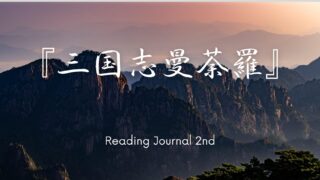 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 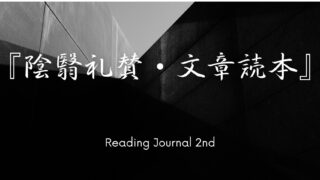 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 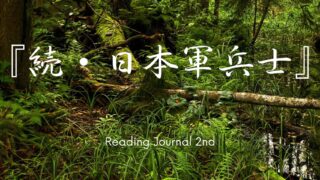 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 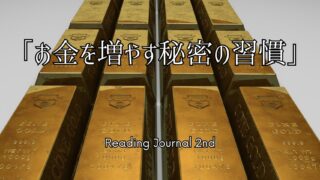 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 1st
Reading Journal 1st  Reading Journal 1st
Reading Journal 1st