『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 「呉越同舟」 — 乱世の生きざま 1 春秋五覇(後半)
今日のところは、「第二章 呉越同舟」の「1 春秋五覇」の”その2”である。”その1“では、斉の桓公、晋の文王について語られた。今日のところ”その2“では、「斉桓・晋文」に次いで春秋第三の覇者となった、楚の荘王と宗の襄公、秦の穆公についてである。このうち後者の二人、襄公、と穆公については、前の三者ほど実力がなく小覇者くらいの位置づけである。それでは読み始めよう。
「鳴かず飛ばず」楚の荘王
「斉桓・晋文」に次いで春秋第三の覇者となったのが、楚の荘王である。この荘王は、即位したものの三年の間、酒と美女にうつつを抜かしていた。
業を煮やした臣下が、「ある鳥が岡にいますが、三年、飛ばず鳴かずでした。これはいったい何という鳥でしょうか」と謎をかけると、荘王はこう答えました。「三年飛ばないが、飛べば天に至るだろう。三年鳴かないが、鳴けば人を驚かせるだろう」。時期を待っているのだと、豪語したわけです。(抜粋)
この故事より、なりをひそめ、パッとしないさまを「鳴かず飛ばず」というようになった。
そして、やがて荘王は素行を改めて、内政を充実させ祖父や父から受け継いだ北進を開始し、東周の首都洛陽まで軍勢を進める。
荘王が洛陽まで、兵を進めると、東周の定王は、王孫満を使者として荘王のところへ使わす。そのとき荘王は、使者の王孫満に、天子の象徴の九つの鼎の大小軽重を尋ね、九鼎を持ち帰ると恫喝した。すると王孫満は、
「周の徳はおとろえたといっても、天命はまだ改まっていません。周の軽重はまだ問うべきではありません」と答えました。(抜粋)
荘王は、むなしく帰路につくしかなかった。
この故事により「鼎の軽重を問う」という言葉が「ある地位についている人の実力を疑い、その地位から追い落とそうとする」という場合に使われるようになった。
その後、荘王は晋軍と邲での激戦(「邲の戦い」)に勝ち、春秋の覇者となった。
これには、へぇ~~、と思った。鳴かず飛ばずで・・・そのうち忘れられちゃうんじゃなくって、やがて立派になっちゃうんだね。つくジーも「鳴かず飛ばず作戦」でいこうかな?え?サボってるだけじゃん!って、そのとおりです。(つくジー)
「宗襄の仁」宗の襄公
ここまでの、斉の桓公、晋の文公、楚の荘王の三人は、正真正銘の覇者であったが、あとの宗の襄公と秦の穆公は、三者ほどの実力がないため、覇者に準ずるという位置づけとなる。
宗の襄公は、楚の成公との戦いで泓水を挟んで対峙していたとき、相手が布陣し終わるのを待って攻撃を仕掛けた。そして宗は大敗し、襄公も負傷してしまった。
しかし襄公は「敵が布陣を完了しないうちに攻撃はかけないものだ」と言い、自分の不明を後悔する気配もなりませんでした。(抜粋)
この故事により「人に無用な情をかけること」を意味する「宗襄の仁」という言葉が生れた。
「怨み骨髄に徹す」晋の文公と秦の穆公
もう一人の小覇者は秦の穆公である。穆公は、内政・外交を整え国力を増強する。そして、穆公は晋の文公と協力関係を築いたが、文公が亡くなるとその協力関係は崩れた。穆公は文公の後継者襄公の率いる晋軍と闘い、大敗を喫した。そのとき秦の三人の将軍は捕えられて晋に連行された。
このとき、晋の文公の婦人(秦の穆公の娘)が、「穆公はこの三人の将軍を、怨み骨髄に入るほど憎んでいます。どうか彼らをこのまま秦に帰国させ、穆公に思う存分、煮殺すようにさせてください」と嘆願しました。(抜粋)
晋の襄公がこれを聞き入れて、三人を変えたところ穆公は彼らを許して罪を問わなかった。
この故事が元になり、人を徹底的に恨むことを「怨み骨髄に徹す」というようになった。
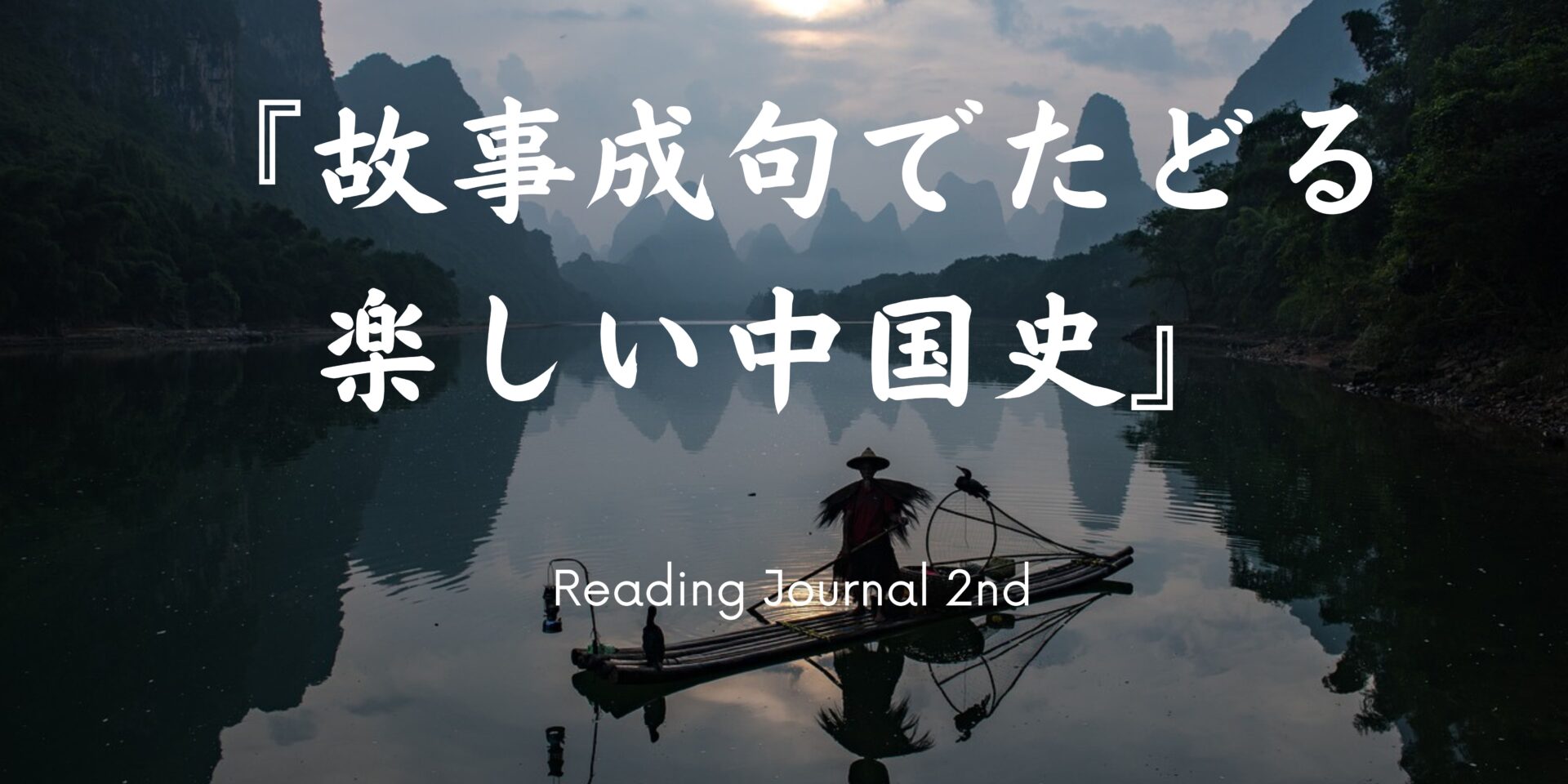


コメント