『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 みんながしています
今日のところは「第5章 みんながしています」である。伝統的経済学では、「合理的な人(ホモエコノカミクス)」を仮定しているが、実際には、バイアスにより合理的な判断をすることができない。本章では、そのようなバイアスとして「利他性」「互恵性」「社会選好」「社会規範」が取り扱われる。そして私たちは「限定的合理性」しかないために起こる「フレーミング効果」や「ヒューリスティックス」について説明されている。それでは読み始めよう。
利他性と互恵性
まず、自分の思いや好みと一致している行動をとっている人を、経済学では「合理的な人」と呼んでいる。しかし普通の人は「現在バイアス」があるためこのような行動がとれない。つまり合理的でないことになる。
そして伝統的経済が仮定している合理的な人は、自分の好みを最大にすることを目標に行動するとしていて、つまり利己的な人となる。
しかし、多くの人は自分の利益にも他人の幸福にも関心があるのが普通であり、つまり「利他性」を持っている。行動経済学では、人が喜んだ姿を見て自分も幸せになるケースを「純粋な利他性」、(受け取った人が喜んでいるかと関係なく)人に良いことをすること自体がうれしいケースを「不純な利他性」と呼ぶ。また、「利他性」と近い概念に、良いことをしてくれた人に良いことをしてあげたいという「互恵性」がある。
社会的選好と社会規範
このようなに私たちが持っている「利他性」や「互恵性」のような性質を「社会的選好」といい、つまり私たちは自分以外のことも考えて行動する。また、私たちは「社会規範」つまり他の人がどのように行動するかも判断基準と知る。
この「社会規範」は「損失回避」と似ていて、「社会規範」を参照点とするためそれからずれた行動については強い損失を感じる。またこの「社会規範」と似たものに「ピア効果」(第7章)や「相対所得仮説」がある。
「相対所得仮説」とは、周りの人の所得がどれくらいかによって私たちの満足度が変わってくるという特性のことです。(抜粋)
「他利性」や「互恵性」に加えて「不平等回避」という特性もある。つまり自分だけ損をすることや得をすることはつらいということである。
限定的合理性とフレーミング効果
私たちは合理的な意思決定を行おうとしても、さまざまなバイアスにより、多くの場合は直観的な意思決定をしてしまう。これは、私たちが限定的な合理性しか持ち合わせないということである。そしてこのような特性を「限定合理性」という。
限定合理性の中には「フレーミング効果」と呼ばれるものがある。これは、情報の伝達の仕方によって意思決定が違ってくる現象である。
ヒューリスティックス
私たちの計算能力や認知能力には限界があるため、時として近道の直感を用いて判断することがある。このような特性を「ヒューリスティックス」と呼ぶ。つまり「ヒューリスティックス」とは「合理的な推論によらずに直観を用いて発見的に判断する方法」である。
このヒューリスティックスには、
- 代表性ヒューリスティックス:「何かが特別なカテゴリーに属する確率という属性」を「ないかが特別なカテゴリーの代表的なもの類似しているか」と置き換えて判断すること
- 利用可能性ヒューリスティックス:ある事象の「確率(目標属性)」を、その状況がどれくらい頭に浮かびやすいかという「ヒューリスティックス属性」と置き換えてしまうこと
- アンカリング:一番初めに目にした数字(初期値)をアンカーといい、その初期値が修正されず判断に影響すること
がある。
ここで、「属性」とは、人や事柄が持っている性質や特性のことである。また、私たちが判断に用いる対象の属性を、より簡単に心に浮かぶ別の属性に置き換えることを「属性代替え」とい呼ぶが、代表性ヒューリスティックスや利用可能性ヒューリスティックスは、属性代替の特殊ケースと言える。
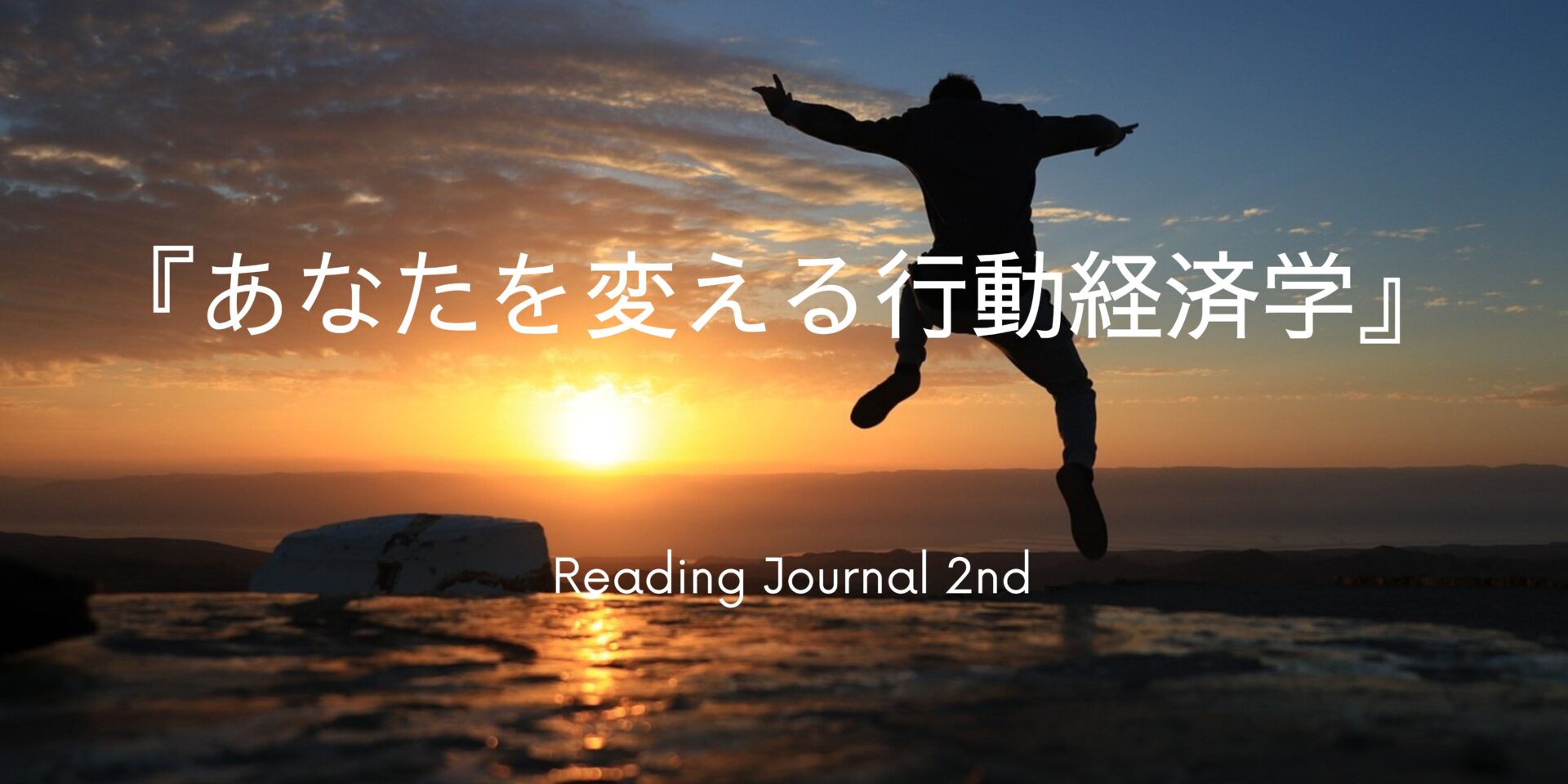


コメント