『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 「もったいない」を考える
今日のところは「第1章 「もったいない」を考える」である。第1章のテーマは「サンクコスト」( = 埋没費用)である。ここでは、レンタルビデオの例、キャベツの廃棄の例、そして福沢諭吉の例などを示し、「サンクコスト」の問題について説明している。結論は「サンクコスト」は忘れるに限るというものだろうか?それでは、読み始めよう。
「サンクコスト」( = 埋没費用)
既に払ってしまって取り返すことができない費用のことを経済学では「サンクコスト」(=埋没費用)という。このようなに既に支払ってしまって取り返すことのできない費用について合理的な意思決定ができない場合が多い。(このように取り返せないものを取り返せると思って、合理的でない選択をしがちであることを「サンクコストの誤謬」という。
しかし、過去のことは変えることができないので将来のことを考えることが大切である。
多くの人が間違った直観的意思決定をしてしまうのは、「サンクコスト」への対応を間違えているからと言っていいかもしれません。お金だけでなく、もう取り返せないものはあきらめることが大事です。(抜粋)
福沢諭吉の教訓
この「サンクコスト」への対応として、著者は福沢諭吉の話をとりあげている。(福沢諭吉著『福翁自伝』より
福沢諭吉は、適塾でオランダ語を勉強していたが、横浜に行ってみると外国人と言葉が通じないし、看板の文字も読めなかった。横浜にいる外国人はイギリス人だったのである。福沢諭吉は、この数年間死に物狂いで勉強してオランダ語の本を読むことで勉強したが、それが今は何にもならないと落胆してしまう。しかしここで福沢諭吉は、ここで落胆している場合ではないと思い返し、今度は英語が必要になると考え、横浜から帰った翌日から、英語を習い始めた。
しかし、多くの蘭学者は、それでは、数年間刻苦勉強したオランダ語が役に立たなくなってしまう、と考えて英語の勉強に切り替えることができなかった。つまり「サンクコスト」にとらわれてしまっていた。
そして、英語の勉強を始めた福沢諭吉は、オランダ語と英語の文法はほぼ同じで、オランダ語の勉強はまったく無駄というわけではないことに気が付いた。
ここで著者は、この話に二つの教訓があるとしている。
- 福沢諭吉はオランダ語の勉強が「サンクコスト」であることを正しく認識し、過去(オランダ語の勉強)にしがみつくのではなく、将来(英語の勉強)に切り替えたこと
- オランダ語の勉強がまったく無駄でなかったこと。すなわち、埋没してしまったように見えることも、まったく無駄でなく、すべて「埋没」しているわけではないこと
である。
ここで取り上げられている『福翁自伝』は、前に読んだ辰濃和男の『文章の書き方』で、分かりやすい文の例として取り上げられていたのを思い出しました(ココ参照)。(つくじ-)
関連図書:
福沢諭吉(著)『現代語訳 福翁自伝』、筑摩書房(ちくま新書)、2011年
辰濃 和男(著)「文章の書き方」 岩波書店(岩波新書) 1994年
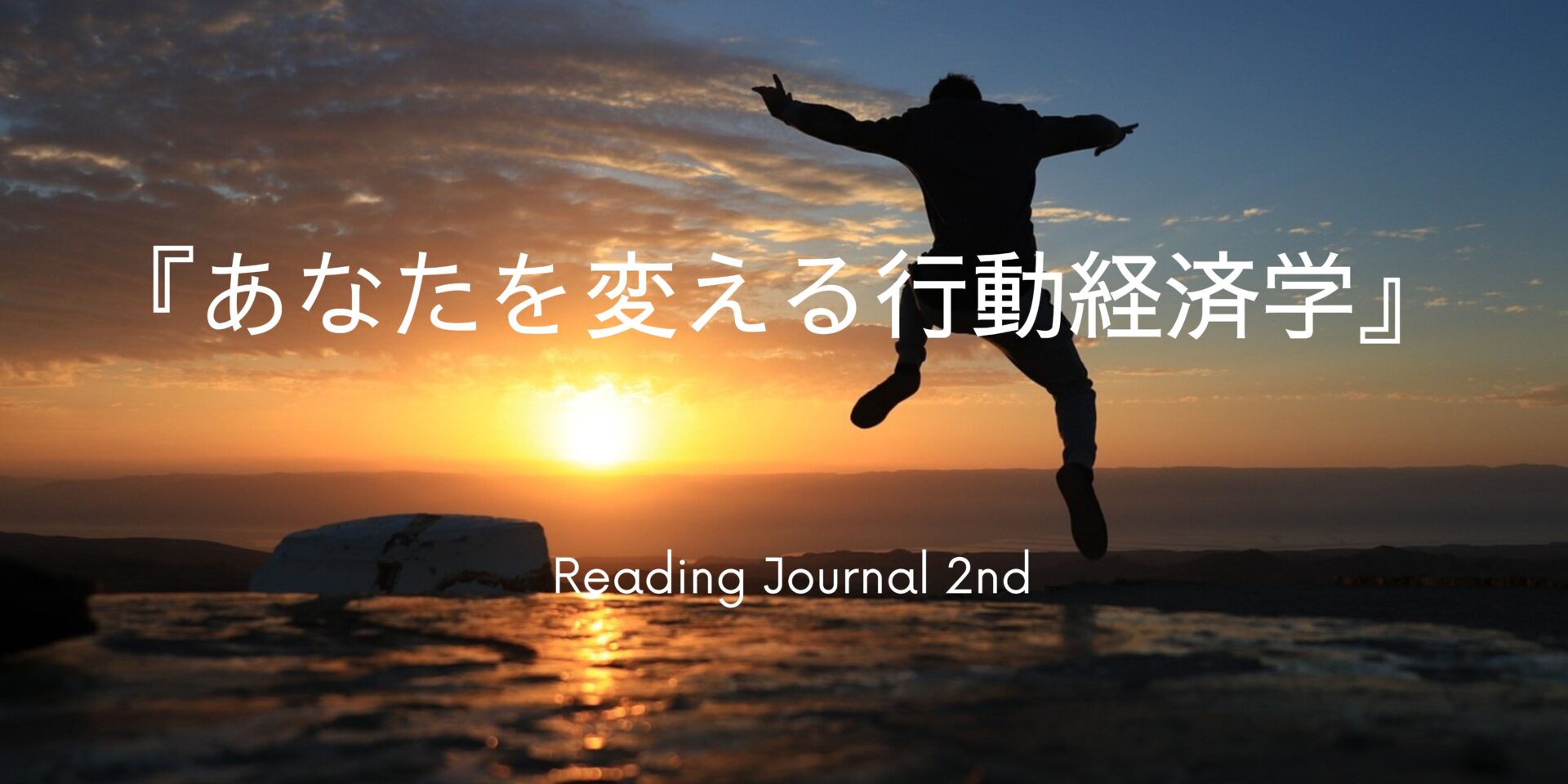


コメント