『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
3 相づちを打つ
カウンセラーの相づち
プロのカウンセラーの聞き方の特徴は、「相づち」を打つことである。普通の会話やインタビューでも相づちを入れることはあるが、カウンセラーのように入れることはない。
それは、普通の会話では、相手が話しているとき、聞き手は次の質問や自分の話すことを考えていて「耳は聞くモード」だが「頭は話すモード」になっているからである。耳も頭も聞くモードになっていないと、相づちは打てない。
逆に考えると、相づちを打つことは、「話をよく聞いているよ」と相手に伝える最良のコミュニケーションである。人は言葉よりも態度を基準にして判断するためである。人は言葉と態度は逆のメッセージを発することが出来るが、態度と態度で同時に反対のメッセージを発することはできないので、人は態度で相手を判断する。
そのため相づちは肯定的なものになる。そして話がはずむためには、聞き手が話し手を肯定的に受け取ることが大切である。
カウンセラーの姿勢として重要なものに、相手の話を肯定的にとらえるということがあります。これは専門的に「受容」といわれています。(抜粋)
この「受容」とは、聞き手が話し手になんでも賛成しないといけないということではなく、「相手の言ったことを肯定的にとらえる」ということである。聞き手の意見と関係なく「単に相手がそう思っている」ということを客観的にとらえるということである。
これは相手の話が自分から遠い場合は、自分の意見と関係なく肯定的に客観的に聞けるが、自分と関係してくるとなかなか冷静になれず、自分の感情を押さえて相手の話に合わせてもどこか態度にでてしまう。
プロのカウンセラーの場合は、自他の区別をつけて相手の話を自分の意見をださずに肯定的に聞いていて、相手のから直接非難されるような言葉を発せられても、「そうだね」と相づちが打てるように鍛えられている。話が聞けなってくると、相づちの代わりに「しかし」とか「けれども」とか「でも」のような逆説の助詞が出てくるようになる。
相手の話を肯定的に聞けているかどうかを確かめるのが、相づちであり、相手の話が聴けなくなってくると相づちも打てなくなる。
誰でも自分の相づちを注意深くチェックしているだけで、聞き上手になれます。相手の話を黙って聞くのではなく、必ず相づちを入れながら聞いていると、話しては話しやすいものです。(抜粋)
4 相づちの種類は豊かに
プロのカウンセラーの聞く技術は、「相づち」に支えられている。そのためプロのカウンセラーは、種類豊かに、工夫した相づちをもっている。
聞き上手になるためには、まずこの相づちの種類を豊かにする必要がある。
肯定の相づち
まず「ハイ」と「エエ」であるが、それぞれにレパートリーとして
- 「ハイ」・・・・「ハイ」「ハイそうですね」「ハイハイ」「ハイ・ハイ」「ハアイ」「ハア~」「ハイ?」
- 「エエ」・・・・「エエ」「エエ・エエ」「エ・え?」「エエそう」
- 「そう」・・・・「そう」「そうそう」「そうよ」「そうよ、そう」
- 「なるほど」・・・「なるほど」「なるほどなるほど」「なるほどね」「なるほどねぇ」「なるほどなぁ」
などがある。「ハイ」と「エエ」は相手の年齢や上下関係などで使い分ける。また「そう」は相手が肯定してほしい時に便利で、「なるほど」はより肯定してほしい時に使える。
否定的な(ニュアンスを加味した)相づち
相づちは、本来肯定的なものなので「否定の相づち」といっても、完全に否定しているわけではない。使い方と相手により、否定的なニュアンスを含んだ微妙な相づちである。
この種の相づちには、「フン」がある。この「フン」は、強く言うと強い肯定の相づちになるが、「ふんふん⤴」と語尾を上げると、相手をバカにしたように受け取られる危険性がある。しかし「ふんふん」と落ち着いた調子で相づちをいれると、よく聞いているというサインになる。また、目上の人に「ふんふん」と相づちをいれると、相手に見下されたように感じるので注意が必要である。
「うそ~」という相づち
若者の相づちに「うそ~」というのがある。「本当のことを言っているのに、嘘とは、なんだ」と思った人は常識のある年齢の人である。
相づちの高等テクニックとしての「繰り返し」
相づちの高等テクニックとして「繰り返し」がある。これは相手の言ったことを繰返すことであるが、ただ相手の言ったことをダラダラ繰り返すとバカにされたと取られるので、テクニックが必要である。
繰り返しの相づちは「明快に」「短く」「要点をつかんで」「相手の使った言葉で」ということが大切なポイントである。具体的には相手の話からセレクトしたキーワードを繰返せばよい。ここで、相手の言葉どおりに繰り返すのがポイントである。相手の言葉を変えて繰り返した場合、そのような意図がなくとも間違って解釈されてコミュニケーションに齟齬が生じる可能性がある。
「わかる」という相づちには注意
プロの聞き手が使わないのに、ふつうの人が良く使う相づちに「わかる」「わかるわ」というのがある。わかるという相づちは、聞き手が自分なりにわかったという、自己満足の相づちであり、話し手の反発をまねくことがある。
臨床心理士は、人間の心の解釈を仮説的にわかることもあるが、実際には「人間の心は究極的にはわからない」ということを良く知っている。
だからこそ、プロの聞き手なのです。会ってすぐに相手の人間性と心を見抜けるくらいなら、聞く必要はないでしょう。ていねいに相手の話を聞くのは、わからないからです。「わかる」と思っている聞き手が相手から反発され、「わからない」と思って一生懸命に聞く人が、相手から理解してもらえたと思われるという逆説は、おもしろいでしょう。(抜粋)
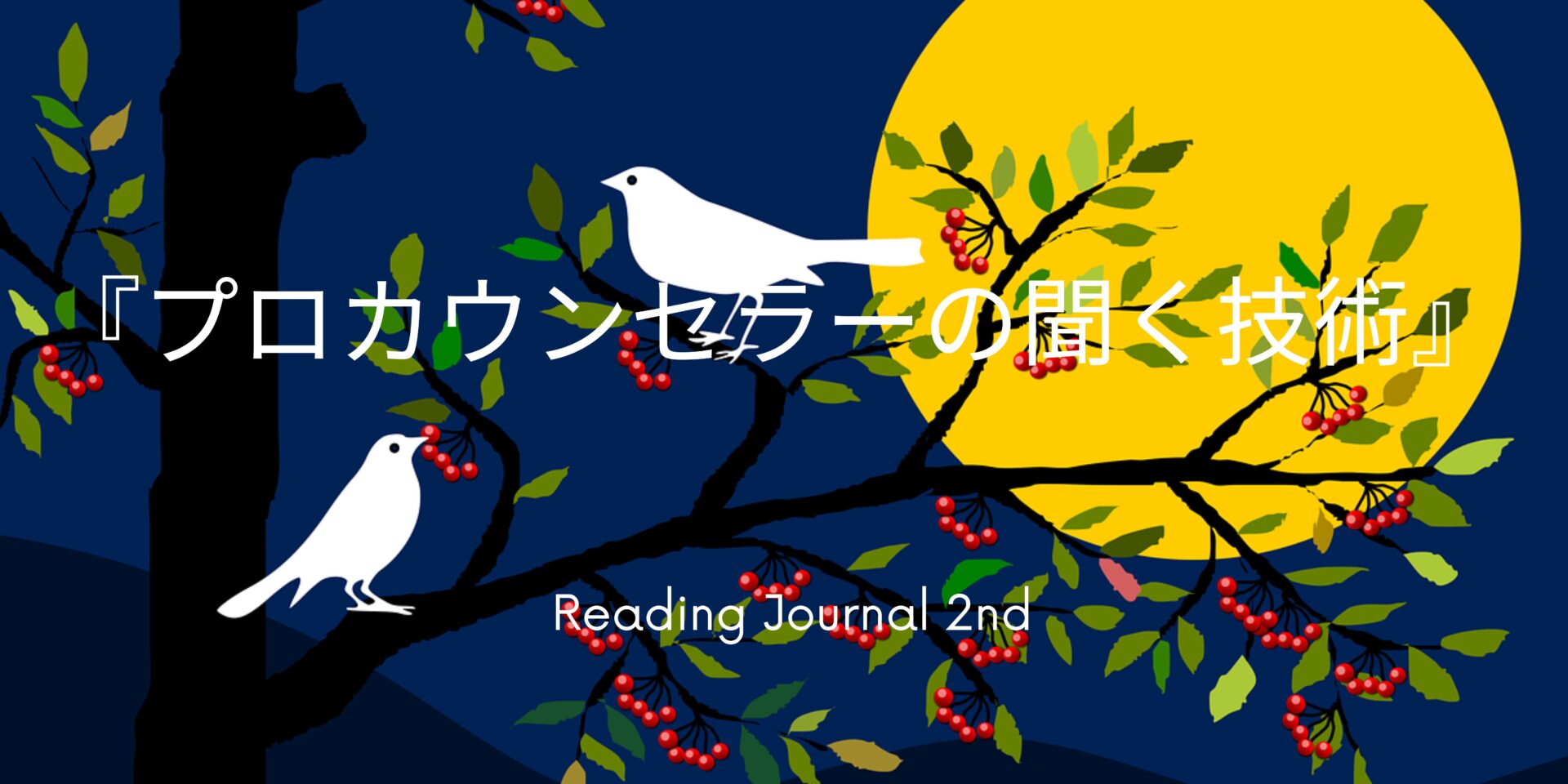


コメント