『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤 陽子著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
1章 日清戦争 列強にとってなにが最も大切だったか
本章から本編に入る。第1章では、日清戦争までの時代についてである。
教科書などで説明している江戸時代末期から明治時代初めまでの歴史では、アヘン戦争とアロー戦争での清国の敗退と欧米列強の圧力による日本の開国、近代化という流れで書かれていて、ややもすると「落ちる中国、伸びる日本」あるいは「弱い中国、強い日本」という紋切り型の概念で理解されている。
しかし、このようなコントラストは、日清戦争頃までの明治時代や辛亥革命以降の大正時代には当てはまらない。
この章では、このような視点ではなく別の視点から考える。それは、アメリカのウォーレン・F・キンボーンにより述べられた視点で、
日本と中国は、東アジアでの日中両国の関係にて、どちらがリードするか、そのことをめぐって長いこと競争をしてきた国であって、そのリーダーシップめぐる競争という点では、軍事衝突などは、文化、経済、社会、そして知識人の思想やイデオロギーをめぐる競争の、ほんの一側面に過ぎないとの見方です。(抜粋)
著者は、中国を日本が侵略するという文脈でなく、そのような見方では、みえにくくなる、
十九世紀から二十世紀前半における中国の文化的、社会的、経済的戦略を、日本側のそれと比較しながら見ることで、日中関係を語りたいわけです。(抜粋)
としている。
ここから、本節の話題「列強にとってなにが最も大切だったか」ということを、日本と中国について述べている。
まずこの時期の列強が何を日本に望んだのかについて考察する。列強が日本に望んだことは貿易で利益を上げるために、
「価格や産出量などを安定的に維持することができて、貿易相手の国にたいしては、どの国に対しても等しい条件で対応してくれる国」(抜粋)
になってもらうことである。そのために必要な法律、商法と民法の成立を望んだ。列強は、不平等条約の廃止を求めたとき、それでは商法と民法の編纂を条件とている。
ところが中国はこれとは違う道を歩んだ。この時点で中国は、「華夷秩序(かいちつじょ)」(朝貢体制)という列強にとってうまみのある資産を持っていた。華夷秩序とは、文化の中心である中国が、その徳によって生ずる周辺国との属的秩序の事である。
この「華夷秩序」により、列強は安南(ベトナム)や朝鮮半島の李王朝などと貿易をする際に、清国に話をつければ無用な争いを避けることができた、これは、非常に安価な安全装置だった。
このような日中の異なった体制は、一八八〇年代くらいまでは両方ありえ、日中は、共に八〇年代に成長を遂げている。しかし、この後、競合という側面が強まる。このことを次節以降で述べられている。

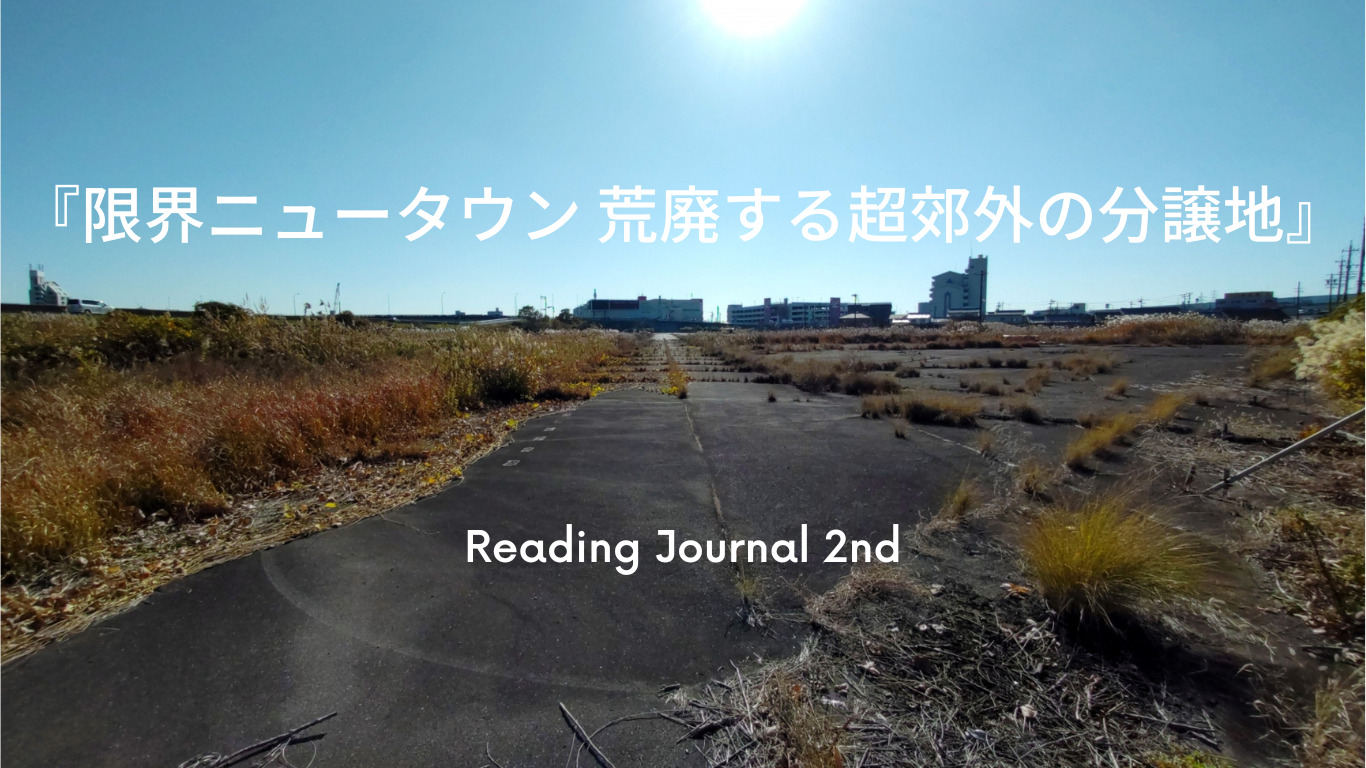
コメント