『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 弟子たちとの交わり(その4) — 2 大いなる弟子たち — 子路 「由や果」、純情な熱血漢
今日のところは、「第三章 弟子たちのとの交わり」(その4)である。“その2”では、顔回、“その3”では、子貢が取り上げられた。今日のところは、孔子の三人の高弟の三人目、「子路」である。それでは読み始めよう。
子路 – 「由や果」、純情な熱血漢
No.86
子路聞くこと有りて、未だ之れを行うこと能わざれば、唯だ聞くこと有るを恐る。(公冶長第五)(抜粋)
子路は先生(孔子)から何か教えを聞き、まだそれが実行できないうちに、次の教えを聞くことをひたすらこわがった。(抜粋)
子路は直情径行の快男子であった。孔子を崇拝する粗利は、孔子から何か教示を受けるとすぐに実行しようと努力し、それが達成できないうちに、次の教示を受けること恐れた。これは、両方とも中途半端になることをいやがったからである。
著者は、子路はやや粗暴なところもあるが、誰にも愛される人物であり、孔子も大変かわいがったと言っている。
子路は派手ないでたちで、肩で風を切って歩いていた遊侠であった。最初は孔子をバカにしていたが、次第に圧倒され心酔するようになった。孔子の弟子となった後は、純情一筋に孔子に寄り添った。
No.87
顔淵・季路侍す。子曰く、盍ぞ各おの爾の志を言わざる。子路曰く、願わくは車馬衣裘、朋友と共にし、之れを敝りて憾み無からん。顔淵曰く、願わくは善を伐ること無からん。労を施すこと無からん。子路曰く、願わくは子の志を聞かん。子曰く、老者は之れに安んじ、朋友は之れを信じ、少者は之れを懐く。(公冶長第五)(抜粋)
顔淵(顔回)と季路(子路)がお側にいたとき、先生がいわれた。「どうだ、めいめい自分の理想を言ってごらん」。子路が言った。「できたら、馬車や上等の衣装や毛皮を友だちと共有し、それがいたんでも気に病まないようでありたいと思います」。顔淵はいった。「善い事をしても自慢せず、いやなことを他人に押しつけないようにしたいと思います」。子路は行った。「先生の理想を聞かせてください」。先生は言われた。「老人からは安心して頼られ、友だちには信頼され、若い者からは慕われというふうでありたい」。(抜粋)
顔回と子路が孔子と一緒にいた時に、孔子が二人に理想を聞いたという話である。
ここで著者は、顔回、子路、そして孔子の理想の弁を比べて
孔子の答えは率直にして目配りがきき、熱意の塊のような子路、面白みに欠ける顔回の答えと比べて、はるかに円熟し、穏やかな味わいがあることに、改めて感心させられる。(抜粋)
と評している。
No.88
季康子問う、仲由は、政に従わしむ可きか。子曰く、由や果。政に従うに於いてか何か有らん。曰く、賜は政に従わしむ可きか。曰く、賜や達。政に従うに於いてか何か有らん。曰く、求は政に従わしむ可きか。曰く、求は芸。政に従うに於いてか何か有らん。(雍也第六)(抜粋)
季康子がたずねた。「仲由(子路)は政治にたずさわらせることができますか」。先生は言われた。「仲由は果断です。政治にたずさわることなど、何でもありません」。(季康子は)たずねた。「賜(子貢)は政治にたずさわらせることができますか」。(先生は)言われた。「賜は達識(ものの道理に広く通じること)です。政治にたずさわることなど、何でもありません」。またたずねた。「求(冉求)は政治にたずさわらせることができますか」。言われた。「求は多才です。政治にたずさわることなど、何でもありません」。(抜粋)
この条は、季康子が孔子の高弟である子路、子貢、冉求のそれぞれに政治能力があるかと問うたとき、孔子がそれぞれの長所をあげて答えたという話である。
すなわち子路は果断、子貢は達識、冉求は多才として、政治をこなす能力があると断言している。
No.89 子 南子を見る
子 南子を見る。子路 説ばず。夫子 之れに矢いて曰く、予れ否らざる所の者は、天 之れを厭てん、天 之れを厭てん。(雍也第六)(抜粋)
先生が南子と会われた。子路は不機嫌であった。すると先生は子路に誓って言われた。「もし私のしたことが道にはずれていたならば、天が私を見捨てるだろう、天が私を見捨てるだろう」。(抜粋)
この条は『論語』で唯一、女性が登場する条である。
この南子は、衛の霊公の夫人だが、結婚後も口実をもとの恋人を呼び寄せるような悪女であった。そして彼女が原因で後年、衛に内乱が起こりその内乱で子路も戦死してしまう。
この条は、孔子が衛に身を寄せたとき、霊公と親しく交際するものは夫人である南子に会見するのが習いであると、南子に求められた。そして子路は、孔子がその悪女に会いに行ったことを怒っている。そして、それをみた孔子が、疚しいところは何もないと誓ったのがこの条である。
この条は小説の題材にもなっていて、谷崎潤一郎の短編小説『麒麟』はこの話をもとにしていて、中島敦の『弟子』にもこの話が見えている。
No.90
子曰く、敝れたる縕袍を衣、狐貉を衣る者と立ちて、而も恥じざる者は、其れ由なるか。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「ぼろぼろの上衣をはおり、上等の狐やむじなの毛皮のコートを着た者と並んで立っても、堂々と恥ずかしがらない者がいるとすれば、それは子路だろう。(抜粋)
この条は、服装など問題にしない武骨な子路を賞賛した言葉である。
孔子は、No.51でも「士 道に志して、而も悪衣悪食を恥ずる者は、未だ与に議るに足らざる也」と言っている。子路はこのような孔子の言葉を体現している。
No.91
子曰く、由の瑟、奚ん為れぞ丘の門に於いてせん。門人 子路を敬せず。子曰く、由や堂に升れり。未だ室に入らざる也。(先進第十一)(抜粋)
先生は言われた。「由(子路)の瑟の弾きかたなら、なにも私の家でひかなくてもよさそうだ」。(これを聞いた)門弟たちが子路に敬意をはらわなくなった。先生は言われた。「由は座敷には上がっているのだが、奥の間にまだ入れないだけなのだ」。(抜粋)
孔子門下では、音楽が重視されていた。しかし、武骨な子路は優雅に瑟を弾くことを不得手としていた。それを孔子がからかったのだが、これを聞いた門弟が子路に敬意を払わなくなったため、孔子は、子路を弁護している。
No.92
子路問う、聞けば斯ち諸を行わんか。子曰く、父兄在す有り。之れを如何ぞ其れ聞けば斯ち之れを行わん。冉有問う、聞けば斯ち諸を行わんか。子曰く、聞けば斯ち之れを行え。公西華曰く、由や問う、聞けば斯ち諸を行わんかと。子曰く、父兄在す有りと。求や問う、聞けば斯ち諸を行わんかと。子曰く、聞けば斯ち之れを行えと。赤や惑う、敢えて問う。子曰く、求や退く、故に之れを進む。由や人を兼ぬ、故に之れを退く。(先進十一)(抜粋)
子路がたずねた。「何か聞いたらすぐに実行に移しますか」。先生は言われた。「お父さんやお兄さんがいらっしゃる以上、どうしてすぐに実行に移せようか」。冉有がたずねた。「何か聞けばすぐに実行に移しますか」。先生は言われた。「聞いたらすぐに実行に移しなさい」。公西華がたずねた。「由(子路)」が「何か聞いたらすぐに実行に移しますか」とおたずねすると、先生は「お父さんやお兄さんがいらっしゃる以上、どうしてすぐに実行に移せようか」とおっしゃいました。求(冉有)が「何か聞いたらすぐに実行に移しますか」とおたずねすると、先生は「聞いたらすぐに実行に移しなさい」とおっしゃいました。赤にはわかりませんので、そのわけをおたずねしたいと思います」。先生は言われた。「求は引っ込み思案だ。だから進めたのだ。由はでしゃばりだ。だから抑えたのだ」。(抜粋)
子路と冉有への同じ問いに対して、孔子がそれぞれの性格に合わせた返事をした。このように孔子は画一的な教育はせず、弟子の個性や性格に合わせた教え方をした。
また、子路と冉有は、No88にも登場している。
No.93 子路宿諾無
子曰く、片言以て獄えを折む可き者は、其れ由なるか。子路宿諾無し。(顔淵第十二)(抜粋)
先生は言われた「(被告・原告の)一方の言い分を聞いただけで、正しい裁きができる者は由(子路)だろうな」。子路は宵越しの承諾はしなかった。(抜粋)
この条は、前半が孔子の言葉で、後半の「子路宿諾無し」は、論語の編者の言葉だとされる。子路は一旦承諾したことは、必ずその日のうちに実行し、翌日まで先延ばしすることはなかったということである。著者は、これを子路の心に脈打つ爽快な侠の精神への賛辞であると評している。
No.94
子路曰く、衛の君 子を待ちて政を為さば、子 将に奚れをか先にせん。子曰く、必ずや名を正さんか。子路曰く、是れ有る哉、子の迂なるや。奚ぞ其れ正さん。子曰く、野なる哉 由や。君子は其の知らざる所に於いて、蓋闕如たり。名正しからざれば、則ち言順わず。言順わざれば、則ち事成らず。事成らざれば。則ち礼楽興らず。礼楽興らざれば、則ち刑罰中らず。刑罰中らざれば、則ち民 手足を措く所無し。故に君子は之れに名づくれば、必ず言う可き也。之れを言えば、必ず行う可き也。君子は其の言に於いて、苟しくも所無きのみ。(子路第十三)(抜粋)
子路が言った。「もし衛の君主が先生を厚遇して政治をまかされたならば、先生は何をまっさきになされますか」。先生は言われた。「きっと名称を正すことからはじめるだろう」。子路が言った。「そんなことがありますか。先生ときたらまったく迂遠ですね。どうして正そうとされるのですか」。先生は言われた。「野蛮だね、おまえは。君子は自分のわからないことには、黙っているものだ(黙ってなさい)。名称が正確でなければ、言語が混乱する。言語が混乱すれば、政治が混乱する。政治が混乱すれば、礼や楽による文化が盛んにならない。礼や楽による文化が盛んにならなければ、裁判が公平でなくなる。裁判が公平でないと、民衆は身のおきいどころがなくなる。だから君子は名称をつける場合は、必ず適切な言語であらわすようにし、これを口にするときは、必ず実行しようとする。君子は言ったことに対し、いいかげんであることはないのだ」。(抜粋)
この条は、衛の霊公の孫の出公が君主だったころの話とされる。
ここで、著者は、No.89で触れている最後について触れている。No.89の会見の後、霊公の息子で皇太子だった蒯聵が、身持ちの悪い、霊公の夫人南子を殺害しようとして失敗し国外に逃亡するという事件が勃発した。その後が蒯聵の息子の出公が即位した。
しかし蒯聵は晋のバックアップを受け、十数年にわたり戦闘が繰り返された。蒯聵は姉の孔伯姫と結託しクーデターを起こし、出公は国外に亡命する。
このクーデターの時、衛の役人になっていた子路は、緊急事態に駆け付け蒯聵の手の者に殺害された。
このとき、子路は冠の紐を断ち切られたが、「君子は死すとも冠は免がず」(『史記』仲尼弟子列伝)と、紐を結び直して絶命したという。この時六十三歳。いかにも一本気な子路らしい最期だった。孔子は衛で内乱がおこったこと知った瞬間、「嗟呼 由や死せり(ああ、由(子路)は死んだ)」と嘆いたという。(抜粋)
その後。蒯聵は、念願の君主の座を手に入れたが、在位三年にして、内憂外患により進退きわまり出奔し、出公が帰国した。
関連図書:谷崎潤一郎(著)『刺青 痴人の愛 麒麟 春琴抄』 、文藝春秋(文春文庫・現代日本文学館)、2021年
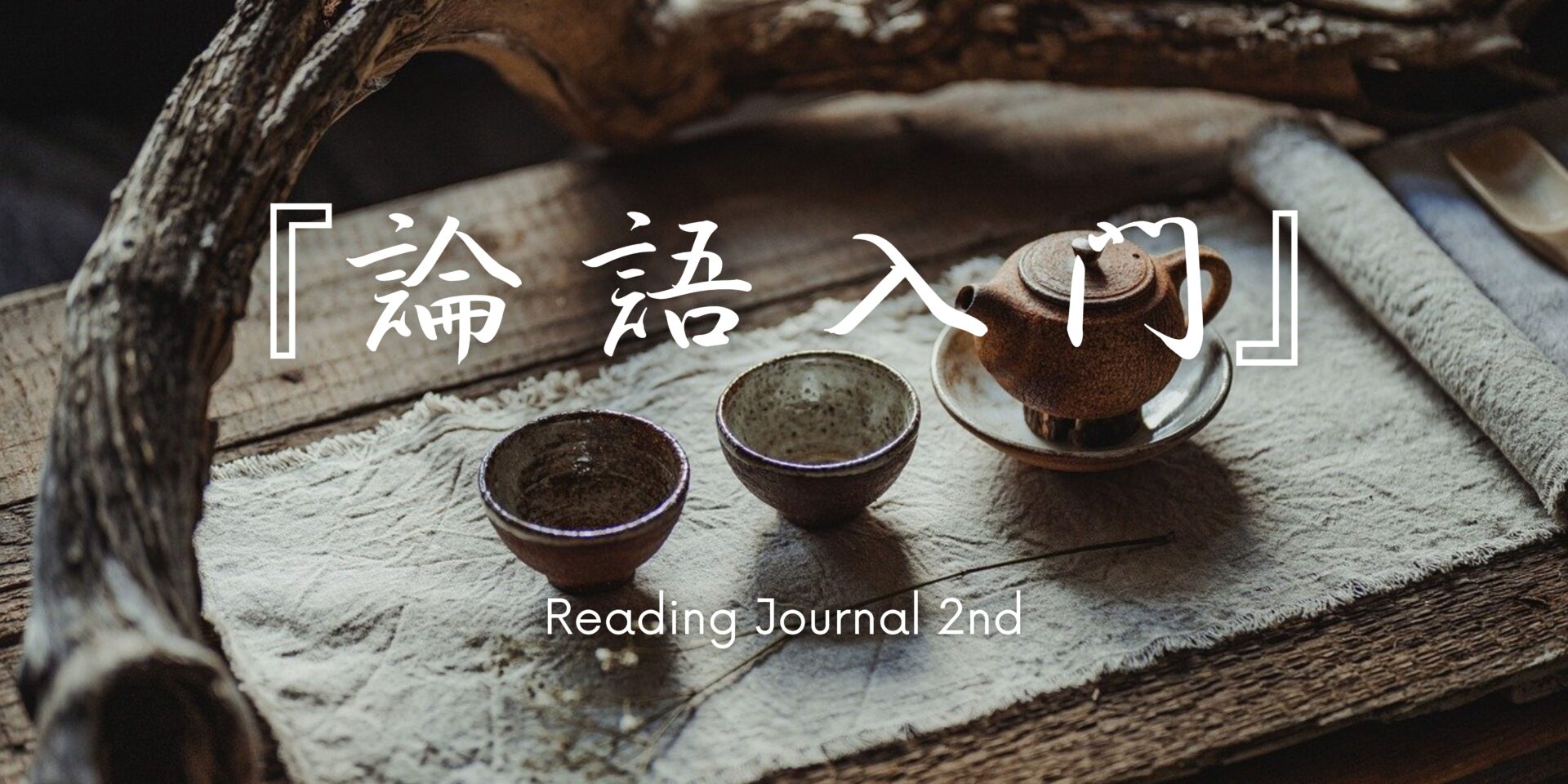


コメント