『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四部 読書の最終目標 14 シントピカル読書 — 読書の四レベル(後半)
今日のところは、「第四部 読書の最終目標」「14 シントピカル読書」の“後半”である。“前半”では、シントピカル読書における点検読書の役割とシントピカル読書の五つの段階について説明された。今日のところ“後半”は、シントピカル読書に関する様々な話題や実例、さらにシントピコンという参考書の使い方などである。そして最後に、シントピカル読書の手順のまとめがある。それでは、読み始めよう。
客観性の必要性
ある問題について十分に分析すると、主な論点がはっきりしてくる。論考では、意見が一致する場合にも、大抵は反対意見が伴う。論考で意見の一致が多ければ、それは真実に近いと推定されるが、多くの意見があり一致しない場合は、真実がどうであるかは、わからない。
ここで著者は、シントピカル読書では、質問の答えや主題の最終解決(つまり一致した意見)を目的にしているのではないと注意している。
重要な論点に関する意見が、真実かまちがいかをきめようとすれば、独断的になり、弁証法的ではなくなる。それでは、シントピカル読書の失われてしまう。(抜粋)
シントピカル読書で重要なことは、絶対の客観性と公正さである。それは「弁証法的客観性」という言葉で言い表される。つまり、あらゆる側面から公平にものを見るようにする、ことが必要である。
シントピカル読書の実例 — 進歩の観念について
ここで著者は、「進歩の観念」を題材にしてシントピカル読書の実例を示している。
まず点検読書では、集めた多数の書物(450点)を数回にわたり点検読書を行い、適切な資料を選ぶ。選ばれた資料から進歩の論考も極めて混沌としていることがわかる。
次に行うことは、「進歩」という用語の使い方をきめることである。この用語は、著者により微妙な違いがあり、「改善」という意を含むものと含まない者があることがわかった。この「改善」という意を含まない「進歩」を使う著者は少数派であるため、「進歩」という用語は「改善」の意を含むものとして使うことにする。
ここで第一の質問は「歴史に進歩はあるか、歴史的な変化は、人類の状態を改善するか」である。この答えは、(一)はい、(二)いいえ、(三)わからない、のいずれかである。
そして、この答えが集まって論争を構成する。それらを「全体論争」と呼ぶ。そして、進歩に改善の意を含む著者が参加する「特殊論争」がある。この「特殊論争」についての問いを三つあげると
- 進歩は必然的なものか、それとも他のできごとに付随して起こるものか
- 進歩は際限なくつづくものか、それともいつかは終了、あるいは停滞するものか
- 人間の作った制度だけでなく、人間の本性にも進歩はあるか
となる。
最後に、進歩がみられる分野についても六つの論点がある。
- 知識の進歩
- 科学技術の進歩
- 経済的進歩
- 政治的進歩
- 道徳的進歩
- 芸術における進歩
である。
これは改善派の著者だけの論点だが、改善はであるからにはすべてを否定することはない。
以上、進歩という主題について、分析のやりかたを説明した。これで、主題に関する論考に含まれる論点を分析するとはどういうことかわかったと思う。すなわち、それは、シントピカルに読む読者は、常に、こうした作業を行わなければならない。(抜粋)
シントピコンとその利用法
シントピカル読書にはパラドックス(ココ参照)がある。つまり「同一主題について二冊以上の本を読むからには、はじめに、主題そのものがはっきりしなければならない。ところが、まず読んでみなければ、主題がはっきりしない」というものである。
そこで必要になるのが、膨大な数の主題について、何を見ればよいかと示す参考書である。(抜粋)
そのような参考書として「シントピコン」がある。この「シントピコン」は、「西洋名著全集」の項目別索引で、三〇〇〇にのぼる項目について、その全集で扱われている参照ページが書かれている。
このシントピコンは、ある問題について研究しようとしている学者や読書家の予備調査の手間を大いに省く。そして、初心者にとっては、さらに役立つ手ほどきや示唆を与える。
同一主題について二冊以上の本を読む読者には『シントピコン』が役に立つと信じている。そこで、このレベルの読書を「シントピカル読書」と名づけたのである。(抜粋)
シントピカル読書の原理
ここで著者は、シントピカル読書に対する主な批判に対して答えている。
用語の使い方
最初の批判は、「著者の用語の使い方は、神聖なものだから、読者の決めた用語の使い方を著者に押しつけるのはよくない」というものである。
これに対して著者は、「ある考えを説明するのに一通りの表現以外にはないとするのは、まちがっている」と答えている。これは「ある用語が翻訳できない」と同じ意味であり、ある用語を翻訳するのは困難であるということは、もっともなことである。しかし、困難と不可能を混同してはならない。
著者の間の時間的、空間的隔たりと個性の問題
二つ目の批判は、「著者同士には時間的、空間的隔たりがあり、またそれぞれ個性がある。そのような著者が集まって論じるのは不可能である」というものである。
これに対して著者は、この批判は「古代の書物の著者と現代の人が、たとえ通訳がいてもお互い理解し合えるわけがない」ということであるとし、その気になればお互いに理解しあえることに自信があると言っている。
そして、その通訳こそが「シンピカル読書」であると言っている。
論じかたと文体の問題
最後の批判は、「時間的、空間的に隔たった著者同士が論争するため「主題」よりも「論じ方」の方が重要である」というものである。
これに対して著者は、「そのようなものにこだわる反対派は、人間のあいだのには理性的なコミュニケーションなどなくて、あるのは感情的なコミュニケーションだけだと言いたいのだろう」とし、人間の「コミュニケーションには、感情的なもの以上に内容がある」、としている。
翻訳が可能であり、書物が互いに「語り合う」ことができ、人間に、客観的、理性的なコミュニケーションができるならば、シントピカル読書は可能なのである。(抜粋)
シントピカル読書のまとめ
最後にシントピカル読書のまとめが書かれている。
シントピカル読書の準備作業 --- 研究分野の調査
一、図書館の目録、他人の助言、書物についている文献一覧表などを利用して、主題に関する文献表を作成する。
二、文献表の書物を全部点検して、どれが主題に密接な関連をもつかを調べ、また主題の観念を明確につかむ。
(注意 これらの二つの作業は、厳密に言えば、必ずしもこの順番にするわけではない。つまり、この二つは、相互に影響し合うものだからである。)
シントピカル読書 --- 準備作業で集めた文献を用いて
第一段階
準備作業で関連書とした書物を点検し、もっとも関連の深い箇所を発見する。
第二段階
主題について、特定の著者に偏らない用語の使い方をきめ、著者に折り合いをつけさせる。
第三段階
一連の質問をして、どの著者にも偏らない命題をたてる。この質問には、大部分の著者から答えを期待できるようなものでなければならない。しかし、実際には、著者が、その質問に表立って答えていないこともある。
第四段階
さまざまな質問に対する著者の答えを整理して、論点を明確にする。あい対立する著者の論点は、必ずしも、はっきりした形で見つかるとは限らない。著者の他の見解から答えを推測することもある。
第五段階
主題を、できるだけ多角的に理解できるように、質問と論点を整理し、論考を分析する。一般的な論点を扱ってから、特殊な論点に移る。各論点がどのように関連しているかを、明確にすること。
(注意 弁証論的な公平さと客観性とを、全過程を通じてもちつづけることが望ましい。そのために、ある論点に関して、ある著者の見解を解釈するとき、必ず、その著者の文章から原文を引用して添えなければならない)
(抜粋)
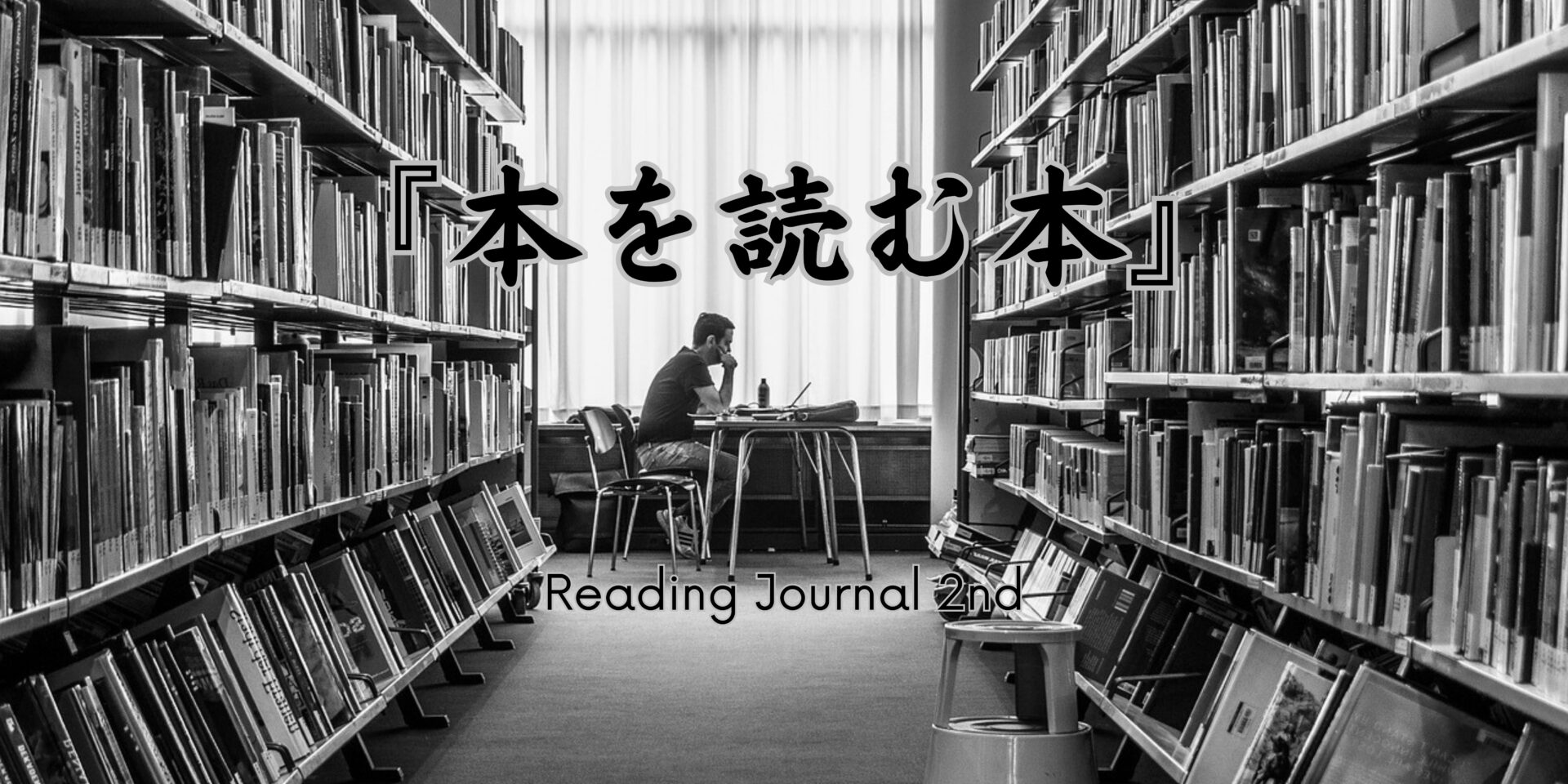

-1-120x68.jpg)
コメント