『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 さらなる高度な本読み(その4)
今日のところは「第5章 さらなる高度な本読み」の“その4”である。“その1”、“その2”、“その3”に続き、ここでは「関連読み」・「並行読み」、そして本書全体のまとめとして「おわりに」が置かれている。
「関連読み」・「並行読み」とは、異なる分野の本の共通性に注目して関連させながら、時に同時に読む技術である。「おわりに」では、本を読むことの意義とは、思想を自分の中に再構成して、それを未来に生かすためであると著者は主張している。それでは読み始めよう。
「関連読み」
知識や思想を、より大きな構造の中に位置づけることは、その分野内部だけでなく、他の分野の知識と結び付けて理解することが重要である。
「関連読み」とは、異なる分野の知識を統合していく読み方である。それには、それぞれの分野の本をしっかりと「詳細読み」をして理解し、それらの本に共通している要素について考える必要がある。
この「共通している要素」には「問題の共通性」「手法の共通性」「概念の共通性」がある。
これらの共通性をきっかけにして、複数の「異なる分野に属する知識や思想」を関連づけていこうと考えるのが、ここでいう「関連読み」である。(抜粋)
具体的には、「これはどこかで似たような概念(手法、問題)だぞ」と直感が訪れるのを待ち、その直感が来たときには、しっかりと読書ノートにメモする。そして読書ノートを頼りにその共通性を検証するという作業となる。
「並行読み」
また、共通していると考えられる概念や問題、手法があると思われる複数の本を、同時期に読んでいくことを「並行読み」という。並行読みは、一歩踏み込んだ「関連読み」である。この「並行読み」も「通読-詳細読み」の順に行うが、複数の本を同時期に平行して読みつつ、その「共通性」「相違性」に着目していく。
「おわりに」
本章の最後「おわりに」では、この本全体のまとめとして、「本を読むことの意義」とについて著者の考えが示されている。
本は何度か読み終え、自分の目標を達すると、日常的にはその本に戻ることはない。しかし、それで「本読みが終わるわけではありません」、その後日常生活の中で、その思想を使っていかなければならない。それが、思想を「生かす」ということである。
本読みとは、単に知識を吸収する行為を指す概念ではありません。テクストとして表現されたものを、現代に生きる人間が未来を創造するために再解釈し、再度その現代的意義を創造するという営みが「本読み」です。(抜粋)
長い歴史のある名著を未来に創造するための力に変換するためには読書という営みが欠かせない。
思想は技術と違い、それを蓄積するし使用するためには、個人個人がもう一度知識の蓄積過程をたどる必要がある。
すべての学問は、未来を紡ぐために存在しています。そして学問は、前述のように知識の蓄積を基礎としており、その中心に位置するのが「読む」という作業です。私たちは、読書することによって、知識を継承します。そして、継承し蓄積された知識を使うことによって、未来を構築していきます。未来は自然と訪れるものではなく、私たちが作り出していかなくてはならないものです。(抜粋)
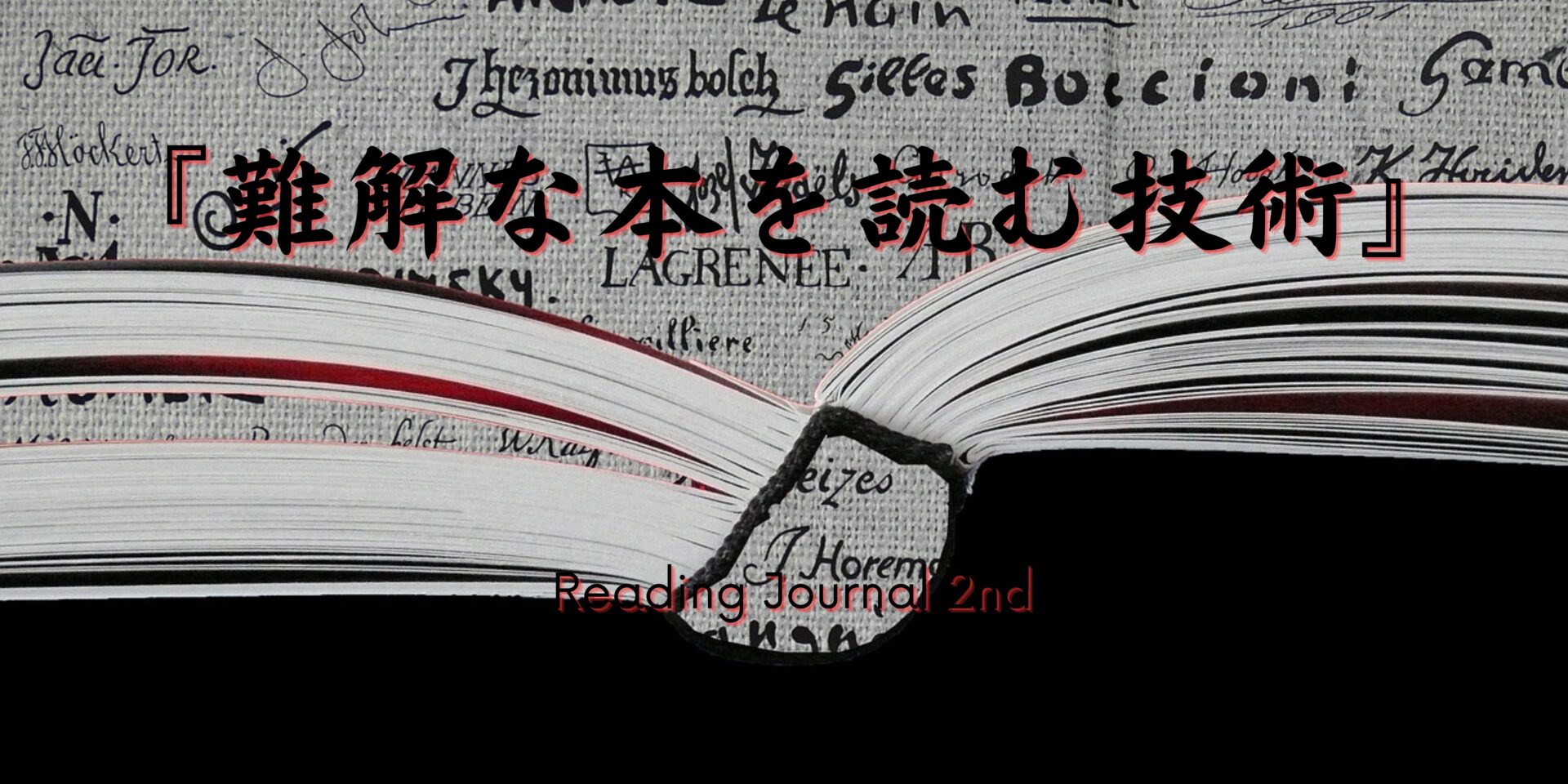


コメント