『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑨ 支援関係における7つの原則とコツ(後半)
今日のところは「⑨ 支援関係における7つの原則とコツ」“後半”である。”後半“は”前半”から続く、「支援関係における7つの原則とコツ」の4~7がある。そして、最後に、著者からの、最後のメッセージ「最後に」がある。それでは、ラストスパート!
原則4 あなたの言動のすべてが、人間関係の将来を決定づける介入である。
コツ⑨ 支援者としての役割の中で、人間関係を与えそうな衝撃によって、自分の言動をすべて評価すること。
ある状況における行動はすべて何らかのことを相手に伝えている。それは支援をせずに傍観者であっても同じである。
問題は、あなたが何をしようと、あるいは何をするまいと、いくつも合図を送っているということだ。あなたはその状況に介入しているのである。・・・・中略・・・・だから、どんな介入をするつもりかということに基づいて、どうコミュニケーションするかを選ぶべきである。(抜粋)
コツ⑩ あなたがクライアントなら、やはり自分であらゆる行動がメッセージを伝えていることを自覚すべきだ。
クライアントであっても、自分の行動について認識し、人間関係への影響を考える必要がある。
コツ⑪ フィードバックを与えるときは、現実の姿の記述にとどめるようにし、判断は最小限に抑えること。
支援者がクライアントに、いつ、どのようなフィードバックを与えるべきか。
まず、心理学の考え方から
- 正の強化を行えば成功する
- 負の強化や懲罰は、排除すべき行動に用いると効果的
であることが知られている。
また、フィードバックの理論から、最高のフィードバックは記述的なものと考えられる。
しかし、人間関係で生じる微妙な問題はこれらのガイドラインでは解決できない場合がある。
コツ⑫ 不適切な励ましは最小限にすること。
正の強化をもたらす「励まし」は、適切であると思われるかもしれないが、そうした励ましは相手を子ども扱いしたり、侮辱したりすることになる場合があるので、慎重にすべきである。
コツ⑬ 不適切な修正は最小限にすること。
間違いだと支援者が知っていることを、クライアントがしようとしている場合、
- 間違いを指摘する。(クライアントを罰している、侮辱を与えていると捉えられる)
- あとでその状況を再検討して持ち出す
- まったく放っておく
の、どの対処をすべきか。
もし、ネガティブな結果がすぐに生じるなら、すぐさま間違いを訂正する必要がある。しかし、間違いを指摘するよりもクライアントが自分で気づくのを待っていた方が良いことも多い。また、間違いを指摘してほしいかどうかクライアントに尋ねることも有益である。
原則5 効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる。
コツ⑭ 純粋な問いかけからつねに始めるべきである。
支援を求められたとき、反応する前にしばらく間をおいて、純粋な問いかけから始め、それからどんな方法で反応すべきかを考える。
コツ⑮ 求められた支援がどれほどお馴染みのものに聞こえても、これまで一度も聞いたことのない、まったく新しい要求だと考えよう。
求められた支援は、同じように思えても、必ず純粋な問いかけから始める必要がある。それは、同じように思える求めが、同じであるとは限らないからである。「純粋な問いかけ」の鍵は、「自分の無知に気づく」ことである。
原則6 問題を抱えている当事者はクライアントである。
コツ⑯ 関係を築くまでは、クライアントの話の内容に関心を示しすぎないように注意すること。
支援者が陥りやすい罠のひとつに、話の内容に惹かれることである。そのせいでプロセス・コンサルタントの役割にとどまり続けることが難しくなり、純粋な問いかけに専念することや、無知の領域に気づくことが困難になる。
コツ⑰ あなたがすべて知っていると思う問題とどれだけ似ているようでも、それは他人の問題であって、あなたのものではないことを絶えず思い出そう。
ある問題について他人がどう感じているか、支援者は理解できることはない。そのため、何が効果的かを決められるのは、結局クライアントだけである。支援者はそれを見つけられるようにクライアントを支援することしかできない。
クライアントから支援を求められた場合、クライアントが考える能力を妨げることなく、代替的解決法を幾つか提案することが必要である。
原則7 すべての答えを得ることはできない。
著者は、経験を積めば積むほど、自分は支援の方法を知っているという考え方になってしまい自分の経験から解決策を作り上げていることに気がつく。しかしそれは役にたたない助力である。そしてときには、正しい選択肢は「問題を分かち合う」ことだと学んだと言っている。
コツ⑱ 支援の対象となる問題を分かち合うこと。
誰かを支援すべき状況で、何をすべきか全くわからなくなることがある。そのときは、自分も行き詰っていることを相手に伝えることによって、クライアントが取組むべき問題は自分のものであることを自覚する。
問題を分かち合うことは、控えめな問いかけを明確に表すための別の方法なのだ。(抜粋)
最後に
この著書で私が行おうとしたのは、「支援」としてさまざまな社会的プロセスを見直すことである。これには、信頼を築くこと、協調、協力、リーダーシップ、変革マネージメントが含まれている。
こうしたことを実行する中で、蟻について語るときでも、鳥や人間について語るときでも、支援があらゆる社会生活の中心であると私は認識するようになった。
だから、われわれ支援者としてもっと有能になれれば、誰にとっても人生がよりよいものになると思われるのだ。(抜粋)
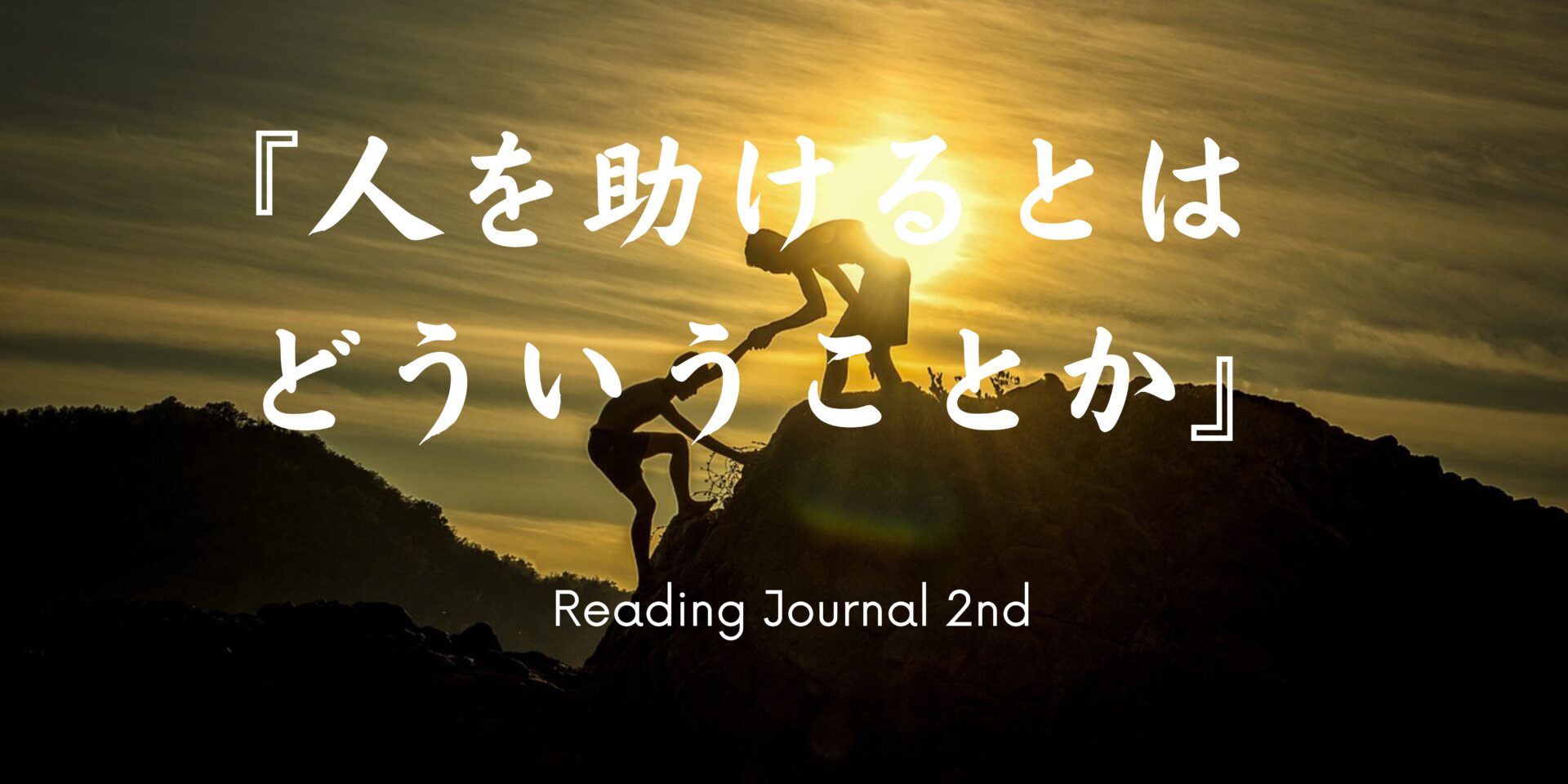


コメント