『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 ポピュリストが語ること(その4)
今日のところは、「第1章 ポピュリストが語ること」の“その4”である。これまで、ポピュリズムの定義は不明確で一般的なアプローチでは、袋小路に迷い込んでしまうことが示され、そして“その3”において、著者によるポピュリズムの定義が提示された。その定義では、ポピュリズムは「エリート批判」と「反多元主義」が必要とされた。今日のところ“その4”では、それを受けてポピュリストが何を代表するのかについて、論が進められる。それでは、読み始めよう。
ポピュリストは何を代表すると主張しているのか
ポピュリズムとその政策
ポピュリストは、代表という概念自体に反対してはいない。
正しい代表者正しい判断をして正しいことをするために正しい人民を代表する限り、ポピュリストは代表制と相性が良い。(抜粋)
ポピュリストは、単一の共通善なるものを人民が欲していて、彼らがそれを明快に実行できると提示する。その意味で、ポピュリストはある程度「ルソー主義者」と見える(ポピュリズムとルソー主義の間にある重大な違いは、後述される)。
そして、ポピュリストは、単一の共通善を常識により把握し正しい政策を導き出せると強調する。
このことより、なぜポピュリストが過度に単純化された政策課題の理念と結びつくことが多いかを、少なくとも部分的には説明してくれる。(抜粋)
ポピュリストの「人民」の概念
ポピュリストが政権を目指すときは、彼らにとって“正当”な競争相手などあり得ないとする。また政権にあるときは、“正当”な反対者も存在しない。
この点は、ポピュリストによる政治的代表の理解のきわめて重要な側面が関わってくる。つまり、彼らは、人民の意志の民主主義的な代表という考えを支持しているかのように見えるけども、実際には「真の人民」(たとえば、ジョージ・ウォレスが愛用した「真のアメリカ人」といった観念)という象徴的な(symbolic)代表に依拠しているのである。(抜粋)
ポピュリストの「人民」は、民主主義的手続きの外にある擬制的な存在であり、同質で道徳的に統一されたもので、その意思は民主主義国家での選挙結果に対抗しうるものである。
そのため、ポピュリストが選挙で失敗した場合は、自分たちが人民を代表していないからでなく、まだ「サイレント・マジョリティ」が声を上げていないからであると主張する。
このような政治形態や政治構造を超越した「人民」という概念は、戦間期に右翼の方理論家のカール・シュミットにより理論化されたものである。彼はファシズムの方が民主主義それ自体よりも民主主義の理想を実現できると主張することで、民主主義から非民主主義への概念上の架け橋を提供した。
そして、ハンス・ケルゼンのようなシュミットの敵対者は、議会の意志は人民の意志でなく、そもそも人民の意志を明確に認識することは不可能であると主張している。ケルゼンは、われわれが確認しうるものは、選挙結果だけであり「人民」という統一体は、結局のところ「メタ政治的な幻想」であると主張する。
人民全体は決して把握できないものだが、それを認識できるという主張は、つねに魅力的である。
ポピュリストの人民の意志とルソーの一般意思の違い
ここで著者は、少し前にあった「ポピュリズムとルソー主義の間にある重大な違い」を説明している。
まずルソーの一般意思の形成は「市民による実際の参加を必要とする」。これに対して、ポピュリストの適切な「人民意思」は「一般意思」ではなく「真のアイデンティティ」が決定をくだすもので“数の多さではない”、というものである。
これに対して、「ポピュリストはしばしばレファレンダムを要求するではないか」という反論がある。しかし著者は、ポピュリストがいうレファレンダムは、人民が継続的に政治に参加することを望んでいるわけではなく、彼らが真の人民の利害だとすでに認識していたものを追認するためのものである。
注)レファレンダム:政治に関する重要事項の可否を、議会の決定にゆだねるのではなく、直接国民の投票によって決める制度。[goo 辞書より]
参加なきポピュリズムというのは、全く筋の通った命題なのである。(抜粋)
彼らは、権力が可能な限り広範囲に広がる意味においては、反エリート主義者ではなく、自分たちが代表である限りは、代表制に賛成であり、自らが人民を指導するエリートである限りにおいてはエリート主義に意義はない。
ポピュリストにとって大事なのは、自らがエリートではないことではなく、エイリーとであっても、「彼らが人民の信頼を裏切ろうとせず、人民が明確に述べた政治的アジェンダを実際に忠実に遂行しようとすると彼らが約束すること」である。そのため、政権を握ったポピュリスト(次章で詳説)は、本質的に受動的な人民に対して、ある種の「世話人」のような態度を取ることは偶然ではない。
ポピュリストと人民との契約
われわれはいまや、なぜポピュリストがしばしば「人民」と「契約」を結ぶのかをよりよく理解できるだろう。(抜粋)
ポピュリストは、人民がひとつの声で語ることが可能で、政権獲得後にしなければならない「命令委任」的なものを想定している。
そしてこの「命令委任」は、代表者が自ら判断しなければならない「自由委任」とは反対のものである。そのため最初から議会などで議論などする必要性が無くなってしまう。
しかし、実のところ、命令委任は現実に人民から発せられたものでは断じてない。(抜粋)
人民が発したとする命令の詳細な指示はポピュリスト政治家による解釈に基づいている。このような、人民の意志が存在すると言い張ることは、民主主義のアカウンタビリティを弱める。
ポピュリストは、自分は人民の望んだことを実行した、上手くいっていない場合は、自分たちの落ち度ではない、と言い張ることができる。
「自由委任」の場合は、「命令委任」と違い、選挙期間(アカウンタビリティーのための期間)には、代表者が政治的判断を用いた責務を、代表者に課す。
ポピュリストは自由委任を非民主主義的と主張するが、そうではなく「自由委任」が民主主義的である。
代表の役割ついての解釈が記されている民主主義的な憲法が、命令委任でなく、自由委任を選択しているのは偶然ではないのである。(抜粋)
ここの「自由委任」と「命令委任」の議論はなるほどと思った。
つまりは、「命令委任」だと人民がこのようにしろと命令しているのだから議論の余地はないということになる。しかし「自由委任」の場合は、選挙で政策を聞き代表を選んだ後、その人たちが議論して政策を進める。そして選挙の時、その実績をもとに代表者つまりわれわれ国民が彼らの政治判断について判断して、責務を課すということですよね(つくジー)
ポピュリストは、反多元主義の信念に基づいて道徳化し、組織化されていない「人民」という概念に依拠するため、選挙結果が自分たちに不利だった場合は、その結果に反対する。そして、腐敗したエリートたちが人民を裏切るようなことを舞台裏でしていると主張する。
陰謀論は、ポピュリストのレトリックの奇妙な付属物などでない。陰謀論は、まさにポピュリズム自体のロジックに根差したものであり、ポピュリズムのロジックから生まれたものなのだ。(抜粋)
ポピュリズムの本を読んでいるんですが、ちょうど今「トランプ氏当選確実」ってニュースが出てまして・・・・アメリカもまた、ポピュリズムの国になっちゃうんですね。(つくジー)
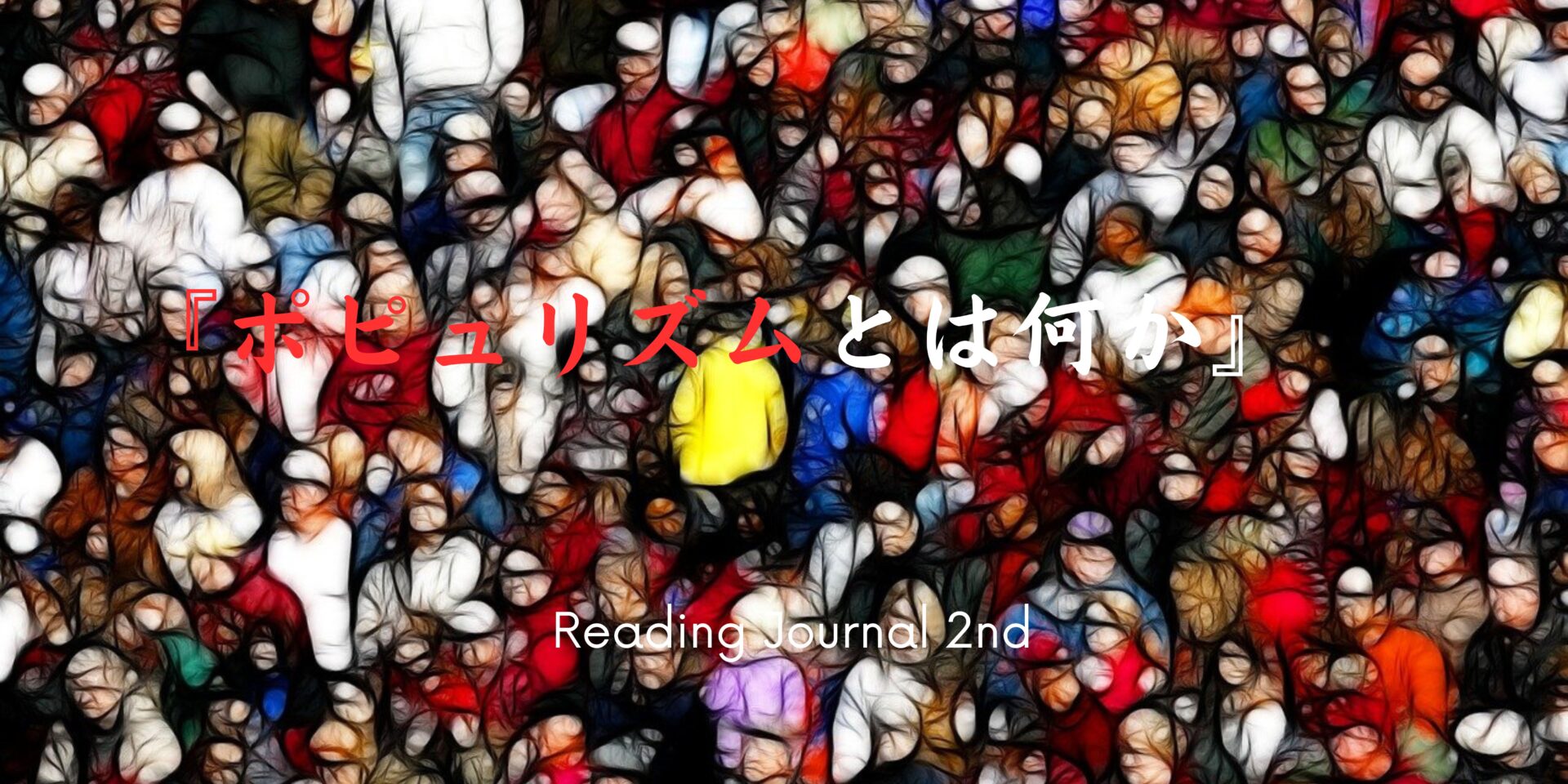

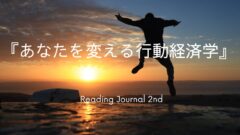
コメント