『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 ポピュリストが語ること(その1)
今日より「第一章 ポピュリストが語ること」が始まる。ポピュリズムという概念は、その歴史の最初から混乱していて明確に定義できるものではない。現在でもヨーロッパと北米では、その意味が大きく異なっている。本章では、ポピュリズムの理解のが袋小路になってしまうのかを示し、そして、それの内在したロジックを持つものと捉え、ポピュリズムがどのようなものかを探求している。なお、第一章は、5つにわけてまとめることにする。それでは読み始めよう。
ポピュリズムの歴史
一九六七年にロンドンで「ポピュリズムを定義する」ことを目的とした大きな学術会議が行われた。そこで、わかったことは多くの参加者がひとつの定義で合意できないということだった。そこではすでにあらゆる政治的不安が「ポピュリズム」について語る際に表明され、ポピュリズムという言葉が一見すると共通性のない政治現象に用いられている。
一九六〇年代末にまで遡ると、「ポピュリズム」は脱植民地化をめぐる論議、「小農主義」の将来の関する推測、(現在からすると驚くべきことに)共産党主義全般にも用いられていた。
ヨーロッパとアメリカにおけるポピュリズム
今日ではとくにヨーロッパにおいて、あらゆる種類の政治的不安が、ポピュリズという言葉であらわされている。一方でリベラル陣営では、大衆がポピュリズムやナショナリズムにとらわれますます非リベラルになっていくと見なし、他方では、民主主義の理論家たちは「リベラル・テクノクラシー」の興隆について懸念している。また、ポピュリズムは、一方では脅威とみなされるが、他方では、「人民」からあまりに乖離してしまった政治を矯正する力であるとも見られている。
アメリカ合衆国では、ポピュリズムは、真の平等主義的な左翼政治の理念と結びついていて、それは民主党のスタンスとは対立する。そのためポピュリスト的な批判者には民主党は中道的になってしまったと映る。アメリカでは「リベラル・ポピュリズム」という言葉が使われるが、ヨーロッパではその言葉は矛盾に聞こえる。ヨーロッパとアメリカでは、リベラリズムとポピュリズムも異なって理解されている。
北米では、「リベラル」は「社会民主主義的 (Social Democratic)」なものを意味しており、「ポピュリズム」はその非妥協的なバージョンであることを含意している。対照的にヨーロッパでは、ポピュリズムは決してリベラルと結びつけられない。[ヨーロッパにおいて]リベラリズムが意味するのは、多元主義の尊重とか、抑制と均衡(そして一般的には人民の意志による制約)を必然的に含んだ民主主義理解といったものなのだ。(抜粋)
二〇一六年アメリカ大統領選におけるポピュリズム
二〇一六年のアメリカ大統領選においては、ドナルド・トランプとバーニー・サンダースがどちらもポピュリストと呼ばれた。一方は右派のポピュリスト他方は左派のポピュリストである。両方とも市民の「怒り」「不満」「憤懣」によって駆り立てられた「反エスタブリッシュメント」であるという点では共通している。
ポピュリズムは政治的に論争的な概念であり、ヨーロッパでは「エスタブリッシュメントな人びと」が自分の対抗者をポピュリストと呼びたがる。そしてそのレッテルを貼られた対抗者も人民のために奉仕するポピュリストであると誇った。
私たちは、本当のポピュリストと単にポピュリストと烙印を押された人びとをどう区別したらよいか。われわれのほとんどの人が、左派であれ右派であれ、民主主義的であれ反民主主義的であれ、ポピュリストと呼ばれる可能性はないだろうか?
本章の内容について
本章では、混乱したポピュリズムの概念を扱うために3つの段階を踏む。最初にポピュリズム理解の共通したアプローチが、なぜ袋小路に陥るのかを示す。そのアプローチとは、
- 投票者の感覚に焦点を当てた社会心理学的な視座
- 特定の階級に着目する社会学的分析
- 政策提案の質の評価
である。
これらは、ポピュリズムとは何かを適切に扱うことができない。
次にポピュリズムを一つの体系的に整備された教義のようなものでなく、一組の明瞭な諸現象であり、ひとつの内的なロジックを持つと論じる。
このロジックを吟味するとポピュリズムが「エリート主義」になってしまった民主主義を矯正するものでは決してないことがわかる。エリートから無視された「サイレント・マジョリティ」を、選挙で選ばれた政治家と闘わせることで 民主主義により近づくというのは幻想である。
ポピュリズムは、近代の代表制民主主義の永続的な影のようなものであり、不断の危険である。その特徴に自覚的であることは、われわれが実際に生きている民主主義諸国の特徴—そして、ある程度はその欠点も—理解するのにも有益だろう。(抜粋)
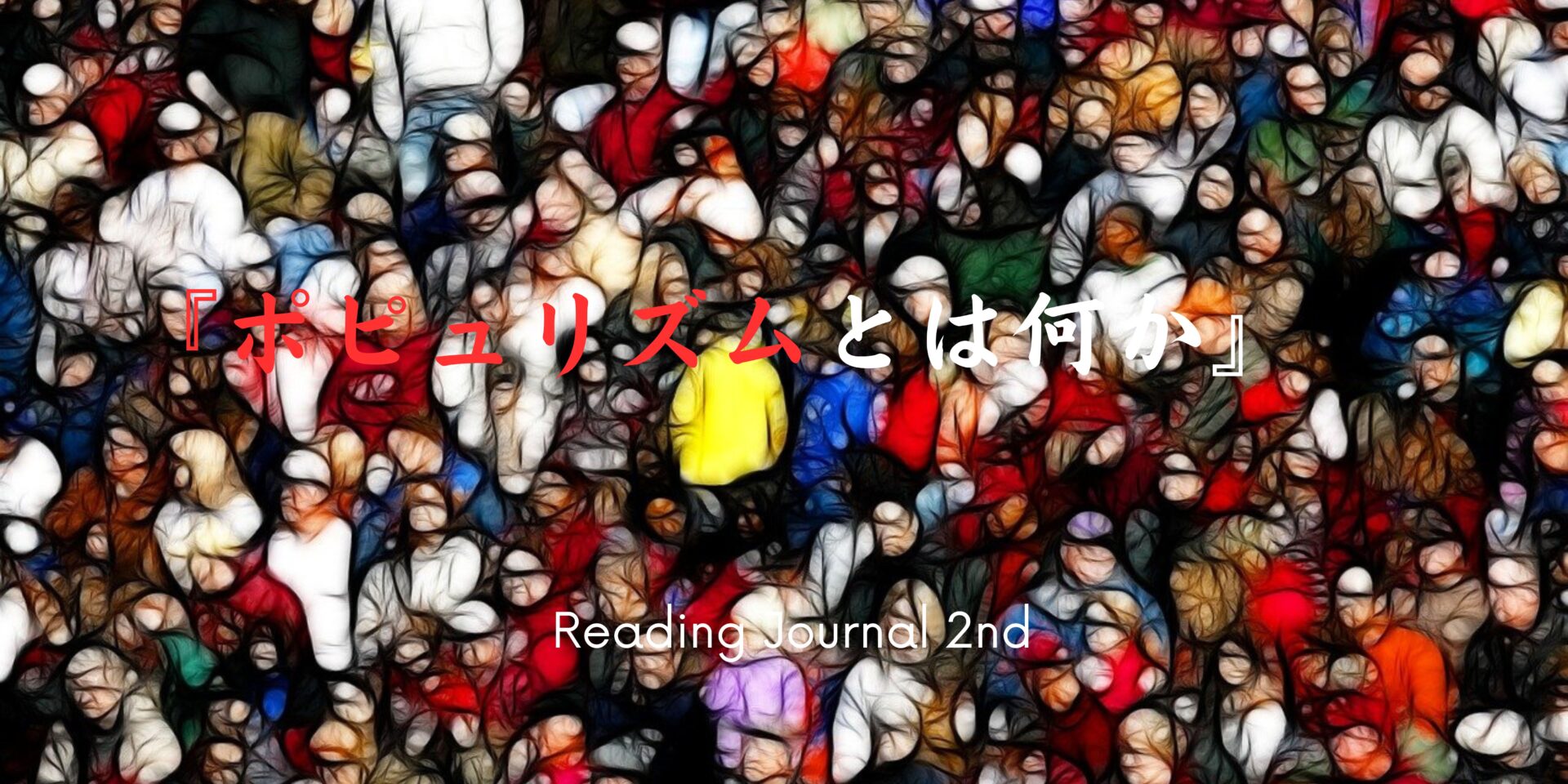

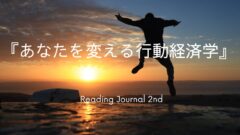
コメント