『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 ポピュリストがすること、あるいは政権を握ったポピュリズム(その6)
今日のところは「第二章 ポピュリストがすること、あるいは政権を握ったポピュリスト」“その6”である。ここから、「人民は「われら人民」と言えないのか?」の節にはいる。この節では、民主主義やその憲法と人民の問題について取り扱われる。この節は“その6”“その7”に分けてまとめる。
人民は「われら人民」と言えないのか
民主主義での人民の代表
これまでの分析の含意が、著しく保守的ではないかと思われるかもしれない。(抜粋)
ここで著者は、今までの議論が保守的であると読まれることに懸念を示し、それは誤解であると言っている。
保守的な議論とは、「政治が公式な政治的諸制度に限定されるべきで、その結果のみが正当であるという見解」である。この見解では、人民による、人民の関する、人民のための主張は禁じられる。
このように捉えられることに対して、著者は反論している。
民主主義では、「誰もが代表を主張でき、その主張を特定の支持層が応答するかを確かめることができる」。つまりどんな支持層が、自分たちのグループ・アイデンティティの象徴的表現を支持してくれるか確かめることができる。
民主主義はそのような主張を増やすように考案されていて、公的な代表は競争的であるべきである。この競争的であるというのは、有権者の為に振るまえてないとか政治共同体の自己理解に背いていて、代表を代表し損ねているという議論も含む。
ここは難しかった。著者はきっと自分はポピュリストたちのような政治的意見を禁じて、選挙などの政治的諸制度だけで政治を運用するべきと主張しているかのように誤解されると考えているんだろうな?と思った。
そして、そうではなく、民主主義のもとでは誰もが代表を主張でき、どんな人がその主張に賛成するかを確かめることができるシステムだと言っている。
なので、ポピュリストが人民に語ることを禁じたほうがよいとしているのではないと言っているんだろうな?そうそう(つくジー)
ここで著者は、街頭での抗議やオンライン誓願などの行為は、民主主義的な意味があるが、適切な民主主義的形態を欠いており、代議制に対抗するようなものを生み出せないとしている。しかし、「人民の力」の名において奮闘している人たちは、民主主義を理解しておらず、立憲主義を誤る者と言えるだろうか?と疑問をていしている。
著者は、本書の分析は排除に関する主張を排除していないとし、誰もがみな既存の手続きを批判でき、道徳的な盲点を批判でき、さらなる包摂的な基準や手段を提案できる、としている。
問題なのは、現在の取り決め(arrangements)が失敗しているという主張ではなく、批判者が、それも批判者のみが「人民」のために語ることができるという主張なのである。(抜粋)
そしてさらに問題なものは、ラディカル・デモクラットを自称する人たちの「全体に代わりうる一部分という主張のみが、それまで排除されてきた者たちにとって真に価値のあることを成し遂げる」という主張である。
著者はこの意見は、全く正当化されないとしている。それはこの「われわれが、それもわれわれのみが人民を代表しうる」という主張は、長期的な安定の確保が困難であるという視点を欠いているからである。そのため一旦紛争が起こるとその紛争は終わらなくなる。
民主主義憲法と「包摂」
ここで著者は、憲法の問題に話題を変える。
まず民主主敵的な多くの憲法は、「包摂」のための闘いのゆえ発展した(「包摂」とは、異なる意見や立場を調和させること)。そのため市民は「われわれもまた人民を代表する」と主張してきたが、「われわれが、それもわれわれのみが人民である」と主張してきたことはない。
このように民主主義的な諸原理を備えた憲法は、「その諸原理の意味について開かれた論争を許容」し「新しい公衆の新しい代表要求の出現を許容」してきた。
憲法は、いわば「包摂のための要求形成の連鎖」を理論上は促進することができる。最初の「われら人民(We the People)は、通常の政治過程のなかで完全に消え去ることも無ければ、経験的に存在する統一されたエージェント --- ある種のマクロな主体 --- として、憲法秩序の外側にとどまるわけでもない。(抜粋)
この「われら人民」というものは、Openな存在であり、多くの民主主義は、それについての問題である。
クロード・ルフォールが述べたように、「民主主義は、掴みどころがなく制御不能な社会という経験を新たに開くものであり、そこではもちろん人民が主催者とされるけれども、そのアイデンティティはつねにオープンな問題であり続け、永遠に潜在的なものにとどまるであろう。」
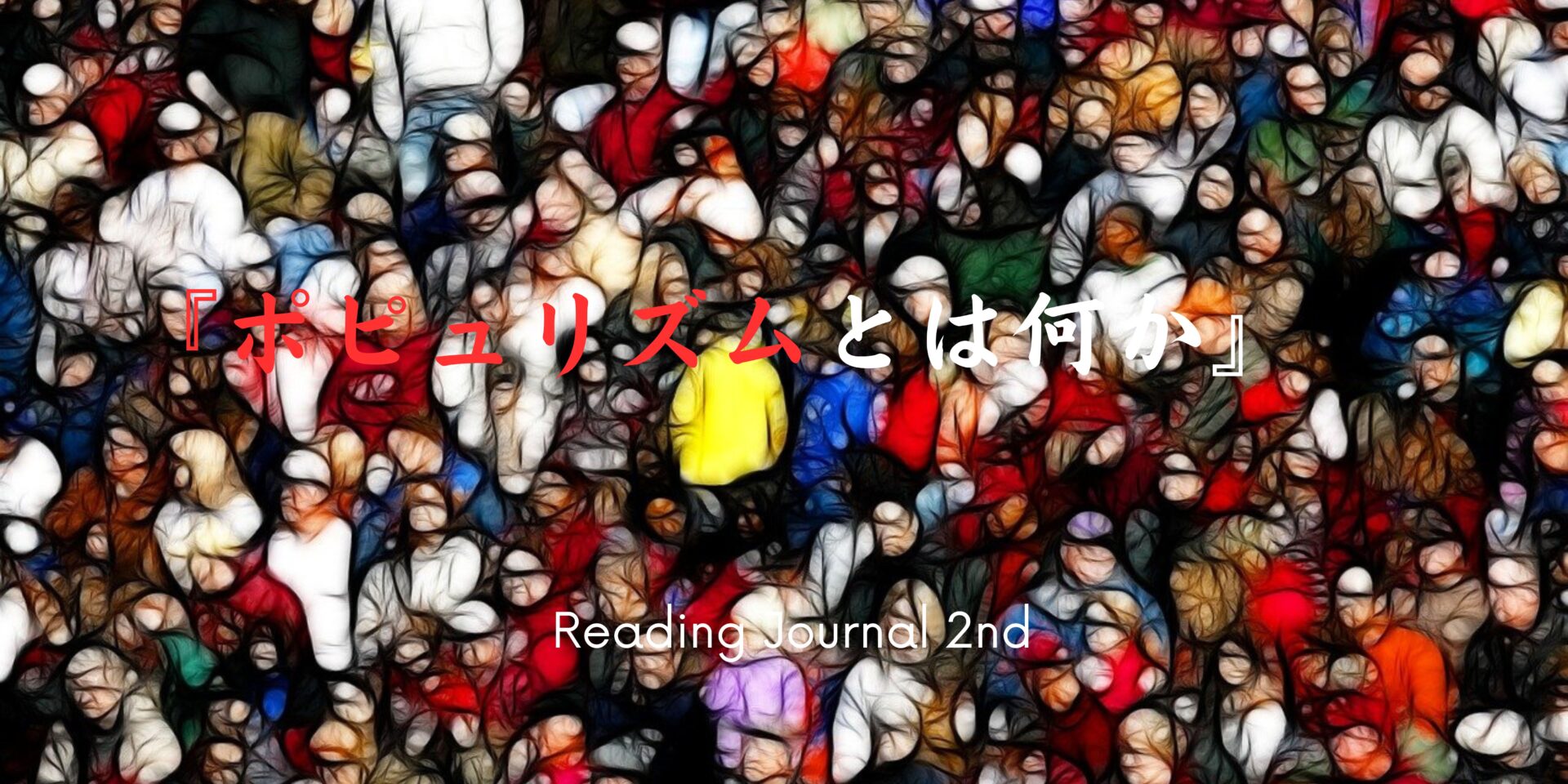

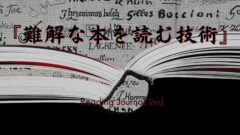
コメント