『忘れられた日本史の現場を歩く』 八木澤 高明 著、辰巳出版、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『忘れられた日本史の現場を歩く』
『忘れられた日本史の現場を歩く』という本を買った。この本は、著者の八木澤が実際に現場に赴き、写真と文章によって、今や埋もれてしまっている物語を語るという内容である。書名を見てすぐに思い出すのが、民俗学の権威・宮本常一の『忘れられた日本人』である。この本も当然、『忘れられた日本人』をオマージュしているのだろう。
この本は、民俗学的な話も多いが、わざわざ著者が、”日本史“としているように、伝承のようなもので無く、実際にその場で人々がうごめいた歴史のある場所、そこに立つことを重視している。
構成は、写真と文章を合わせて4から8ページ、全19話である。古代から比較的最近の原発事故による帰宅困難地域まで幅ひろい。著者は、『遠野物語』に登場する姨捨山のような有名なものから、古い資料によって知った、それこそ本当に忘れられてしまった日本史の現場に赴いている。そこで著者は、現地の人に話を聞き、その歴史の痕跡を探し、そして、写真に記録する。
話をいくつか紹介しよう。第9話・「朝廷に屈しなかった蝦夷の英雄 人首丸の墓」という話がある。人首丸は平安時代に現在の東北地方を征服するためにやってきた坂上田村麻呂に抵抗した人物であるという。この坂上田村麻呂と抵抗した人物としてまずアテルイとモレが有名である。著者はまず彼らの戦いを概観した後、
蝦夷の首領アテルイが討ち取られても、朝廷に屈しない人物がまだいた。それが人首丸だった。(抜粋)
と、人首丸を紹介している。しかしやがて人首丸も討ち取られてしまう。年齢はまだ一五、六歳だった。著者はその人首丸の墓を訪ね、未舗装の林道に分け入った。そしてその深い森の奥に、白い看板と共に人首丸の墓碑と書かれた白い杭があった。
墓石には、何も刻まれていなかったが、長年この場所に鎮座していることが一目瞭然であり、土地の人々の人首丸に対する敬愛を感じずにはいられなかった。(抜粋)
最終19話は、「自由に立ち入れない場所 津島村」である。福島県浪江町津島は、東日本大震災に伴う原発事故により、帰宅困難区域に指定されている。著者は一時帰宅の元住民の方々に同行するという形でこの津島を訪れ、その変わり果てた現状をレポートしている。しかし、この誰も人がいない景色は、原発事故以前にも津島いや東北地方の幾つかの地域で起こっているという。それは、江戸時代に発生し広谷地や羽附では、村民が餓死したり、逃亡したりして地区が全滅した。そして、そのように村民が全滅した地域には、江戸時代には北陸から移民が推奨され移り住んだ。さらに戦後の津島には満州からの引揚者たちも入植した。
高度経済成長に日本が突き進む一方で、津島の開拓地では第一回の東京オリンピックの五年前になってやっと、電気が灯った。
この土地に暮らした人々が何世代にもわたって築いてきたものが、村の風景であった。それが二〇一一年の原発事故により、一瞬にして消えた。(抜粋)
関連図書:
宮本常一(著)『忘れられた日本人』、岩波書店(岩波文庫)、1984年
柳田国男(著)『遠野物語』、新潮社(新潮文庫)、2016年
目次
はじめに
独自の呪術信仰”いざなぎ流” 拝み屋が暮らす集落(高知県香美市①)
パンデミックの悲劇 面谷村(福井県大野市②)
インドから帰ってきた女性 からゆきさんがいた村(山口県岩国市③)
蝦夷に流れ着いた和人たちの城 志海苔館(北海道函館市④)
かつて栄えた風待ちの港 大崎下島(広島県呉市⑤)
『遠野物語』に記された”デンデラ野” 姨捨山(岩手県遠野市⑥)
海外への出稼ぎ者が多かった土地 北米大陸と繋がっていた村(静岡県沼津市⑦)
本州にあったアイヌの集落 夏泊半島(青森県東津軽郡平内町⑧)
朝廷に屈しなかった蝦夷の英雄 人首丸の墓(岩手県奥州市⑨)
国家に背を向けた人々の”聖域” 無国籍者たちの谷(埼玉県秩父市ほか⑩)
飢餓に襲われた弘前の地 菅江真澄が通った村(青森県つがる市⑪)
八〇〇年前から続く伝説 平家の落人集落と殺人事件(山口県周南市⑫)
潜伏キリシタンが建てた教会 中通島(長崎県南松浦郡新上五島町⑬
飢餓で全滅した三つの村 秋山郷(長野県下水内郡栄村ほか⑭)
難破船と”波切騒動” 大王崎(三重県志摩市⑮)
本土決戦における重要拠点 館山湾(千葉県館山市ほか⑯)
古より遊女が集まる場所 青墓宿(岐阜県大垣市⑰)
江戸時代の大阪にあった墓地群 大阪七墓(大阪府大阪市⑱)
自由に立ち入れない場所 津島村(福島県双葉郡浪江町⑲)
おわりに
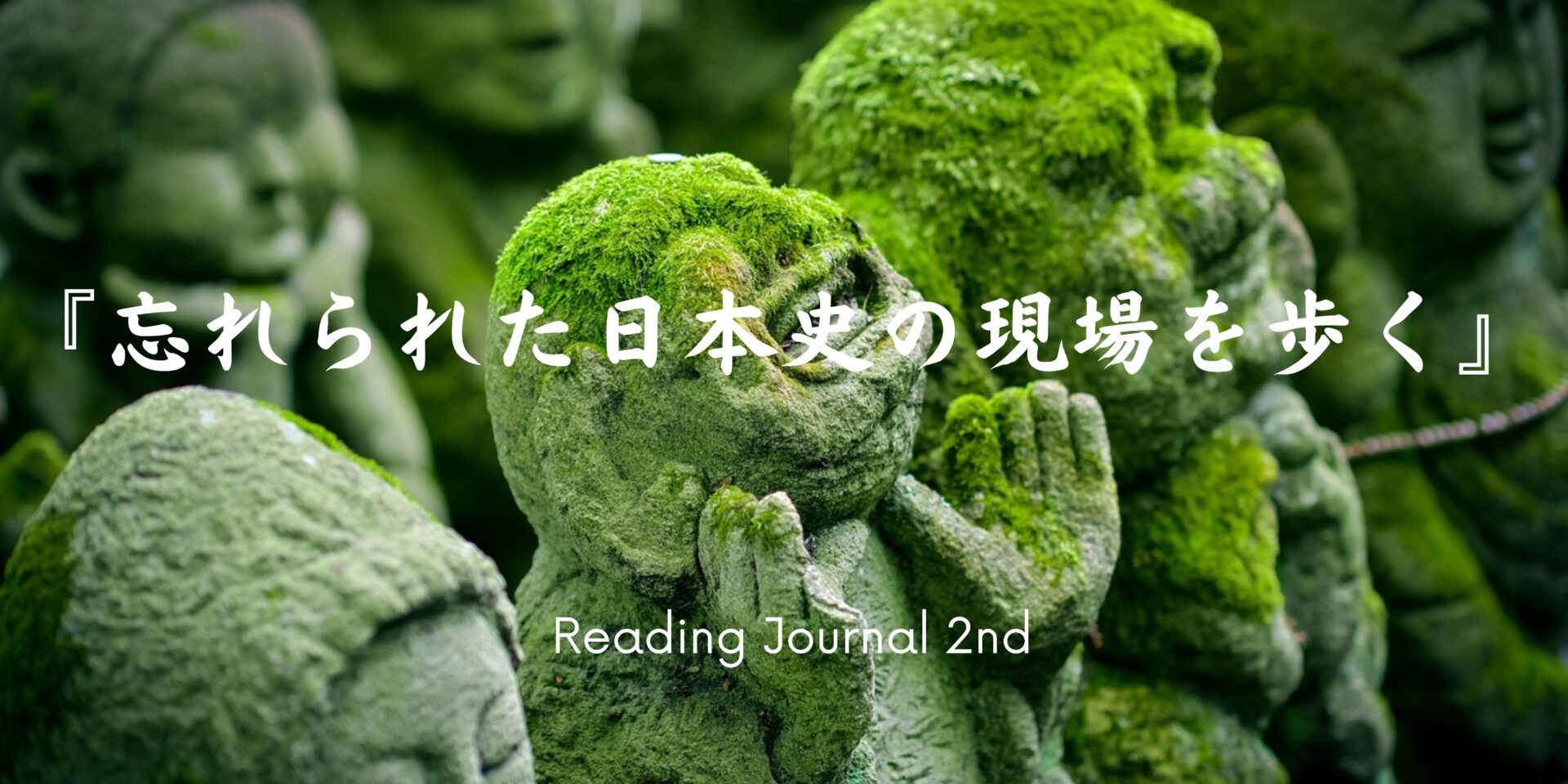


コメント