『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 ほかの問いかけと「謙虚に問いかける」はどう違うのか(後半)
今日のところは「第3章 ほかの問いかけと「謙虚に問いかける」はどう違うのか」の“後半”である。第3章で扱う4つの問いかけのうち、”前半“では、「謙虚な問いかけ」と「診断的な問いかけ」を取り扱った。そして今日のところ”後半“は、「対決的な問いかけ」と「プロセス指向的な問いかけ」についてである。それでは、読み始めよう。
対決的な問いかけ
質問というかたちをとりつつも、自分の考えを差しはさむ ---- 。これが対決的な問いかけの本質的要素だ。(抜粋)
自分の主張を強めるための質問や誘導的な質問は、自分が言いたいことを言うために質問という形式をとったものである。そのためこのタイプの質問が「謙虚な問いかけ」の範疇に入ることは稀である。
質問する側が主導権を握り、暗黙のうちに助言をあててしまうので、このような質問は相手の反感を招き、関係を築くことをむずかしくしやすい。
対決的な質問は、あなたに相手の役に立ちたいという動機があって、あなたとその人のあいだに信頼関係があり、その人も議論を挑まれたとは思わずサポートされていると感じられるなら、「謙虚な問いかけ」だと言うことができる。(抜粋)
もし対決的な質問をしようとするならば、その前になぜそれを聞きたいのか自分に確認することが必要である。自分が相手に謙虚な気持ちや好奇心を持っているか、それとも、自分には解決策が見えているから、自分の正しいことを証明しようと思っているだけか、判断する必要がある。
プロセス指向的の問いかけ
「プロセス指向の問いかけ」は、会話の焦点を中身でなく会話そのものにシフトさせる聞き方である。これが「謙虚に問いかける」の範疇に入るかどうかは、焦点をシフトさせようとする人の意図による。
もし良好な関係を築きたいと思っている相手との会話が少々おかしな方向へズレてしまったら、「どうなさいました」(「大丈夫ですか。私の言葉でお気を悪くなさったのでしょうか」)というような主旨の質問を、へりくだってしてみるといい。そうすれば、なにがいけなかったのか、どうすれば修正できるのかを探ることができる。(抜粋)
このような問いかけにより、両者の関係性が焦点として浮上し、互いの目的が合致しているかどうかを判断する機会が持てる。しかしこの問いかけも習得するのは難しい。
私たちは会話をどのように進めるかについて話し合ったり、互いの関係に言及したりするのをつい避けてしまう。しかし、会話がぎごちなくなったり難航してしまったりした時に、このような問いかけが有効な時が多い。
まとめ
自分ばかり話すことを控えて、相手に質問するように心がけても、相手より自分が一段高い位置にあることを証明したいという心がある場合は、その気持ちが態度に現れ「謙虚に問いかける」にはならない。
「謙虚に問いかける」の実践には、まず謙虚な態度を保つことから始める必要がある。そのうえで相手にどのような質問をするのかを選択する必要がある。
その質問は、自分の期待や先入観を挟むのでなく、相手に対して興味を持つようにすればするほど適切な質問をする態勢を維持できる。
私たちは、無意識に「ああしろ、こうしろ」と言ってしまう。議論を吹っ掛けるような質問や相手を診断するような質問も、あまり考えずにしてしまう。
相手としっかり向き合い、自分の無知を自覚できるようになるには、一定の訓練と自己を律する気持ちが求められる。(抜粋)
この「謙虚に問いかける」の難しさを考えるには、自分が話すことを推奨する文化的な影響力について考える必要がある。
本章「ほかの問いかけと「謙虚に問いかける」はどう違うのか」で扱われた四つの分類は、前著『人を助けるとはどういうことか』に出てきた問いかけの4つの分類をもとにしている(“前半”を参照)。しかし、全く同じでもない。
前著では、「控えめな問いかけ」の重要性について、多く語られているが、分類に関しては、
- 純粋な問いかけ
- 診断的な問いかけ
- 対決的な問いかけ
- プロセス思考的な問いかけ
となっていている。
ここで「純粋な問いかけ」=「謙虚な問いかけ」と思うと、ちょっと違うような気もする。
前著は、「専門家」「医師」「プロセス・コンサルタント」の役割について解説し、支援は「プロセス・コンサルタント」 の役割から始めるべきであるという主旨であった。そして、この「プロセス・コンサルタント」の役割では「謙虚な問いかけ」が重要であるという流れであったと思う。
前著の「純粋な問いかけ」は、本書の「謙虚な問いかけ」の核になのかもしれないが、専門的でちょっと一般人には難しすぎるように思う。そこで、どのような問いかけが支援の場において重要であるか、そのことの研究結果が本書になるような気がするのです・・・・・が、どうでしょうかね。(つくジー)
関連図書:エドガー・H・シャイン (著)『人を助けるとはどういうことか』、英治出版、2009年
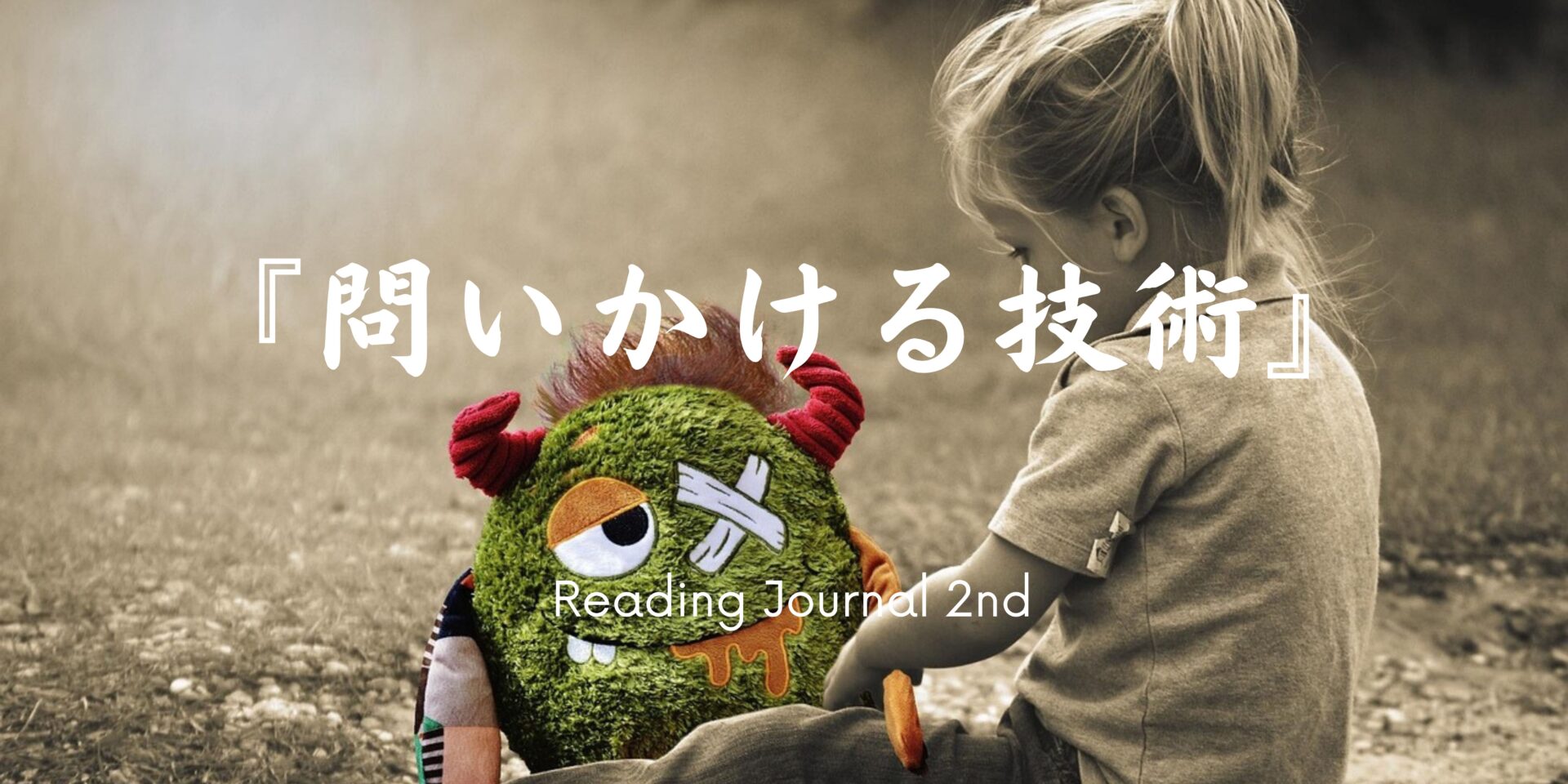


コメント