『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 ほかの問いかけと「謙虚に問いかける」はどう違うのか(前半)
今日のところは「第3章 ほかの問いかけと「謙虚に問いかける」はどう違うのか」である。これまで説明されてきた「謙虚に問いかける」を理解するために、ここでは、ほかの問いかけ、つまり「診断的といかけ」「対決的問いかけ」「プロセス志向的問いかけ」との違いについて説明される。
第3章は、“前半”と“後半”に分け、“前半”で「謙虚な問いかけ」と「診断的な問いかけ」、”後半“で「対決的問いかけ」と「プロセス指向的問いかけ」をまとめることにする。それでは読み始めよう。
四種類の問いかけ方
「謙虚に問いかける」をしっかりと理解するためには、ほかの問いかけ方と照らし合わせて考えるとわかりやすいだろう。(抜粋)
「謙虚な問いかけ」は、「自分ばかり話すのではなく、こらからもっと相手に問いかけよう」と思うだけでは不十分である。問いかけ方にもいくつもの選択肢があり、中には自由に答えさせるような質問もあれば、実は相手をコントロールしてしまう聞き方もある。
ここでは、前著『人を助けるとはどういうことか』に出てきた問いかけの4つの分類(ココとココを参照)、
- 謙虚な問いかけ
- 診断的な問いかけ
- 対決的な問いかけ
- プロセス志向的な問いかけ
にしたがって、それぞれの問いかけがどのようなものであるかを考察する。
謙虚な問いかけ
まずは、本書の主題である「謙虚な問いかけ」である。
謙虚に問いかけると、相手にたいする興味が最大限に高まり、偏見や先入観は薄れていく。そこでは自分が知らないということを積極的に認め、偏見を持たないように、相手を怖がらせないような方法で情報を求めたい。そして、避けたいのは相手を誘導したり、優等生的な回答を期待したりすることである。
ここで大切なことは、いかに質問を取り繕っても、本気で興味を持ってないと、それは相手に伝わってしまうことである。逆に、たとえ一方的な話し方でも相手に対する純粋な興味から出た言葉であれば、いかなる質問も「謙虚な問いかけ」になりうる。
このように「謙虚な問いかけ」は、状況により異なる。
ただし一つはっきりと言えるのは、謙虚な姿勢で尋ねようとしているときは先入観をできるだけ排除し、頭のなかをすっきりとさせて会話を始め、相手との話が進むにつれて自分はなるべく聞くことに専念するように心がけよ、ということだ。(抜粋)
相手が興味を持ってくれているかどうかを判断する決め手は、どんな質問をされたかではなく、どれくらい熱心に聞いてくれたかである。
診断的な問いかけ
診断的な問いかけは、一方的に話すつもりがなくても、会話の主導権を握ってしまう。その質問が相手の思考プロセスに影響を与えることに特徴がある。
このような質問が望ましいかどうか見極めなければならない。そのときのポイントは、会話の主導権を握る行為が、頼まれたことをきちんとやりたいという意思に基づくものかである。もし単に自分の好奇心を満たすことが目的ならば成功しない。
このような依頼者の思考プロセスに影響を与えるような問いかけは、聞くが側がなにに診断の焦点をあてるかによって四つに分類される。
① 感情は反応に関わる質問
その人がどのように感じたか、どのように反応したかに焦点をあてる。このような質問は、相手が考慮したくないかもしれないことについて、無理やり考えさせてしまうため「謙虚といかける」になるのは難しい。感想や受け止め方について尋ねるのは、相手との関係を個人的なものにするための一つの手段だが、それが適切かどうかはその場の状況による。
② 理由や動機に関わる質問
なぜそうしたのかの理由や動機に焦点をあてる。このような質問は、どうなっているかについて、相手に無理やり見解を求めることになる。「謙虚に問いかける」の一つと考えることができるかは、質問する側とされる側が共有する任務や業務とその質問がどれほど関連するかの度合いによる。
③ 実際の行為に関わる質問
実際に起きたこと、考えていること、これからやろうとしていること、に焦点をあてる。人は過去や現在、あるいは今後に取りうる行動を、概して打ち明けてくれないので、それを引き出す質問を考えなければならない。行為に特化した質問は、話し手の思考に沿って考えることを聞き手に促してしまうので、あくまでもそれが妥当な行為であると自信を持って入れる場合のみ行うべきである。
④ 体系的な質問
状況の全体像を把握するための質問。これは周囲の人はどう思っているのかどのような対応をしているかに焦点をあてる。このようなアプローチは、状況をもっと細かく検討することに相手が同意していれば、大いに威力を発揮する。
これらの四つのタイプの診断的な質問は、いずれも相手の思考プロセスを在る方向に導き、その人自身に「気づき」があるようにするものだ。とはいうものの、質問はあくまで質問にすぎないので、ある特定の解決策を暗示するものではない。これらの質問が「謙虚に問いかける」の範疇に入るかどうかは聞き方にもよるし、相手のとの距離感にもよる。(抜粋)
関連図書:エドガー・H・シャイン (著)『人を助けるとはどういうことか』、英治出版、2009年
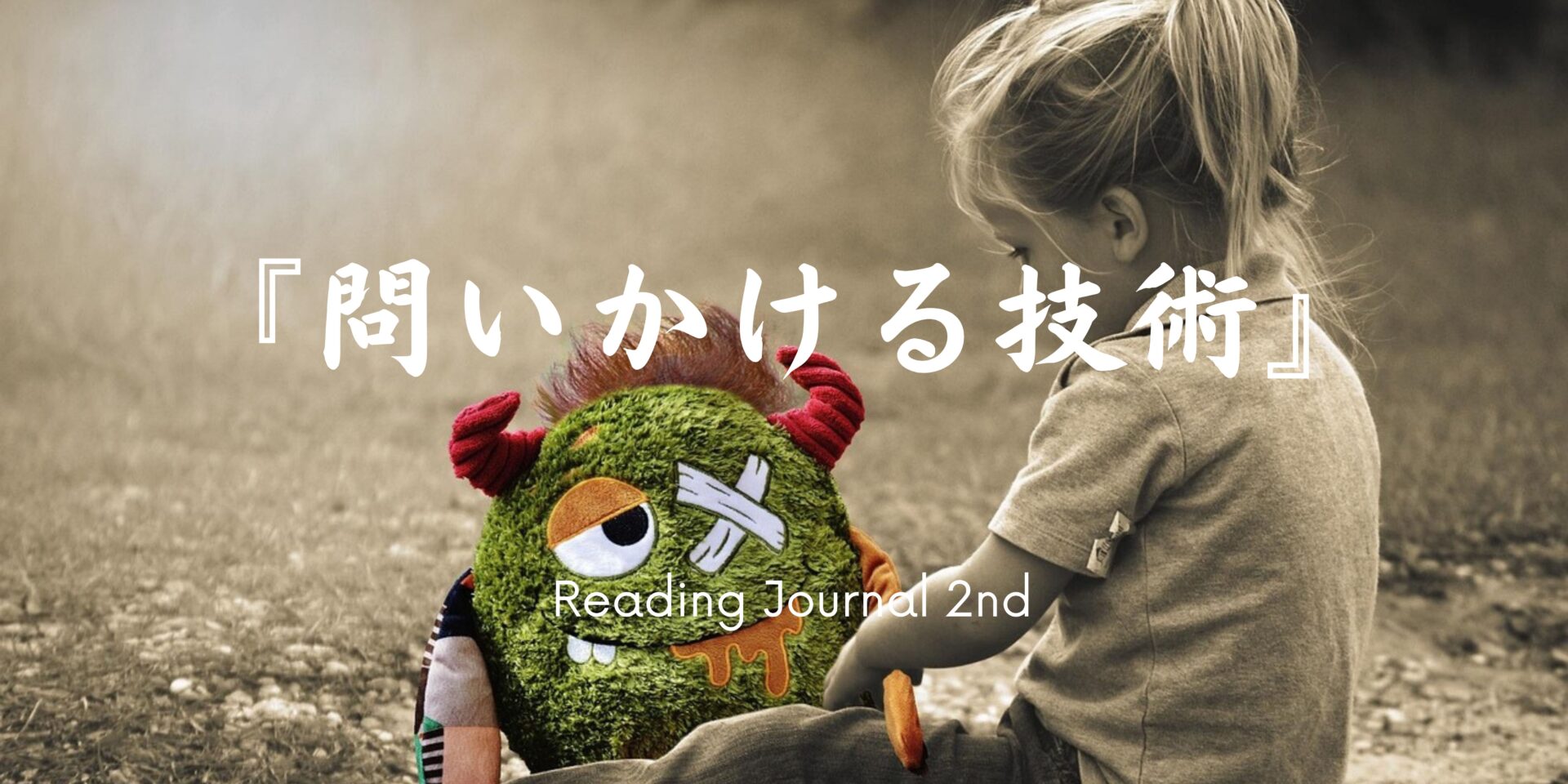


コメント