『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 実例に学ぶ「謙虚に問いかける」の実践
今日のところは「第2章 実例に学ぶ「謙虚に問いかける」の実践」である。前章の「第1章 謙虚に問いかける」において、この本の主題である「謙虚に問いかける」ことについての解説があった。本章では、それを受けて、「謙虚な問いかけ」というものはどういうものかについて、8つの実例を示して解説される。
ここでは、実例を詳細には触れず、要点のみをまとめることにする。それでは読み始めよう。
「謙虚に問いかける」には、必ずこうすべきという決まった型は存在しない。しかし、それぞれの状況に適したものがある。ここでは、そのような「謙虚な問いかけ」を8つの例をもって示されている。
著者はここで、次のように「謙虚な問いかけ」について説明している。
「謙虚に問いかける」は、相手があなたに心を許して話をしてくれるようになったり、あなたがまだ情報を持っていないことについて誰かに質問したり、その人に対する興味と好奇心に基づいてつき合いを深めたりするための技術であり、流儀である。(抜粋)
例1 妻のメアリーをお茶に誘う
ここでは、著者の新婚時代の話が取り上げられている。そのころ妻が「お茶を飲みに出かけよう」と提案したが、いつも忙しいと言って断っていた、ことについて考察している。
この状況のとき3つの選択肢がある
- 妻の申し出を断る(その時は、これをしていた)
- 妻とお茶を飲みに行く
- 妻の気持ちを考え「少し話そう」と提案する(「謙虚な問いかけ」)
このとき、著者は③の問いかけをするべきだったとして、そこから学んだ教訓は、
- 相手をとるか自分をとるかという選択を迫られた場合、二人にとってどうするのがいいかという視点で考える
- 「はい」「いいえ」でしか答えられない質問でなく、オープンな質問をする
- ほんの少しだけ自分が変われば、相手に対する思いやりを示すことができる
- 自分が少し変わることにより、二人で一緒に解決することができる
例2 勤務先の大学での通話料金を削減する
この例は、著者が大学の学科主任をしていた時に、電話代がかかりすぎている連絡を受け、原因を突きとめて、通話料金を削減するように求められたときの例である。
原因を突きとめようと犯人捜しを行うと、反感を買い人間関係をそこなう。著者は、人間関係を損なわないようにして、通話料金を削減するために、「通話記録を見て、他者の費用で賄われるべき通話料金が含まれてないか、確認し、今後もその点を気をつけてほしい」という内容のメモを回すことにした。
この方法はあれこれ指示しているように見えるが、実際は解決のための協力を求めていることになる。協力をして尋ねるかたちを取りながら問題を解決することができる。
例3 厳しい質問をするCEO
これは、重役ポジションの後任人事について会議での例である。ここでは、コンサルタントとして出席していたシャインが、
「次の勤務地に本人がドイツを強く希望しているのであるえば、その気持ちを尊重してあげるべきではないでしょうか」(「謙虚に問いかける」を実践)(抜粋)
とアドバイスした。
ここでは、事実を伝えずに行動してしまうのは相手への敬意が足りず、まず対話をし相手の意見を聞くことが大切であるとの教訓を引き出している。
例4 タスク・フォースを創設する
例4は、著者が理事を務めている環境団体が募金活動を始めようとした時の例である。ここで著者は、理事たちが募金活動のキャンペーンに意欲的であるか調べて欲しいと依頼があった。
これを著者は、チームが会議を開くより前に親睦のための夕食会を開いて、一人ずつ「なぜこの団体に関わっているのですか」と「謙虚な問いかけ」をしした。その結果、大半もメンバーがこの団体の方向性に前向きで意欲的なことがわかった。
- グループでの話し合いのときは、ひとつの質問を投げかけたら全員が発言してから意見交換をすること
- 重要な情報や考え方を引き出せるように質問すること
- 全員に本音を語らせるように始めること
- 司会役の人がコントロールするのは会議の進行で、中身ではないこと
などの教訓を示している。
例5 道案内をする
ここでは著者が、道を尋ねた人に道案内をした例が示される。この道案内の例は、単純に相手が言った情報に対して道案内をしたのではなく「どこにむかっているか」と問いかけたため、正しい道を教えられたというものである。
ここでの教訓は、相手が本当に必要としていることがわかるまで、慌てて返事をしないこと、相手が正しい質問をしたと思いこまないこと、などである。
例6 文化の変革を起こす
例6では、電力会社のCEOから「企業文化を変えたい」という依頼の話である。シャインは、CEOを自宅にまねき、謙虚に問いかけるというアプローチに徹する。そしてCEOの言葉の意味が分からないとき、その具体例を尋ねた。そしてその後、疑問に思うことを素直に問いかけた。その時CEOの頭のなかに何かひらめき、その後あらゆる角度からそれについて検討した。
この例には、具体例を尋ねること、もっと知りたいという意思を示すことなどが有効な手段となるとの教訓が示される。
例7 仕事の中身をはっきりさせようとして浮上した問題
ここでは、シェル石油のオーストラリア法人の依頼で仕事をしていたときに持ち上がった人事の問題についてである。
ここで著者は、無知を逆手に純粋な好奇心に従うこと、具体的な実例について尋ねることなどを教訓としている。
例8 相手の立場になって考えるがん専門医
最後の例8は、がんを発症した奥さんの担当専門医の話である。がんを発症したとき奥さんの担当医は、すぐに奥さんの性格や生活スタイルまで感心を示し、親身に話をしてくれた(「謙虚に問いかける」)。そのため奥さんは医師に全幅の信頼を置き、彼の治療に前向きに受入れ、がんと闘う気持ちになった。
しかし、次にがんが再発したときの専門医は技術的なことを優先し考えるタイプであったため、奥さんは不安となり医師の治療を受けるのが心配と感じた。そのため、担当医をもっとコミュニケーションを重視する人に交替してもらうと、不安は軽減した。
この例より著者は、「謙虚に問いかける」を実践することにより、早期に良好な人間関係はもたらせること、「謙虚に問いかける」とは、質問をすることだけでなく、その人の姿勢全体から感じられること、そして、関係を築く上で重要な役割を果たしたのは、専門的な質問ではなく、個人的な質問だったことが教訓だったとしている。
この8つの例は、奥さんとの新婚時代の話に始まり、奥さんのがん治療の話で終わる。この本の執筆時には、奥さんはがんで亡くなっていることを考えると、奥さんの話を最初と最後に置いた配置や、その内容から、シャインのやさしさや人間性がにじみ出ていると感じた。(つくジー)
まとめ
これらの例は、どんな態度で質問したら、その人に関心を持っていること、その人を尊重しようと思っていることが伝わるかを示すためにえらんだ。「謙虚な問いかけ」とは、チェックリストに従って行動したり、準備された質問をするのではなく、相手を思いやる気持ち純粋な好奇心、会話の質を高めたい望む気持ちから生まれる。
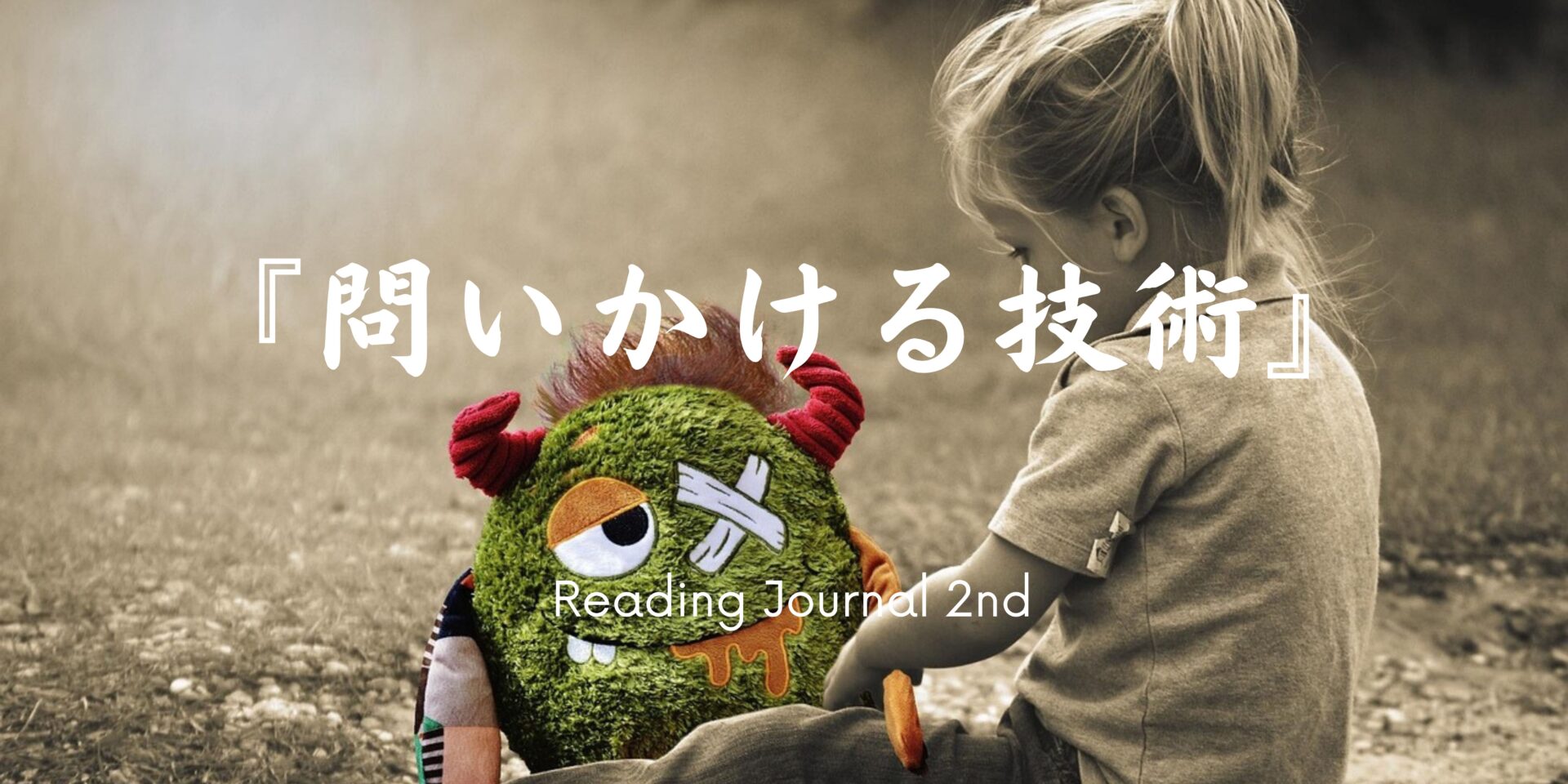


コメント