『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
解説 金井壽宏
「謝辞」と「著者について — 著者自身の言葉で」の後、監訳者である金井壽宏による「解説」がある(シャインの前著『人を助けるとはどういうことか』でも金井は長文の解説を載せている)。
解説では、本書の内容の要点をまとめるにとどまらず、本書が支援学(前著)から派生したこと、本書の内容の理論的背景などにも解説している。さらに、シャインの研究を概観し、その「シャイン経営学」における本書の位置づけなども書かれている。金井はシャインの愛弟子であり、ところどころにシャインの人柄を垣間見ることができるようなエピソードを挿入している。それでは、読み始めよう。
著者のシャインは、組織開発や組織文化、キャリア開発などの分野の第一人者である。そして「キャリア・アンカー」や「プロセスサルタント」の概念により著名である。
そして、近年は「支援学」の研究でも知られ、本書は支援学の延長線上にある。
「問いかける」という行為と人間関係
現在の社会で相手とコミュニケーションをとる場合、「話す力」に重点が置かれている。そして、「聞くにこと」に関しても、最近はコーチングなどの影響もあり、じっくり耳を傾ける「積極的傾聴 (active listening) の大切さがしばしば語られる。
しかし、「問いかける」という行為については、「話す」「聞く」行為と比べて、意識的に学ぶ機会はあまり無い。
そして、本書でシャイン先生が明らかにしているのは、その「問いかける」という行為こそが、良好なコミュニケーションのカギであるということだ。(抜粋)
しかし「問いかける」と言っても、知りたいことを質問する、相手の発言を促すためのもの、さらには質問という形をとって自分の意見を伝える、などさまざまである。
本書では、「謙虚に問いかける」行為が他者との人間関係の構築につながることが示されている。この良い人間関係を築いてこそ自分の目的(知りたいことを聞いたり、考えを伝えたり、他者に動いてもらったりする)も遂げやすくなる。さらに、それは、他者を支援する上でもカギとなる。
アサーションとの共通性
ここで著者は、コミュニケーションスキルの一つである「アサーション」との共通性に触れ、自分の考えを「伝える」スキルを高めたい人に勧めている。
ここで「アサーション」とは、相手に自分の意見を押し付けたり、逆に言いたいことを言わずにフラストレーションを溜めたりするのではなく、お互いに尊重しながら言いたいことを率直に伝える技術である。
背景にある理論と前著とのつながり
本書は、専門書ではないが、心理学や社会学、組織心理学、組織行動学などの学問分野に根差している。
本書は「問いかける技術と心構え」の平坦な入門書という側面を持ちながらも読み進めるなかで自然に理論的視野を学ぶこともできる内容となっている。(抜粋)
本書は、前著の『人を助けるとはどういうことが』で提示した「支援学」に立脚している。前著では、交換によって社会秩序が形成されるとする「社会経済」と、社会生活で人が役割を演じることに着目した「社会劇場」という二つの観点から、対人関係を理論的に考察した。そして、社会経済学における交換のバランスや、社会劇場における役割期待に反すると、人間関係が揺れ動くことを示した。そして、本当に相手のためになる支援、相手が受け入れやすい支援はどういうものかを説いた。そして、その支援を行う時に有効な手段として、「謙虚に問いかける」という行為に着目した。
そして、シャインは、この「謙虚に問いかける」ということが、支援関係だけでなく、あらゆる人間関係を好転させるために有効であることに気が付いた。すでに知っていることを助言したり、教え諭すようなことをするとクライアントは自信を弱め相手との関係が犠牲になってしまう。反対に、「謙虚に問いかける」ことでクライアントは自信を深め、人間関係を回復して問題解決に至る。このような「課題志向の関係」と「人間志向の関係」の対比を支援関係だけでなく、さまざまな人間関係にも適用したのが、本書である。この「課題志向関係」と「人間志向の関係」は「話す」と「尋ねる」の対比となっている。
日本人にとっての「謙虚に問いかける」
ここで、解説者の金井は、シャインの経営学の業績や、研究歴、さらには幼少期からの人生を概観している。
そして最後に、この「謙虚に問いかける」と日本の関係に言及する。
本書においてシャインは、「自分が働き、自分が話す文化」を米国文化の特徴としている。しかし、日本の文化では、それはさほど見られないのではないかと、金井は指摘している。
日本では、相手を立てることをポジティブにとらえる文化があり、間柄を尊重している。しかし近年、日本も米国的な「自分が働き、自分が話す文化」に近づいている。職場の人間関係も人間志向よりも課題志向が強くなってきている。
そして、最後に金井は次のように言って、解説を閉めている。
読者の皆さんが、本書を読み終えた後、家庭でも職場でも友人関係でも、身の回りの人との関係において「謙虚に問いかける」を実践し、良好な人間関係と優れた組織をつくり、幸せで充実した人生を送っていかれることを願っています。(抜粋)
関連図書:
エドガー・H・シャイン (著)『人を助けるとはどういうことか』、英治出版、2009年
平木 典子(著)『アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法』、講談社(講談社現代新書)、2012年
[完了] 全14回
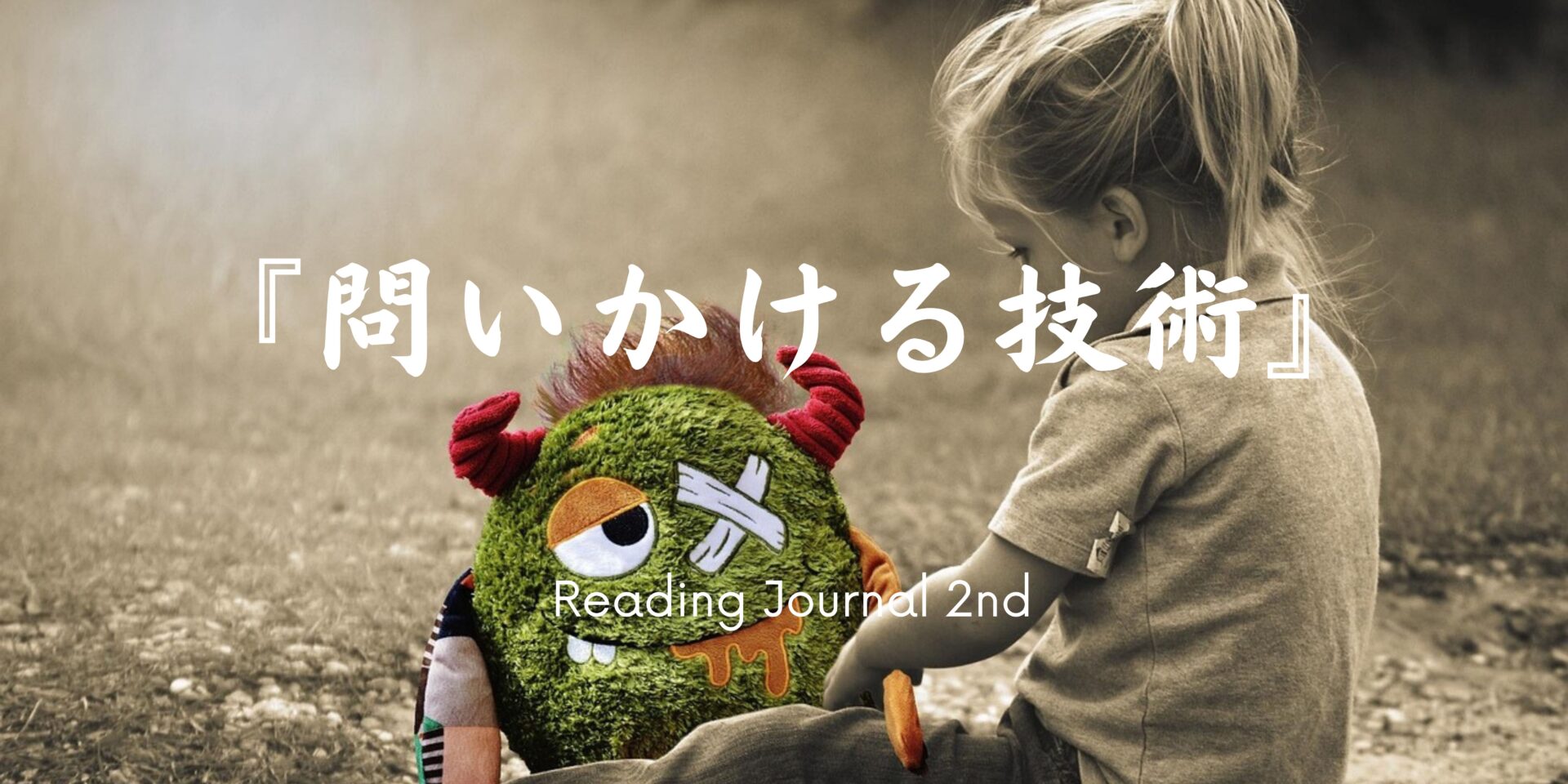


コメント