『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第7章 謙虚に問いかける態度を育てる
今日から最終章の「第7章 謙虚に問いかける態度を育てる」である。本章のテーマは、これまで解説された「謙虚に問いかける」という態度をどのように身につけるか、である。その実践的な方法を「個人の生活において」「組織において」「リーダーや管理職としての役割において」も3つの場面で解説している。それでは読み始めよう。
「謙虚に問いかける」は、
- 個人の生活
- 組織において
- リーダーや管理職の役割として
で必要である。
この三つの場面で求められる態度と行動は、既成の文化に少なからず抗うため、新たに学びなおす必要がある。
なかでも知覚と洞察の力を高めることは、自分がいつどこで話すことを控えて尋ねることを増やすべきかを見極めるために欠かせない。(抜粋)
学んだことを捨て、学びなおす — 二種類の不安
生き残りの不安と学習の不安
「謙虚に問いかける」の態度を学ぶためには、「自分が話し手になる」という古い習慣を手放さねばならない。その時「生き残りの不安」と「学習の不安」の影響を受ける。
まず、「生き残りの不安」は、ある行動が出来るようにならないと、自分が不利になると気づいたときに起こる不安である。
そしてその行動が出来るようになるように学習すべき課題と向き合わなければならない。しかし、その課題の困難さやマイナス面を予想して心配するのが「学習することへの不安」である。この不安により、人は変わることに対して抵抗を感じてしまう。
学習することの不安が生き残りの不安を上回っていると、人は変化を拒み、学びを避けるようになる。(抜粋)
そのため、人が学び直そうとするときには、学習することへの不安を軽減する必要がある。
それでは、謙虚になって相手に尋ねる流儀を学ぶとき、どのように自分自身を支えるべきであろうか。
この「生き残りの不安」と「学習することの不安」ってのは、奥が深いように思う。
ここでは、どうやって「謙虚に問いかける」の学習の不安を軽減するか、って切り口なんだろうけども、やらなければイケないことを出来ない自分の状況をよりよく言い当てているようです。
学習することへの不安を軽減する、ことが大切なんですね♬ (つくジー)
速度を落とし、緩急をつける
そのためには、自分のペースの調整、減速、現状の評価、自分自身や他人を客観的に眺める、などの振る舞いを試すことがよい。これらの振る舞いは「自分が働き、自分が話す文化」からは学ぶことが出来ない。
著者は自身の経験に照らし合わせて、大きな失敗をしたりリスクを負ったりしたときは、考えもなくやたらに急いだことが原因だったとしている。
そして、「謙虚に問いかける」を学ぶことは、物ごとを慎重に見渡して、その場で現実に起きていることをきちんと評価するために減速する方法を学ぶことであると言っている。
課題をやり遂げるための人間関係を構築するために「謙虚に問いかける」を実践し、歩む速度を緩めて信頼を育んでいく必要がある。しかし、ひとたび人間関係が構築されれば、仕事の速さは上がっていく。
内省し、自分自身に対して「謙虚に問いかける」
課題を遂行を優先するせっかちな文化を持つ人に必要なのは、内省することを学ぶことである。
内省することを学ぶ一つの方法は、「謙虚に問いかける」を自分自身に対してやってみることだ。(抜粋)
著者は、行動に移す前に、
- 「今何がここで起きているのか」
- 「もっと適切な対応はなんだろうか」
- 「私はいったい頭のなかでなにを考えていて、心のなかでどんなふうに感じていて、どしたいとおもったのだろう」
と自分に問いかけることを勧めている。
もっとマインドフルになろう
内省するということは、周囲で起きていることがもっと気がつくようになる。つまりマインドフルになるということである。
ここで著者は、マインドフルネスという概念を提唱したエレン・ランガーとの付き合いのなかで起こったことを紹介している。
著者は、エレンの「ほかにどんなことがあったのですか」という問いかけに注目した。
エレンが投げかけてくれた「ほかに何か起きていたのですか」という質問は、内省するときだけでなく、これから足を踏み入れようとしている状況を即座に見極めるときにも、呪文のように自分自身にぶつけるべき重要なものである。(抜粋)
「謙虚に問いかける」ときこのように自問することは、不可欠である。
自分のアーティスト性を発掘し、革新的な発想を心がけよう
自分たちの文化の枠内にとどまっていると、このように内省的になって自分の包容力を広げることは、難しい。
そして、著者はそれを打破するために、アーティスト的な感性を磨くことを勧めている。アーティストのように、より多くのことを見て、感じて、行うようにすると、心と体がもっと動くようになっていく。挑戦して自分らしさの幅を広げることが大事である。
自分の行動を振り返り、内省する
このように、速度を緩め、ペースに変化をつけ、マインドフルになり、クリエイティブな発想をすることができるようになると、自分なりのやり方で内省できるようになる。
これは、グループの場合でも同じで、成果をあげている集団は必ず自分たちの決断を振り返り評価して、そこから学習している。
仕事における調整の必要性に敏感になる
ここで、著者は「謙虚に問いかける」を、個人からグループへ視点を広げる。
自分自身として「謙虚に問いかける」のスキルができるようになったとしても、属している組織全体を見ると不十分かもしれない。組織は、積極的に部署間で協力し合う組織の方が事業はうまくいく。
この点に関して、ジョディ・ギッテルは「目標を共有すること、互いの仕事を理解し合うこと、互いを尊重すること」がカギになると言っている。
組織のマネージャーは、「謙虚に問いかける」を実行し現在の相互依存度を判定するとよい。そして、お互いが相互に依存するような関係を築くためのプロセスを考えるとよい。互いに相手を尊重する組織は階層的な境界を飛び越えて、コミュニケーションを行い、業績を上げるとともに安全にかかわるリスクも低くなる。
リーダーとして、チームのメンバーとの人間関係を構築する
このように古い慣習を捨て「謙虚に問いかける」を学びなおすことは、リーダーにとって難しい。
しかし、ここまで本章に書いてあったこと、つまりペースを落とし、内省し、マインドフルになり、内に秘めたアーティスト精神を呼び戻し、プロセスを点検・検討する機会を増やす、などを行えば、この課題に挑戦することができる。
「文化の島」を築く
チームをまとめるために「謙虚に問いかける」を実践し、信頼できるチームを築くことは、似たような文化的背景をもった人ばかりのチームならば、打ち解けた雰囲気でメンバーを集め、個人的なことを聞く機会を増やしていくようにするとよい。
しかし、文化的な背景が異なる人びとが集まるチームの場合は、違う工夫が必要である。
各々の文化的な背景が違うため、敬意の表し方や態度の見せ方、仕事と個人の付き合いの境界線などが違ってくる。
著者はこのような場合には「文化の島」を作ることが必要であると言っている。
「文化の島」とは、権威や信頼関係についてそれぞれの文化が定めるルールは一旦脇に置いておく、という状況だ。これを実現するためには、職場から離れて気持ちを楽にできるメンバーを集め、食事や余暇的な活動のように個人的な付き合いを深められる機会を設ける必要がある。(抜粋)
このような機会を通して、チームに作用している多様性を把握し、全員が納得して従うことができる共通基盤を探すことが大切である。
結び(見出し)
ここで結びとして著者の最後のメッセージが添えられている。
イノベーションやなんらかのリスク負担が求められる状況を、誰でもたびたび経験する。なかにはリーダーとして公的な肩書を持っている人もいるが、ほとんどの人はその時々で置かれた状況によって、リーダーシップを発揮しなければならない立場に追い込まれる。読者の皆さんにとって究極の課題は、そのような状況に直面したときには、自分が話すという誘惑に屈するのではなく、「謙虚に問いかける」を実践すべきなのだということを、はっきりと認識することである。(抜粋)
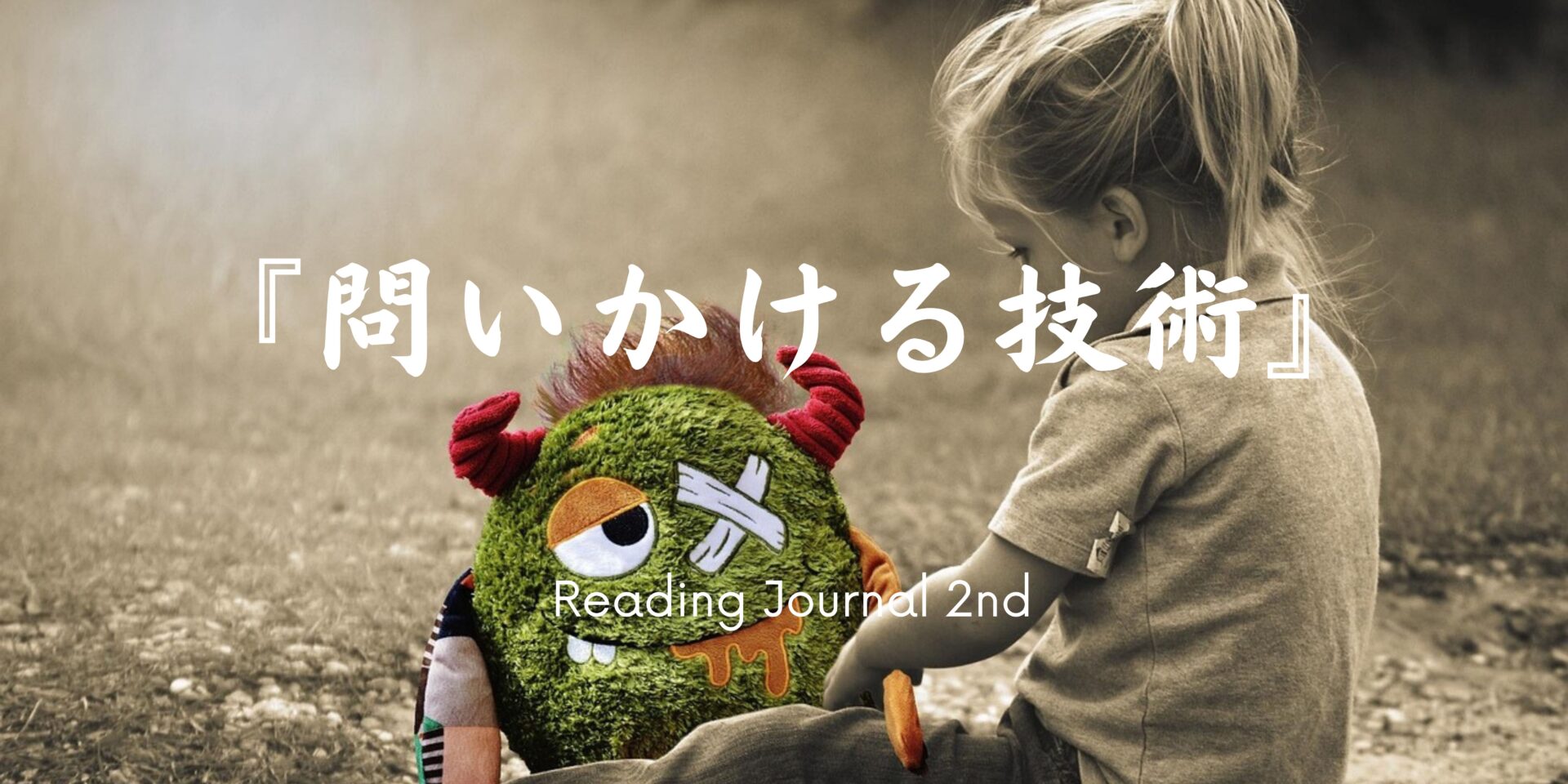
-1-120x68.jpg)

コメント