『問いかける技術』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 地位、肩書、役割 人々の行動をためらわせる「境界」の存在(後半)
今日のところは「第5章 地位、肩書、役割』の“後半”である。に入る。まず”前半“では、社会科学的に人間関係を「課題志向の関係」と「人間思考関係」に分けて考察した。そして現代の(米国)社会は「課題志向の人間関係」に傾いているということをについて疑問をていした。今日のところ”後半“では、現代のような複雑で相互に依存しあう社会では、より「人間思考関係」を求められ、そのキーポイントが「謙虚に問いかける」であると主張している。それでは読み始めよう。
組織、職種、国に特有の文化
組織や職種、その国の文化によって人間関係も影響を受ける。たとえば科学者や技術者の職場では、知識とスキルが軸になるため、お互いを尊重し合い、かなり率直なやり取りが行われる。しかし、医療現場では、この仕事特有の伝統が重んじられるため、医師と看護師の間には立場を明確にする距離ができる。
このよう組織や職種にまつわる文化によっては、誰かが個人的なつながりを増やそうとしても、その努力が打ち消されてしまう。
しかし、現在どのような分野でも人種や国籍の異なる人々が協調することが多くなっている。その場合、いかに謙虚になって個人的な付き合いを深めるかという問題は以前より重要性を増している。しかし、そのためには相手の文化の規範をしらないと、実践が難しい。
信頼と社会経済学
相手に対して謙虚になり、自分が話し手になるのではなく質問し、個人的な付き合いをそれなりに持とうとするためには、その人とのあいだに一定の信頼がなければならない。(抜粋)
著者は、ここで信頼というものについて考察している。
信頼は定義するのが難しい言葉であるが、会話の文脈では「相手が自分を利用したり侮辱したり恥をかかせたりするようなことをせず、自分のことを認めてくれて、ほんとうのことを話してくれると信じていること」を指している。そして、この「あなたのことを認めています」ということは、日々の何気ない行為、つまり顔を合わせる、会釈する、話しかける、などに表れる。
社会はこのようなことが当然のように積み重なっていて、それがベースとなっている。私たちは自分が育った文化のなかで、ベースとなる礼儀や身のこなしなどのルールを学んでいる。そして、基本的な信頼を学び、絶えずそれが試されている。
ここで、もし自分がその人にたよっていることを自覚していたり、魅力を感じていたりして、もっと高いレベルの信頼関係を築きたいとしたらどうするのがよいか。「私のことを信用しても大丈夫ですよ」というメッセ―ジを伝えたいときには、どうすればよいか。
これらのケースのすべてにおいてかぎとなるのは、「謙虚に問いかける」を実践し個人的なつながりを持つことによって、自らをあえて弱い立場に置く方法を学ぶことである。(抜粋)
これは、実践するのは難しいことであるが、あえて自分をされけ出し、弱い部分を見せることは、人との付き合いを深めていくうえで、最も重要な要素である。
まとめ
形式的な礼儀をわきまえた付き合いを越えて、もっとお互いに信頼関係を深めて関わり合うには、「謙虚に問いかける」を実践することが必要である。
仕事においては、内容が複雑化し相互に依存しあう状況におかれることが多くなっている。その場合には、仕事に関係する情報は、立場の違いを越えてオープンにする必要がある。しかし、米国では、仕事のパフォーマンスを高めることと個人的な競争が激しいこと、そして自分が話すことに価値を置く文化があるためそれは容易ではない。
コミュニケーションの通路を広げ、人々が効果的に協働するためには、信頼関係ができなければならない。逆説的ではあるが、そのような信頼関係の構築は、「謙虚に問いかける」を体得することによってのみ可能だ。(抜粋)
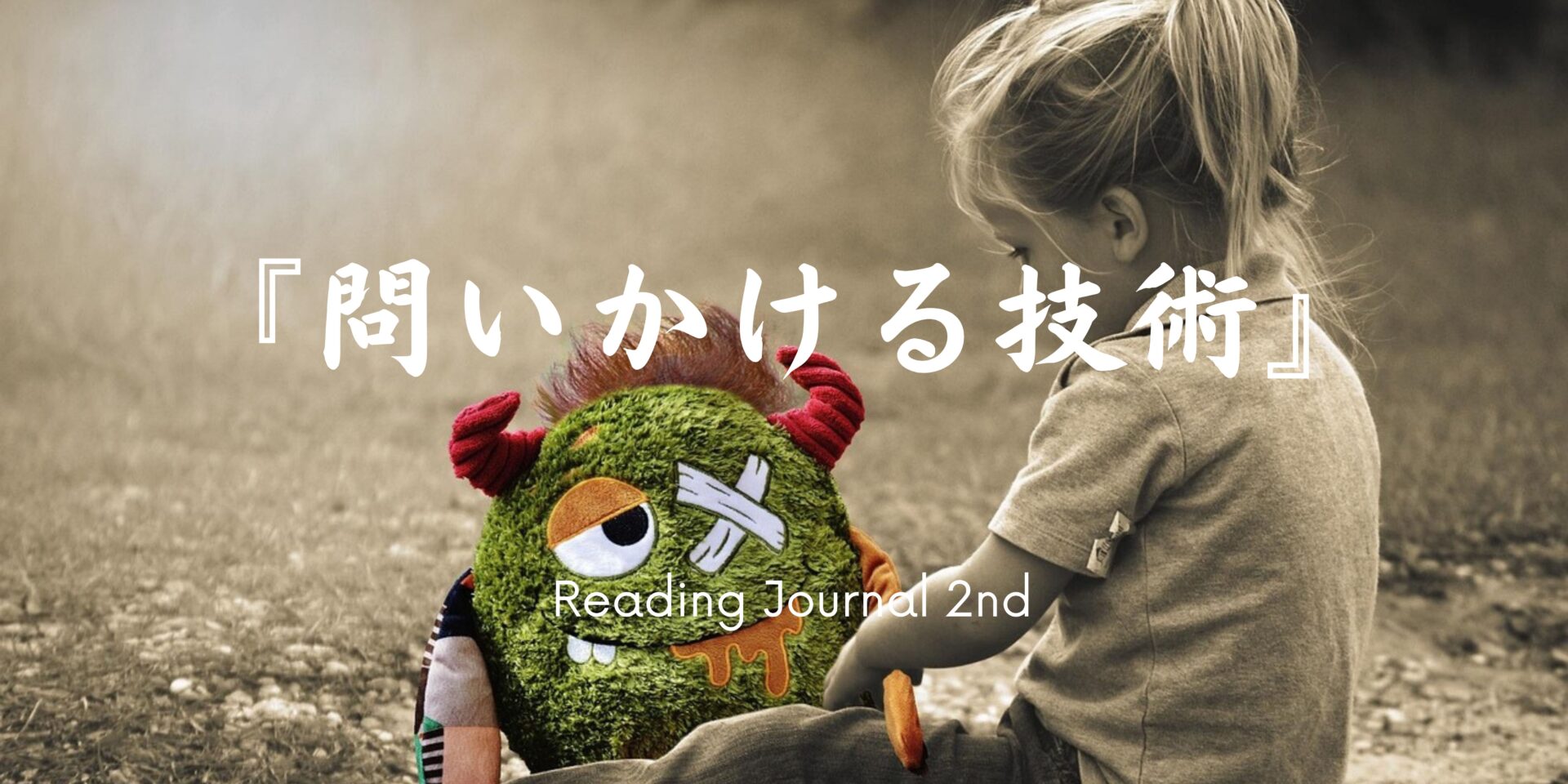


コメント