『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ 著、新潮社(新潮文庫)、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『灯台へ』
さて、何か良い本はないかな?と思って、アマゾンのHPをぱらぱらと見ていると、ビビットな表紙の本が目に留まった!のでした。題名は『灯台へ』。なるほど、表紙も良いし題名もOK!・・・でも、表紙と題名で、読む本を決めていいの?と思った。が、しかし、著者名を見ると・・・・なんと・・・ヴァージニア・ウルフだった。
ヴァージニア・ウルフというと、文学にうといボクのような人でも知っている大作家ですね。そして個人的には、柳田邦男が『人生の一冊の絵本』の中で『きょうは、おおかみ』という絵本が、ヴァージニア・ウルフをオマージュしていると紹介していて、ちょっと気になっていた。(原題の“Virginia WOLF”はヴァージニア・ウルフ”Virginia Woolf”をもじっている)詳細はココとか読んでね♬
これは神からの賜物か?それとも阿弥陀様のお導きか・・・・読まないといけないよね。
さてさて、読み始めてからしばらくして、使っていたamazom.comのロゴ入りブックカバーがだいぶ傷んだこともあって、新しいブックカバーを買いました。

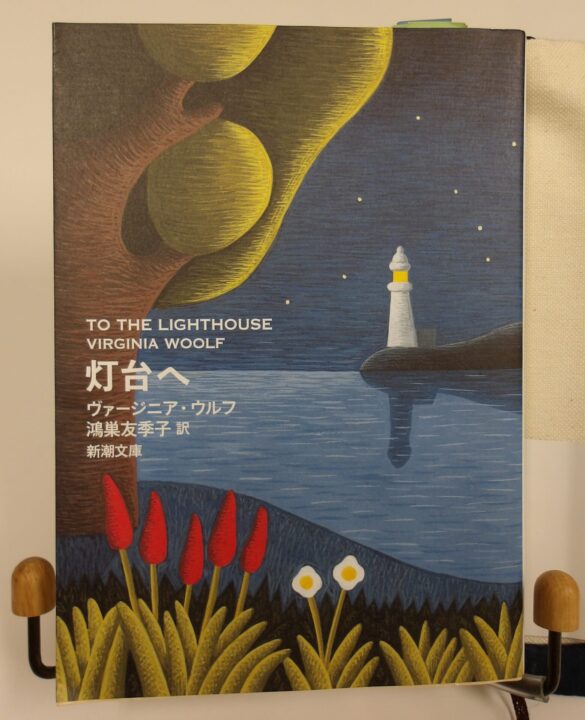
この本、表紙が気に入ってジャケガイぽく買ったが、ブックカバーもうまい具合に灯台柄があったので、そろえてみました。比べてみると灯台が似ている!・・・・・っというか、灯台ってだいたい同じ形なのね♬
この灯台の情景を描いている部分がある。ラムジー夫人がタンズリーを伴った町に出かける途中、波止場に出た時である。
両側の家並みがとぎれ、波止場に出たとたん、眼前に情景がいっぱいにひらけた、ラムジー夫人は思わず、「まあ、なんできれい!」と声をあげてしまった。満々と水をたたえた皿のような碧い海が目の前にある。灰白の灯台がはるかに遠く、その真ん中に厳然とそびえたっていた。右手には、緑色の砂丘がときに霞み、ときに窪みながら、低くやわらかく襞を織りなして、視界の涯までつづいている。野生の草花が鬱蒼としげる砂丘をみるたびに、人の棲まわぬはるか月の国へと通じているかのように思えるのだった。
そう、この侘しげな眺めなのよ。夫人は立ち止まり、灰色の瞳の色を深めながらそう言った。うちの主人が愛していたのは。(抜粋)
やっと読み終わりました。感想を食レポ風に言うと「お・おもろ・・!これ凄いおもろいですよぉ!こんなおもろい小説!初めて読みました!」・・・・・あ、おおげさでしたね。でもこの本は、文学的な名作なのですが、難解ということもなく、ボクのような下世話なものでも楽しく読めました・・・てのは、本当です。
文学的な意味について言えば、「訳者あとがき」に詳しく載っています。冒頭を引用すると
『灯台へ』は、ヴァージニア・ウルフによる To the Lighthouse (Hogarth Press,1927)の全訳である。
ウルフの長編小説としては五作目にあたり、斬新な文体と繊細きわまる内面描写によって、のちのモダニズム文学の先駆であり頂点のひとつと評された作品だ。それまでの文学の手法を受け継ぎながら、新し視点のあり方をとりいれて、文体の未知の領域を切り拓き、小説の書かれ方を根本的に変えた潮流の中心に位置する。(抜粋)
となっている。確かに、いまの普通の小説とあまり変わらず古さを感じないが、百年弱前の作品となんですよね。
このような、「新しい文体」とか「意識の流れの文学」などの難しいことは「訳者解説」に書かれているとして、ひとつ、ウルフと同時期にやはり名高いジェムズ・ジョイスが『ユリシーズ』を書いていて、ウルフも関心を寄せているという事実を記しておこうと思った。
この小説の主人公は、ラムジー夫人とリリーだろうと思う。まず「第一章 窓」では圧倒的にラムジー夫人である。ところが、時間の経過を表わす「第二章 時はゆく」であっさり亡くなったことが伝えられる。そして「第三章 灯台」では、画家のリリーが話の中心に来る。だが、その影にはやはりラムジー夫人がいるように思えた。
ラムジー夫人は、美人で五人の子供を持ち、きちんと夫を立てるような完璧だが古い時代に生きる人である。そして画家のリリーは、おちょぼ口で貧弱で、第一章で結婚の予感をさせるも、第三章ではすっかりオールドミスになっている。そこに対比がある。そして小説はリリーが一本のラインを引き、自分の絵を完成させるところで終わることも意味ありげである。その結末は、リリーが古い(女性の)世界から新しい(女性の)世界との間に一本のラインを引いたのかのようだった。
それはそれとして、読み終わってみてから、ひとつ疑問に思うことがある。この小説は、幼い息子ジェームズが「明日灯台に行きたい」といい、それにラムジー夫人が「ええ、いいですとも。あした、晴れるようならね」と言ったことから始まる。(次の日は嵐となり行けなかった。)そして、10年の時がながれ、ラムジー夫人を含む何人かのメンバーが亡くなった後、また、主要なメンバーが別荘に集まり、ヨットに乗り灯台を目指すという筋なのだが、・・・・なんで、10年後に、灯台を目指したのか?書いてあったのか書いてなかったのか?ちょっと読み落とした。灯台とその光が小説全体の重要なモチーフなんだぞ!‥‥それを読み落とすとは・・・・つくジーったら、残念な人ね♬
最後にこの本の印象的な場面を少し引用しておきますね。
バンクスさんは、こちらになにかを返すのを待っているようだ。あの奥さまも奥さまでドキッとするようなところがあること、いささか高飛車であるというようなことを言って、こんどは夫人のほうを腐そうとして見れば、バンクスがあまりにうっとりして顔をしているので、答えなど無用になってしまった。六十すぎという彼の年齢や、常日ごろ潔癖さや不動心、実験用の白衣を着て歩いているような真面目さを思えば、これは「うっとりした顔」と表現してもいいだろう。ラムジー夫人は釘づけのその目からして、見つめるだけで恍惚になってしまうのがわかる。そのまなざしは何十人という若い男の愛に匹敵しよう(あのラムジー夫人といえども、何十人という若者の恋心を一度にくすぐったことはないだろう)。それは純化し濾過されたような愛。リリーはカンバスをずらすふりをしながら思った --- 相手を決して捕まえようとしない愛。それはむしろ、数学者が記号に与え、詩人が語句に捧げる愛に似て、世界中に広がり、人類全体の一部になるもの。(抜粋)
「明日は雨だろう」父がそういう場面を思い出した。「灯台には行けまい」
あのころ灯台と言えば、おぼろに霞む白銀の塔で、夕どきになると、黄色い一つ目が不意にそっとひらくのだった。いま見るとそれは ---
ジェイムズは近づいた灯台に目をやった。石灰で白く塗られた岩場が見えた。塔はかすみもせず、くっきりと真っ直ぐにそびえている。よく見ると黒と白の縞が入っているのも、窓がいくつかあるのも見えた。岩場に干してある洗濯物までが見えた。そうか、これが灯台の本当の姿なんだな?(抜粋)
なるほど、それによってずいぶん変わるものね。リリー・ブリスコウは染みひとつないような海を見わたしながら、そう思った。海があんまりに穏やかだから、船の帆も雲もその蒼いなかにすっかり融けこんでいる。いろいろなものが距離によって決まるんだわ。リリーはまた思った。人と自分の近さ遠さを決めるのも距離。ラムジーさんに対する気持ちも、あの人が入り江の向こうに離れていくにつれて変わってきた。まるで気持ちが薄く引き延ばされていくかのよう。どんどん縁遠い人に思えてくる。ラムジーさんの子どもたちも、あの蒼のなかに、あの距離のなかに、飲みこまれてしまったかのようだった。(抜粋)
「ミセス・ラムジー!ミセス・ラムジー!」求めても得られないというあの恐怖が蘇ってきて、リリーは思わず声をあげた。あの方にはまだこうして苦しめる力があるの?すると夫人が手控えでもしたかのように、この苦しみも静かに日常の経験の一部となり、椅子やテーブルと同じレベルに落ち着いた。ラムジー夫人はいま --- リリーへのこのうえない優しさの一環だったのだろう --- そこの部屋の椅子にただ座っていた。編み針をひらりひらりと動かして、赤茶色の靴下を編み、上り段に影を落としながら。そこに、なんということなく座っていた。
伝えたいことがある。ただしいまは考え事や目の前の光景で頭がいっぱいだから、イーゼルを離れている暇はあまりないんだけど、と言いたげな足取りで、リリーは絵筆を片手にそそくさとカーマイケルの前を通りすぎ、芝生の際まで歩いていった。舟はいまどのあたりにいるかしら?ラムジーさんは?あの人に話したいことがある。(抜粋)
まるでなにかに呼ばれたかのように、リリーはあわててカンバスに向き直った。まぎれもなくここにある --- 自分の絵が。そう、緑や青をふんだんに使い。ラインを縦横に描きこみ、なにかを表現しようとしているものが。屋根裏部屋に掛けられる絵かもしれない。焼かれてしまうかもしれない。でも、それがなんだと言うのだろう?リリーはふたたび絵筆をとりながら自問した。上がり段に目をやれば、そこにひとけはない。またカンバスに目をもどすと、なんだかぼやけて見えた。そのとき不意に一瞬そこになにかをはっきり見てとったかのような力強い筆さばきで、リリーは一本のラインを絵の中央にひいた。さあ、これでできた。ようやく終わった。疲れきって絵筆を置きながら思う。ええ、わたしは自分のヴィジョンをつかんだわ。(抜粋)
関連図書:
柳田邦男(著)『人生の一冊の絵本』 、岩波書店 (岩波新書)、2020年
キョウ・マクレア(文)、イザベル・アーセノー(絵)、小島明子(訳)『きょうは、おおかみ』、きじとら出版、2015年
ジェイムズ・ジョイス(著)『ユリシーズ(全4巻)』、集英社(集英社文庫)、2003年
目次
第一部 窓
第二部 時はゆく
第三部 灯台
訳者あとがき
解説 津村記久子
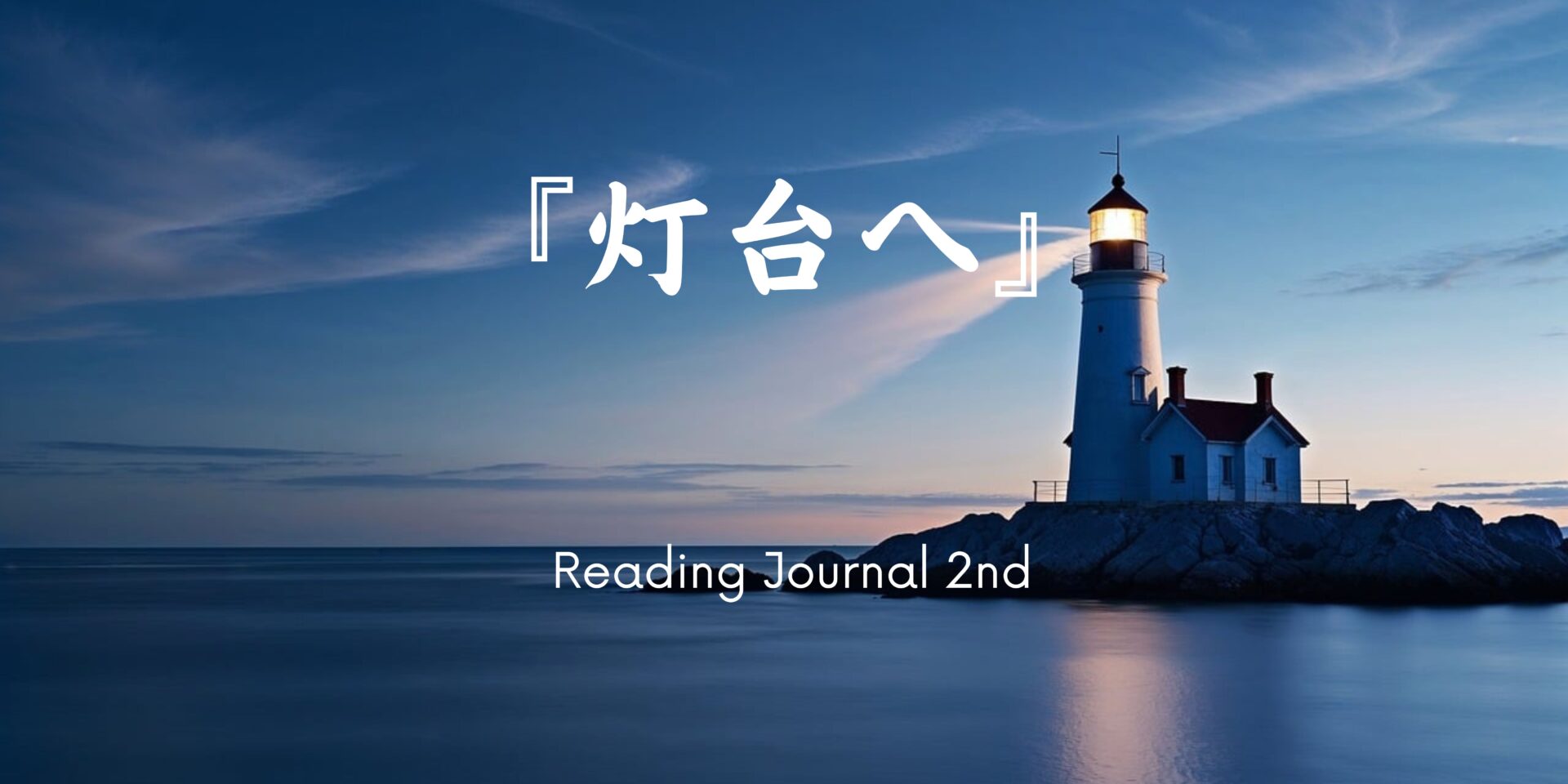


コメント