『成長を支援するということ』 リチャード・ボヤツィス 他 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
4 変化への渇望を呼び起こす
今日から「4 変化への渇望を呼び起こす」である。この章は、持続的な変化へのきっかけをつくるために、正しい問いかけをするにはどうすればよいかについて説明している。ここでは、正しい問いかけをすることによりPEAを呼び起こすことが問題となる。
従来の「誘導型コーチング」では、ネガティブな感情を引き起こす因子(NEA)を呼び起こし、支援される人にネガティブな反応を引き出してしまった。「思いやりのコーチング」では、支援したい相手に焦点を合わせて、相手を理解し、最大限のポジティブな感情を誘引する因子(PEA)を呼び起こすような問いかけが必要である。それでは、読み始めよう。
「正しい問いかけ」と「間違った問いかけ」
示唆に富む正しい問いかけは、相手のPEAを呼び起こし、副交感神経系を刺激する脳の部位を活性化させる。そして、その脳の部位は畏敬の念、喜び、感謝、好奇心といった感情と結びついている。
反対に間違った問いかけは、相手のNEAを呼び起こし、交感神経系を刺激する脳の部位を活性化させる。その脳の部位は、怖れや不安のような感情を活性化し、闘争、逃避反応に繋がる。
思いやりのコーチングを行うとき、相手に「理想の自分」やビジョンを明確にするように促すことから始める。その時、相手はPEAに支えらえてオープンな状態でいるように励まされ、変化とともに訪れる高揚感を経験する。このPEAは意図的変革の5つのディスカバリーを経て変化にたどりつくためのきっかけとして働く。
通常コーチや支援者は、対象者がこうするべきだという自分の考えで、誘導型コーチングへと動いてしまう。しかしその試みは、相手の義務感や防衛的な態度を引き出してしまい、失敗に終わることが多い。
ここで、コーチとして、相手にとって良いとわかっている物事をきれいさっぱり忘れるべきだという意味ではない。ただし、コーチは感情のセルフコントロールを実践する必要がある。相手が何を考えているかわかるまでアドバイスを控えることが必要である。
相手をPEAの支配下に置き、もっと心を開いてもらうためには、「オープンエンド型の質問」(自由回答)を行う必要がある。これは、「外向きのマインドセット」からの質問と同じ意味である。(第5章では、神経科学的側面の解説が行われる)
『人を助けるとはどういうことか』においてエドガー・シャインは、このような質問を「控えめな問いかけ[ハンブル・インクワイアリー]」と呼んでいる。
一方、相手とのやり取りにおいて間違った物事に焦点を合わせると、相手は心を閉ざしてしまう。
思いやりのコーチングは「監督すること」「教えること」に重きをおくコーチングではなく、相手を導くことで、相手に自身の感情を自覚させ、そしてまわりの人々や、状況の別の側面に目を向けさせる。そして対象者にPEAがもたらす助けをする。
手助けをしている相手に意識を集中する場合、相手の考えていること、感じていることを引き出す問いかけをすることが必要である。思いやりのコーチングでの最初の課題は、PEAをもたらす方法を見つけることである。そのため、様々な手段をもちいて相手のPEAを呼び起こす方法を探す。そこには、相手を「正したい」という気持ちを抑える必要があり、忍耐力と謙虚さを試される。そして、それができるためにはコーチが共感を示すことが重要になる。
ポジティブな感情を呼び込む方法
相手にポジティブな感情やPEAを呼び込み相手に希望を持たすきっかけを作る方法はいつもある。相手の夢やビジョンについて尋ねたり、思いやりを示す、ポジティブな感情を伝染させたり、マインドフルネスを実践してもよい、遊び心を掻き立てても、自然の中を散歩してもらうなどの方法もある。
相手に希望を与える
PEAを呼び込む方法として、まず相手に希望を与えることがある。相手に夢やパーソナルビジョンについて尋ねることでそれができる。能磁気共鳴機能画像法(fMRI)の研究では、夢やビジョンの話をすると、副交感系の活動に関する脳の部位が活性化する。
思いやりを示す
思いやりを寄せたり寄せられたりすることでPEAは刺激される。今までの人生で助けてくれた人に感謝することによって思いやりが生じる。また思いやりを引き出す方法として、ペットを飼うなどもある。
感情の伝染
人々は周囲の人の感情をとらえるようにできている。ネガティブな感情を察知すると交感神経系の刺激となり、防衛的になる。そのためコーチは自らの感情を意識することが重要である。感情は伝染するため自身の感情がネガティブな場合はそれが伝染する場合がある。
マインドフルネスの利用
PEAを引き出すためにマインドフルネスを利用することもできる。目の前の物事に集中することによりPEAを活性させる。そのほか祈りや、ヨガなどもこのような効果がある。重要なのは、こうしたテクニックを使って自分自身の気持ちを集中させPEAを呼び起こすことである。
遊びごころ
遊び心、喜び、笑いは副交感神経、ひいてはPEAを刺激する。
自然の中を歩く
PEAを刺激する活動としては、戸外でのウォーキングが挙げられる。森の中の散歩は、自然、動物、天候といった周囲の世界に対する知覚や感覚を敏感にする。
共鳴する関係
他者のためにPEAを呼び起こすこと望ましいが、それ以上にPEAを呼び起こすのが、コーチや支援者と対象者のあいだに築かれる共鳴した関係である。
対象者がモチベーションを与えられ、学び、変化するのには、次の3つが必要となる。
- ビジョンを共有すること
- 互いに思いやりを示すこと
- 二者の関係から生じる活力を共有すること
関連図書:エドガー・シャイン(著)『人を助けるとはどういうことか――本当の「協力関係」をつくる7つの原則』、英治出版、2009年
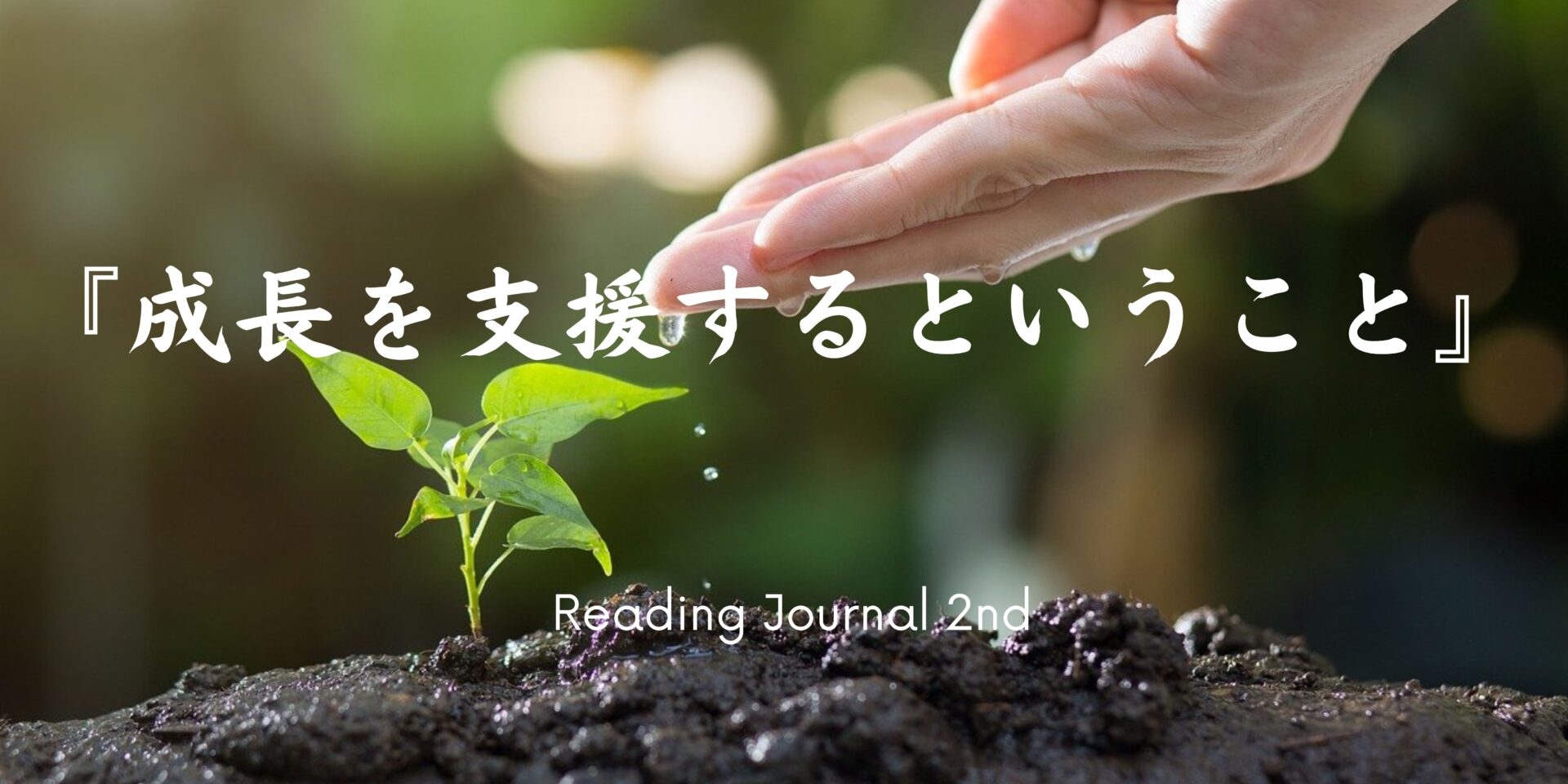


コメント