『作家の仕事部屋』 ジャン=ルイ・ド・ランビュール 編、中央公論新社(中公文庫)、2023年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序
前々から気になっていた本、『作家の仕事部屋』を買った。その実、「作家の仕事部屋ってのはどんなんだろうねぇ」みたいな興味であって、妹尾河童の『河童が覗いたヨーロッパ』のような本をイメージしていた、が・・・・違った。書名は、本来ならば「作家たちはどのように仕事をするか」(「訳者あとがき」より)であって、当然ながら仕事部屋の見取り図を載せているわけでもない。
目次を見ると、フランスのそうそうたる作家の名前が並んでいる。この本は、そのような作家一人ひとりに、「どのような方法で創作をするか」という問いに対する、インタビューをまとめたものである。帯に解説をしている読書猿さんの文が載っている。
因果的に制御できない「書く」という営為にフランスの知性はいかに挑んだか。1970年代からこそ実現した奇跡の書を完全復活。
書き物をしていて煮詰まっているすべての人へ。(抜粋)
なるほど、思っていたより、格調の高い本だったのかもしれない。では、読み始めよう。
今日のところは、「序」である。ここでは、編者のジャン=ルイ・ド・ランビュールが、どのような経緯で、どのような姿勢で、どのような方法で、このインタビューをまとめたかが書いてある。
まずは、このインタビューは、《ル・モンド・デ・リーヴル》(〈書物の世界〉の意で、《ル・モンド》紙の文芸欄)によって企画された。それは、もともと小説家よりも小説家の探索者になりたいと思っていた編者にとって絶好の好機であった。
当初は、インタビューを受けてくれる人がいるかという不安があったが、思いがけずみな積極的な反応を見せてくれた。そして、その候補者の選択に当たっては、フランスの領域に限ることにした。
インタビューにあたってはテープレコーダーを使い、まず常に「同じ質問」から始めた。そして、あとは相手に主導権を引き渡す方法をとる。
このインタビューにより、理想的な方法、つまり作家の卵が少なくともベストセラーが書けるような方法、は見つからなかった。しかし、このインタビューで並外れて興味深かったことは、「どのインタヴューも、そのまえのものと全く違っていた」ことである。
仕事の時間や執筆する環境などは様々に違い、ある人は町自体が影響を及ぼしていた。しかし、その中には正反対に見える作家たちに思わぬ類似、類縁性が潜んでいることも明らかになった。
《文は人なり》という言葉が真実なら、ある作家の仕事の方法を通して表現されるのは、その作家が抱えている問題の総体なのだ。(抜粋)
このように誰一人同じやり方で仕事をする人はいなかったが、その中で《胸を絞めつけられるような不安》という言葉が何度も繰り返された。
インタヴューはいずれも「あなたは仕事の方法をおもちですか。あるとすればどんな方法ですか」という共通の設問への答えからはじまっている。(抜粋)
関連図書:妹尾河童(著)『河童が覗いたヨーロッパ』、新潮社(新潮文庫)、1983年
目次
序 [第1回]
ロラン・バルト - 筆記用具との、ほとんどマニヤックな関係 [第2回]
アルフォンス・ブダール – 監獄や病院は不思議な現像液の役割を果たす [第3回]
エルヴェ・バザン - なにひとつ偶然にまかせない [第4回]
ミッシェル・ビュトール - 人格の二重化の企て [第5回]
ジョゼ・カバニス- 私は時間に賭ける、それは卓越した小説家だから [第6回]
ギ・デ・カール - 小説はラファイエット百貨店のようなものです [第7回]
エレーヌ・シクスー - 書いていない時の私は死んだも同然です [第8回]
アンドレ・ドーテル - 私は放徨する・・・夢と街と言葉のなかを・・・ [第9回]
マックス・ガロ - 書く楽しみのなかでももっとも本質的なもの、それは驚きです [第10回]
ジュリアン・ダラック - 仕事は一日に二時間 [第11回]
マルセル・ジュアンドー - 私は生きた録音機です [第12回]
ジャック・ローラン - 手で書く書物もあれば口述する作品もある [第13回]
J・M・G・ル・クレジオ - 私は夢を見ないために、苦しまないために書く [第14回]
ミシェル・レリス - 書物の一部は犬の散歩のあいだに出来上がる [第15回]
クロード・レヴィ=ストロース - 私のなかには画家と細工師がおり、たがいに仕事を引き継ぐ [第16回]
フランソワーズ・マレ=ジョリス - 人から聞いた話を利用する [第17回]
J・P・マンショット - あまり長いあいた人を殺さずにいてはいけない [第18回]
A・P・ド・マンディアルグ - 筆が進むのはパリとヴェネチアだけ [第19回]
パトリック・モディアノ - 嘘をつく術を習得すること [第20回]
ロベール・パンジェ - もっとも難しいのは冒頭の一句です [第21回]
クリスチアーヌ・ロシュフォール - 部屋のなかのハプニング [第22回]
フランソワーズ・サガン - 書くこと、それは自分をわすれようとすることです [第23回]
ナタリー・サロート - スナックの片隅のテーブル [第24回]
フィリップ・ソレルス - 回教僧の踊り [第25回]
ミシェル・トゥルニエ - 私は泥坊かささぎに似ている [第26回]
訳者あとがき [第27回前半]
解説 結果を約束しない様々な儀礼 読書猿 [第27回後半]
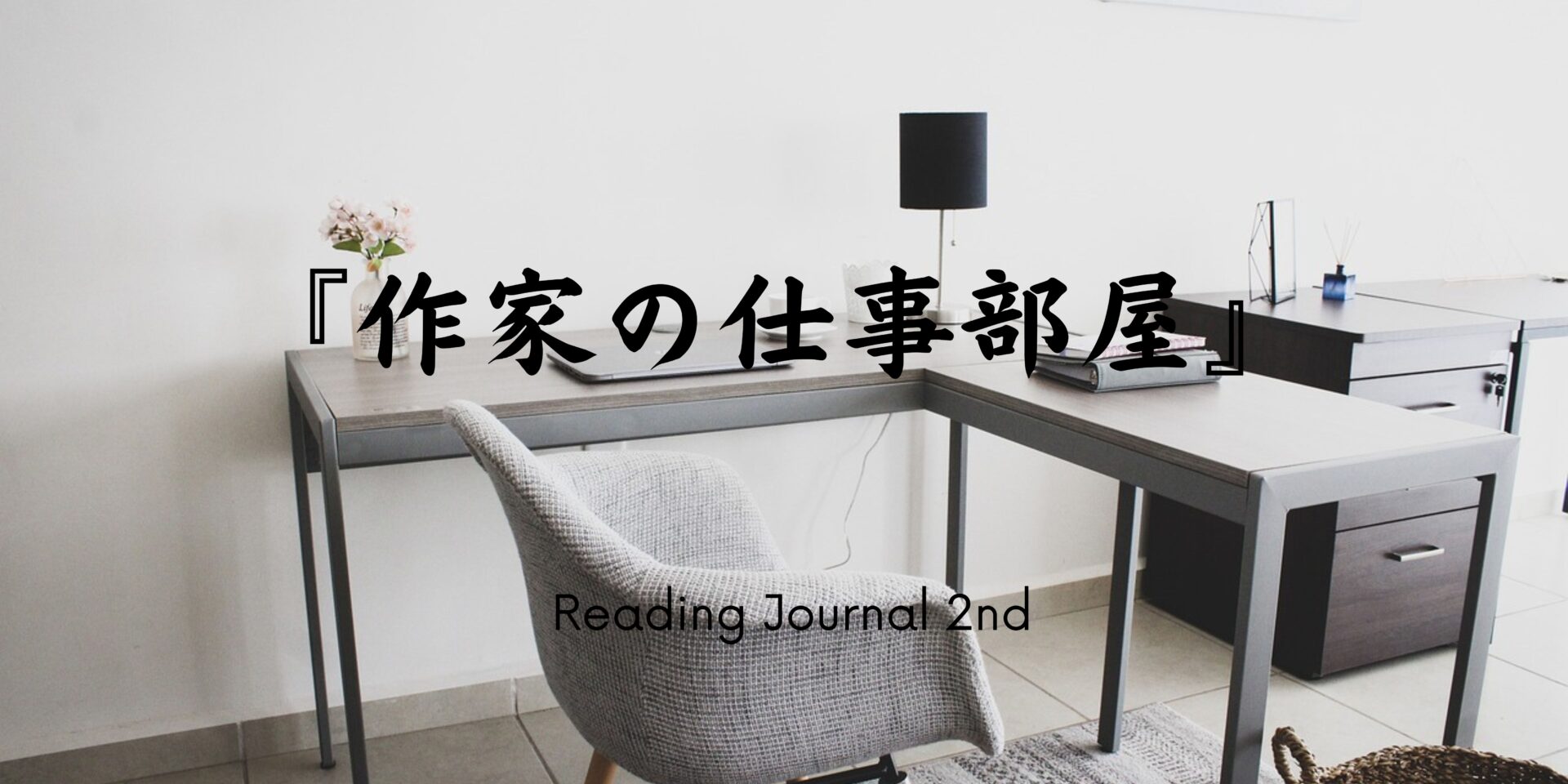


コメント