『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 孔子の素顔(その4) — 4 嘆く孔子
今日のところは、「第四章 孔子の素顔」の“その4”である。不屈の精神を持っていた孔子であるが、時として深い絶望感にとらわれることもあった。今日のところ“その4”では、そんな孔子の嘆きがわかる条である。それでは読み始めよう。
嘆く孔子
No.123
子曰く、甚しいかな 吾が衰えたるや。久しいかな、吾れ復た夢に周公を見ず。(述而第七)(抜粋)
先生は言われた。「私もひどく年老いたものだ。ずいぶんになるな、周公の夢をみなくなってから」。(抜粋)
孔子は、周公旦を理想の人物として崇拝していた。しかし、その周公旦の夢を見なくなったと、自分の老いを嘆いている。
この言葉には、いつまでも周公旦の夢をみつづけたいものだという気持ちを込め垂れており、孔子が最後の最後まで不退転の理想主義者だったことがわかる。(抜粋)
No.124
子曰く、鳳鳥 至らず。河 図を出ださず。吾れ已んぬるかな。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「(聖天子が出現すると飛来するという)鳳鳥(鳳凰)は飛来せず、黄河からは(聖天子が出現すると浮かび出るという神秘的な図形の)河図もでてこない。私はもうおしまいだ」。(抜粋)
この条は、節度ある社会の到来を切望した孔子が、その努力が報われず世の中の混乱が増すばかりという徒労感や絶望感を「鳳凰」「河図」という伝説により表現している。
「不可を知りて、而も之れを為す」(No.115)と不可能なことに挑戦し続けた孔子も、聖天子による太平の世がけっして到来しないと、嘆くことがあった。
No.125
子 川の上に在りて曰く、逝く者は斯くの如きか、昼夜を舎かず。(子罕第九)(抜粋)
先生は川のほとりで言われた。「すぎゆくものはすべてこの川の流れと同じだろうか。昼も夜も一刻もとどまらない」。(抜粋)
この条が有名な「川上の嘆」(上はほとりを指す)である。
ここでは川の流れてのようにすべてが時間とともに流れゆくことを嘆いている。しかし著者は、
ここには、暗い絶望感は認められず、生きとし生ける者は尽きることなく滔々と流れる川と同様に、大いなる流動性とともにあるという、一種、宇宙的ダイナミズムも読み取れる。(抜粋)
と言っている。
また、朱子の新注(ココ参照)により、「川の流れのように人はたゆまず努力し、無限に進歩、向上すべきだ」と説く読み方もあると紹介している。
No.126
子曰く、予れ言うこと無からんと欲す。子貢曰く、子如し言わずば、則ち小子何をか述。子曰く、天 何をか言わんや。四時行わる、百物生ず。天 何をか言わんや。(陽貨第十七)(抜粋)
先生は言われた。「私はこれから何も言わないでおこうと思う」。子貢が言った。「先生が何もおっしゃらなかったら、私たちは何によって語ったらいいのでしょうか」。先生は言われた。「天は何も言わないのに、四季はめぐり、もろもろの生物が生育する。しかし天はなのも言わない」。(抜粋)
ここで、孔子はなかなか理解しない弟子たちにいらだち、これからは何も言わないと宣言している。そして、子貢の私たちは何を頼りにしたらよいかという問いに対して、天が何も言わなくても万物がうまくいっているように、自分で考えて自立してやっていけると答えている。
著者は、この話を弟子たちに失望した孔子と、見放されたと思い驚いている弟子たちの様子が垣間見える面白い話と評している。
No.127
伯牛 疾有り。子 之れを問う。牖より其の手を執りて、曰く、之れを亡ぼせり。命なるかな。斯の人にして斯の疾有るや。斯の人にして斯の疾有るや。(雍也第六)(抜粋)
伯牛が不治の病にかかった。先生は見舞いにいかれ、窓の外からその手を握って言われた。「もうおしまいだ。天命というほかない。こんないい人間がこんな病気になるとは。こんないい人間がこんな病気になるとは」。(抜粋)
伯牛は冉耕のあざなである。徳行には、顔淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓と称される有徳の人だった。この条はその伯牛が不治の病になり、孔子が見舞いに行った時の話である。
有名な条であるが、幾つかわからないことがあると著者は言っている。一つはなぜ病室に入らず窓の外から手を握ったかであり、もう一つは、病人を前にして「之れを亡ぼせり(もうおしまいだ)」というのはあまりに露骨であるということである。これらにはいくつも説があるが、いずれも深刻な病状であることは一致している。さらに著者は、次のように言っている。
このように不明な点はあるものの、この孔子の発言においてもっとも印象的なのは、「斯の人にして斯の疾有るや。斯の人にして斯の疾有るや」のくだりである。深い詠嘆のこめられたこの言葉は、理不尽な病気にかかった人に捧げるもっとも感動的な言葉として、今に至るまで伝えられる。(抜粋)
No.128
顔淵死す。子曰く。噫、天 予れを喪ぼせり。天 予れを喪ぼせり。(先進第十一)(抜粋)
顔淵が死んだ。先生は言われた。「ああ 天が私を滅ぼした。天が私を滅ぼした」。(抜粋)
孔子が最も信頼していた最愛の弟子顔回(あざな淵)が亡くなったときの孔子の嘆きである(No80を参照)。このとき顔回四十一歳、孔子に先立つこと二年であった。七十一歳だった孔子は翌年には、子路を失っている(No94参照)。
No.129
顔淵死す。子 之れを哭して慟す。従者曰く、子慟す。曰く、慟する有るか。夫の人の為に慟するに非ずして誰が為にせん。(先進第十一)(抜粋)
顔淵が死んだ。先生は哭礼され慟哭された。従者が言った。「先生は慟哭されましたね」。(先生は)言われた。「私は慟哭したか。彼のために慟哭しないで、いったい誰のために慟哭しようというのか」。(抜粋)
前条と同じく顔回が死んだときの孔子の言葉である。「哭」は哭礼(死者のために大声をあげて泣く喪礼(喪中の礼)の一種)。慟は、哭礼の域をこえて慟哭すること。
顔回の棺の前で、激しく慟哭した孔子は、「彼のために慟哭しないで、いったい誰のために慟哭しようといすのか」と言い切っている。著者は、顔回を失った孔子の悲嘆が堰を切ってあふれるさまを如実にあらわした話であると評している。
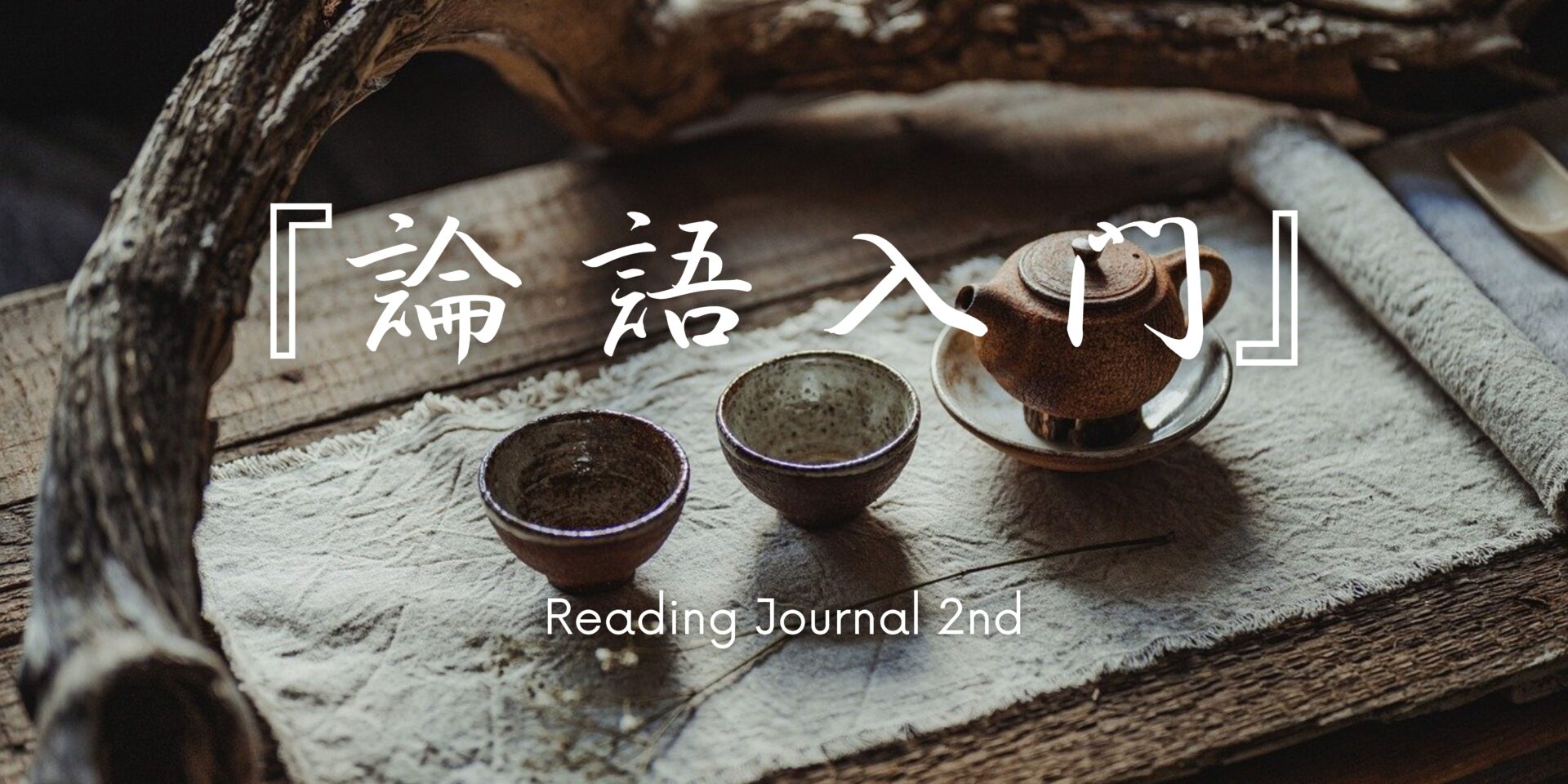


コメント