『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤 陽子著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
序章 日本近現代史を考える 歴史の誤用
前節を受けてこの節では、政治的な判断をするときに、過去の出来事からどうし誤った教訓を導いてしまうのかを論じている。
ここで著者は、アーネスト・メイが一九七三年に出版した『歴史の教訓』を題材にする。
『歴史の教訓』でのメイの問いは、
「なぜこれほどまでにアメリカはベトナムに介入し、泥沼にはまってしまったのか」(抜粋)
であった。
メイは、数々の史料や記録をみながら、三つの命題にまとめた。
① 外交政策の形成者(makers of foreign policy) は、歴史が教えたり予告したりしていると自ら信じているものの影響をよく受けるということ。
② 政策形成者(policy makers)は通常、歴史を誤用するということ
③ 政策形成者は、そのつもりになれば、歴史を選択して用いることができる。(抜粋)
非常に優秀な政策の形成者といえども、歴史の教訓を導き出す時に思い浮かべる範囲は限定的であり、そしてまず思いついた事柄に囚われ、より広範囲に類型例を探すような事はしない、このようだメカニズムで歴史の誤用が起きるとメイは、言っている。
メイは、第二次世界大戦が終結した時に、「無条件降伏」を選んだことは、「第一次世界大戦の終結方法」の教訓の誤用であり、アメリカがベトナムに深入りしたのは、「アメリカにとっての中国の喪失」の経験からの教訓の誤用であるとしている。この節の後半は上の二つの誤用について論じている。
関連書:アーネスト・R1・メイ(著)『歴史の教訓―アメリカ外交はどう作られたか憲法とは何か』岩波書店(岩波文庫)2004年

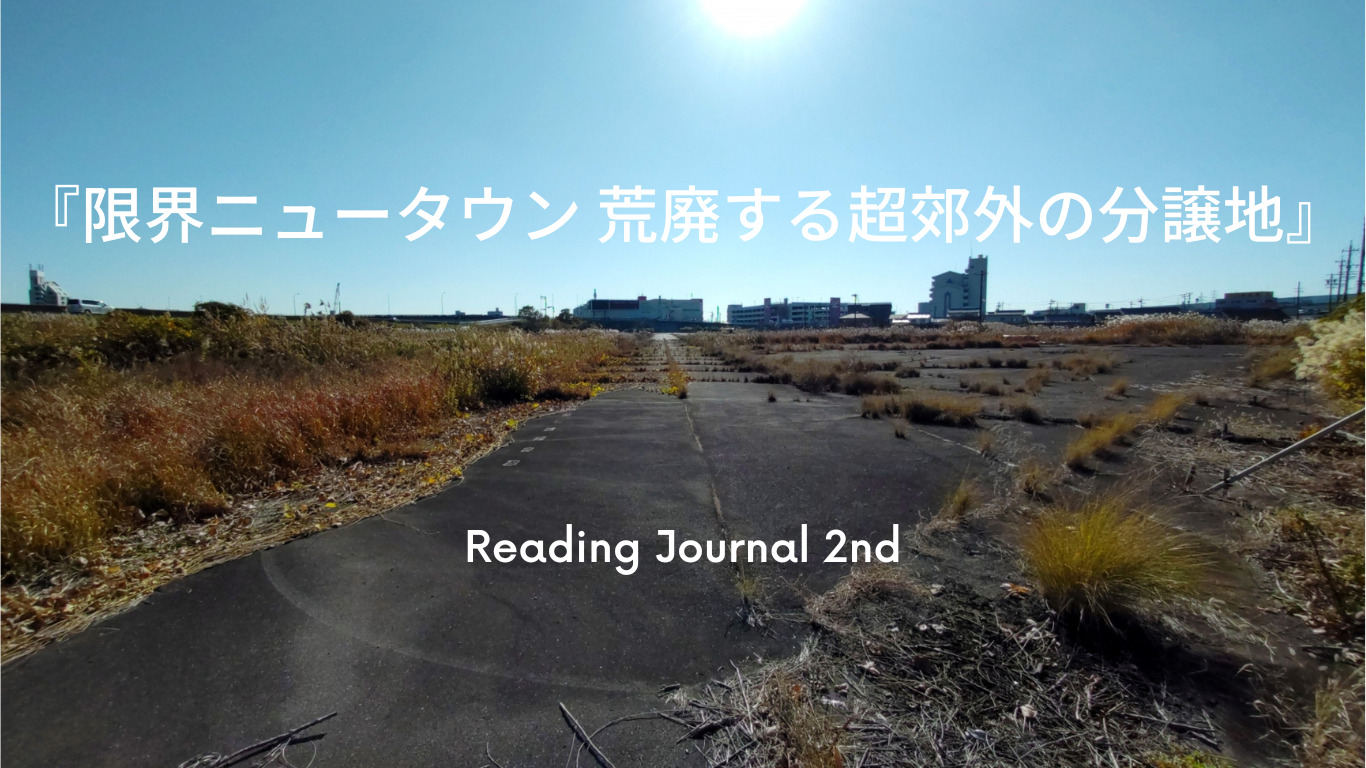
コメント