『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
声喩 音の形で意味する(形のレトリック2 形を工夫する)
擬声語(音そのものを写したことば)や擬態語(さまざまな様態を写したことば)を合わせてオノマトペという。
ここで著者は、井上ひさしの『私家版 日本語文法』でゴルゴ13に注目した部分を引用して、解説している。しかし、このオノマトペは、あまり評判が良くなく、多くある文章読本でも分が悪い。しかし、井上ひさしは、このオノマトペを多用する。ここで、さらに井上ひさしの『日本亭主図鑑』『吉里吉里人』からオノマトペの部分を引用している。
次に著者は、このオノマトペは、場面転換の合図として有効に働きます、として宮沢賢治の『注文の多い料理店』から猟に来た二人の若い紳士が道に迷う場面を引用している。
風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はかさかさ、木はごとんごとんと鳴りました。(抜粋)
ここで、著者はロジャー・パルバースの『新本当の英語がわかる』から、この部分の英訳を引用している。
The wind bellowed, the grass swished, the leaves rustled, and the trees rumbled low. (抜粋)
ここで、「どうと」「ざわざわ」「かさかさ」「ごとんごとん」に対応する英語のオノマトペは”bellowed”、”swished”、”rustled”、” rumbled”であり、日本語ではオノマトペ+動詞となっているのに、英語では動詞ひとつであることを指摘している。
日本語はSOV型のことばですので、動詞が文末にきます。文末は文の締めくくりですから、そこにはなんらかの重みが必要となります。そのとき、動詞一語ではちょっと軽く、「どうと吹いて」のような動詞を補う表現があるとちょうど釣り合いがとれるということがあるでしょう。日本語でオノマトペが活躍する理由のひとつは、こんなところに潜んでいるのかもしれません。(抜粋)
「オノマトペ」ってよく聞くけど、擬声語と擬態語を合わせて言うんだね!メモメモ。っで、「オノマトペ」って・・・・・なんでそういうの??
っと思って、検索してみました。すると、
もともとの語源は、古代ギリシャ語で「onoma(名前)」と「poiein(作る)」を組み合わせた「onomatopoiia(オノマトポイーア)」に由来する、とある。英語では「onomatopoeia(オノマトペア)」、フランス語では「onomatopēe(オノマトペ)」という、らしい。つまり、おフランス語なんだね♪(出典はOggi.jpのココです!)
そうなんだ。もともとギリシャ語? てっきり変な和語だと思ってた。(つくジー)
関連図書:
井上ひさし(著)『私家版 日本語文法』、新潮社(新潮文庫)、1984年
井上ひさし(著)『日本亭主図鑑』、新潮社(新潮文庫)、2013年
井上ひさし(著)『吉里吉里人』(上)(中)(下)、新潮社(新潮文庫)、1985年
宮沢賢治の『注文の多い料理店』、新潮社(新潮文庫)、1990年
ロジャー・パルバース(著)『新 ほんとうの英語がわかる―ネイティヴに「こころ」を伝えたい』、新潮社(新潮選書)、2002年
漸層法 しだいに盛り上げる(構成のレトリック1 仕掛けで語る)
ここより、構成のレトリックに入る。構成のレトリックでは、「文より大きな単位の構成の変化に関係するレトリック」を取り扱う。
「漸層法」とは、ことばを足していくことで、クライマックスを形成する技法である。ここでは、まず、芥川龍之介の『藪の中』から引用をしている。
一度でもこの位憎むべき言葉が、人間の口を出た事があろうか? 一度でもこの位忌まわしい言葉が、人間の耳に触れたことがあろうか? 一度でもこの位、 --- (突然迸る如き嘲笑)(抜粋)
ここでは、「一度でも」で始まる文が形を変えながら、三回繰り返し、しだいに盛り上がり、最後に絶句してしまう。
次に著者は、漸層法とは違い、「反漸層法」とも言うべき用法があるとして、清水義範の『蕎麦ときしめん』と井上ひさしの『ブンとフン』から引用している。
ブンの決心はダイヤモンドや大理石より、それどころか、ついてから一か月たったお餅よりかたそうだった。(抜粋)
ここで「AやBより、それどころか、Cよりかたそうだった」となっていてA、B、Cの順に硬度が下がっている。このズレにおかしみが生じている。
漸層法は、つまり、クライマックス形成には、このような語句や文の連鎖にのみかかわるのではありません。山場の形成は、ひとつの段落やテクスト全体にもかかわります。意味を均等配分したテクストは、平板で印象がうすく、なかなか最後まで読んでもらえないでしょう。テクスト全体に構造を与え、どこに大きな山をもってきて、どこに小さな山をいくつ配置するか---、これは、個々の文を仕上げることと同じくらい大切なことです。漸層法は、テクストの仕掛けです。それゆえ、事前によくプランを練ることが大切である。(抜粋)
関連図書:
芥川龍之介(著)『地獄変・邪宗門・好色・藪の中』、岩波書店(岩波文庫)、1980年
清水義範(著)『蕎麦ときしめん』、講談社(講談社文庫)、1989年
井上ひさし(著)『ブンとフン』、新潮社(新潮文庫)、1974年
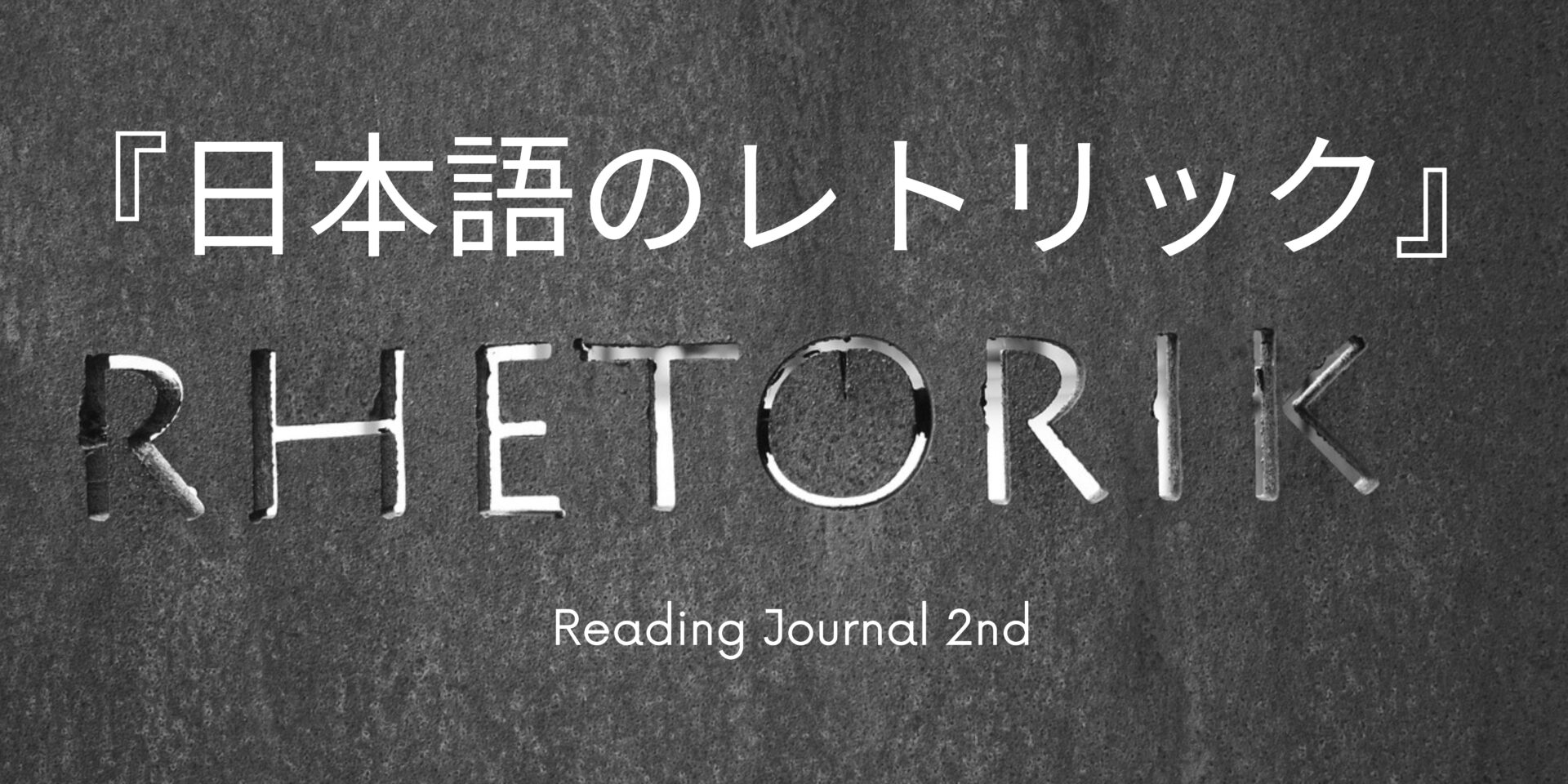


コメント