『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
修辞疑問法 疑問文で叙述する(意味のレトリック3 意味を迂回する)
「修辞疑問法」は、形は疑問文でも、意味は平叙文という表現法である。たとえば
「誰がこんな事態を予想できただろうか」(抜粋)
は、形は疑問文であるが、「誰も・・・できなかった」という意味である。形のうえでは問いでるが、「誰」の答えを求めているのではない。
ここでは、伊藤正男の『脳の不思議』、養老孟司の『考えるヒト』からの引用文を使って修辞疑問法を説明している。
一般に疑問文は、疑問を発することによって、相手(聞き手・読者)に問いかけ、話しかけます。ダイアログ(対話)を求めます。問いと答えのキャッチボールといえばいいでしょうか。修辞疑問法は、たとえ本当に答えをもとめているのではなくとも、やはり対話指向です。(抜粋)
つまり、修辞疑問法は、テクストの中に対話を用い、文が一本調子の独白調(モノローグ)になることを防ぐ働きがある。そして、もう一つの利点は、文末に「か」が来ること。つまい、文末がそろってしまうことを防ぐことである。
関連図書:
伊藤正男(著)『脳の不思議』、岩波書店(岩波科学ライブラリー)、1998年
養老猛司(著)『考える人』、筑摩書房(ちくま文庫)、2015年
含意法 意味を推測させる(意味のレトリック3 意味を迂回する)
コミュニケーションは、ある発話そのものより、そこから推測される内容によって進むことがあります。(抜粋)
「含意法」とは、推論によって意味を伝える方法である。
ここで著者は中島敦の小説『山月記』から文を引用している。
己の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。(抜粋)
ここで、虎に変身していた李徴の毛皮が濡れていたのは、涙を流したからである。李徴が泣いていたことを「夜露のためばかりでなない」と表現している。
話し手と聞き手が協調して進む会話(文章)は、
- (一) 本当のことを
- (二) 必要なだけ
- (三) 当面の話題に直接関連あることにかぎって
- (四) 明快に順序だてて
話すという暗黙のルールがあり、このルールに従っていれば推論をする必要はない。
しかし、実際はこのように話が進むわけではなく、真実以外の余分なこともまぜこぜに語ることもある。そしてこれを意図的に行えばその場に応じていろいろな含意が生じる。
一例として、話を唐突に変える場合は、「当面の話題に直接関連あること」に反する。この意図的なルール違反は「その話題は不適切なのでやめましょう」とう含意を含んでいる。ここで著者は筒井康孝の『ロートレッタ荘事件』からの引用でこの例を説明している。
会話は、上記の(一)~(四)のルールが前提であるので、これに反する場合はそれなりに理由があると、私たちは推論する。これにより含意、暗黙の意味を引き出している。
日常会話は、このような含意にもとづいておこなわれている。ここで実際の例を、同じく筒井康隆の『文学部唯野教授』から引用している。
全然違う話であるが、前に読んだ『モチベーションの心理学』に、この『山月記』が出てきた。「自尊心」についての議論のところだったが、『山月記』の内容を詳しく紹介し、
この短い小説にわれわれが感銘を覚える理由のひとつは、自分の心に潜んでいる李徴を感じ取るからではなかろうか。(抜粋)
と言っていた。感慨深い内容だったよぉ~~~。(つくジー)
関連図書:
中村敦(著)『李陵・山月記』、新潮社(新潮文庫)2013年
鹿毛雅治(著)『モチベーションの心理学 : 「やる気」と「意欲」のメカニズム』、中央公論新社(中公新書)、 2022年
筒井康孝(著)『ロートレッタ荘事件』、新潮社(新潮文庫)、1995年
筒井康孝(著)『文学部唯野教授』、岩波書店(岩波現代文庫)、2000年
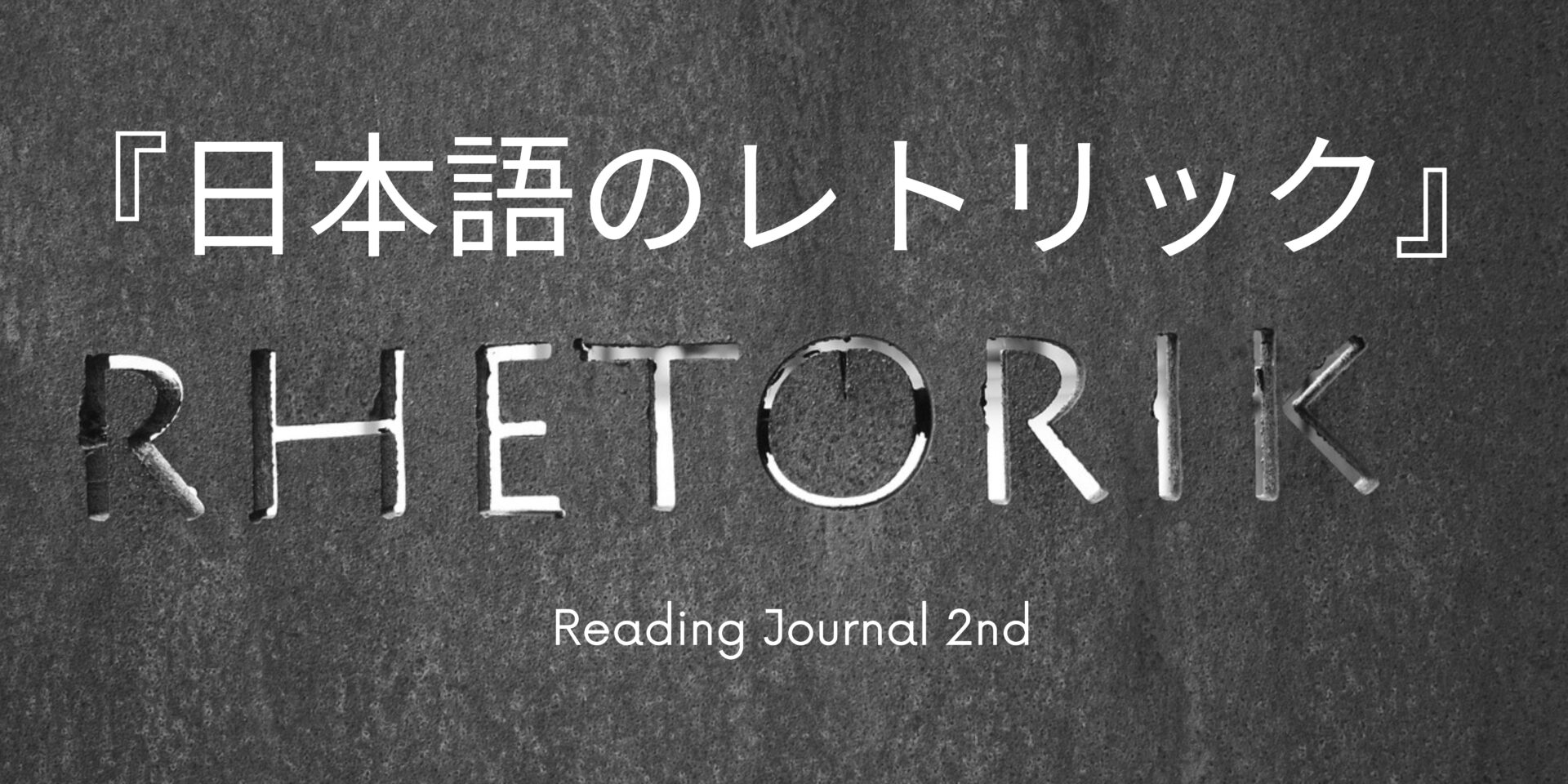


コメント