『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
原本あとがき、学術文庫版あとがき
前々回の「エピローグ」で終わりかと思ったら、前回「付録」があった。もう絶対終わりだよね!と思うと、「原本あとがき」と「学術文庫版あとがき」と2つも”あとがき”があった!それでは、読んでしまおう
原本あとがき
まずは、「原本あとがき」である。最初に、本書(原本)で夏目漱石の「吾輩」(学術文庫版には付録として収録)と浮世絵師・歌川国芳をなぜ取り上げなかったかが書かれている。夏目漱石の「吾輩」を取り上げなかった理由は、単に近代文学に疎いからであるが、歌川国芳を取り上げなかった理由は、文献がほとんどないからである。
歌川国芳が猫好きだったで「あろう」ということはその絵からうかがえるが、資料としては、後代の『歌川列伝』くらしかない。
また、膨大な江戸俳諧や連句、絵草紙の猫も取り上げなかったことについては、自分の怠慢であったと反省しているとしている。
そして、次にこの本における著者の姿勢について、
私はこの本でなんでも「文献、文献」といってきた。文献がなぜそんなに大事なのか眉をひそめる人もいるだろう。しかし、今までの猫の本で文献を中心としたものは意外なことにあまりないからである。(抜粋)
としている。
著者は、「文献がないもと何も語ってはいけない」という教育を受けていたため、伝説や口承ばかりの猫の本に満足が出来なかった。そのため、文献に猫がどのくらい登場するかを総ざらいしてみたいと思ったのが、本書を書く動機であるとしている。
本書では、これまであまり言及されてこなかった、禅宗と猫の関係や朝鮮出兵について行った(らしい)猫の話などの新しい面にも光があてられたと自負していると言っている。
学術文庫版あとがき
次に「学術文庫版あとがき」である。
まず、著者は原本の出版から十四年がたち、著者自身の考え方も随分変わったと言っている。そこで
文庫化にあたっては論調をなるべく変えないようにしつつ、出来るだけ加筆・訂正を行うことにした。(抜粋)
としている。
まず、大きく考えが変わったところとして、猫と人間とのかかわりを素朴に受け止めて礼賛する姿勢を保留した点であるとしている。文献や絵に描かれた猫は、単に可愛い愛玩動物だからではなく、書き留められるだけの必然性があったからであり近代的な感性で切り取ってはいけないと考えを改めた。
「昔も今も同じ感情を持っていたのだ」という共感が古典文学が読み継がれている一つの理由ではある。しかし著者は、それだけでは理解しがたいことがあるとしている。そして、
古典文学が生き残ってきたのは、どんな時代や環境の違いがあっても人はみな同じことを考えるということが「実感」されるからではない。むしろ、世の中が変われば人も変わるということを疑似体験できるからだといいいだろう。単なる共感の「だだ洩れ」に終わらない古典文学の理解は、残された資料を読み解いていくという手続きさえ踏めばかなうのだ。(抜粋)
と言っている。
[完了] 全19回
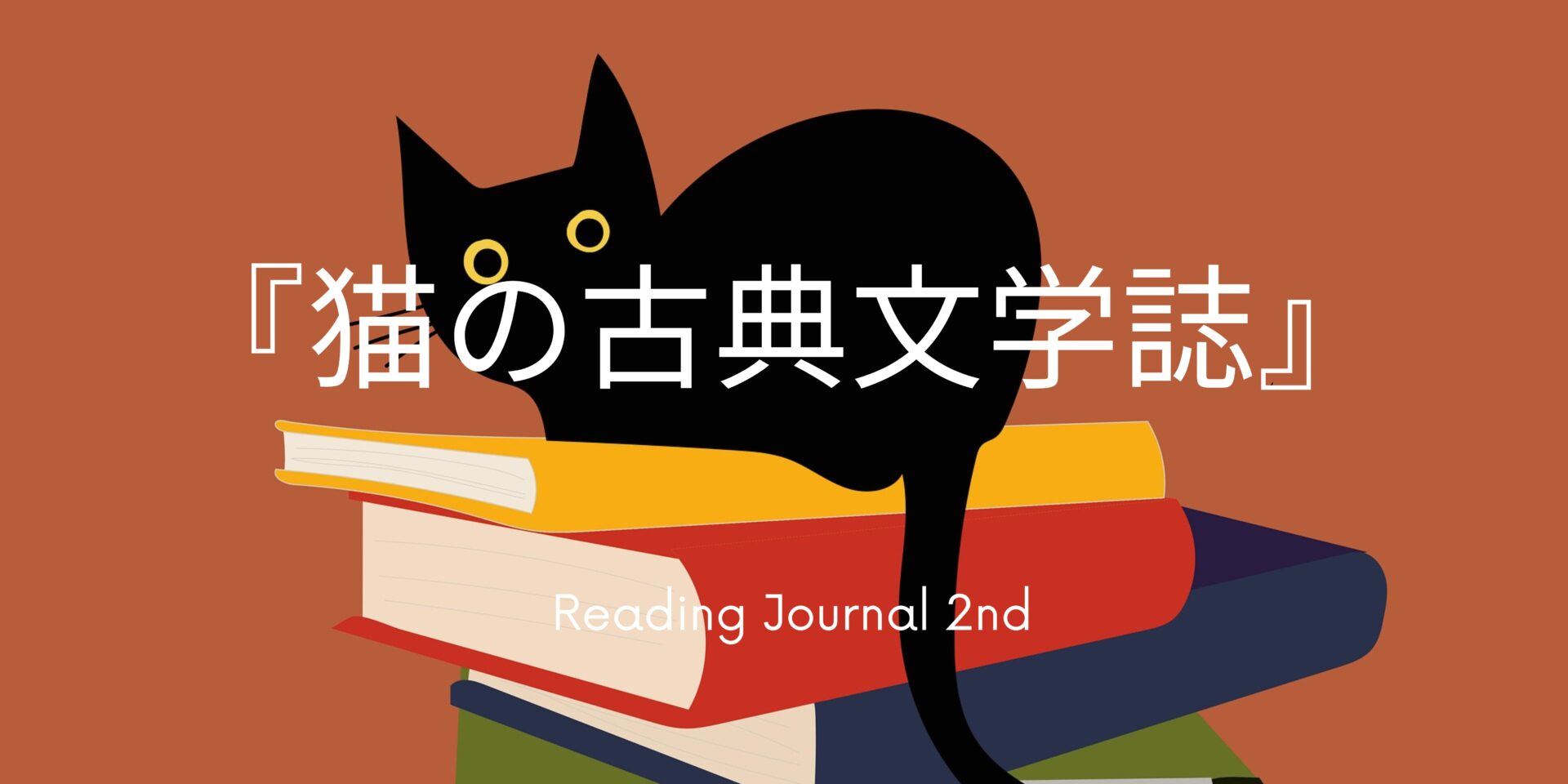


コメント