『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
【付録】漱石先生、猫見る会ぞなもし
前回「エピローグ」まで達したので、この本も終わりかと思うと、付録として“漱石先生、猫見る会ぞなもし”があった。これは、渋谷区立松濤美術館で行われた「ねこ・猫・猫」展の図録に所収されたものを、加筆・修正したものであるらしい。それでは、読み始めよう
漱石の猫の毛並み
漱石の猫「吾輩」は、日本で一番有名な猫であると言ってもいい。著者は、この漱石の猫に改めて関心を持ったのは、同僚の研究室の机の上にあった文庫本『吾輩は猫である』(新潮文庫、2003年)の表紙を見たときであった。その表紙には、真っ白な長毛種に丸い顔の猫、ペルシャ猫のような猫が描かれていた。
「吾輩」は、駄猫で毛色は「単灰色に斑入り」(『吾輩は猫である』六)でもちろんペルシャ猫ではない。著者が思い当たるのが、「吾輩は波斯産の猫の如く黄を含める淡灰色に漆の如き斑入りの皮膚を有している」(一)という部分だけである。そしてその絵の作者を確かめると、「カバー装画 安野光雅」であった。
『吾輩は猫である』は、これまで二度映画化されていて、著者はそのうち一九七五年公開の映画を見ているが、その猫はいやに立派なロシアンブルーや、シャルトリューのような猫で、著者は違和感があったと言っている。
著者にとっての「吾輩」は、漱石筆の『あかざと黒猫』(大正三年(一九一四)、神奈川近代文学館蔵)である。この猫は夏目家三代目の猫がモデルである(夏目鏡子『漱石の思い出』、文春文庫、一九九四年)。しかしこの絵は、漱石の絵の先生である津田青楓に酷評されている(夏目房之介「趣味の効用」『芸術新潮』二〇一三年六月号)。また、この芸術新潮の表紙は矢吹申彦の漱石と猫であるが、猫は真っ黒な毛色に喉の下と足先だけ白い。
漱石は猫好きか?
夏目家の初代の猫は、どこからやってきたのかわからない猫で、いくらつまみ出してもまた戻ってくる猫だった。しかし、
この猫を見た按摩のお婆さんが、「奥様、この猫は全身足の爪から黒うございますが、これは珍しい福猫でございますよ。飼っておおきになるときっとお家が繁昌いたします」というので買うことにしたという。(抜粋)
この猫は、「全身黒ずんだ灰色の中に虎班があり、一見黒猫に見える」猫で、「吾輩」に影響を与えている。鏡子自身は最初「猫が好きでない」とし、初代の猫をだいぶ邪見にあつかった。しかし、按摩のお婆さんが「福猫」の太鼓判により、自分で猫のご飯におかかを振りかけたりするようになった。
そして、漱石自身もインタビューで、猫を「好きではありませんよ」と言っている(大正四年(一九一五)八月二十五、二十六日付『報知新聞』「猫の話絵の話」)。しかし、漱石はこのインタビューで、当時シャム(タイ)にいた井田芳子にふれてシャム猫の話に興じている。そして、井田への書簡(「漱石全集」二十四巻)に「シャムの猫を是非下さい」と書いている。
猫が好きか嫌いかなどという詮索は、漱石にとって無用であろう。文筆稼業の気晴らしとして、昼寝を決め込む猫にちょっかいを出す以上のものはない。明治三十一年(一八九八)漱石は正岡子規にこんな句を送っている。(『漱石全集』十七巻)漱石と猫とのつきあい、推して知るべしである。
行く年や猫うづくまる膝の上
膝の上の猫とは、漱石先生、うらやましいぞなもし(抜粋)
猫の展覧会
朝倉文夫の猫塑像
漱石が唯一残した美術評論「文展と芸術」は第六回文展(大正元年(一九一二))の鑑賞録でもある(陰里哲郎解説『夏目漱石・美術批評』講談社文庫、一九八〇年)。この文展で漱石は朝倉文夫の彫像(青年の像)を絶賛している。
この朝倉文夫は、多数の猫とともに暮らした愛猫家で、多くの猫の塑像を製作した(『作家の猫』平凡社・コロナ・ブックス、二〇〇六年)。朝倉は「猫百態展」を開くことが夢(宮下太郎「幻の「猫百態展」」『作家の猫』所集)で、実際に数十点にのぼる猫の塑像を作った。
上野精養軒での猫の展覧会
実際の猫を見る「品評会」もこのころ始まった。このような品評会が開かれるには、猫の品種が認定されることが必要で「純潔種」を保護する役割を担っている。
ここで著者は、ウィルリッヒ・クレヴァー『猫の本』(同朋舎、一九八七年)、ハリエット・リトヴォ『階級としての動物』(国文社、二〇〇一年)などの参考文献を使って、イギリスで発祥したキャットショーの歴史を解説している。
そして日本でキャットショーが、イギリスに遅れること数十年、大正二年(一九一三)、上野精養軒で行われた。三月十五日の東京朝日新聞に
ニコニコ倶楽部にて四月五日を期し、猫の展覧会を上野公園精養軒に開き、動物園の黒川技師以下、審査員となり、賛成者中に夏目漱石、村井弦斎、菊五郎、小さん、島崎柳塢氏等ある由。加入希望者は来る三十日迄に申し込むべしと。(抜粋)
という記事が載った。夏目漱石自身は、当時胃潰瘍で入院していて展覧会には顔を出していないようだが、この展覧会には漱石にゆかりの朝倉文夫が自分の猫を出品していた。
この会は、生身の猫と猫の美術をダシにした社会的地位の高い人々の社交場であったようだが、日本において猫が鑑賞の対象として価値を持つ存在となった時代の到来を象徴している。
少なくとも都市においては、猫はねずみ対策の必要に迫られて近所から適当に調達する「家畜」ではなくなったのだ。美しい猫を愛で、和毛を愛撫するだけでない。見られる存在としての猫は、階級を端的に示すシンボルとして日本の文化に組み入れられたのである。(抜粋)
関連図書:
夏目漱石(著)『吾輩は猫である』、新潮社(新潮文庫)、2003年
夏目鏡子(著)『漱石の思い出』、文藝春秋(文春文庫)、1994年
夏目房之介(著)「趣味の効用」『芸術新潮』2013年6月号、新潮社、2013年
夏目漱石(著)、陰里哲郎(解説)『夏目漱石・美術批評』、講談社(講談社文庫)、1980年
平凡社編集部(編)『作家の猫』、平凡社(コロナ・ブックス)、2006年
ウィルリッヒ・クレヴァー(著)『猫の本』、同朋舎、1987年
ハリエット・リトヴォ『階級としての動物』、国文社、2001年
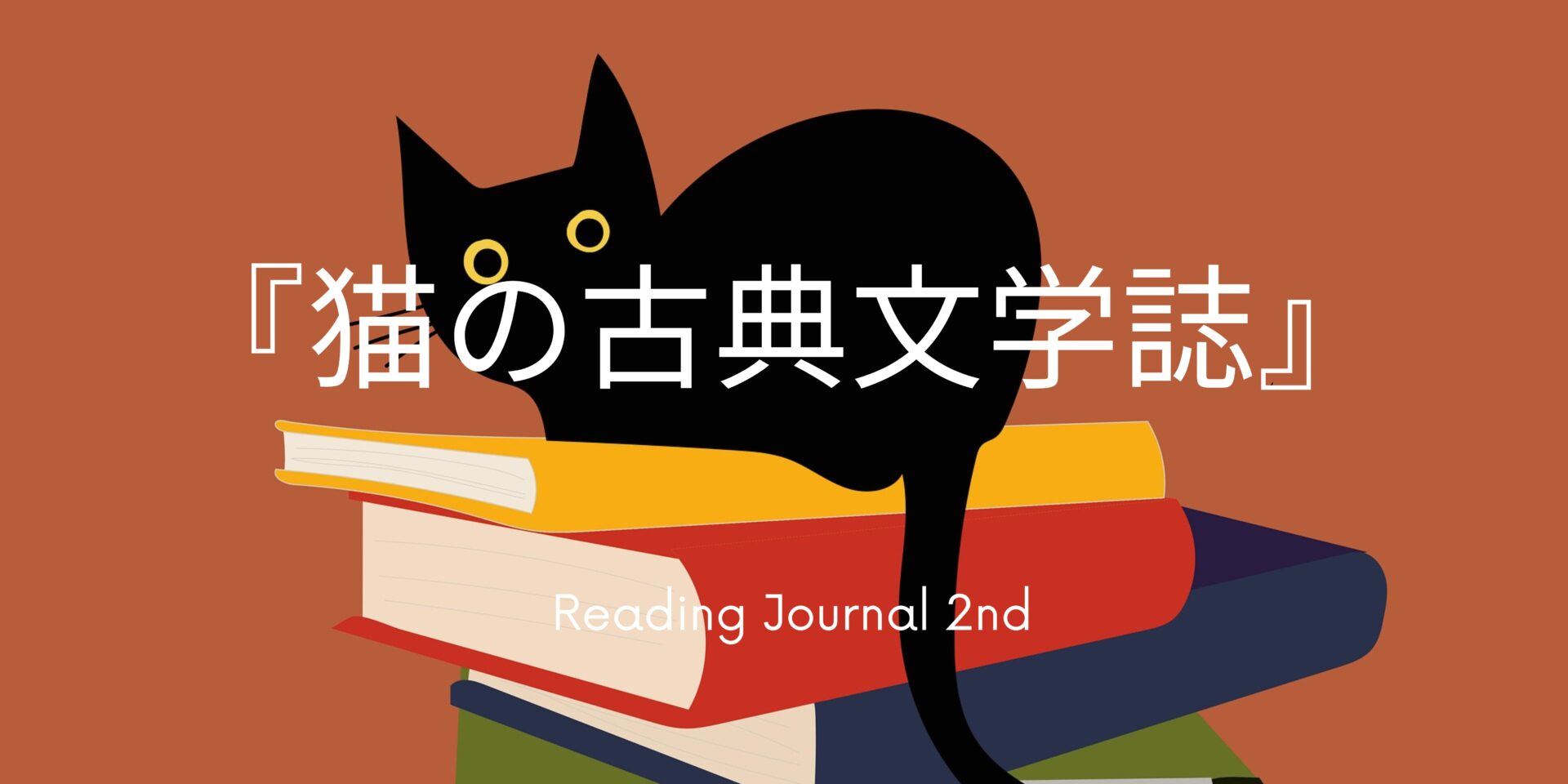


コメント