『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第九章 描かれた猫たち(後半)
今日のところは、第九章『描かれた猫たち』の”後半“である。”前半“では、“涅槃図の猫”と『十二類合戦絵巻』をまとめた。今日のところ“後半”では、“招き猫”をまとめる。そしてそして最後に「エピローグ」がある。さてと、ラストスパートである。
日本最古の招き猫
ここでの話題は「招き猫」。しかし、著者は招き猫の研究は多く、ここでその歴史を語るつもりはないと言っている。そして、
私が述べたいのは、京都にある日本最古の招き猫のことなのである。(抜粋)
と話題をフォーカスしている。
通常の研究書では、最も古い招き猫の由来は東京の豪徳寺の物としている。豪徳寺の由来書には、
豪徳寺がまだ小庵であったころ、庵主の僧が一匹の猫を飼っていた。あるとき、庵主が猫をなでながら、独り言に、精あるものならば、育ててもらった恩に報いてもよいのにといった。それを聞き、猫は門前でうなだれていた。そこへ立派な狩装束の武士が、二、三の供の者をつれて通りかかった。すると猫が、前足をあげて武士を招いた。不思議に思った武士が、猫についていくと、庵がある。和尚が一行を内に招じ入れるや、外では激しい雷雨となった。そこで雨やどりしながら、武士は庵主の法談を聞いた。老僧の高徳・博識と猫の霊妙なふるまいに感じた武士は、その庵を菩提寺に定めた。その武士は、近江の彦根藩主、井伊家の第二当主、井伊直孝であった。(抜粋)
この豪徳寺の直孝の墓の近くに猫塚を作って菩提を弔ったのが招き猫の信仰の始まりで、寺の門前で焼き物の座像を作って売り出したのが招き猫の像であるとしている(小島瓔禮『猫の王』、小学館、1998年)。豪徳寺が井伊家にふさわしい大寺となったのは、寛文年間(一六六一~七三)から延宝年間(一六七三~八一)であるので、そのころに招き猫信仰が始まったということが出来る。
しかし、この豪徳寺のよりも少し早く招き猫信仰が京都に発生していたのである。それが三条京坂の近くにある壇王法林寺、通称「だん王」さんだ。(抜粋)
井上頼寿の『京都民俗志』(平凡社、一九八二年)によると
三条大橋東づめの壇王(今の壇王法林寺)の主夜神の神使は猫なので、招き猫を出す。緑色の猫で右手をあげる。徳川時代は民間では左手の方の招き猫より他は作らせなかったという。(抜粋)
と書かれている。
壇王法林寺を慶長十六年(一六一一)に復興した袋中上人は、琉球まで行ったことで有名で『琉球神道記』を著している。この袋中上人は、「主夜神尊」という神を祀った。そしてこの「主夜神尊」の信仰が十八世紀になると急速に高まった。
井上頼寿氏が記している「緑色の招き猫」とは、この主夜神尊のお使いである黒猫をかたどったもので、右手をあげて招いている。この猫像がいつ頃から作られ始めたかはわからないが、寺では豪徳寺よりは少し古いと説明している。(抜粋)
関連図書:
小島瓔禮(著)『猫の王』、小学館、1998年
井上頼寿(著)『京都民俗志』、平凡社、1982年
エピローグ
最後に短いエピローグがある。ここでは、その終わりの部分を抜粋する。
猫と人との繋がりは、長く、深い。一九九八年の冬、「古代エジプト展」を見に行ったとき、猫面人身の「バスト」と呼ばれる知の女神の像や、猫のミイラを目にして、私はいっそうその思いを強く持った。あるいは貴族の膝に抱かれ、あるいは僧侶の伴侶となり、あるいは民家でねずみを退治をし、数限りない猫たちは人とともに生きてきたのである。そして、私は、過去においてよき友だった幾匹かの猫に思いをはせた。
「猫は九つの命を持っている」ということわざがある。そういえば、佐野洋子氏も『100万回生きたねこ』という名作絵本を作った。一匹の猫の命は、人よりもはるかに短いけれど、人が愛した猫の魂は永遠に生きるのだ。長い長い歴史の中でくりひろげられた猫と人とのドラマ---。そのすばらしさを心に刻みつつ、この本を閉じることにしたい。(抜粋)
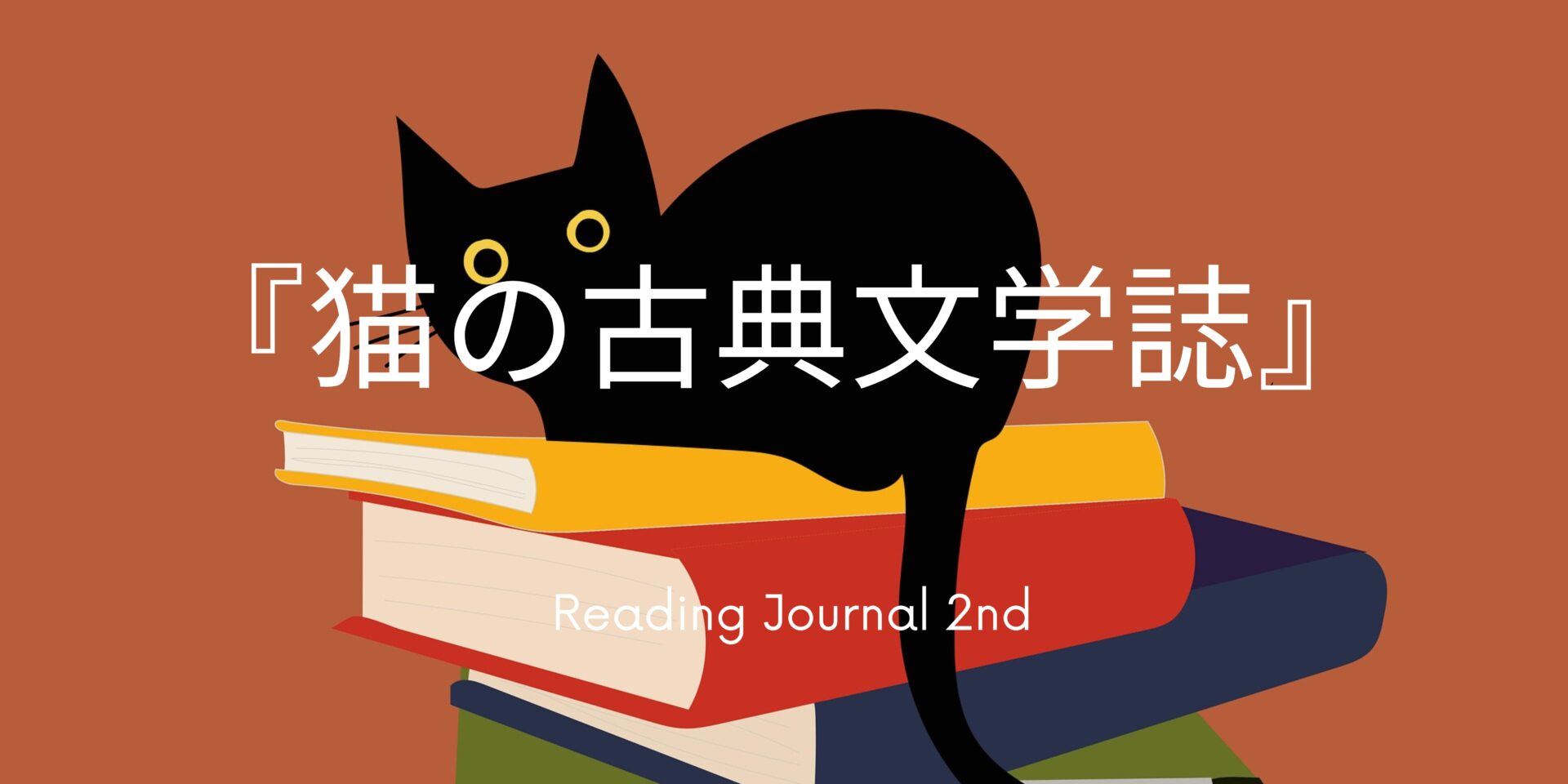


コメント