『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第八章 江戸お猫さまの生活(前半)
今日のところは、第八章 「江戸のお猫さまの生活」である。江戸時代になると俳諧、芝居、草双紙などの文芸に猫がうじゃうじゃと登場する。著者は、この章で「江戸時代の猫の生活を文献にもとづき、たどっていく」としている。第八章は、前半で”俳諧と猫”の話と”江戸の猫の暮らし”、そして後半で、”江戸の文人と猫”と”回向院と猫”の話をまとめる。では、読み始めよう。
俳諧と猫
うらやまし思ひきるとき猫の恋 越人 (『猿蓑』) (抜粋)
著者は、この章をこの句から始めた。この句は、猫が発情期を終えた瞬間からもう「恋」に見向きもしなくなることを詠んでいる。それは、
「猫はいいなあ。さかりがすぎればこんな辛い恋なんか忘れてしまえるもんな」としみじみ感慨にふける男の句なのである。(抜粋)
松尾芭蕉も似たような句を詠んでいる。
猫の恋ややむとき閨の朧月 (『己が光』)(抜粋)
そうぞうしかった猫のさかりがすぎて、ふと寝室から外をのぞくと朧月がかかっている、という意で、恋は思いきれぬもの、叶わぬものという人間の宿命を猫に託している。
中村真理は「猫の恋はほとんどが片思いで成就しないものとして読まれている」と言っている(「俳諧の猫 - 「本意」と「季語」の視点から-」『連歌俳諧研究』125号、二〇一三年)。そして中村は、越人の句について、
「猫の恋」を「人の恋」に見立てるのではなく、猫の恋は「猫の恋」のまま人の心に訴えかけるという新機軸を見出したからこそ、越人の句は芭蕉の賞賛を得たのであろう。(抜粋)
と言っている。
禅語の影響から「猫と蝶」「猫と牡丹」といった組み合わせが連歌俳諧の符号語となったが、その後、禅語から離れて独自の猫の句が作られるようになっていった。猫の恋という俳諧のテーマは、新しい「伝統」になっていった。
芭蕉には、次のような句もある。
猫のつまへつゐの崩れより通ひけり(『六百番俳諧発句合』)(抜粋)
ここで「つま」は、古語では夫も「つま」という。また、「へつゐ」とはかまどのことである。この句は、台所の崩れたかまどの穴から猫が目当ての相手の家に通って来るさまを描いる。『伊勢物語』の第五段の「むかし男」が、築地の崩れから女のもとを訪れた話を下敷きにしている。
俳諧では、宝井其角が猫好きで知られていた。彼は『焦尾琴』を編んでいて、その中に『古麻恋句合』という、猫の恋を詠んだ句を集めたものが収録されている(古麻は、猫の別名)。
芭蕉の資料には、『貝おほひ』(句を歌合せのように番にして合わせたもの)に芭蕉が批評文を付け加えたものがある。
四番
左
さかる猫は気の毒たんとまたたびや
右
妻恋のおもひや猫のらうさいけ(抜粋)
左の句は、発情期に苦しむ猫が気の毒だから、またたびをたくさんやりたい、という意である。右の句の「らうさい」は、元禄のころに流行った小唄のことである。
芭蕉は、この二つを批評したあと、右の句を勝ちとしている
江戸時代の猫の生活
ここからは、江戸時代の猫の生活を資料から見ていく。江戸時代になると猫は、ねずみを捕るという面もあったが、愛玩動物化に一層拍車がかかる。『雲萍雑誌』という随筆には、「猫の飯に鰹節を入れるようなことをすると、ねずみを捕らなくなるので良くない」と書いてある。著者は、この記事より当時の愛玩ようの猫は、ご飯に鰹節を混ぜたものが常食だったとわかる、としている。
次に山東京伝の弟の山東京山作の『朧月猫のさうし』には、猫の妙薬という項目があって、
猫の妙薬はなんといってもまたたび。そして青魚とドジョウは猫の人参(人間の高麗人参に相当する強壮薬か?)だという。そして
どんな病気でも烏薬は飲ますべきであります。あるいは、硫黄と胡椒を半々にしてのりで丸めたものを飲ませなさい。何の病にもききます。猫の腰が抜けたときは、背中と尻尾の間に灸をしなさい。不思議に足が立ちます。猫にからす貝をたべさせてはいけません。食べればできものができて耳が落ちます。これは『求聞医録』に見えております。(抜粋)
のようなことがもっともらしく書いてある。
なんと、からす貝を食べさせると・・・・・耳が落ちる!!!!・・・・・ド・…ドラえもん化するって事ですね!(つくジー)
そして、井原西鶴の『西鶴織留』には、猫のノミを取る商売の記載がある。著者は、その方法は合理的であり今でも応用が出来そうと言っている。
男は、まず猫に湯をかけて洗い、濡れたままの身を狼の毛皮でくるでしばらく抱いている。すると、濡れたところが嫌いなノミがどんどん狼の毛皮に移ってくる。みんな移ったと思うころに、毛皮を道にふるい捨てるのである。(抜粋)
唐猫から始まった猫のペット化は、江戸時代になり現代の形と近くなった。
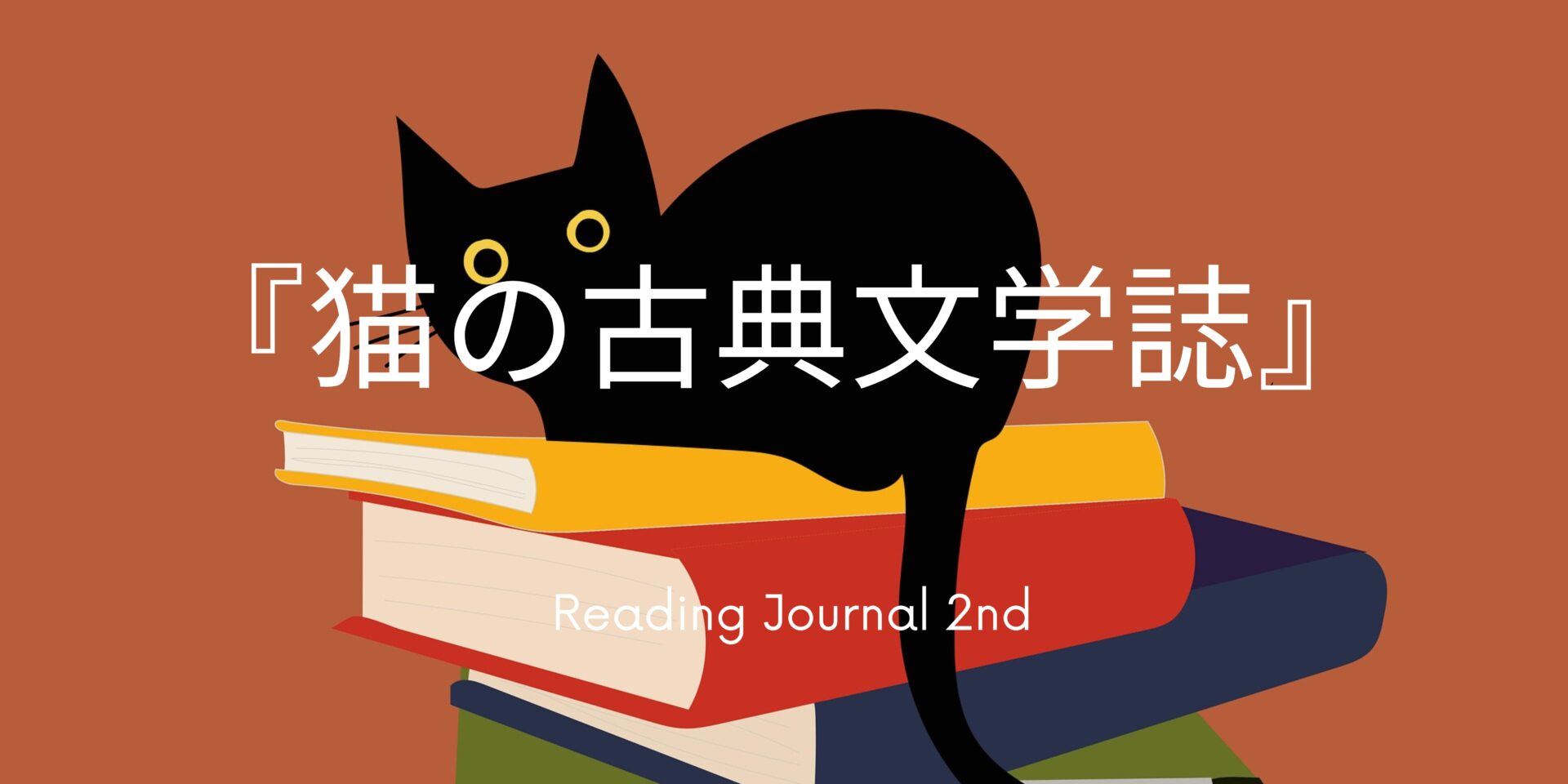


コメント