『猫の日本文学誌』 田中 貴子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第六章 新訳 猫の草子
第六章は、これまでとは一風変わって江戸初期の渋川版お伽草子の一冊『猫の草子』の著者訳が載っている。そしてその後、そのお伽草子の解説がつづく。では読み始めよう。
まず著者訳の『猫の草子』が書かれている。これは、「洛中の猫の綱を解き、放し飼いにすすること」という高札から始まったドタバタ劇である。
高札により解き放たれた猫は、京中のねずみを襲いかかった。ねずみは逃げまどい、なりをひそめる。こうしたある日、ねずみが上京にいた名高いお坊さんの夢に現れ窮状を訴えた。すると翌日には猫が夢に現れ自分たちの立場を説く。そうした後、結局ねずみは、このまま我慢していられないと、逃げ出す算段をする。京のねずみを集め、相談をして各々バラバラに逃げ出すことにした。
この『猫のさうし』は、江戸初期に成立した渋川版お伽草子の一冊である。ここで最初に出てくる高札は実際に存在している。黒田日出男の『歴史としての御伽草子』(ぺりかん社、一九九六年)には、『時慶卿記』の記事に書かれていることを示し『猫のさうし』は実際の出来事を背景にしていると述べている。また、黒田は、このようなおふれが出た理由は、ねずみ対策と断じている。
ここで、猫好きの著者ならではのコメントがある。
本文では、猫は「綱から放たれてとても自由」という意味のことを言っているが、現代の獣医さんによれば、猫は家の中だけで飼う方が数倍長生きするそうである。野良猫の寿命はせいぜい二、三年だそうで、大切な猫は室内で飼い、家で十分運動させてやればよいとのことだった。(抜粋)
なるほど!ちょっと前に猫を大事に大事に育てて、(妖怪化して)喋れるようになったら一緒にお茶を飲もうか?(ココ参照)ということを言ったが、「室内で飼うことが秘訣!」って事だね!メモメモ(つくジー)
このお伽草子にはやたらと地名や物の名前が列挙されている。それは、お伽草子には、年少者の学習用という目的があるためである。そのため、物語の中に仏教の教えや地名、物名が長々と出てくる。この話の中で、ねずみたちが「移民」しようとしている近江の国の地名は、和歌や物語で知られた地名となっているし、街道ぞいの宿の順番もおおむね守られている。さらにねずみが詠む和歌は、小倉百人一首のパロディーになっている。
そういうことを知って読めば、猫とねずみの楽しい(?)お話である。(抜粋)
また、物語でねずみが「じじ」と鳴く、とあるが、これは室町から戦国時代の人々はねずみの鳴き声をそう聞いていた。さらにもっと古くは「しうしう」と鳴いているとされる(山口仲美『犬は「びよ」と鳴いていた』光文社新書、二〇〇二年)。
この物語には、猫は殺生するので往生できないという問題が横たわっている。人間からするとねずみをとる猫は便利な存在だが、その理由で成仏できないというのは矛盾しているが、仏教が殺生と成仏をどのように考えているかがうかがわれる。
最後に著者は、新訳の原文は、桑原博史全訳注『おとぎ草子』(講談社学術文庫、一九八二年)と三弥井書店の影印刷『猫のさうし』(一九七一年)によったとしている。
関連図書:
黒田日出男(著)『歴史としての御伽草子』、ぺりかん社、1996年
山口仲美(著)『犬は「びよ」と鳴いていた』、光文社(光文社新書)、2002年
桑原博史(訳注)『おとぎ草子』、講談社(講談社学術文庫)、1982年
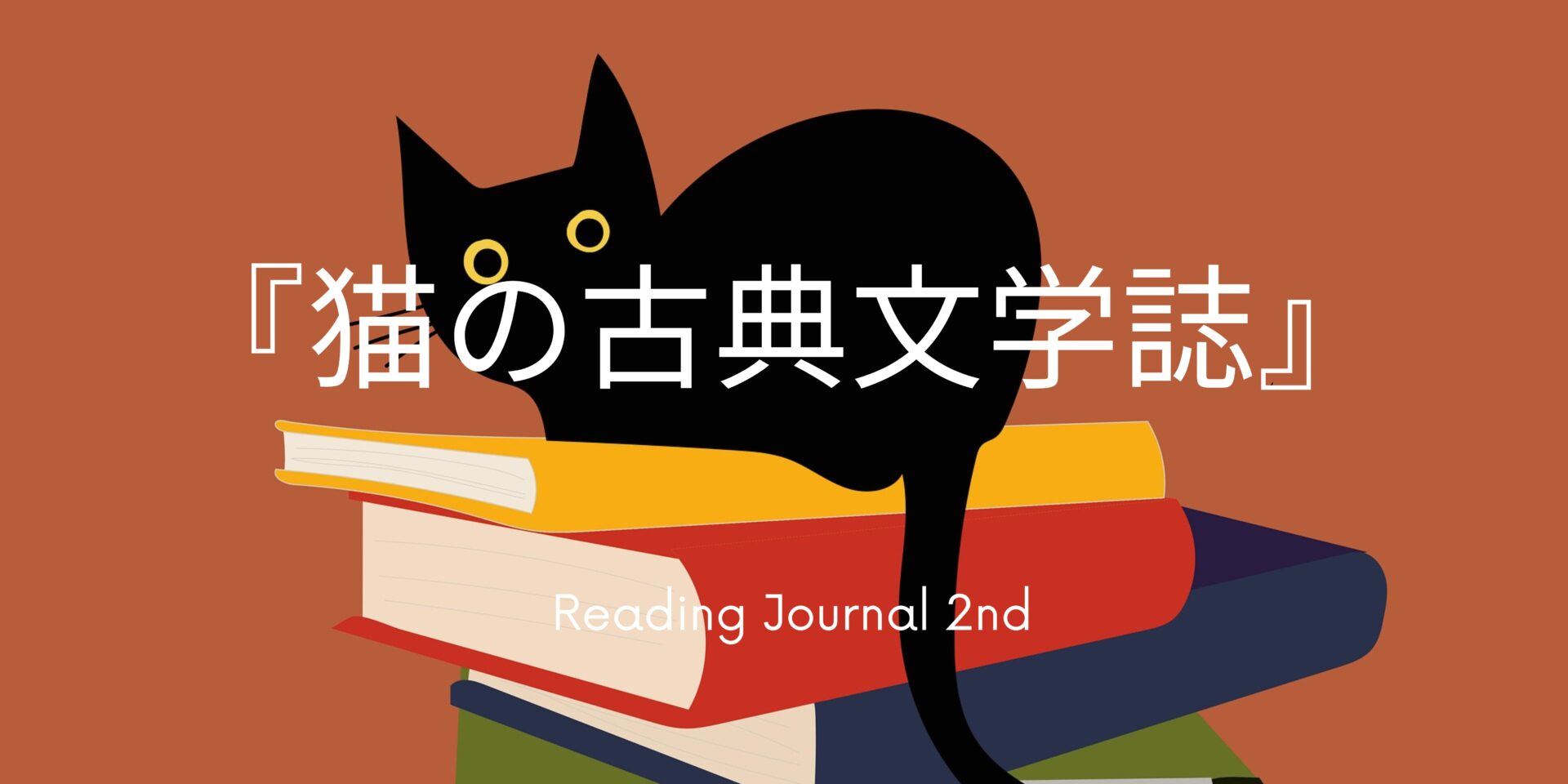


コメント