『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 さらなる高度な本読み(その1)
これまで、本書の中心的読書の技術として、第3章で通読(”前半”、”後半”)、第4章で詳細読み(”前半”、”後半”)、の説明がされた。今日のところ「第5章 さらなる高度な本読み」では、その延長線上にある「さらに進んだ」技術について説明される。
第5章は、4つに分けてまとめることとし、
- その1:さらに進んだ読書の意味、「読まない読書」
- その2:「包括読み」・「縦断読み」、「系統読み」
- その3:「著者読み」「究極の同化読み」、「批判読み」
- その4:「関連読み」・「並行読み」、おわりに
と分けてまとめることにする。それでは読み始めよう。
読書は、複数の本の内容を有機的に関連づけながら読み進めていくことによって、それまでとまったく別の世界に私たちを連れて行ってくれます。(抜粋)
関連性を意識しながら複数の本を読むことによって、大きな知識の構造の中に、それぞれの本の内容が位置づけることができる。
本の「根」「茎」「花」「葉」の側面を知る
どんな知識も他の知識と関連性があるため、ある本を読み込んだあとで、その本の内容を、「より大きな知識構造」の中に位置づけて認識することが必要である。
ここで著者は、本を植物にたとえ「根」であり「茎」であり、同時に「花」であったりするとしている。ここで、
- 根:それに続く思想を育む土壌になるという意味
- 茎:他の知識や思想を土壌として発生したものという意味
- 花:この世界に大きく影響したという意味
- 葉:その時代における要求を受取り、それを養分に変化させるという意味
である。
この「より大きな知識構造」の中に位置づけて認識するという作業は、その本の「根」「茎」「花」としての側面を知る作業である。名著といわれる本は、必ず世界を変化させたという「花」という側面を持つ。このようなことは、概説書や哲学史、思想史の本を読まないとわからないことがある。
上記の「根」「茎」「花」「葉」の要素を知る上では、やはり概説書やその分野の通史の本が役に立つでしょう。しかし、必ずしも概説書や通史の本を読まなければならないというわけではありません。「ある程度読み込んだ本」の内容が、どのレベルで、「根」「茎」「花」となっているかということを、少し気に留めておくだけで十分です。(抜粋)
読まない読書 — 情報収集の読書法
ここでいう「読まない読書」とは、情報収集のために、いわゆる斜め読みする本、優先順位による取捨選択をして「読まない」本についてである。
本は「何を読むか」が重要であるが、それは「何を読まないか」という意味もある。また、本自体を読まないだけでなく、ある本のどの部分を読み、どの部分を読まないかという「部分」も含んでいる。
ここで著者は、情報収集のため、覗いた本は「読まない」読書のものと認識する必要があるとして、読みの表現を
- 「手に取った」「眺めた」本:情報収集のために覗いた本
- 「見た」本:一度通読した本
- 「読んだ」本:二度目の詳細読みをした本
- 「読み込んだ」本:さらによく読んで理解が進行した本
とするとしている。ここでいう「読まない」読書とは、「眺める」ことを指す。
「眺める」読書の方法
- まず、その本の目次をしっかり見る:目次より「論理的道筋」を探し、論理性が感じられない場合は、「読まない」と決める
- 目次の章題、もしくは小見出しなどの中から、自分にとって重要であるという項目を探し出し、その部分をざっと読む
- もしもその部分に、自分にとって「意義がある」と思われることが書かれている場合には、少し周辺を読む、そうでない場合には、すぐにやめる。
- 適当にパラパラめくり、指のとまったところを読む。
著者は、このようなことは、誰でも日常的にやっていることであるが、この作業に尋常でない時間をかけるのが「本読み」であるとしている。著者の目標は、年5000冊(実際には2000冊程度)以上の本を「手にしたり、眺めたり」することである。
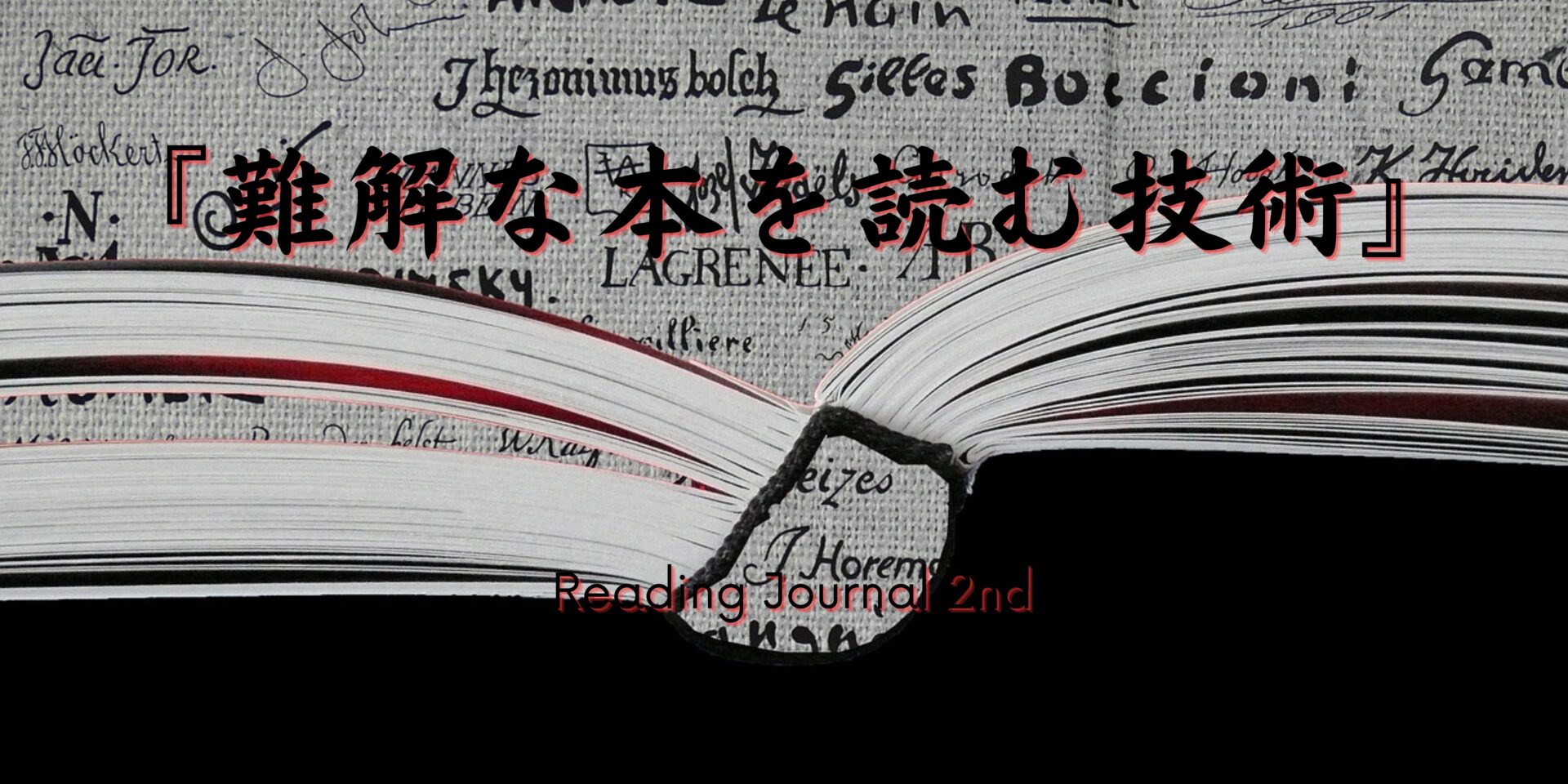


コメント