『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 基本的な考え方(後半)
今日のところは「第1章 基本的な考え方」の”後半“である。”前半“では、読書で大切な「わかる」ことの意味。そして「わかる」ために必要な知識として、「開かれた本と閉じた本」、「外部参照の必要な本」などについて書かれていた。これに続き”後半“では、「登山型の本とハイキング型の本」の違いと、シーケンスパターン。さらに、読みの違いとして「批判読み」と「同化読み」について調べる。そして、本書がどのような組み合わせの読書について対応しているかの説明がある。それでは読み始めよう。
「登山型の本」と「ハイキング型」の本
「登山型の本」とは、概念を一つ一つ「積み上げ式」で構成し、最初から地道に概念を理解していくことが必要な本である。
それに対して「ハイキング型」の本とは、様々な新しい概念や論理が次々と述べられていくタイプの本である。このハイキング型の本にも難解なものが多く含まれている。
ハイキング型の本は、その「ハイキング」という名称の通り、どこかの山の頂上に到達することよりも、「その途中の行程での景色を楽しむ」ことに主眼が置かれていると言えます。(抜粋)
そして、登山型の本とハイキング型の本では、それぞれ読み方を変える必要がある。
重要なのは、まずその本が、おおまかに「登山型」と「ハイキング型」のどちらに分類できるものかを知ることです。(抜粋)
また、その本のシーケンスパターン(難度の変化のパターン)を知ることも重要である。難解な本の中にはところどころ断崖のように難しい場所があり、その箇所をあらかじめ把握しておかないと、登りきることが難しくなる。
「批判読み」と「同化読み」
本を読むときに、読者はまずその本を読む態度を決めなければならない。それは基本的に「同化読み」と「批判読み」がある。
ここで「同化読み」は「その本の内容を、その著者の方針にしたがって理解しようとする」態度であり、本書ではこちらの読み方をメインとする。
次に「批判読み」は、「その本を疑いながら読む」態度で、問題点を発見することを主眼とする。
難解な本を読む場合は、とりあえずは「同化読み」を試すのがよいと思われます。なぜなら、批判読みをしている場合には、疑問点や不明点が自分の無理解に由来するものである場合でも、それを著者の誤謬だと考えてしまう可能性が大きくなるからです。(抜粋)
「同化読み」をする場合の基本方針は、疑わないということであり、どのページに書かれていることも、必ずある目的のために書かれていると信じ、それを理解しようとする態度を貫く必要がある。疑問が発生した場合にも、その疑問を一旦放置し読み進める、そしてもしそのような疑問の部分が多くなってきた場合には、「批判読み」に変更することは可能である。
本書の基本方針
ここで著者は、今までに説明した分類のうち、この本で取り扱う範囲を示している。
まず、
- 基本的にハイキング型の本は取り扱わない
- ある程度の地図を作ってから読む方法を勧めている
- 本書で中心として扱うのは、以下の二つである
- 閉じている-登山型の本-同化読み
- 開いている-登山型の本-同化読み
- また、以下の二つは、第5章で部分的に解説する
- 閉じている-登山型の本-批判読み
- 開いている-登山型の本-批判読み
- 以下のハイキング型の本は、補足的な説明がある
- 閉じている-ハイキング型の本-同化読み
- 閉じている-ハイキング型の本-批判読み
読書にかかる時間
本書では「予備調査-選書-通読-詳細読み」の四つの段階を想定している。
かかる時間は300ページ程度の難易度が中くらいとして、
- 「予備調査-選書」・・・約3時間
- 「通読」・・・4時間
- 「詳細読み」・・・・10時間
合わせて17時間くらい。読書時間が1日2時間とすると1週間程度である。
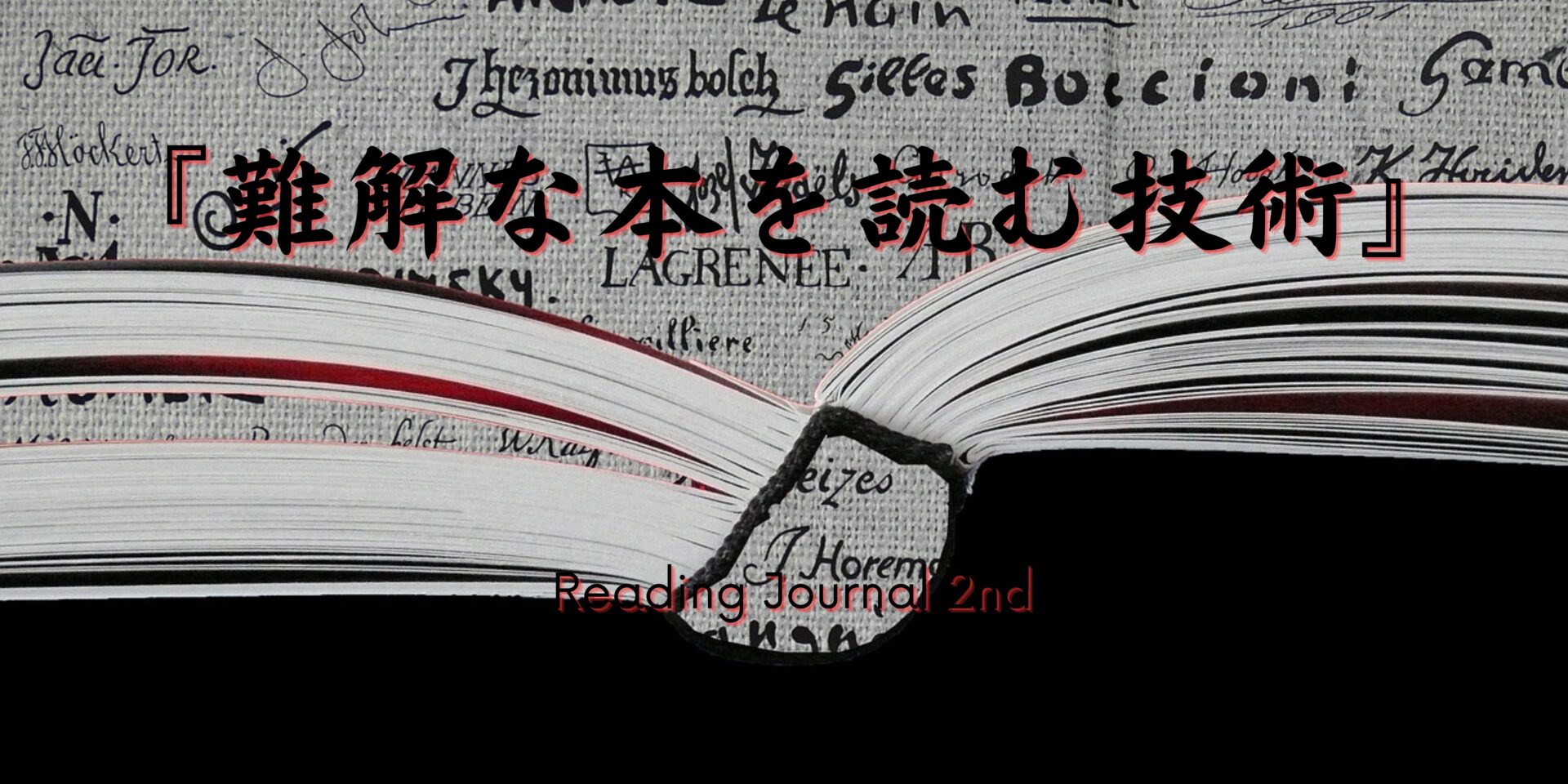


コメント