『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
この本の最後に、大部な付録が2つある。「付録1 読書ノートの記入例」 — 10ページ、「付録2 代表的難解本ガイド」 — 114ページである。
本書に書かれた読書法の具体例で、特に付録2は著者の研究の成果を元としている。
ここでは、詳細にまとめることはせずに、概要のみに留めることにする。
付録1 読書ノートの記入例
読書ノートどんな感じで取って行けばよいかというのは、かなり難しい問題です。ものすごく几帳面にとるのがいいという人もいれば、私のようにとても乱雑にとっていくほうがいいという人もいます。それは各自の性格によると思いますので、とりあえずは、自分にあった方法でとっていけばよいでしょう。(抜粋)
ここでは、著者自身の読書ノート(ドゥルーズ『襞[ひだ]』)と学生さんの読書ノート(ウィゲンシュタイン『青色本』、ウォーフ『言語・思考・現実』 、アダン『物語論』)の記入例があげられている。
付録2 代表的難解本ガイド
ここでは、難解本のうちよく知られているもの、10冊を選んでさらにその著者のその他の著作、関連入門書などについての説明がある。
デリタ 『有限責任会社』
デリダの本の難解さは「ハイキング型」の本を「登山型の本」として読んでしまうことにある。
ここでは、デリダの『有限責任会社』についての解説がなされる。
また、デリダの他の著作として『根源の彼方に グラマトロジーについて』『声と現象』『エクリチュールと差異』『後記 討議の論理に向けて』について触れている。
デリダの補助的なテクストとしては、『デリダを読む』(ペネロペ・ドイッチャー)をあげている。
スピノザ 『エチカ』
スピノザについては、最も重要な著作である『エチカ』の解説がなされている。
また、スピノザの他の著作としては『神学・政治学』『国家論』『知性改善論』がある。
スピノザの入門書としては、単純すぎたり難しすぎたりするものが多いとしながら、『スピノザとい暗号』(田島正樹)(やや専門的)、『個と無限 – スピノザ雑考』(佐藤一郎)(専門的)、『スピノザ入門』(ピエール = フランソワ・モロー)(読みやすいがスピノザの著作の理解の助けにならない)、『スピノザ — 「無神論者」は宗教を肯定できるか』(上野修)(簡単にまとめられすぎている)『スピノザの世界 — 神あるいは自然』(上野修)(非常によくできている解説書)を紹介している。
ウィトゲンシュタイン 『論理哲学論考』
ここでは、ウィトゲットシュタインの『論理哲学論考』の解説がある。
その他の著作として、『青色本』、『哲学的探求』についての言及されている。
また、入門書としては、『ウィットゲットシュタインはこう考えた』(鬼界彰男)を勧めている。
ソシュール 『一般言語学講義』
ソシュールの著作としてここでは有名な『一般言語講義』が解説される。
他の著作としては『ソシュール講義録仲介』、『ソシュール一般言語学抗議 – コンスタンタンのノート』、『一般言語学第一回講義』などの講義をまとめたものが手に入る。このうち『ソシュール一般言語学講義 — コンスタンタンのノート』は、親切なつくりとなっていて入門書としても使えるとしている。
また、ソシュールの入門書・概説書としては『ソシュールと言語学』(町田健)、『コトバの謎解きソシュール入門』(町田健)をあげている。
フロイト 『精神分析入門』
心理学、精神分析学で有名なフロイトの著作は現代思想においても重要な位置にある。ここでは、フロイトの歴史的名著『精神分析入門』の詳細な解説がある。
その他フロイトの著作では『自我論集』、『夢判断』をあげている。
フーコー 『言葉と物』
フーコーの著作物の難解さは、その著作に結論じみたことが書かれず、読者自ら踏み込んで自分の思想を構築しなければならないことによる。
この社会の価値は連続的かつ論理的に形成されたわけではなく、偶発的な「出来事」の蓄積に大きく影響を受けている。簡単に言うと、ある文化的現象の背後に存在する価値観は「うっかり」形成されたものである。ということだ。私たちは、この社会があたかも一定の方向へ持続的に進化していたり、合理的に正しい方向へ向かっていると漠然と感じているが、それは幻想でしかない。したがって、その幻想を暴露するために、従来の方法ではなく、文化的な事象・出来事を丹念に拾い上げ、それらの「意味するところ」を解釈していくという作業によって、我々の持っている文化的価値観を検討することが必要となる。フーコーはそれを「考古学(アルケオロジー)」にたとえて「知の考古学」という方法を提示した。(抜粋)
ここでは、フーコーの著作で最も難解で最も重要な『言葉と物』についての解説がなされている。この本は「登山型」でありかつ「開かれた」本である。
他の著作については『狂気の歴史』、『監獄の歴史』、『臨床医学の誕生』、『性の歴史I 知への意思』、『性の歴史II 快楽の活用』、『性の歴史III 自己への配慮』が紹介される。
ラカン 『エクリ I』『エクリ III』
ラカンについては『エクリ I』、『エクリ III』 についての解説がある。著者はラカンを相当読み込んでいるようで、ラカンの節に30ページ弱を使っている。
先ず『エクリ I』であるが、この本の難解さは「文章表現」と「外部参照が必要」という2点にある。また、指示語も多く、指示語が何を指示しているのかをしっかり認識しないといけない。次に『エクリ III』は、その記号表現を中心に詳細な解説がなさている。
他の著作については、『ディスクール』、『家族複合』、「二人であることの病 – パラノイアと言語」について触れている。
入門書・解説書については『ラカン対ラカン』(向井雅明)は出色ので記であるとしている。ただし『ラカン対ラカン』は入門書・解説書という位置づけだが、内容的には専門書で平易ではない。
ドゥルーズ 『襞』
ここでは、ドゥルーズの作品のなかから、特に群を抜いて難解な『襞』についての解説がなされている。ドゥルーズの難解さは、「視覚的表現」を多用しているところにある。このような本を読む場合に大事なことは、鉛筆を動かし自分なりの理解を「図示」することである。
他のドゥルーズの著作として『批判と臨床』、『アンチ・オイディプス』(ガタリとの共著)、『千のプラトー』などが紹介されている。
ナンシー 『共同 – 体(コルプス)』
現代思想において、最も重要な論者はナンシーであると個人的には考えている。(抜粋)
ここでは『共同 – 体(コルプス)』についての解説がある。この本は、94ページと短いが、その難解さは壊滅的である。重要なことは、この本が「開かれている-ハイキング型」の本と確認してから読み進めることである。
このタイプの本を「理解する」というのは、そこに書かれている概念や思考の流れを理解するということを意味するのではなく、その内容に触発されて「様々な思考を展開しうる」という意味である。(抜粋)
その他の著作としては、ナンシーの主著である『無為の共同体』、『声の分割』、『哲学の忘却』、『複数にして単数の存在』、『共出現』(バインとの共著)がある。さらに、ナンシーが編集した『主体の後に誰が来るのか?』もナンシー入門には良い本であるとしている。
ジジェク 『厄介なる主体』(1,2)
ジジェクの著作は「開かれた-ハイキング型」の本である。そしてジジェクの本は「包括読み」と「批判読み」となっている要素がふんだんに含まれている。
ここでは『厄介なる主体』についての解説が書かれている。この本を難解本という範疇に入れなくてもよいという意見もあるが、それは「開かれた」「ハイキング型」の本であり、読者のレベルによってさまざまな読み方ができるからで、思ったよりも難解である。
他の著作としては『ラカンはこう読め!』、『斜めから見る — 大衆文化を通してのラカン理論へ』、『否定的なもののもとへ滞留』、『厄介な主体』などがあげられている』あげられている。
ジジェクを読む場合は、ヘーゲルやハイデガーについての知識がいるため、『ヘーゲル『精神現象学』入門』(長谷川宏)、『ハイデガー = 存在神秘の哲学』を読む良いとしている。
[完了] 全13回
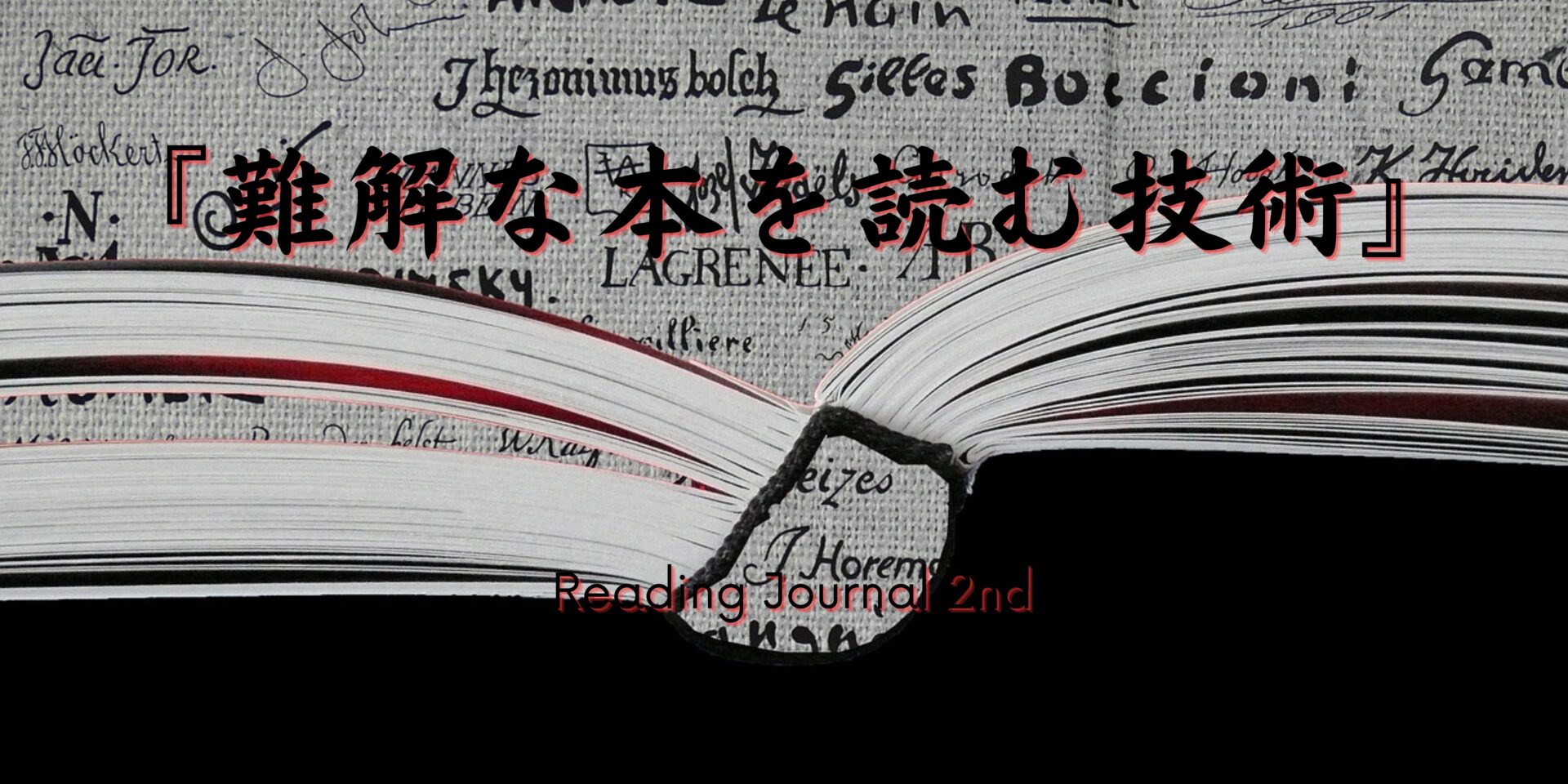


コメント