『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6章 グローバル化するモディ政治(その3)
今日のところは、第6章「グローバル化するモディ政治」の“その3”である。国内的にはヒンドゥー至上主義的な政策によりイスラーム教徒を抑圧しているモディ政権は、外交面では「グローバルサウス」という言説を利用して自国に有利な外交をしている。そしてその頂点が二〇二三年のG20首脳会議であった。ここでは、そのインド外交の虚像と実像について語られている。それでは読み始めよう。
「グローバルサウスの盟主」の虚像と実像
モディ政権下では、宗教的少数派に対する差別と抑圧が強まっているが、アメリカをはじめとする欧米諸国は、中国に対する安全保障や経済分野での協力を意識して表立って非難することを避けてきた。その足元を見るかのようにインドは、国際政治の舞台をますます国内政治に利用するようになった。
グローバルサウスという言説
二〇二三年にインドは「グローバルサウスの声サミット」を開いた。インドがこの「グローバルサウス」という言説を採用した目的として次の二点が重要である。
- ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに動揺していた外交言説を立て直す狙い。インドは西側諸国と関係を深めていたが、ロシアへの対応は独自路線を貫いている。その外向的方便として大国間対立で犠牲となっている「グローバルサウス」の側に立つことは都合が良い。
- 中国およびロシアの関係性の変化に対応して、グローバル外交を立て直そうという狙い。インドは二一世紀に入ってからBRICSなどの新興国連携の枠組みを重視してきたが、中国との関係やウクライナ紛争などの国際情勢の変化により、新興国の枠組みだけにたよれず、グローバルサウスを旗印に発展途上国との連帯を打ち出した。
また、著者は、グローバルサウスの言説の狙いとして、インドを「権威主義」の陣営に属しているという印象を避け、インドが「民主主義」陣営の一員というイメージを維持しようとする意図もある、と言及している。モディ政権がインドを「民主主義の母国」という突飛な発想からの言葉を、国内外に触れ回っているのもそのためである。
しかし、このグローバルサウスという言説であるが、モディ政権は国内に積極的にアピールしているわけではない。つまり国内と国外で意識的に使い分けている。
G20サミットでのワンマンショー
そして、インドがG20の議長国になると、モディ政権は国内向けの政治宣伝のためにG20 サミットをおおいに利用することになる。そして二〇二三年のG20サミットは、モディ首相のワンマンショーを披露する場と化した。そのため街には異様なほどモディ首相の肖像画が飾られ、会場付近では「都市美化」が徹底的に行われた。
このG20でもっとも劇的な瞬間は、モディ首相が会合初日の午後に首脳宣言が採択されたと発表した時だった。それは、それまでインドで開催された関係閣僚会議では、共同声明が一度も採択されていず、G20サミットで初めて首脳宣言が出ない事態となることが懸念されていたからである。
しかし、この首脳宣言の採択の発表は、参加国関係者すら寝耳に水の話で合った。そして、その強引な発表手法だけでなく内容も問題があった。ウクライナ戦争に関する項目では、ロシアに全く言及せず、前回のパリ・サミットの首脳宣言から大きく後退していた。また、首脳宣言では、グローバルサウスという単語が一度も登場せず、グローバルサウスの声が反映されているか、大いに疑問である。
モディ外交のゆくえ
このようにG20サミットはインドの政府の政治宣伝として国内・国外の双方で大成功した。
しかし、G20サミットが終わって間もない時期に、インドと一部の先進国のあいだの亀裂が表面化した。
カナダのトルドー首相は、カナダ国籍を持つインド出身のシク教徒の殺害にインド政府の工作員が関与した疑いがあると発表した。これにインドは全面的に否定し反発をし、両国間で外交官の国外退去などの事態に陥った。
その一方で、インドを表立って非難することは、アメリカも慎重である。ただし、インドの権威主義化や宗教的少数派の人権抑圧などの問題について、非公式の場でインドに懸念を伝えているとの発言が、アメリカ政府の高官から聞かれることが最近になって増えてきているのも確かである。(抜粋)
欧米各国は、インドとの「普遍的価値の共有」をあきらめ、ヨルダン、ベトナム、その他の非自由主義的なパートナーと同じく「利害の共有」という現実を踏まえて協力する必要があるという議論も出ている。
しかし、著者は、ますます存在感を高めているインド社会に対して「利害の共有」という「いいとこ取り」の関係が可能であるか、疑問とていしている。
また、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなど国内に多くのインド系住民を抱えている国では、インド系住民の間にヒンドゥー至上主義が浸透し、SNSによる国境を越えたヘイトや扇動的メッセ―の拡散など問題が起こっている。そして、著者は次のように言って、第六章を閉じている。
インドの影響力の増大を背景に、ヒンドゥー至上主義と個人支配に突き動かされるモディ政治は、各国の外交だけでなく内政にも暗い影を落としている。(抜粋)
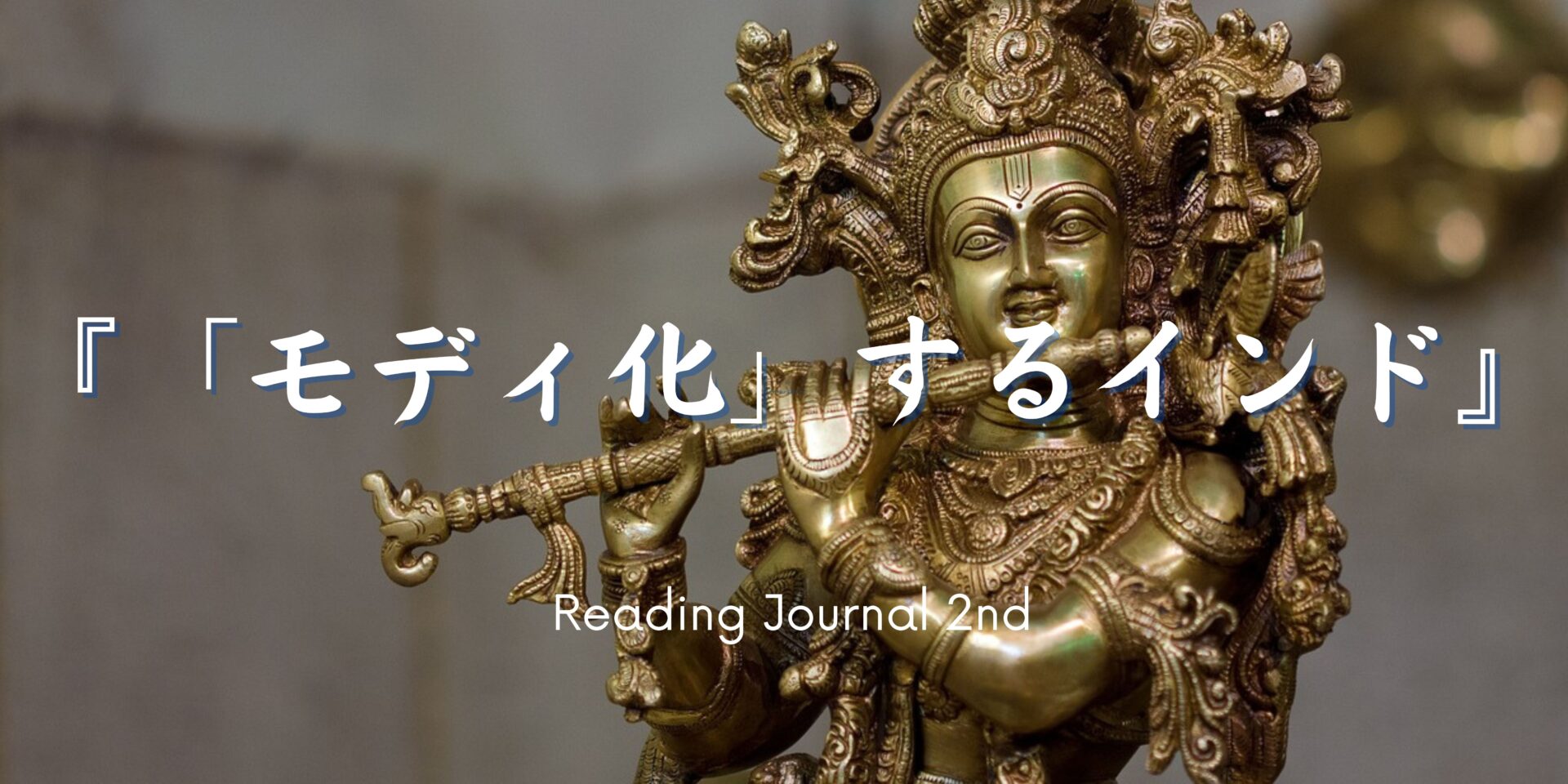


コメント