『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第6章 グローバル化するモディ政治(その1)
今日から第6章「グローバル化するモディ政治」に入る。ここでは、インドの外交とその裏側。そして、そのような外交の陰で行われているヒンドゥー至上主義の活動について語られている。第6章は、3つに分け“その1”でトランプ訪印とその裏側について、”その2“でヒンドゥー至上主義の脅威について、そして”その3“で「グローバルサウスの盟主としてのインドについてまとめる。それでは読み始めよう。
トランプ大統領の訪印とその裏側
「ナマステ・トランプ」と「ハウディ・モディ」のイベント
二〇二〇年、新型コロナウィルス感染症がしだいに広がりを見せる中、トランプ大統領がインドを訪問した。その訪印中トランプ大統領は、グジャラート州の中心都市のアフマダーバードに4時間だけ滞在し「ナマステ・トランプ」という歓迎集会に参加した。
このイベントを成功させるために多額の費用と入念な準備が行われた。参加人員を集めるためにインド人民党(BJP)の地方組織と業界団体が動員された。
この集会では、アメリカとインドがこれまでないほど友好的な関係にあり、その背景には、トランプ大統領とモディ首相のあいだに築かれた個人的関係があると強調された。
しかし著者は、これを額面どおりに受けとめることはできないと言っている。まず、アメリカとインドは、貿易と直接投資など経済全般、中国の台頭を背景とした安全保障と防衛協力といった分野で関係を強めていた。しかし、これは二〇〇〇年のクリントン大統領訪印時からの一貫的な傾向であり、それをトランプ大統領とモディ首相の功績とするのはおかしい。さらに実際はトランプ大統領とモディ首相のもとでは、安全保障と防衛協力を除けば両国が協力関係を結ぶ領域は極めて狭くなって、米印関係は良好とはいえず、両国の間で様々な摩擦や軋轢があった。
米印両国間で対立や摩擦があったにもかかわらず両首脳が「いままでにないほど友好的な米印関係」を前面に押し出した理由は、対立を際立させるよりも友好ムードを演出した方が、それぞれの政治的利害に適っていたからである。
「ナマステ・トランプ」の前年、二〇一九年にテキサス州ヒューストンで「ハウディ・モディ」というイベントが行われ、訪米中のモディ首相とトランプ大統領が出席した。このイベントは在米インド人の団体が主催している。
したがって、「ハウディ・モディ」にしろ「ナマステ・トランプ」にしろ、トランプは主体的に関わっていたというよりも、自分にとって都合がよいイベントだったので、「ゲスト」として参加したといえるだろう。むしろ、世間の注目を集めるために、これらのイベントをより積極的に利用したのは、モディの方だったのである。(抜粋)
モディ首相には、トランプ大統領との間の親密さを派手にアピールし、国内で自らの人気を高めようという思惑があった。
モディ外交の特徴
モディ政権下のインドでは、「インドの国際的地位がにわかに高まったのは、首相の個人的功績である」と国民に印象づけるために、国家レベルと個人レベルでの友好関係を意図的に混同しながら、友好ムードが演出されることが多い。(抜粋)
著者は、モディ外交の特徴をそのように指摘している。
また、モディ首相の外遊の背景には、グジャラート暴動への関与の疑いなどで国際社会からの疑惑の払拭する狙いがあるとも言われている。
さらに、モディ政権の外交政策は、ヒンドゥー至上主義的世界観に基づいていることにも特徴である。
つまり、インドは偉大なる「ヒンドゥー文明」の遺産を受け継ぐ国であり、独自の優れた文化とその英知にもとづいた外交を通して世界に平和と繁栄をもたらし、それによってしかるべき尊敬と影響力を勝ち取るべきである、という考え方がモディ外交の底流にある。(抜粋)
このようにモディ政権は外交の舞台で政治的宣伝を巧みに利用した。第二期もモディ政権になると、国内でのヒンドゥー至上主義的な政策を一気に進めた結果、国外でのモディ政権に対する非難の声が大きくなってきた。
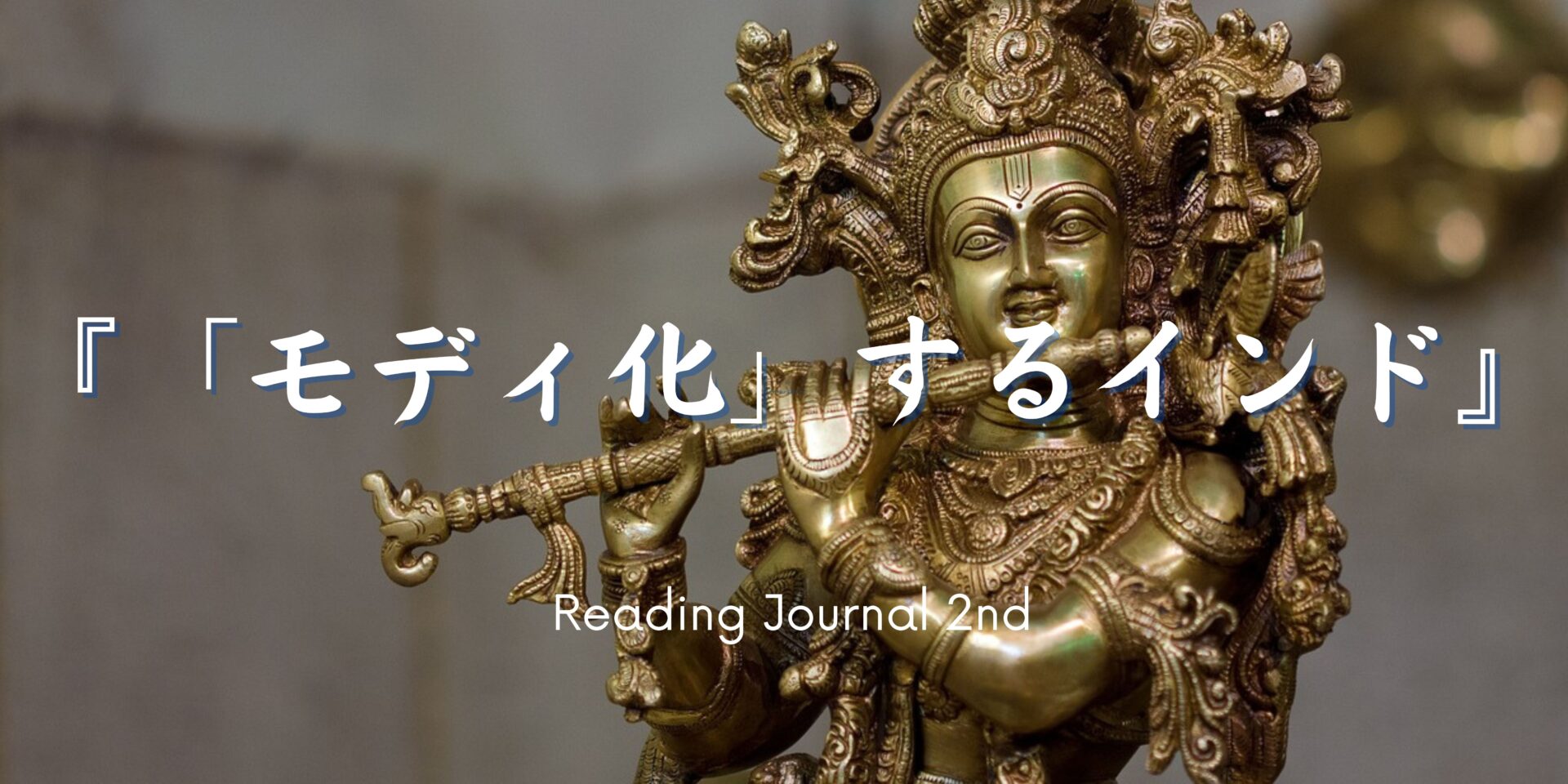


コメント