『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3回 「ほんたうのたべもの」としての童話(その1)
第3回は“「ほんとうのたべもの」としての童話”である。第2回(前半、後半)は、詩・『春と修羅』とその背景にある法華経の影響について書かれていたが、第3回は、賢治の童話と「諸法実相」などの法華経の影響についてである。第3回は、3つに分け、その1で『注文の多い料理店』の序文、その2で「どんぐりと山猫」、その3で「よだかの星」についてまとめる。
宮沢賢治の童話
宮沢賢治の童話は、動植物を擬人化したファンタジックな物語や、擬音を多用したリズムカルな文体で知られている。
第2回(前半)にあったように、賢治が童話を書き始めたきっかけは、国柱会の高知尾智耀に勧められたからである。仏教の教えでは、営利活動に対して否定的な立場もあるが、法華経では、生業を仏法の行為として肯定している(「法師功徳品第十九」)。
「私たちのありのままの現実を肯定する」というのは、天台教学、そして法華経の根本的な考え方です。つまり、仏法の真理に生きようとする仏法第一主義、と私たちが生きている日常との二つを分断しないのが、法華経の特徴と指摘できるのです。(抜粋)
賢治は、自分の得意な文章を書くことを自らの修行として、童話の執筆を重ねた。
童話集『注文の多い料理店』の序文と法華経
宮沢賢治は、百編ほどの童話を残している。そのうち、生前に出版されたのは、大正十三年に出版された童話集『注文の多い料理店』に収録された九編だけである。
著者はここで童話集『注文の多い料理店』の序文に注目して、賢治がどのような視点から物語を書いているかを探るとしている。その序文の以下のように始まる。
わたしたちは、氷砂糖をほしいくらゐもたないでも、きれいにすきとほつた風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。 またわたくしは、はたけや森の中で、ひどいぼろぼろのきものが、いちばんすばらしいびろうどや羅紗や、宝石いりのきものに、かはつてゐるのをたびたび見ました。 わたくしは、そういふきれいなたべものやきものをすきです。 これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹や月あかりからもらってきたのです。(『全集』12巻、一九九五)(抜粋)
このように賢治は、「きれいなすきとほうた風」「桃いろのうつくしい朝の日光」を飲んだり食べたりできるとし、「ぼろぼろのきもの」が魅力にあふれ一番よいと言っている。賢治には、一見無価値なもの、ありふれたもの、汚いものが輝いて見えている。
そして、著者が注目しているのは、序文の最後である。
けれども、わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまひ、あなたのすきとほったほんとうのたべものになることを、どんなにねがふかわかりません。(同前)(抜粋)
著者は、この「すきとほったほんとうのたべもの」は、私たちが生きる、「あれがいい」「これは嫌いだ」などという世界を超えたもの、時代にも社会にも左右されない真の生き方を示しているものとしている。そして、
それは、法華経でいうところの、み仏の真実の智慧によってさとられている境地、すなわち「諸法実相」に通じるものがあると私は思います。(抜粋)
「諸法実相」と賢治の童話
ここで、法華経における「諸法実相」の解説と、賢治の童話との関係について解説されている。著者は「方便品第二」の解説をしてから、「諸法実相」についてこのように解説している。
「諸法」とはこの宇宙のすべての事象であり、「実相」とは「真実なるもの」のことです。つまり「諸法実相」とは、諸仏の体得した最も深い真理であることが、ここで明かされます。 この宇宙の存在するすべての真実のすがたは、真理を体現し、その真実のありようが諸法実相であり、永遠の真理である。(抜粋)
天台教学では、この究極の真理を「空諦・仮諦・中諦」の三種に分け、それを「三諦」という。
- 「空諦」・・・すべてのものは堅固な実体をもたないこと
- 「仮諦」・・・すべてのものは、因縁によって仮に生じているということ
- 「中諦」・・・この「空」であり「仮」であるという現象を踏まえつつ、すべての事象が真実の相を具現化していると見ること
ここで著者は、コップを例にして「諸法実相」の意味を次のように説明している。
このような「空」と「仮」の世界において、物として本体があることを認識する、これが「中」である。このように物のありようをそのまま認識することが、法華経の「方便本第二」に説かれた「諸法実相」の意味です。今、目の前にある現象を絶対的に肯定する、存在論としての哲学なのです。(抜粋)
そして、凡夫である私たちも、「空諦・仮諦・中諦」の三諦をさとることによって、迷いを取り払い、真実を真実として認識できる智慧を得られる。
ここで、著者は賢治の童話の意図について、次のようにいっている。
私は、この「真実なるもの」である諸法実相を童話というかたちで示すことが、童話作家・宮沢賢治の本意だったのではないかと考えています。つまり、この現実世界はみ仏のさとりの世界であり、み仏とともにあることを私たちに示そうと志向しているところに、彼の作品の特徴があるように思うのです。彼の作品には、私たちが日常の価値観に左右されない「真実の安らぎの世界」に、周囲の人たちが到達するように、という願いが込められているのではないでしょうか。(抜粋)
この部分は「諸法実相」の概念が難しい、言わんとしているところはわからなくもないけど・・・・ちょっとボクには難しかったかな?(つくジー)
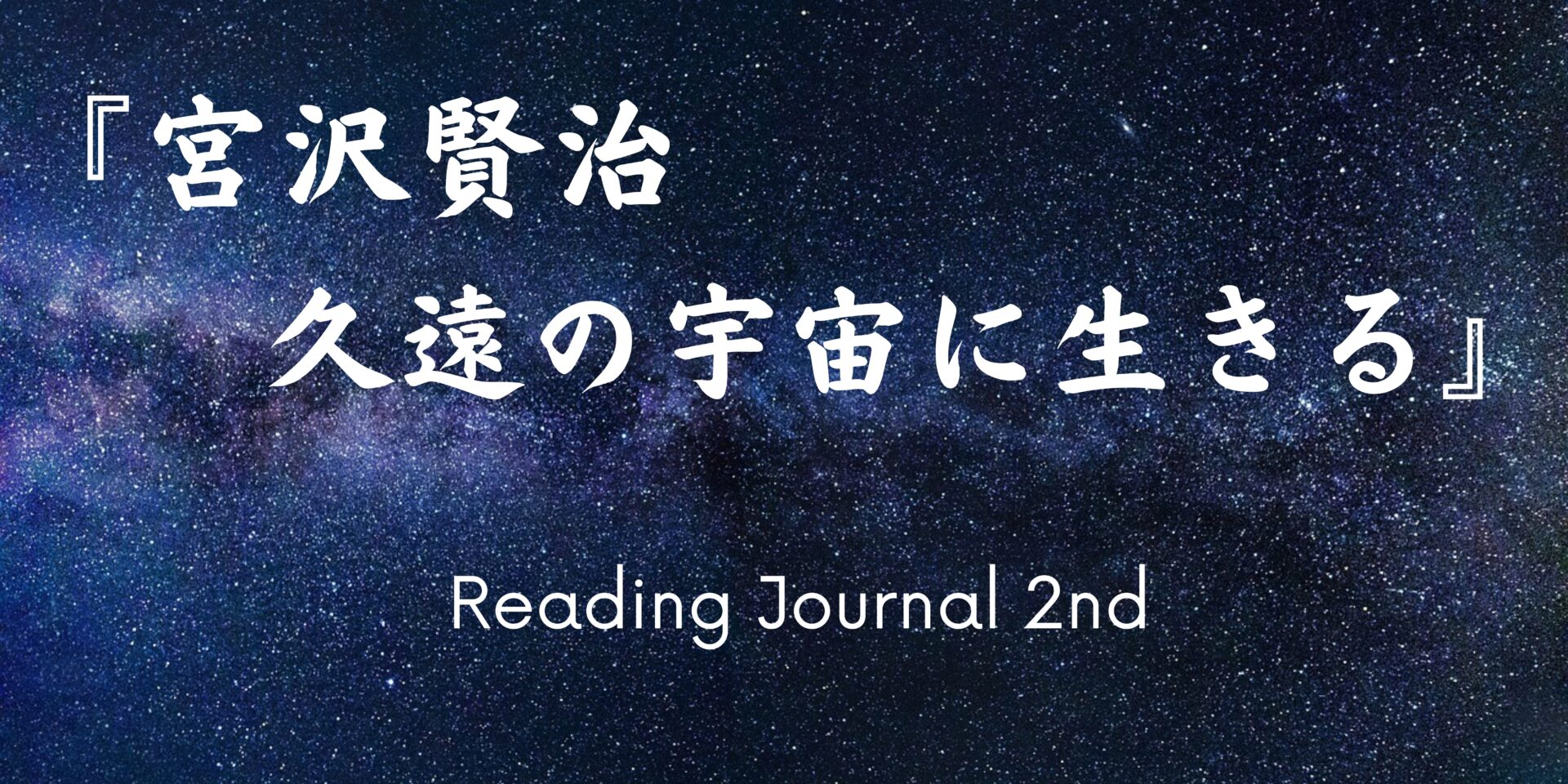


コメント