『宮沢賢治 久遠の宇宙に生きる』 北川前肇 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2回 「春」と「修羅」のはざまで(後半)
今日のところは、“「春」と「修羅」のはざまで”の後半である。ここでは前半を受けてまず、賢治の生家や父・政次郎への反発と葛藤を法華経と言う視点から解き明かす。そして最後に『春と修羅』が法華経を基盤とした作品であることを示している。
父への失望
『春と修羅』に描かれている、賢治の心の葛藤は、生家の商売にも要因がある。
賢治の生家は、古着商と質店を営み花巻でも有名な資産家であった。父・政次郎は地域の有力者で熱心に地域貢献をしていた。幼い賢治はそんな父を純粋に尊敬していた。しかし、中学校に入学する時、父に対する尊敬と信頼が揺らぐ事件が起こる。
盛岡中学校の宿舎へ入る日、政次郎と一緒に舎監長たちへ挨拶をしたときのこと、政次郎は三人の職員の前で、おもむろに大きな銀の懐中時計を取り出してねじを巻きました。(抜粋)
この何気ない父の仕草の裏にある特権階級意識を賢治は見抜き、失望した。
この事件をきっかけに賢治は、はじめて「父との乖離」を経験する。
父・政次郎の目指すところも「すべての人の救い」であるが、実際は階級世界に生きている。そのことを、目の当たりにした中学生の賢治は、家業が自分の進むべき道と思えなくなってしまう。そして、そのころ賢治は法華経と出会う。
賢治は、「真実なるもの」を法華経の中に見いだし歩み始めるが、現実には父の経済的な支援のもとでしか生きられず、その理想と現実の間で深く葛藤することになる。
一仏乗とは
ここで、法華経の一仏乗の解説が入る。仏教が誕生した古代インドでは、カースト制度によって明確に階級が区別されていました。しかし、釈迦は「すべての人は生まれながらに平等である」と説いた。このことを示す言葉がは、「方便品第二」にある。ここで、釈迦は一仏乗(仏になるための「ただ一つの乗り物」)について説き、二乗や三乗は、ないと言っている。
ここで三乗とは、菩薩・縁覚・声聞が仏になるための方法である。
- 菩薩・・・自分がさとるだけでなく、衆生(すべての人々)に修行をする存在。
- 縁覚・・・自らさとりを得るが、他者に教えを伝えることが出来ない存在。
- 声聞・・・自分が苦しみから逃れるためだけにさとりを求める存在。
このうち「縁覚」と「声聞」は、仏に成れないとされていた。
しかし、釈迦は、縁覚の声聞も菩薩と同じように仏になれると言っている。これが「一仏乗」の意味である。そして、三乗と言うのは、仏の教えを分かりやすく伝えるための「方便」であるとする。
法華経の世界観(三千大千世界と一念三千)
著者は、賢治が法華経に魅了された理由を、法華経の世界観–存在論・認識論・時間論・空間論—が、合ったのではないかと、推察している。
法華経の世界観は、「三千大千世界」と言う言葉で表される。世界の中心には「須弥山」という巨大な山があり、周囲に四つの大陸がある。そして、その周囲に九山八海がある。この須弥山世界を一つの単位とする。
そして一つの須弥山世界(太陽系)が千個集まったものが、「小千世界」。小千世界が千個集まった者が「中千世界」。中千世界が千個集まった者が「大千世界」であり、それを「三千大千世界ともいう(中村元[なかむらはじめ]著『広説佛教語大辞典』、縮小版・東京図書、2020)。
三千大千世界は、一仏が教化・活動される範囲であると考えられています。そして、この三千大千世界が宇宙には無限に展開するのです。広大な三千大千世界を一人で統括する仏とは、釈迦牟尼尊、つまりお釈迦様です。(抜粋)
「三千大千世界」を「仏国土」といい、仏は、仏国土の中を変幻自在に活動し、過去・現在・未来の三世を貫いて存在する。つまり空間も時間も超越した「久遠の仏」である。
それでは、八十歳前後でなくなったゴータマ・ブッタが、なぜ永遠に仏国土に存在し続けているかについては、「如来寿量品第十六」に説明がある。釈迦は、衆生(人々)を導くために、「若くしてさとり、八十歳で入滅した」と説明していた。つまり、それは「方便」だったと説明し、自身は常住にして滅せず(永遠に生きる)と告白している。
久遠の仏が、歴史的にはゴータマ・ブッタの姿として顕現されたように、今もなお、この三千大千世界で自由自在に活動されている。その仏国土に仏の子として私たちは生まれ、なおかつ私たちの一瞬の心の中にも、その世界のすべてが存在する。まさに壮大な世界観です。(抜粋)
そして、三千大千世界を包括する久遠の仏と、「一念三千」という私たちの一瞬の心の働きと区別を設けず、同一のものと捉えるのが「法華経の哲学」である。
ここで「心」と「衆生」と「仏」は一体であると捉える(「華厳経」)。これを「三者無差別」と言う。この三者無差別の世界では、心の情景は、周りの人々や仏の世界に反映され、万物と自分が一体であると考える。
賢治と「一念三千」
賢治の偉大さは、天台大師智顗が構築された「一念三千」という法華経の世界観を理解していたことです。(抜粋)
ここで著者は『春と修羅』の序の中盤を引用し、「すべてがわたくしの中のみんなであるようにみんなのおのおののなかのすべてですから」と言う部分に注目する。そして、こういう文章は、法華経を理解していなければ出てくるものではないと言っている。
そして、賢治の作品に「一念三千」という語は、いまだに確認できていないとしながらも、花巻農学校で賢治の教えを受けた松田奎介の追悼文から賢治が自らの行動を「一念三千」という理念に依拠していたことを示している(草野心平編『宮澤賢治研究』十字屋書店、1947年)。
賢治の詩は、「銀河」「宇宙」などの言葉が登場し、難解であると言われているが、それは「法華経の世界観が背景にある」からである。
このように、法華経に基づく天台教学と、賢治の感性と、賢治が体験している一瞬・一瞬の心象が、文学化されることによって、『春と修羅』が誕生したように思われます。(抜粋)
関連図書:
中村元(著)『広説佛教語大辞典・縮小版』、東京図書、2020年
草野心平(編)『宮澤賢治研究』、十字屋書店、1947年
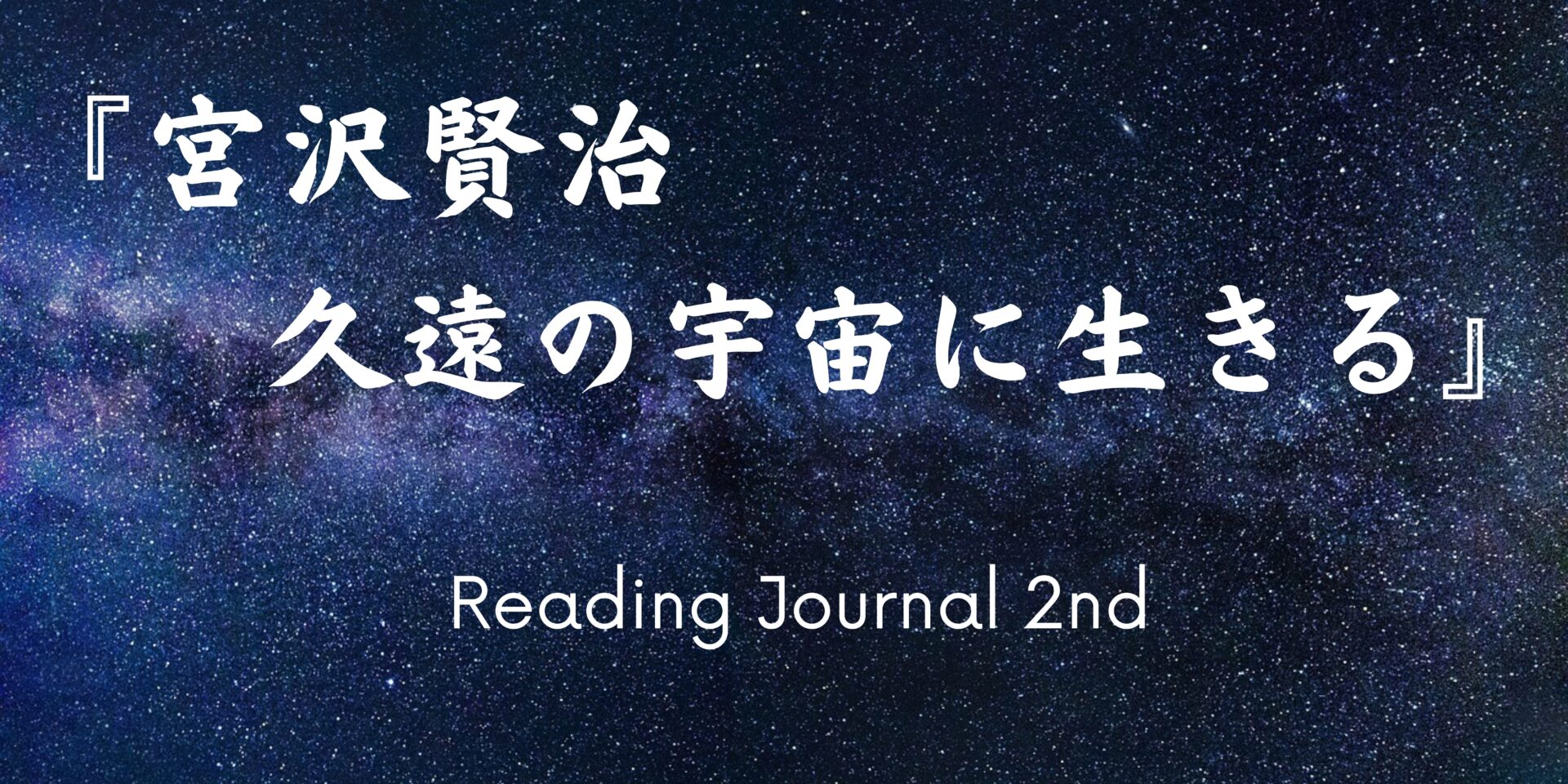


コメント