『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 先延ばし行動
今日のところは第4章「先延ばし行動」である。ここでは、年功賃金や失業期間、社会保障給付の申請、さらには長時間労働などの問題を、構造経済学的な視点で見ることにより、それぞれの問題を考えている。それでは、読み始めよう。
年功賃金と参照点の効果
ここでは、年功賃金を行動経済学ではどのように解釈しているかを解説している。
日本企業の多くの会社では、新入社員の頃は賃金が低く、勤続期間が長くなるいしたがって賃金が上昇していく年功賃金を採用している。しかしこれには、生産性が高い若手社員の賃金が低く、生産性が低くなった定年間際の社員の賃金が高いという生産性との乖離に問題がある。
伝統経済学的な解釈
この年功賃金を行動経済学的に解説する前に、伝統経済学ではどのように説明されているかが書かれている。
伝統経済学では、この年功賃金を
- 労働者は企業に入ってから経験を積むことで生産性があがる。つまり、年功賃金は生産性の上昇を反映している
- 若い頃には生産性より低い賃金を支払い、年齢が高くなると生産性以上の賃金を支払う(インセンティブ仮説)
- 勤続年数が上がると生産性が高い人だけその企業に残るので、それだけ勤続年数の長い人の賃金が高くなる(セクション仮説)
という3つの方法により説明されている。
行動経済学での解釈
しかし行動経済学では、この年功賃金を次のように解釈する。
つまり、現在の賃金水準を参照点とすると、賃金上昇を利得、賃金下落を損失と感じる。そのため、賃金上昇が続く賃金制度の方が、賃金下落の可能性のある賃金制度よりも満足度が高くなる、というものである。
現在価値が少ないにもかかわらず、賃金が上昇していくパターンを人々が選ぶ理由としては、現在の賃金水準を参照点にするため賃金が減少していくと損失を感じること、現在多くの賃金をもらうと現在バイアスのため無駄遣いするので、年功賃金をコミットメント手段として利用していることが考えられる。(抜粋)
(コミットメント手段についてはココ参照)
失業期間を短縮するナッジ
現在バイアスが失業期間を長期化させていることに繋がっている可能性がある。この失業期間と就職を決めたさいの賃金情報を用いて、求職者の現在バイアスの程度の大きさを調べた研究がある。
この研究によると、低賃金及び中レベルの賃金の労働者は、職探しの計画は立てられるが、就職活動をするよりも別の楽しみに時間を使ってしまい、就職活動を先延ばしにする傾向がある。つまり、大きな現在バイアスが存在していることがわかった。
このように現在バイアスによる就職活動の先延ばしを防ぐナッジを行動経済学的に検討すると、
- 再就職支援
- 職探し行動のチェック
が有効であることがわかった。
伝統的経済学では、失業保険給付が充実していると、失業者が職探しに熱心にならずに失業期間が長期化すると考えられてきた。しかし行動経済学的なバイアスが問題であるとすると政策の対応も考える必要がある。
行動経済学的なバイアスとして
- 上にあるように失業者の現在バイアスにより、失業期間が長引いている場合
- 給与の参照点が仕事の賃金相場でなく、過去に働いていた時の賃金になっている可能性
- 職探しを継続することによって将来得られる賃金について楽観バイアスがある可能性
などが考えられる。①の場合には、職探し行動に直接リンクした報酬か罰金、頻繁なリマインダーが有効となる。②の場合には失業者の賃金と相場賃金のギャップを小さくするような介入が効果的となる。
社会保障給付の申請をどうするか
次に行動経済学的にみた社会保障給付の問題についてである。
社会保障(失業保険、年金、生活保護等)の給付を受けようとする人は、受給資格があっても自分で申請手続きをしないと給付を受けられない(これを申請主義と呼ばれる)。これは、本当に困っていれば面倒な申請手続きであってもそれを厭わないだろうという伝統的経済学の考え方に拠っている。
しかし、行動経済学的な視点では、この仕組みには問題点がある。社会保障給付の申請をしていたに人の中には、本当に困っているのに社会保障制度が理解できなかったり、手続きを先延ばししている人が多い可能性がある。実際に生活保護や失業給付の受給資格があるにもかかわらず、受給の申請をしていない人は多く、伝統経済学ではパズルとされている。
行動経済学の視点から考えると貧困者ほどストレスが多く、意志力を使い果たし、先延ばし行動をしがちになる、事が考えられる。研究では、貧困者は合理的な金銭的計算をする能力が低下し、認知能力も長期的な意思決定よりも短期的な意思決定に集中してしまうことが報告されている。
長時間労働を行動経済学で考える
伝統的な経済学では、競争的な労働環境において、労働者の意に沿わない長時間労働は発生しないと考えられている。そして、伝統的経済学において、長時間労働が問題になるのは、労働市場において企業側の買い手独占と呼ばれる経教が発生した場合である。
買い手独占の状態では、労働者は他に就職機会がないので、企業側は労働者の生産性よりも低い賃金で一定の時間働かせることが出来る。この場合は、最低賃金制度による賃金への介入、労働時間規制をすること正当化される。
しかし、競争的な労働環境においても、健康を悪化させるほど長時間労働が問題になっていて、その場合は、行動経済学的なバイアスが影響している可能性がある。
たとえば就業時間内において重要な業務を先延ばししてしまい長時間労働になる可能性がある。また、社会的選好が影響し、同僚が長時間労働をしている場合に自分だけ早く帰ることを嫌う可能性がある。
この長期間労働を抑制するためには、残業手続きを面倒にする、消灯して残業をできなくするなどが有効である。
また、休暇の取得を促すナッジとして、休むことをデフォルトとして制度を整えることなどがある。
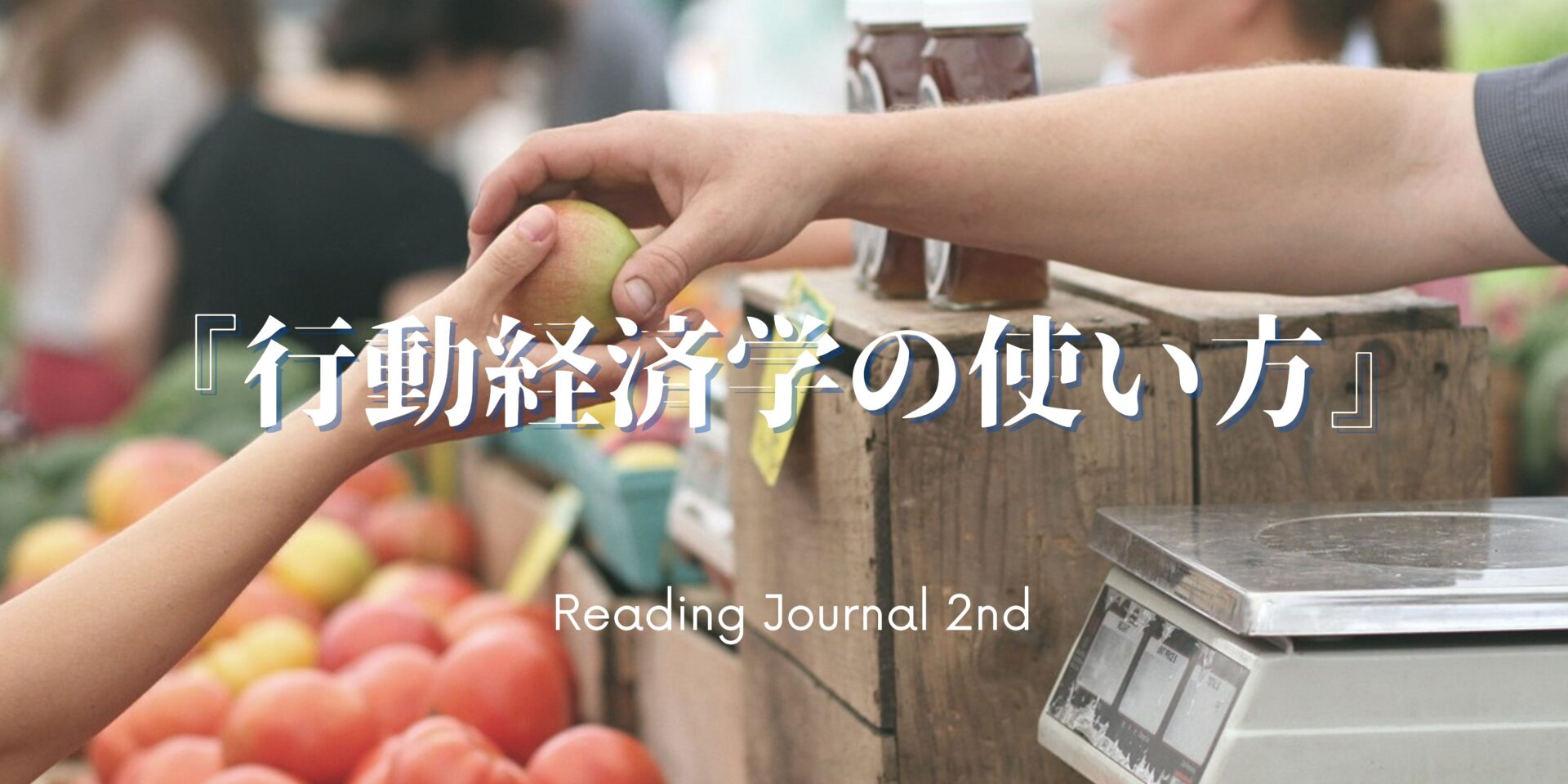


コメント