『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 行動経済学の基礎知識(その3)
今日のところは、第1章「行動経済学の基礎知識」の“その3”である。“その1”で、「プロスペクト理論」、“その2”で、「現在バイアス」「互恵性と利他性」が取り扱われた。そして今日のところ“その3”では「ヒューリスティックス」について説明される。ここまでで行動経済学の基礎知識についての説明が終わる。
ヒューリスティックス
伝統的な経済学では、人間は得られる情報を最大限用いて合理的な推論に基づいて意思決定をすると考えられていた。しかし、実際には意思決定には、思考費用がかかるので、直感的判断をすることが多く、合理的な意思決定と比べて系統的に偏った意思決定になる。
意思決定に思考費用がかかること、また計算能力にも限界があるため、合理的意思決定をすることが難しくなる。そのようなとき、「ヒューリスティックス(=近道による意思決定)」と呼ばれる直感的意思決定を利用することがある。
ヒューリスティックスの種類
ヒューリスティックスは、様々なものがあり
- フレーミング効果:論理的には同じ内容であっても、伝達されるときの表現方法の違いによって、伝えられた人の意思決定が異なること
- ヒューリスティックス:直感的な意思決定による系統的な意思決定の偏り
- メンタルアカウンティン:意思決定の際にその範囲を狭く(ブラケッティング)して考えること
などが代表的である。
また、人々の計算能力に限界があると言う意味の限定合理性のために用いられるヒューリスティックスとして、「サンクコストの誤謬」「意志力」「選択過剰負荷」「情報過剰負荷」「平均への回帰」「メンタル・アカウンティング」「利用可能性ヒューリスティックス」「代表性ヒューリスティックス」「アンカリング効果」「極端回避性」「同調効果」「プロジェクション・バイアス」
サンクコストの誤謬
われわれが既に支払ってしまって回収できないような費用のことを「サンクコスト」という。サンクコストは、すでに回収できないので、それを忘れて自分の満足度が一番高い意思決定をすべきである。しかし、取り戻せないサンクコストを回収しようとする意思決定をすることがある。これを「サンクコストの誤謬」と呼ぶ。
意志力
精神的・肉体的に披露している時は、意思決定能力そのものが、低下する。したがって、精神的・肉体的に疲労しているような状態にある場合は、意思決定に際には、意思決定能力の低下を考慮する必要がある。
選択過剰負荷、情報過剰負荷
意思決定において、選択肢が多い場合は選ぶのが困難になる。これを「選択過剰負荷」と呼び、選択肢を減らす(選択負荷を減らす)ことにより選択行動を促進させることが出来る。
同じように、情報量が多すぎると、情報を正しく評価できないために意思決定が難しくなる。こえを「情報過剰負荷」と呼ぶ。よい意思決定をするためには、重要な情報をわかりやすく提示する必要がある。
平均への回帰
ランダムな要因で数字が変動している場合、極端に平均から乖離した数字が出た後に現れる数字の平均値はその前に試行と変わらない。ただし、数字自体は極端な数字よりも平均値に近くなる確率が常に高い。これが平均への回帰と呼ばれる統計的性質である。(抜粋)
平均値よりも高い数字がでると次は平均値近くになるというのは統計的な現象であるが、それをその時にしたこととの因果関係があるように思いこんでしまうことがある。
これは、数学的な定義もあって、ちょっと難しい。ようするに統計的な揺らぎなのに、そこで何かしたこととの因果関係があると誤解してしまうってことらしい。ここでは、健康状態が悪化した時に、ほっといても良くなるのに、悪化した時に行った民間療法が効いたと思ってしまうことがある、という例で説明していた。なるほど、気の迷いってこわいよね(つくジー)
メンタル・アカウンティング
われわれは、同じお金であっても手に入れ方(給料とかご祝儀とか宝くじとか)によって、使い方を変える傾向がある。また、予定外の事態が発生しても、最初に決めた会計の範囲で意思決定を行う傾向がある。このような特徴を「メンタル・アカウンティング」と呼ぶ。
利用可能性ヒューリスティックス、代表性ヒューリスティックス
「利用可能ヒューリスティックス」とは、正確な情報を手に入れない、または利用しないで、身近な情報や即座に思い浮かぶような知識で意思決定してしまうことである。
また、「代表性ヒューリスティックス」とは、統計的推論を用いた合理的意思決定をするのではなく、似たような属性だけをもとに判断することである。
アンカリング効果
「アンカリング」とは、最初に見た数字などを無意識に参照点に用いて、その参照点がその後の意思決定に影響することである。高級ブランド品店の店頭に最高級品が展示してあると、その金額が参照点となり店内の他の商品の価格が安く感じるなどの例が示されている。
極端回避性
同種の商品の価格や品質に上・中・下とある場合、多くの人は両端を選ばず南中を選ぶという傾向を、「極端回避性」と呼ぶ。
同調効果
われわれは、自分の意思決定をするさいに、多数派の行動に合わせれば安心であるため、無意識に多くの人と同じ行動をおとる傾向がある。これは参照点を同僚や隣人の行動に設定しているとも解釈できる。多数派に同調することは、社会規範を参照点にした行動であるとも考えられる。
プロジェクション・バイアス
現在の状況を未来に過度に投影してしまい、未来を正しく予測できないことを「プロジェクション・バイアス(投影バイアス)」と呼ぶ。
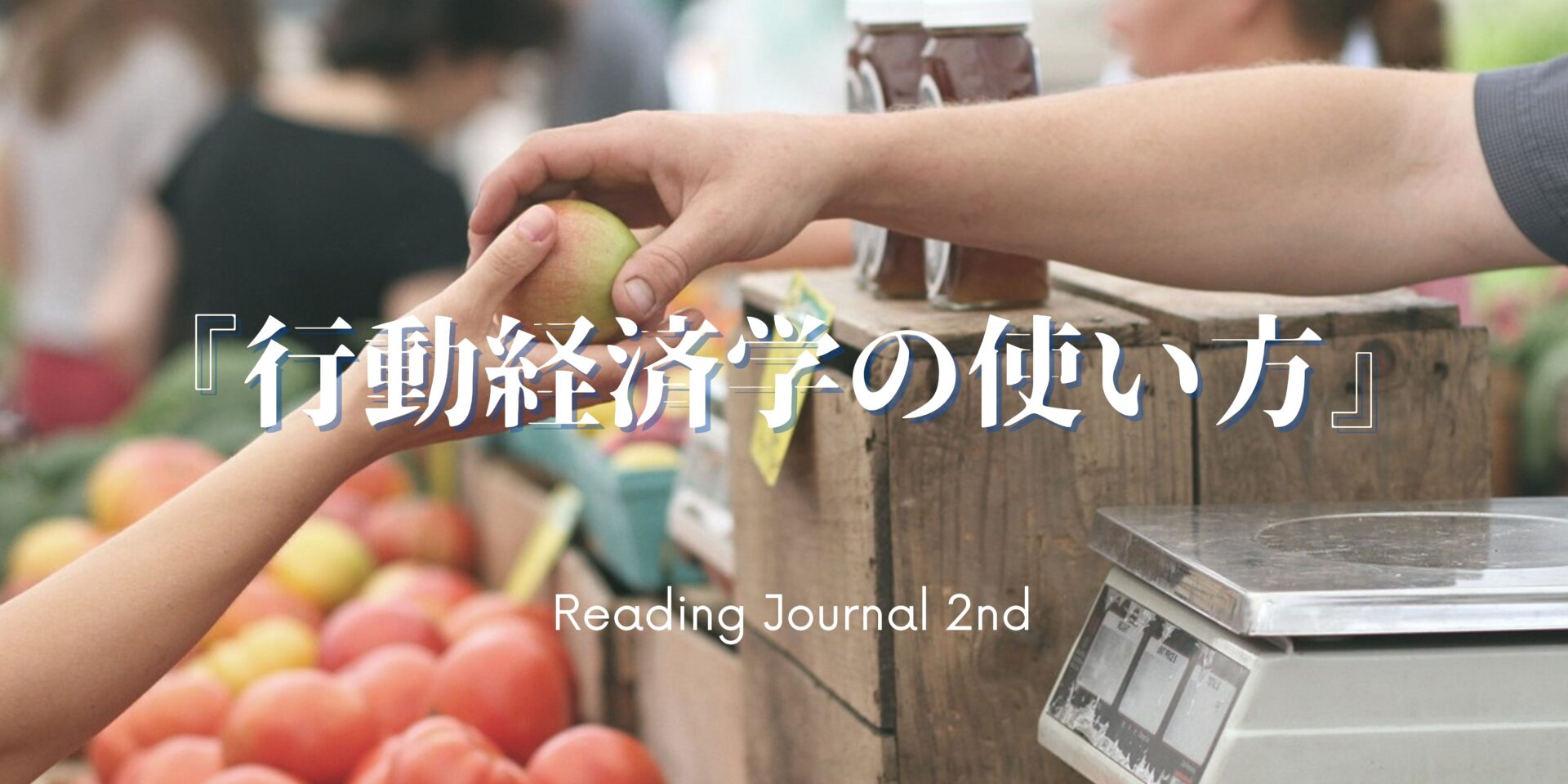


コメント