『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第8章 公共政策への応用(前半)
今日から、第8章「公共政策への応用」である。第7章では「医療・健康活動」の応用が取り扱われた。第8章は、それにつづき公共政策への行動経済学の応用が取り扱われる。第8章は、前半と後半に分けてまとめることにする。それでは読み始めよう。
消費税負担及び軽減税率
重く見える消費税
まず著者は、次のような問いを発している。
「定率所得税率20%で得られた税収を、所得税を廃止して消費税で得るには所得税率をいくらにすればいいでしょうか?(抜粋)
そしてその答えとして、いくつかの前提条件があるが、として「所得税20%の税収を得るには、消費税25%の必要がある」と言っている。
つまり、ずいぶんと消費税の方が重い負担に見える。
このような私たちの認識もあり、毎年のように値上げされる社会保険料には反対しないのに、消費税の値上げには強い反対が起こる。
伝統的な経済学では、所得税の課税と消費税の課税は同じものであると考えられてきた。しかし、実労働実験を用いて消費税と所得税の等価性を検証した研究によると所得税の方が消費税より実労働時間が減り消費が少なくなった。その理由として考えられるのは、税金が課されるタイミングである。つまり、所得税の場合は、手取りが少なくなるため、意欲が減衰するが、消費税の場合は、消費する段階で課税するため作業中は意識されないからと考えられる。
同じように本質的に同じ税でも行動が変化する結果は、スーパーマーケットの値札の表示を変えた実験でも観察される。
消費税と所得税の違いで消費行動が変わるのは、私たちが消費税を無視して行動していることが理由と考えられる。つまり「消費税無視バイアス」がある。
また、税額を無視していなくても税額の計算を間違えれば同じことが起こる。複雑な累進所得税制のもとでは、所得税の「誤計算バイアス」によって、税の誤認が生み出される。
軽減税率は補助金と同じ
次に現在食料品に導入されている軽減税率の話である。
2019年に消費税が10%に引き上げられたとき、食料品のみ8%という軽減税率が施行された。この軽減税率は、経済学者は次に2点で批判的である。
- 軽減税率は低所得者対策として有効ではない
- 軽減税率は消費行動に影響を与えるという意味で非効率的である
まず、①であるが、ふつうの意見としては、生活必需品の消費税を軽減することは、低所得者の税負担を減らすのだから、低所得者の負担軽減になる、というものである。しかしこの意見は、生活必需品は高所得者も購入するという事実を見逃している。低所得者と高所得者では、高所得者の方が購入する食料品の「金額」は大きい。すなわち、高所得者の方が軽減税率の恩恵を多く受け取ることになる。
この軽減税率は、消費税を一律で取ると同時に軽減税率対象商品の購入金額に比例して、購入者に補助金を支払うことと同じである。そして、高所得者の方がより多く補助金を受け取っていることになる。
このような軽減税率に賛成する人が多いことを行動経済学的に考えると
- 比率と金額を誤解すること。つまり、低所得者の方が支出比率の高い品目で税率が軽減されると、低所得者の方がより多くの税金を軽減されると誤解してしまう
- アンカリングの効果。つまり消費税の10%であると、それがアンカーとなって、その消費税率よりも税率が低ければ得をしたと考えてしまう
- 中所得者以上の人が、実際は軽減税率によって自分たちが得をすることを知っているが、それが、低所得者向けの政策という名目で正当化できること
- 生産者が自分たちの製品の需要をふやすために、軽減税率を低所得者対策と主張すること
などが考えられる。
保険料負担について
つぎは、社会保険料の負担に関する問題である。
ここで、社会保険料の事業主負担と労働者負担のことを考える。社会保険料事業主負担分は事業者が払っていて、実際にも事主者が負担している、と多くの人が考えている。そして、厚生労働省も公的年金の事業主負担を労働者の負担と考えていない。それの理由として
- 労働者は事業主負担を自分の負担と認識していない
- 事業主の負担は、100%は労働者に転嫁されていない
をあげている。
伝統的経済学では、事業主は価格や賃金を調整することにより取引相手や労働者にその一部または全部を転嫁することができると考えている。つまり、事業主負担の社会保険料は、賃金低下や雇用減少かどちらかの形で労働者が負担していると考えられる。
この問題について、最近の行動経済学的な研究によって伝統的経済学の想定と現実が異なっていることが示された。
実質的には同じ税制、社会保険料であっても、事業主負担か労働者負担かによって、人々の行動は変わってくる。伝統的経済学では、それを無視して制度の設計をしていたが、現実の人々の行動を前提して制度を考えていく必要は高そうだ。(抜粋)
この最後の部分はちょっと難しくて・…要するによくわからなかった…残念です。(つくジー)
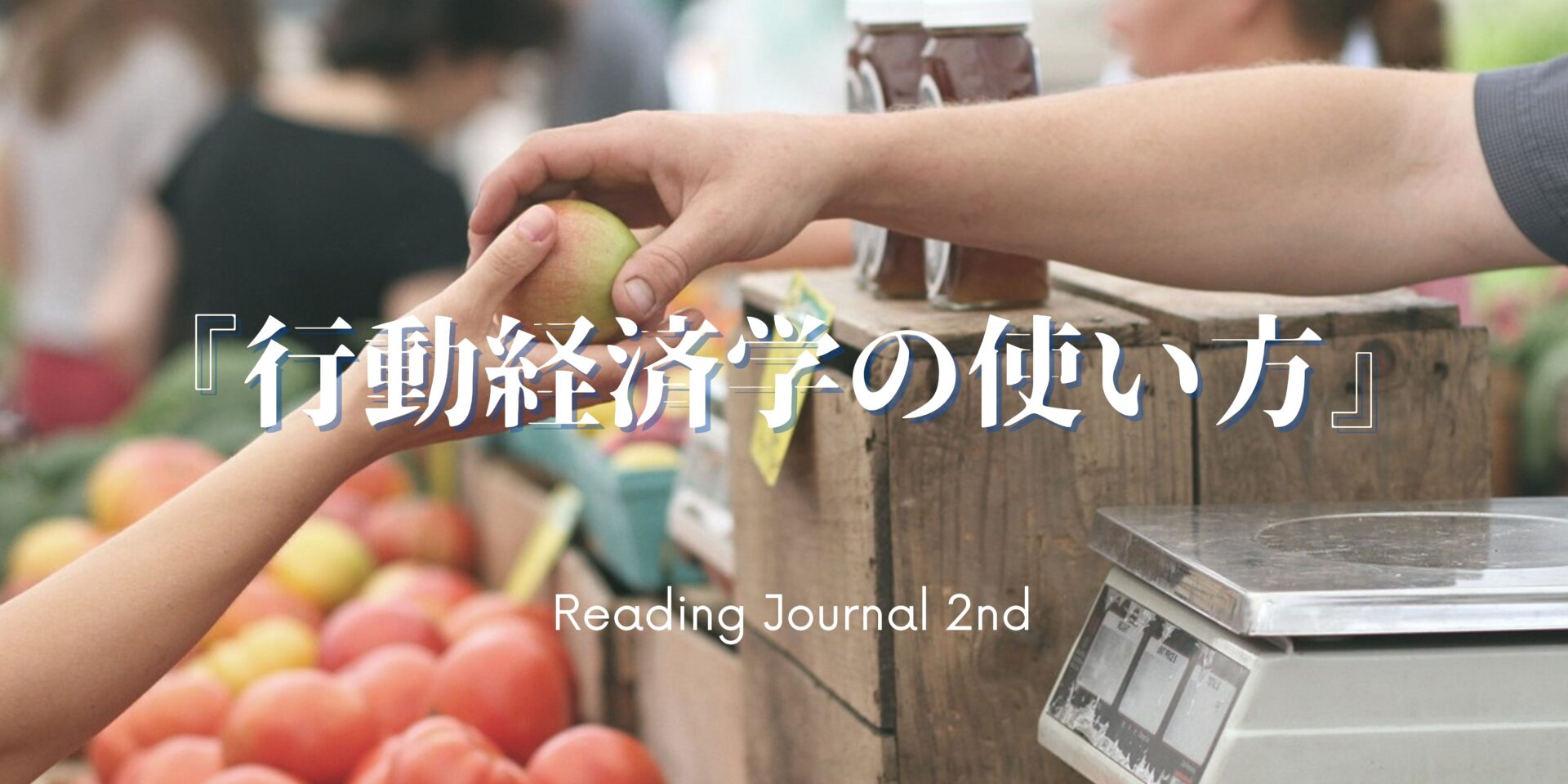


コメント