『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第六章 「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」 — 故事成句をあやつる人びと 1 耶律楚材と王陽明(前半)
今日から「第六章 山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」に入る。まずは第1節「1 耶律楚材と王陽明」である。ここでは元王朝と明王朝の成立と滅亡についてである。
「耶律楚材と王陽明」は、二つに分け”前半“で元王朝を、”後半“で明王朝をそれぞれまとめることとする。それでは、読み始めよう。
「器を制する者は必ず良工を用い、守成する者は必ず儒臣を用う」元王朝の立役者耶律楚材
モンゴル元王朝が中国全土を統一するまでになった陰の立役者は、耶律楚材であった。金の官吏であった耶律楚材は、モンゴル軍の攻撃により首都中都が陥落したとき、耶律楚材が逸材と聞いたチンギス・ハンに取り立てられた。その後耶律楚材はチンギス・ハンの西方征伐に同行し、つねに厚い信頼を得ていた。チンギス・ハンの死後もオゴタイ(元の太宗)にも尽くし、モンゴルの行政や経済の機構の整備をした。
耶律楚材は、オゴタイの補佐役として、絶妙なタイミングで諫め忠告している。
あるときオゴタイに、行政機構を整備し維持してゆくためには、儒臣(教養の高い文官)が必要だと説いたときは、「器を制する者は必ず良工を用い、守成する者は必ず儒臣を用う」(器物を制作する場合には良い職人を用いる必要があり、できあがったものを保持する場合には儒臣を用いる必要がある)」と述べた。
この言葉は明らかに唐の大宗にまつわる「創業は易く守成は難し」(ココ参照)という成句をふまえている。
「一利を興すは一害を除くに若かず」耶律楚材の言葉
耶律楚材は、大金を国家におさめて特権を得ようとする者は、結局、害になるので取り締まることを提案した際に、
「一利を興すは一害を除くに若かず、一事を生ずるは一事を減ずるに若かず。人は必ず以らく班超の言を蓋し平平たるのみ、と。千古の下自ずから定論有り」と言った。
これは、班超が言った「水清ければ大魚なし」(ココ参照)をふまえ、一見、消極的に見える方法のほうが、けっきょくリスクをともなわず、状況を安定させるのに役立つと、言う意味である。
「此の鉄は酒の蝕む所と為りて」耶律楚材の言葉
また、耶律楚材は、大酒飲みのオゴタイを戒めるときに、酒槽の腐食した金属の口を示し、「此の鉄は酒の蝕む所と為りて、尚お此くの如きを致す。況んや人の五臓を損せざること有らんや(この鉄の口は酒のために腐食してこんな状態になっています。ましてや人間の内臓を損なわないはずはありません)」と言った。これを聞いたオゴタイは以後酒を控えるようになった。
この言葉は、『世説新語』(ココ参照)の「任誕篇」にある、大酒飲みを戒めて「酒屋の瓶をおおう布が日ごと月ごとにただれゆくのを見よ」という話をふまえている。
耶律楚材はオゴタイの死後は、政治の中枢から排除され、憤死に近い状態でこの世を去った。
フビライの中国統一と元曲
モンゴル族の元王朝はフビライの代になり、中国全土を統一した。フビライは中国統一にあたりすべての官僚機構のトップにモンゴル人を配置しモンゴル優先の原則を貫いた。
そのため宗王朝での科挙も機能せず、漢民族の士大夫知識人は世に出ることが出来なかった。そのため彼らのなかから生計を立てるために、大衆芸能のなかに活路を見いだす者が現れた。
元では「元曲」と呼ばれる戯曲が文学の主要ジャンルとなり、関漢卿、鄭徳輝、白仁甫、馬致遠の四大家をはじめ、多くの戯作者が現れた。元末になると語り物を母胎とする『西遊記』、『水滸伝』、『三国志演義』など白話(話し言葉)で書かれた小説も形づくられた。
元王朝の滅亡
元は皇帝が亡くなるたびに激しい後継争いに明け暮れ、しだいに統率力が失われる。そして天災やモンゴル支配の反発により白蓮教の信者を中心とした民衆反乱が勃発する。これがしだいに「紅巾の乱」という大反乱に発展する。
そしてこの「紅巾の乱」から朱元璋が現れる。彼は次々と紅巾軍を撃退し、しだいに勢力を拡大する。そして元の首都大都を陥落させ、朱元璋(洪武帝)が即位し明王朝を打ち立てた。
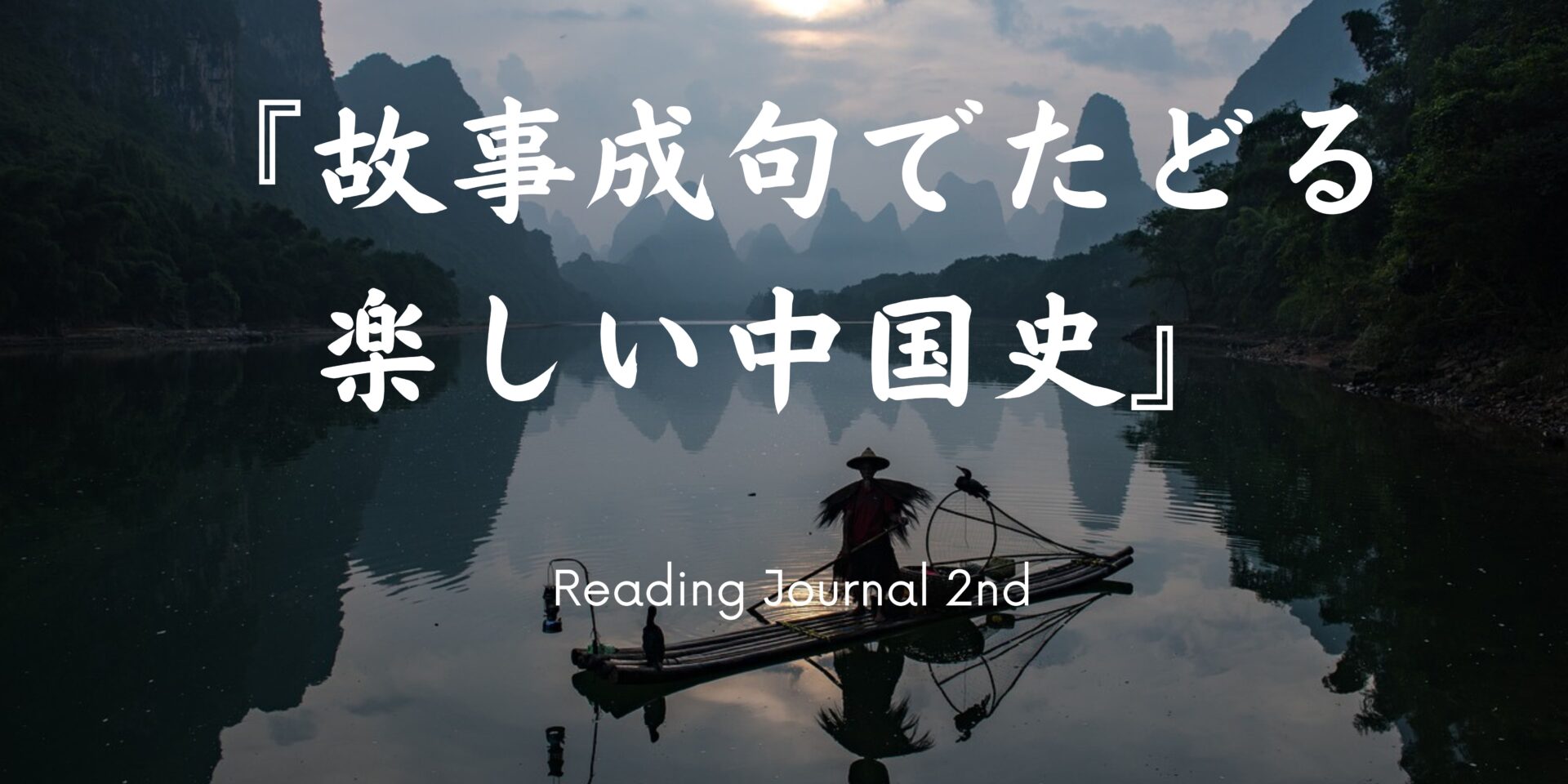


コメント