『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 「破竹の勢い」 — 英雄・豪傑の時代 2 諸王朝の興亡(その1)
今日から「第四章 破竹の勢い」「2 諸王朝の興亡」に入る。魏王朝が滅亡したのち中国は西晋、東晋、劉宗、さらには南北朝になるなどが次々と交替する。この西晋、東晋などの時代は貴族文化が起こり文学などの芸術が盛んになる。
「2 諸王朝の興亡」は3回に分けてまとめるとする。それでは読み始めよう。
「破竹の勢い」杜預の活躍と西晋の中国統一
西晋が誕生すると重臣たちは太平気分を謳歌し、厭戦ムードとなった。そのためなかなか呉討伐に踏み切らなかった。
そんな時、鎮南代将軍・杜預は、武帝の賛同を得て呉に出撃した。そしてあと一歩というところまで来たところで、軍中会議で慎重論を唱える者が現れた。すると杜預は「今、兵威已に、譬えば竹を破くが如し(今、わが軍の威力は大いにふるい、破竹の勢いさながらだ)」と言って決戦を主張した。結果、杜預を総司令官とする西晋の軍が呉に総攻撃をし呉を滅亡させ西晋が中国を統一する。
この故事により、後世、勢いが強く押しとどめ得ないことを「破竹の勢い」というようになった。
「貨殖聚斂」西晋王朝の混乱
西晋王朝は全土統一を果たした後から、混乱を深めていく。武王自身が呉の財産と後宮にひしめく美人に目がくらみ、すっかりやる気を失ってしまう。そして、政権を担う貴族たちも「貨殖聚斂(金儲け)」に励み、競って贅沢三昧に耽った。
「漱石沈流」貴族たちの贅沢三昧
西晋貴族の贅沢三昧の代表的存在が石崇、王愷、王済の三人である。『世説新語』の「汰侈篇」には、彼らの贅沢競争にまつわるエピソードがいくつも収められている。
また、王済は人をやり込めることを好んだ、そして親友の孫楚も意地っ張りだったので、彼らはよくやりあった。『世説新語』の「排調篇」には王彩と孫楚の話が載っている。
孫楚が隠遁しようと思い王済に決意を告げるとき「沈石漱流(石を枕として流れで漱ぐ)」というべきところを間違えて「漱石沈流(石で漱ぎ流れを枕とす)」と言ってしまう。王済に間違いを指摘されると孫楚は、「流れを枕とするのは耳を洗うためだし(伝説の隠者許由が堯から天子の位を譲られたとき、汚らわしいことを聞いたと耳を洗った故事をふまえる)、石で漱ぐのは歯をとぎすますためだ」と言い返した。
この故事により、意地っ張りで負け惜しみの強いことを「漱石沈流」といい、夏目漱石のペンネームの由来もこの話にある。
「鶏群の一鶴」嵆紹と恵帝
このように皇帝も貴族も快楽にふけるうちに、政権基盤がガタガタとなる。そして、武帝が死去し暗愚な恵帝が即位すると、西晋の崩壊は決定的となる。
そして、司馬氏の諸王の争いとして「八王の乱」が勃発する。この時右往左往する恵帝を守ったのが、竹林の七賢のメンバー、嵆康の遺児嵆紹である。彼は頗る付きの硬骨漢で「野鶴の鶏群に在るが如し(野生の鶴が鶏の群れのなかにいるようだ)。」と称された。
この故事により、他と比較を絶する優れたい人物を「鶏群の一鶴」というようになる。
嵆紹は、八王の乱の渦中で恵王を守って戦い、殺害された。それは、恵帝の服に嵆紹の血が飛び散るという、凄惨な最期だった。
かろうじて命拾いした恵帝は、近侍の者が血の付いた服を洗おうとしたとき、「これは嵆侍中(嵆紹)の血だ。洗ってはならぬ]と言ったとされます。嵆紹の忠義一徹はあやめも分からぬ暗愚な恵帝の心すら動かしたのです。(抜粋)
八王の乱はつづき、西晋王朝は分裂・崩壊する。そして北方異民族も猛攻にさらされながら「永嘉の乱」で西晋王朝は滅亡し、以後華北は、五胡十六ヵ国が入り乱れる異民族の世界となる。
「洛陽の紙価を高める」左思と西晋文学
豪華な貴族文化が華ひらいた西晋時代は、文学の世界も潘岳や陸機に代表される華麗な修辞を施した詩文が主流となった。
もちろん、修辞主義だけでなく左思のような写実的な詩文もあった。左思は魏・呉・蜀の首都の特徴を描き分けた「三都の賦」を完成させたところ、大評判となりみなが競って筆写した。そのため「洛陽、之が為に紙貴し(西晋の首都洛陽では紙の値段が上がった)」とされた。
この故事により、ベストセラーについて「洛陽の紙価を高める」という表現をすることがある。
「屋上に屋を架す」謝安の皮肉
そして左思の死後数十年たって、東晋の時代に、庾闡という人が「揚都の賦」を著した。これを親戚だった実力者が、左思の「三都の賦」と合わせて「四都の賦」というべき傑作だと宣伝した。すると、評判になり、また東晋の都・建康の紙価が上がった。
このとき、名士の謝安は「これは『屋下に屋を架す(屋根の下に屋根をつくる)』ようなもので、『三都の賦』の真似をしただけの駄作だ」と酷評しました。(抜粋)
この故事により日本では「屋上に屋を架す」の言い回しで流布し、すでにあることをくりかえし、むだなことをするという意味でつかわれる。
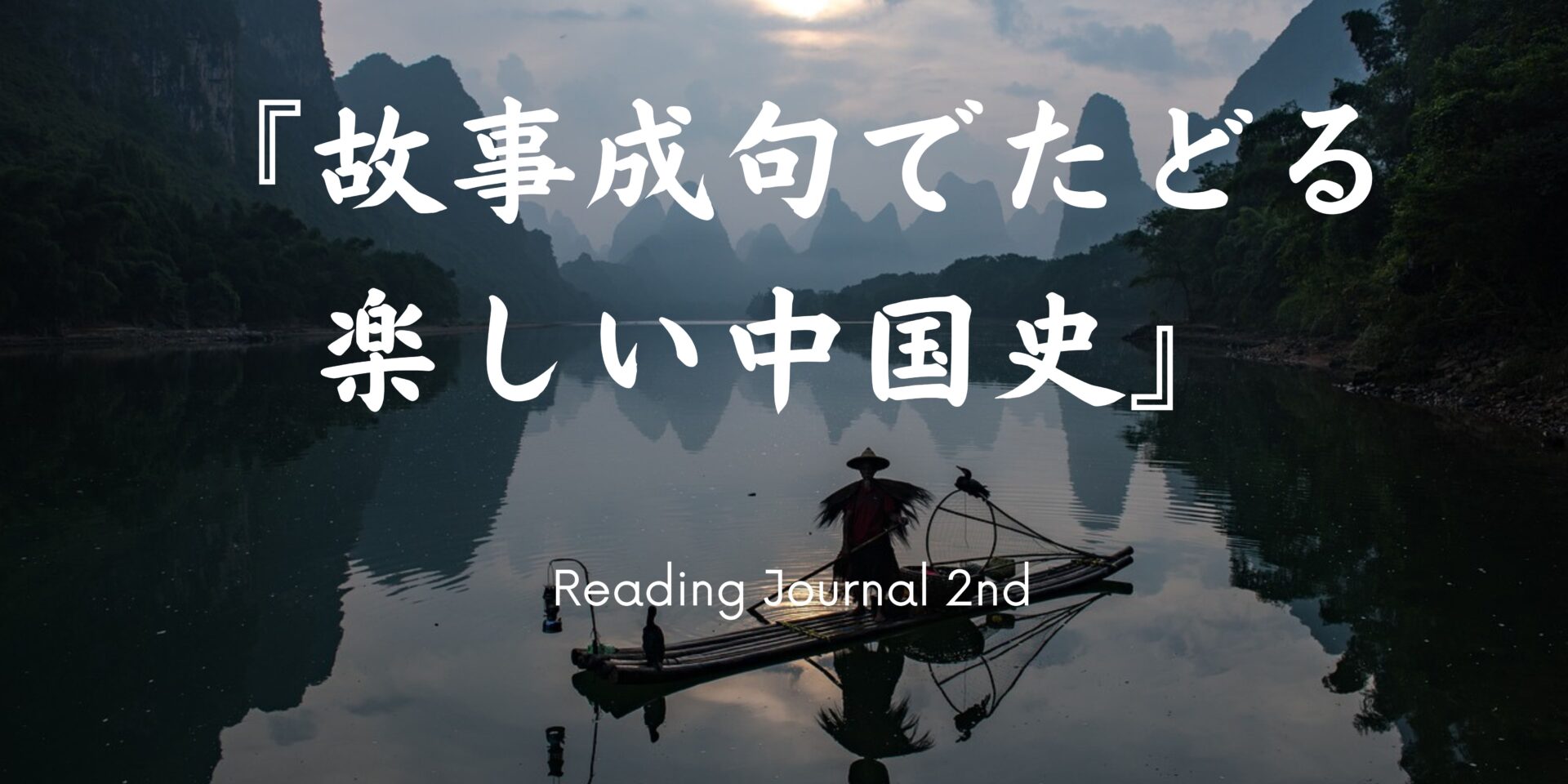

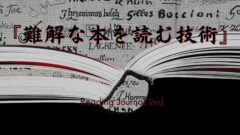
コメント