『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 「破竹の勢い」 — 英雄・豪傑の時代 1 三国分立(後半)
今日のところは「第四章 破竹の勢い」「1 三国分立」の”後半“である。”前半“では、「黄巾の乱」で後漢王朝が事実上滅亡したところに始まり、魏・呉・蜀の三国分立が確立したところまでをまとめた。
今日のところ”後半“では、三国志の第一世代の退場と諸葛亮の北伐、そして司馬氏による魏王朝の簒奪と、それに組しない「竹林の七賢」、最後に司馬氏の西周による中国の統一である。それでは読み始めよう。
「呉下の阿蒙」関羽の最期と呂蒙
曹操を漢中から撃退するころまでが劉備の絶頂であった。その後、まず関羽が戦死する。
関羽は荊州から北上し曹操軍の猛将曹仁との戦闘中に曹操と手を組んだ孫権軍に挟み撃ちされ、生け捕りにされ殺害された。この、計略は孫権軍の軍師・呂蒙の考えたものである。
この呂蒙は、若いころ勉強が嫌いで「呉下の阿蒙(呉のオバカサン)」と呼ばれていたが、その後一念発起し学問に励み名将になった人物である。
魏王朝、蜀王朝、呉王朝の成立と曹操、劉備の死
呂蒙は関羽の死の翌月に死去する。曹操の長男曹丕は、後漢王朝の献帝から禅譲を受けた形で即位し、魏王朝の文帝となった。劉備も負けじと即位し蜀王朝をたて、孫権も少し遅れて呉王朝をたてる。
皇帝となった劉備は、関羽の復讐のために呉に攻め込むが、呉の陸遜に撃退された(夷陵の戦い)。そして命からがら逃げ帰った後、暗愚な長男劉禅をのこし亡くなる。
こうして第一世代があいついでこの世を去ったあと、三国志世界は諸葛亮の独り舞台となります。(抜粋)
「泣いて馬謖を斬る」諸葛亮の北伐
諸葛亮は、劉備の信頼にこたえて劉禅を輔佐し、七年間に五回(六回という数え方もある)北伐を行った。
なかでも魏を震撼させたのが、第1回の北伐であるが、諸葛亮の愛弟子である馬謖が致命的な作戦ミスを犯し失敗した。諸葛亮は信賞必罰(功績のある者は必ず褒賞[ぼうしょう]を与え、罰すべき者は、必ず処罰すること。初出は『漢書』「芸文志」)として、心を鬼にして馬謖を処刑した。
この故事がいわゆる「泣いて馬謖を斬る」である。
「死せる孔明、生ける仲達を走らす」諸葛亮の最期
その後、諸葛亮は魏の将軍・司馬懿あざな仲達にはばまれて、北伐はうまくいかなくなる。
そして、五丈原の陣中で諸葛亮は病死してしまう。諸葛亮は、遺言で蜀軍にその死を隠したまま、撤退するように伝えた。これには司馬懿も騙され恐れをなして軍を引いてしまう。
これが「死せる諸葛、生ける仲達を走らす」である。この故事は陳寿の『三国志』「諸葛亮伝」に付され、裴松之の注に引く『漢晋春秋』にも見える表現であるが、後に「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という表現として流布する。
ここで『三国志演義』の世界が大体終わる。Blogの第一回にも書いたが、著者の井波律子は『三国義演義』の翻訳者である。そういうこともあるのか、ここの部分はちょっと熱が入っていたように思えた。
それから、三国志の世界を故事成句を絡めて追っているのだが、その筋の追い方がやはり見事である。『三国志演義』を読んでいた時は、大部であることもあり全体の流れがあまりよくわかってなかった。あらためて・・・・・なるほどなるほど、確かにそういう話だった!と思ったのでした。(つくジー)
「司馬昭の心は、路ゆく人も知る」司馬氏による魏の支配
諸葛亮の死後、魏では司馬懿が実権を握った。そして長男の司馬師、次男の司馬昭の代になると、「司馬昭の心は、路ゆく人も知る」と司馬昭が魏王朝を簒奪しようとしていることを知らない人はいない状態になった。
「竹林の七賢」
このような時代背景の時、注意深く危険な罠から身をそらし自分自身の生き方をしたのが「竹林の七賢」と呼ばれた、阮籍、嵆康、山擣、劉伶、阮咸、向秀、王戎である。
彼らは、老荘思想の無為自然をモットーとし自由な生き方を求めて隠遁し、竹林に集まって酒を飲み、時を忘れて「清談(哲学談義)」や音楽にふけった。彼らのエピソードは、南朝宋の劉義慶が編纂した魏・晋のエピソード集『世説新語』に収録されている。
彼らは大体三つの型に分けられる。
- 司馬氏に非妥協的な態度をとり続け処刑される:嵆康[けいこう]は、彼の妻が曹操の曾孫であるため司馬氏と関わるのを拒否し、ついに司馬氏と衝突し処刑される。
- 形だけ司馬氏傘下に入るが、大酒を飲み機構にふけり、役立たずの無能者を誇示し無事に生き延びる:阮籍、劉伶、阮咸
- 司馬氏政権に積極的に参加:山擣、向秀、王戎
「白眼視」阮籍
七賢のリーダー格だった阮籍は、老荘思想の実践者として、奇矯なふるまいも多かった。彼は、青眼[(普通の目つき)と白眼(白目をむく)を使い分け、欲物に対しては白眼を見せ、超俗的な人物に対しては青眼を見せた。
後に、冷たい目で見ることを「白眼視」するというが、この故事から来ている。
阮籍は、司馬氏の服喪規定にわざと反抗しきわどいポーズをとって政策に反対した。しかし、司馬昭が彼に親愛の情を持っていたこと、さらに都合が悪くなると大酒を飲み前後不覚になって見せたことなどが功を奏して、生命を全うすることが出来た。
『世説新語』「任誕篇」には、「阮籍は胸中に塁塊あり、故に酒を須って之に澆ぐ」(阮籍は胸の中に塊があった。だからこれを酒で洗ったのだ)」という評言がある。著者は、魏末の救いがたい時代状況に対する違和感、憤懣、絶望がしこりのように固まっていたとする、この評言はまさに言い得て妙、と称している。
「形骸を土木にす」劉伶
阮籍と同じく②のタイプに属する劉伶は、阮籍のような深刻さはなく「形骸を土木にす(肉体を土くれや木ぎれのように見なす)」として、陽気に酒浸りな日々を送った。
山擣、王戎 、向秀の生き方
山擣、向秀、王戎は言わば転向であった。しかし、彼らは最後まで「竹林の七賢」のスピリットを失ってなかった。
山擣は、嵆康の刑死後、その遺族を見守り、遺児嵆紹を引き立てて出仕させた。王戎は、政権の中枢に位置する大立者になったが、西晋が退廃し回復の見込みがないと判断すると、政務を投げ出し金儲けにせいをだし、滅びゆく西晋と運命を共にすることを回避した。
王戎の生き方は、なるほど機をみるに敏、俗気にあふれたものですが、その底にはやはり悪しき権力との同化を拒否する、七賢スピリットが認められます。(抜粋)
司馬氏による西晋の成立と中国統一
司馬昭がなくなると、息子の司馬炎がついに魏を滅ぼして即位し武帝となり西晋王朝が確立した。この司馬氏の西晋は、呉も滅ぼし、ついに中国全土を統一した。これにより魏・呉・蜀の三国時代は完全に終わる。
関連図書:井波律子(著)『三国志演義 (全四巻)』、講談社(講談社学術文庫)、2014年
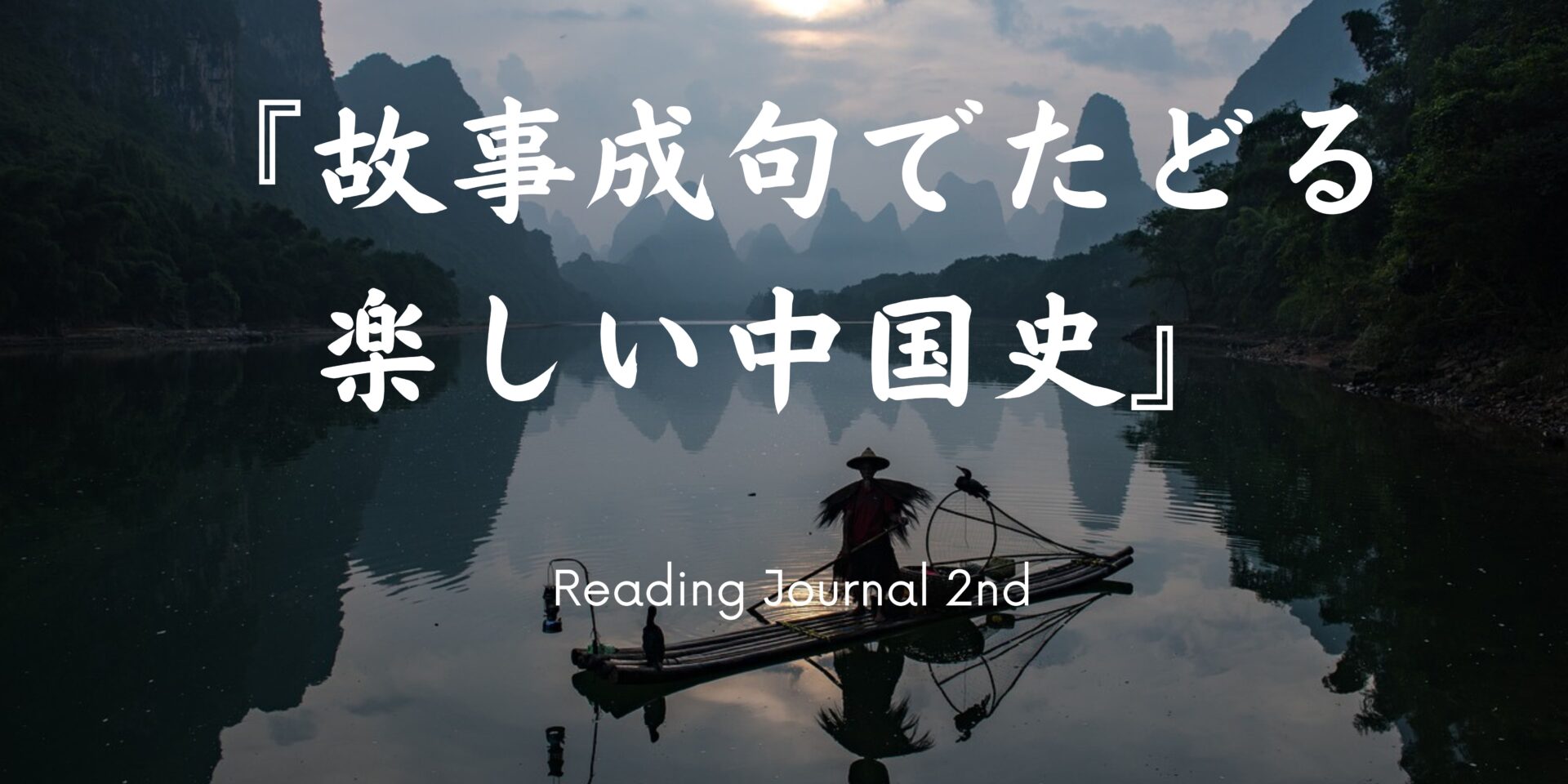

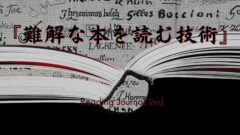
コメント