『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
五〇歳からの六歳児感性の再生法
著者の柳田邦男は、トーベ・ヤンソンのムーミン童話やA・A・ミルン(文)、E・H・シェパード(絵)によるクマのプーさん童話を例に挙げ
優れた児童文学の数々を読んでいつも感心するのは、六歳児くらいまでの幼いこころの動きを、みごとと言えるほど鋭くとられている点だ。それはとりもなおさず作家が六歳児くらいまでの感性をそのまま失わずに持ち続けているということを示している。
(抜粋)
と言っている。
『さびしがりやのクニット』
ヤンソンの絵本『さびしがりやのクニット』は、ヤンソンのこころのなかに息づいている六歳児の感性が全開している。
この物語は、孤独な男の子クニットの“こころの成長の物語”である。一人で暮らしているクニットは、夜になると怖くてさびしくてたまらない。そして、クニットはもうこの家に入られないと、朝もやの中、鞄一つで逃げ出す。そして、白夜の日暮れ時に、海岸で一本のビンを拾った。ビン中にはスクルットという女の子が書いた手紙が入っていた。スクルットは、ひとりぼっちで怖くてさびしくてたまらないので、誰か慰めに来て欲しいという。
クニットのこころに大きな変化が起こる。勇気がわいてきて、強くてやさしい少年になったのだ。(抜粋)
その後、怪物モランなどの困難をのりこえてスクルットと出会う。
クニットのこの“こころの成長の旅”の途上には、ムーミン童話のなかに登場する怪物をはじめ擬人化された愉快な生きものたちや人物たちが描かれて、物語展開の脇役を演じ、スクルットの内面の葛藤やこころの変化と成長を浮き彫りにする役割を果たしている。(抜粋)
『プー あそびをはつめいする』
著者は、ミルンとシェパードによるプーさん童話にもヤンソンと同じ六歳児の心を感じると言っている。
「はじめてのプーさん」の『プー あそびをはつめいする』は、短編よりも少し長めの童話がまとめられている。この話はプーさんが「発明したあそび」について書かれている。その遊びとは、まず上流の橋の上からみんなで棒切れをおとし、走って下流の端まで行って、誰の棒が先に流れてくるかを競うというものである。
この絵本のなかの、橋の柵から川面をのぞきこむクリストファーとプーとコブタの三人の後ろ姿を描いた挿絵は、子どものこころの世界のすばらしさを表現した傑作である。
絵本や童話を読んでいつも思うことがある。人は人生のなかで青年期から中年期にかけては、ガツガツと仕事仕事の日々を過ごすのはやむを得ないとしても、五〇歳を過ぎたら、忙しくても、毎日二〇分は絵本や童話を読むライフスタイルを身につけるように心掛けてはどうか、と。その日常を積み重ねていくなら、いつしか幼いころの無垢な感性を取り戻し、還暦を迎えるころには、周囲から「あなた、変わったね」と言われるようになっているだろう。(抜粋)
関連図書:
トーベ・ヤンソン(作)、渡部翠(訳)『さびしがりやのクニット』、講談社、1991年
A.A.ミルン(文)、E.H.シェパード(絵)、石井桃子(訳)『プー あそびをはつめいする』、岩波書店、2016年
夢のなかで遊ぶ子供の世界
インドネシアのある島では、子どものころから、見た夢をその日のうちにお年寄りに話すという日常生活の文化があるという。かなり前だが、臨床心理学者で夢分析の専門家でもあった故・河合隼雄先生がご健在だったころに聞いた話だ。その島では、こころの病気になる人が一人もいないというので心理学者や精神医学者が関心を持っているとのこと。(抜粋)
著者は、これを受けて心の中の葛藤や苦痛、抑圧感情が現れた夢を第三者に話すことによって、その一端を引き受けてもらう効果があるのではないかと言っている。また、その夢を聞いてくれる人が家族の中心であるお年寄りであることも重要である。
ここでは、夢を題材にしたファンタジーを三冊紹介している。
『はんなちゃんがめをさましたら』
一冊目は『はんなちゃんがめをさましたら』である。この本は、幼い女の子の夢なのか現実なのか茫洋とした世界を描いた傑作である。
はなちゃんが、眼をさましたらまだ夜だった。そして、おねえさんが添い寝をしているお人形やオルゴール、ノートと色えんぴつなどを借りてあそぶと物語が展開していく。
鳥の鳴き声が聞こえたので窓辺に寄ると、色とりどりの美しいハトが木の枝に止まっていた。
幼い子の感覚はファンタジーとリアリティの間に境がなく、両者の間を自由に往来したり、一体のものとして受けとめたりする。そんな心模様がみごとに表現されている。(抜粋)
『3びきの くま』
二冊目は『3びきの くま』。サーカス一座の女の子のコルディちゃんが森で花を摘んで遊んでいるうちに帰り道がわからなくなり迷っていると、おかしな家を見つける。それはくまさん一家の家だった。コルディちゃんは、なかに入って椅子に座ったり、おかゆを食べたりして、ベッドにもぐり寝てしまう。
そしてくまさん一家が帰ってきて、それぞれが、
〈わしの いすにすわったのは だれだ〉
〈わたしの おかゆを たべたのは だあれ?〉
と騒ぎ出し、寝室の子ぐまのベッドに寝ているコルディちゃんを見つける。コルディちゃんはびっくりして逃げ出すのだが、子ぐまがやさしく声をかける。
〈おかゆ もう いらないの?〉(抜粋)
『こくばん くまさん つきへいく』
三冊目は、『こくばん くまさん つきへいく』である。パパに月の絵本を読んでもらったアンソニーくんが、月に行ってみたいと思う。その夜、黒板に描かれたくまが動き出す。一緒に宇宙船を作って、一人の乗りの宇宙船にくまさんが乗り込み出発する。アンソニー君はベッドにもどって再び眠ると、くまさんが窓から帰ってきてまた黒板のなに戻る。
日本には、子どもが見た夢をお年寄りが聴いてあげるという文化はないが、子どもが抱く願望を実現するファンタジーの絵本をしっかりと読み聞かせする文化が広く根づくなら、夢の話す文化と同じような深い意味を持つのではないかと、私は思っている。(抜粋)
関連図書:
酒井駒子(作)『はんなちゃんがめをさましたら』、偕成社、2012
ゲルダ・ミューラー(作)、まつかわまゆみ(訳)『3びきの くま』、評論社、2013年
マーサ・アレクサンダー(作)、風木一人(訳)『こくばん くまさん つきへいく』、はるぷ出版、2013年
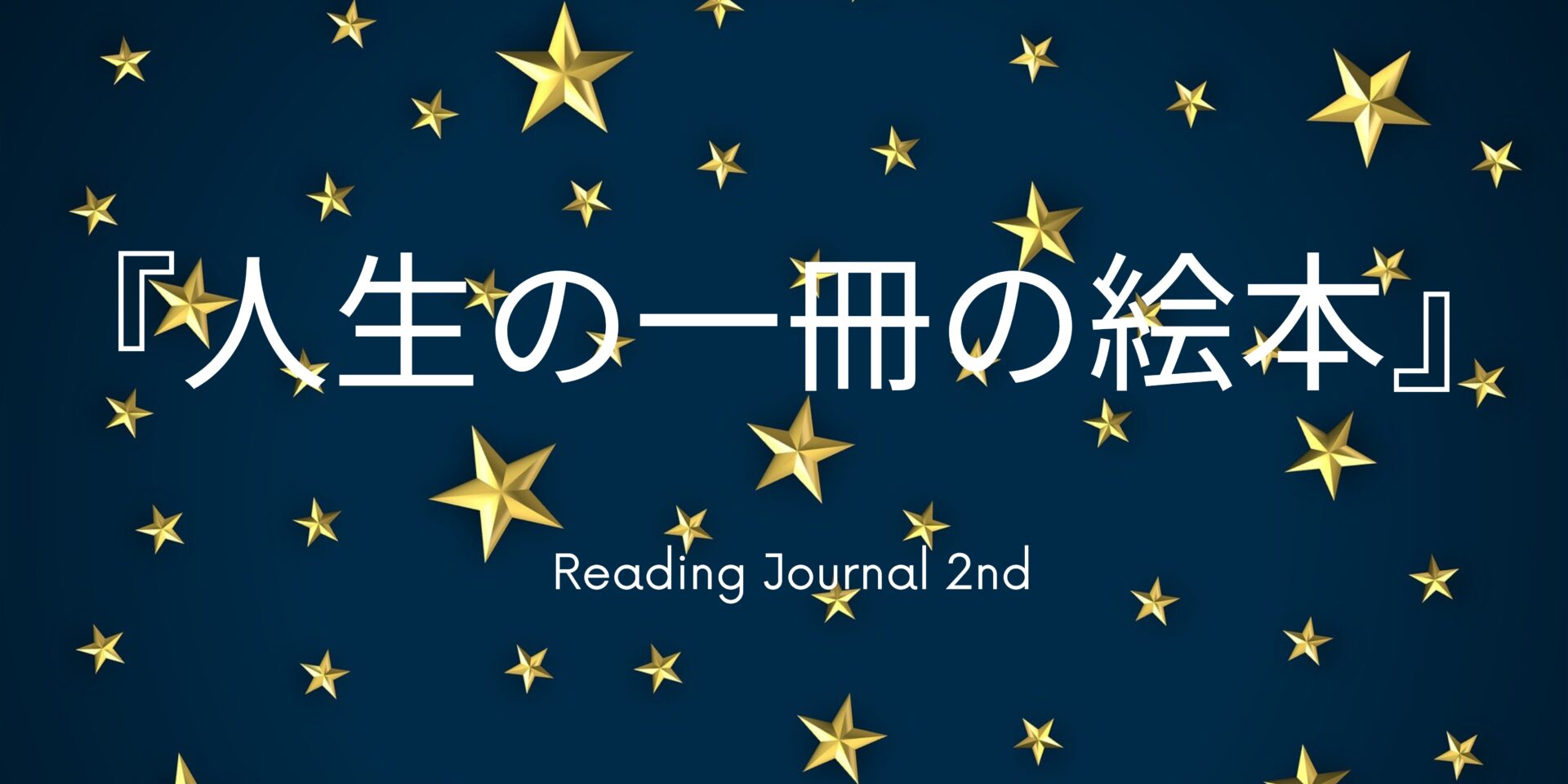


コメント