『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
人生の最後の「贈り物」と
順天堂大学医学部名誉教授の樋野興夫先生は、「がん哲学外来」を創始した。「がん哲学」と言っても、難しい話をするのではなくがんと診断されて悩む人あるいはその家族とどのようなケアをしたらよいかを、一緒に考えるという意味である。このような「がん哲学外来」の相談室は全国150か所以上の医療機関に設置されている。
また、樋野先生は、医学生のころから毎日夜の三〇分は、専門外の教養書の読書にあてている教養人でもある。
柳田と樋野先生との対談は、『人の心に贈り物を残していく ―― がん患者の幸福論』(悟空出版)としてまとめられている。
二人が一致した重要なポイントは、人生で大事なことは残された歳月をいかに自分らしく生き、いかに内面的な成熟度を高めるかであり、そういう生き方をしたときに、その生き方や言葉が残された家族や親友の心に刻まれ、家族や親友の心の支えになったり、その後の人生を膨らませたりするという点だ。死を前にした生き方は、後を生きる人々への「贈り物」なのだ。(抜粋)
ここでは、そのようなことを絵本という表現形式で表している作品を三冊紹介されている。
『こころのおと』
一冊目は、『こころのおと』である。この絵本は、魂の交流と言ってよいこころの深いコミュニケーションを可能にしている音楽の問題について感銘深く語っている。
幼い男の子・ラジは、だれも弾かないピアノを見つけ、鍵盤を叩いた。そして
<ラジは、いろをまぜて えをかくように、おとを まぜてみた。ゆめのような しらべが、いえじゅうに ひろがっていく>(抜粋)
お父さんはびっくりしてピアノを習わせるが、上手にピアノを弾けるようになるほど、ラジはピアノが面白くなくなり、大人になるともうピアノは弾かなくなってしまう。
やがて年老いた父が倒れ病床にふす。ラジが駆けつけると、お父さんはピアノを弾いて欲しいという。
ラジが昔習った曲を弾くと、<ちがう・・・それじゃない・・・・。ほら、ちいさいころ ひとりで たのしそうに ひいていたじゃないか>と言われる。ラジは<ながいあいだわすれていたものを たぐりよせるような きもちで、ゆっくりと おとを つむぎはじめた。「そう そう、それだ・・・・」おとうさんは めを とじたまま ほほえんだ>。(抜粋)
『3日ずつのおくりもの』
二冊目は『3日ずつのおくりもの』である。ひいおじいさんのホープは、毎年誕生日に<3日ずつ ながいきするように>と、みんなが願ってくれるおかげで、年をとっても元気であった。ところが、ある年の誕生日に、ホープ爺さんは、もう十分に長生きしたからと、願いを変えて、本やCDやDVDがほしいといった。そして本や音楽や映画を楽しんでは、孫のリトルに教えた。そして、ある日、大好きな音楽を聴きながら、息を引き取る。
リトルは「3日ずつ」を願わなくなったことを悔やまなかった。ホープじいさんの思いを分かっていたからだ。(抜粋)
『ありがとうエバせんせい』
三冊目は『ありがとうエバせんせい』である。小学校一年生くらいのクラスの話である。担任のエバ先生は病気で休んでいて、代わりのバンクス先生が子どもたちにいろいろと教えている。子どもたちはお見舞いに行くが、しばらくすると悲しい報せが届く。
子どもたちは、エバ先生の思い出を語り合い、紙に書いた。そして、バンクス先生はエバ先生から教わったことを表わす言葉を、銅で作った葉っぱのかたちをした板に書きましょうと言って、子どもたちにわたす。そして、学校の大きな木に針金でつるした。
このようにして子どもたちのこころに刻まれたエバ先生の思い出と学びは、子どもたちの人生を膨らませることになるにちがいない。(抜粋)
関連図書:
ピーター・レイノルズ(作)、なかがわちひろ(訳)『こころのおと』、主婦の友社、2016年
レミ・クルジョン(作)、こだましおり(訳)『3日ずつのおくりもの』、文溪堂、2016年
ヒラリー・ロビンソン(文)、マンディ・スタンレイ(絵)、きむらゆかり(訳)『ありがとうエバせんせい』、絵本塾出版、2015年
祈りの灯、消えないように、消えないように
二〇一八年に柳田邦男は、長野県にある絵本美術館「森のおうち」で開かれていた、荒井良二や酒井駒子ら四人の絵本の原画展がやっていた。
『きょうというひ』
その作品の中で特に深い感動を得た絵本が『きょうというひ』である。
展示されていたどの原画も、大きいものではなかった。だが、原画の一点一点が幼い子が描くようなのびやかな童画がタッチであるのに、とても品格があって、読む側のこころが浄化されていく感じがする。(抜粋)
夜の暗黒の中に小さな家のシルエットが雪の降る中に描かれている。その次の絵は、一転して朝日に小さな家が現れる。部屋の中では、女の子が今日着るために編んだ真っ赤なセーターを身につけている。
そして、室内のロウソク立てに三本のロウソクを立てて火を灯す。(抜粋)
そして野外で、小さな祠のような家をたくさん作って、その中にロウソクをともしていく。そして女の子は、ロウソクの火が<きえないように、きえないように>と祈る。
<きえないように>と祈るのは、ロウソクの灯のことだけではない。<きょうというひの ちいさな いのりが きえないように きえないように・・・・・>と続けられているのだ。(抜粋)
この<きえないように>という言葉は、柳田の心に深く刻まれている。
『雪の花』
では、何らかの思いこめた祈りは、いつの日に、どんなかたちで、誰に届くろうか。おそらくその瞬間、自分の意図や予想を越えたかたちでやって来るものなのだろう。(抜粋)
そう言った柳田が、そのヒントになるとしたのが、ロシアの児童文学者セルゲイ・コズロフの戯曲を絵本化した『雪の花』である。
動物の森で、クマくんが高熱を出していのちが危ない。キツツキ先生が”雪の花“が無いと助からないという。そして、ハリネズミが雪の花を探しに森の中に行く。松のおばさんの教えに従って、森を抜け泉をみつける。雪の花は泉の底にあると教えられたのだ。
のぞくと、確かに底にある。しかし、飛び込むと見えなくなる。何度飛びこんでも同じだ。ハリネズミは全身が氷の結晶で包まれ、低温と疲れで倒れてしまう。(抜粋)
そして、それでもはやくと帰路についた。ハリネズミが走ると、森の中を白い不思議な光るもの–雪の結晶が森の中を走り抜ける。そして、クマくんの家のドアを開けると、
みんなびっくりする。きらきら光る真っ白な花がゆれているでなないか。”雪の花“だ!すると、クマくんは、熱が下がって治ったではないか!(抜粋)
関連図書:
荒井良二(作)『きょうというひ』、BL出版、2005年
セルゲイ・コズロフ(原作)、オリガ・ファジェーエヴァ(絵)、田中友子(文)『雪の花』、偕成社、2018年
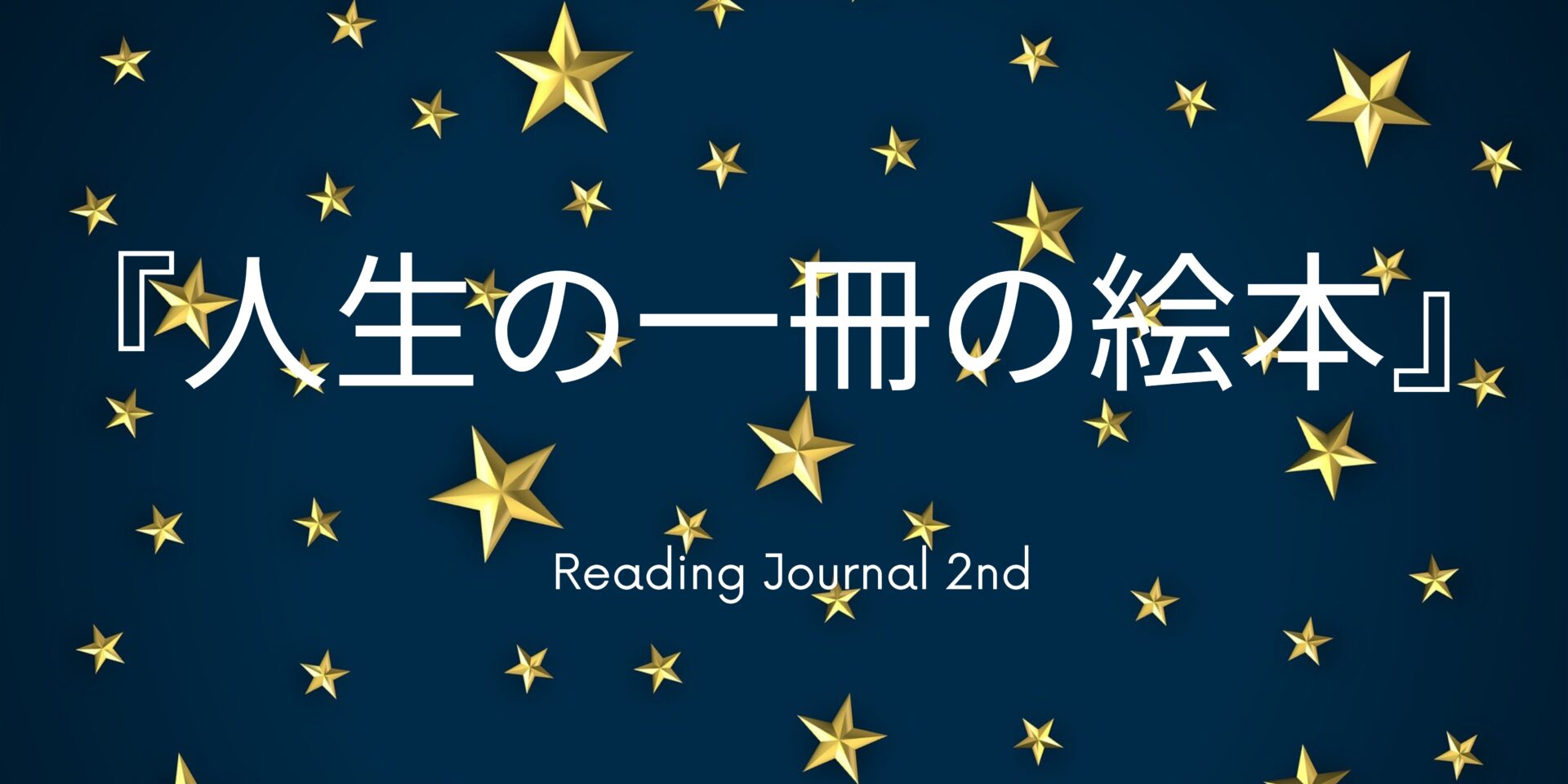


コメント